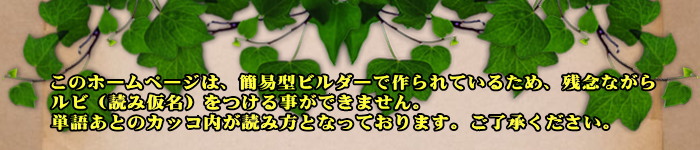
83
1027年 ファレーズ城
遠くから聞こえてくる複数の金属音に、さしもの敵騎士達も戸惑(とまど)いを隠せなかった。
外城門から『領主の館(メヌア)』の城門前まで、100ウナ(約120メートル)は離れていよう。それだけの距離を隔(へだ)てて響いてくる音は、彼らの心にわずかながらも苛立(いらだ)ちと不気味さを湧(わ)き上がらせた。自信満々であった騎士達に、一抹(いちまつ)の不安を芽生えさせたのである。
指揮官の隣にいた騎士が、彼に馬を寄せてくる。
「ヴィルヘルム殿‥ もしや、ロベール伯爵が戻ってきたのでは? 」
ヴィルヘルムと呼ばれた指揮官はそれを否定した。
「そんなはずはないだろう! それは絶対に不可能だ 」
「て‥ では、奴らが何かを企(たくら)んでいるのでは―――? 」
「ああ‥ その可能性はあるな。 クソッ! とりあえず、ハンス達に様子を見させてこい! 」
「は‥ はい! 」
すぐに3人の騎士が、偵察隊として、不気味な音へと向かったのだった。
その様子を確認した物見櫓(ものみやぐら)のピエトロは、傍(かたわ)らに立つエルレヴァに
「ここは危険です。 どうか、安全なところに避難(ひなん)してください 」
と声を掛け、屋敷の中へ移動させた。
3人の偵察隊は、ハンマー音を追って外城門まで一気に走ってきた。
彼らは、ガン、ガン、ガン、ガンとけたたましい音を立てる門へと近づいた。門の内側には誰もいない。音は間違いなく、門の外側で鳴っているのだ。
3人は、閉ざされた城門の外に向かって誰何(すいか)した。
「誰だ? そこで何をしている? 」
「この音は何なんだ? 」
「門を閉じて、何をしようとしている? 」
と、ハンスが扉の異変に気づく。
「あ‥ 閂(かんぬき)が掛けられている! 」
「奴ら‥ 何か企(くわだ)てようとしてやがるな? 」
しかしそんな彼らも、その『企(くわだ)て』とは、逃げるための算段か、せいぜいが防衛の手段ていどだろうと、高をくくっていた。まさか、それが反撃の準備であろうなどとは、思いもよらなかったのである。
なぜなら、自分達の方が圧倒的に有利であったからだ。この状況ならば、相手は無条件に降伏すると、彼らは確信していた―――ライオンは、追い詰めたウサギが木を囓(かじ)ったからといって、それをさほど気に止めないのと同じ理屈である。
そして、完全に油断している偵察隊は、のこのこと城門に近づいてきたのだ。
「答えろ! 何をしている? 」
「答えないと、貴様ら殺すぞ! 」
偵察隊は剣を抜くと、扉に向かってそう怒鳴った。
その3人の頭上に、2本の弓矢と3本の笄(こうがい=かんざしに使われるほど、細く造られたナイフ)が降り注(そそ)いだ。
「ギャンギャン! 」
「ゴヘッ! 」
「グガッバッ! 」
1人目のハンスは肩に矢を受け、目には笄(こうがい)が刺さっていた。2人目は、胸に深々と矢が刺さり、3人目は、兜(カスク)を被(かぶ)っていない頭頂部に矢を射込まれ、喉にも笄(こうがい)が刺さっていた。
彼らはその場で絶命し、2人が落馬した。
敵偵察隊に笄(こうがい)や矢を射かけたのは、サミーラとブノア、プチ・レイ、ドニの4人であった。彼らはハシゴの上に立ったり、城壁の上に坐ったりして、ほぼ真上から弓を引いたのだ。
城内に1人残っていたジャコモが、近くの物陰から出てくる。彼は偵察隊の死体と馬を移動させ、近くの屋敷に隠した。
その間も、3人の『カラス団(コルブー)』はハンマーを打ち続けた。
早く釘(くぎ)を打ち込まなければならない。
ゴルティエらは懸命にハンマーを振った。
その甲斐(かい)あってか、釘(くぎ)は徐々に扉の中へと埋まっていく。
そしてついに、1組が2本ずつ、計6本の釘(くぎ)が城門に打ち込まれたのだ。
これで、閂(かんぬき)をはずす事はできなくなった。それはもう、ピクリとも動かないであろう。つまり、城門を開く事は誰にも―――たとえゴルティエ達でさえも、できなくなってしまったのである。
こうした詳細(しょうさい)な作戦は、ピエトロを中心とした傭兵達と『カラス団(コルブー)』達によって立案されていた。
敵を焼き殺すという基本案はエルレヴァが考えたが、現場の細かい作戦は実行者である彼らに任されていたのである。
『領主の館(メヌア)』前の傭兵(ようへい)騎士団の中に、漠然(ばくぜん)とした不安が広まっていった。
不気味な金属音はいまだ鳴り止(や)まず、すぐに帰ってくると思っていた偵察隊はいっこうに戻らないからである。
「ヴィルヘルム殿、どういたしますか? いまだ、ハンス達は戻りませんが‥‥ 」
「ああ‥ だが、偵察隊の安否(あんぴ)を確認するために、さらなる偵察隊を送るというのもバカバカしい 」
その時、街中に響いていたハンマー音が突如止(や)んだ。
ファレーズの城下にふたたび静寂(せいじゃく)が戻ったのだ。
だが、今度はその静けさが、騎士団の不安をさらに増幅していった。
「なんだか、気持ち悪いな。 ここは、さっさと仕事をかたづけて‥ この地を離れる事にしよう 」
ヴィルヘルムは仲間らに号令を掛けた。
「弓、構えい! 」
騎士や歩兵の半分以上が弓を持っていた。
彼らは弓に矢をつがえると、弦(つる)を大きく引き絞る。そしてその矢先を、どんよりと曇(くも)った天空に向けたのだ。
それを見た物見櫓(ものみやぐら)のピエトロが、中庭に向かって声を張り上げる。
「みんな、弓矢だ! 矢が降(ふ)ってくるぞ! 」
街の人々でギュウギュウ詰めとなった『領主の館(メヌア)』の中庭は、一瞬にして緊張に包まれた。
ピエトロがさらに大きな声で指示を出す。
「鎧戸(よろいど)を構えろ! 板を掲(かか)げるんだ 」
中庭に腰を下ろしていた人々は、尻に引いていた大きな板を頭上に持ち上げた。
ピエトロからの指示で、城壁に水を掛け終わった後、住民らは家々の扉や窓に付けられた鎧戸(よろいど)をはずして、持って来ていたのだ。
鎧戸(よろいど)は、窓などにつける雨戸のような物である。
それは弓矢に対する盾代わりであったが、一方で地面から這(は)い上がってくる冷気対策も兼(か)ねていた。
一番寒いこの時期、野外での野宿は厳しい。地面からの冷気が、人々の体力を根こそぎ奪ってしまうからである。
昨日の雪と塀に掛けた水で、中庭の地面はドロドロにぬかるんでいた。それが、未明(みめい)の急速な低温化でカチカチに凍り付くのだ。そんなところへ、じかに腰を下ろせば、体温は大きく奪われてしまうだろう。
やがて、歯の根も合わぬほどに震(ふる)えはじめ、しだいに低体温症となっていく。気力は衰(おとろ)え、思考力が低下してしまうのだ。
こうなると、もはや戦うどころではなくなってしまう。
そこで、これに対応するため用意されたのが、家屋の鎧戸(よろいど)や扉だった。これら分厚(ぶあつ)い板で、地面からの冷気を遮断(しゃだん)するのだ。
さらに、鎧戸(よろいど)は飛来する弓矢の盾としても代用できる。
しかも、入手が簡単で、全員分をそろえる事が可能だった。
ただし、800人近い避難民がぎっしりと坐る中庭には、老人や女達もいる。ピエトロの号令に全員が素早く反応し、尻に敷いていた鎧戸(よろいど)を構えられるワケではなかった。板を掲(かか)げるのに、もたつく者が大勢いたのだ。
「放て! 」
敵の将軍、ヴィルヘルムが命令した。
一斉に50数本の矢が放たれる。
矢は斜め上空へ駆け上ると、しだいに速度を落とし、今度は落下し始めた。
鋭角な弧を描いて50本を超える弓矢が中庭へと落下してくる。
だが、中庭一面を覆(おお)った鎧戸(よろいど)が、その矢の来襲を防いでくれた。
「な‥ 何だ? どうなってる? 」
『領主の館(メヌア)』を注視していたヴィルヘルムは、城内がいつまでも静まり返っている事に眉を顰(しか)めた。
「なぜ、悲鳴や叫び声が聞こえてこないんだ―――? 」
中庭に何人いるかは知らないが、その気配(けはい)から、それが相当な人数である事はわかっていた。
そうであれば、少なくとも5人や10人には矢が当たっているはず。にもかかわらず、中から何の声も上がらないのだ。
城内の様子がわからないまま、ヴィルヘルムは弓兵(きゅうへい)達を振り返って大きな声を浴びせた。
「撃て! 撃て! 撃て! 撃て! 」
素早く矢をつがえた弓兵(きゅうへい)達が、次々とそれを放っていく。
大量の矢は何度も中庭に落下した。
その執拗(しつよう)な攻撃に、住民の中には、足の甲を貫(つらぬ)かれる者、板を持つ指を射貫かれる者、板を突き抜けた矢が頭に刺さる者など、複数の負傷者がいた。
だが、鎧戸(よろいど)を掲(かか)げていたお陰で、死亡や致命傷を負った者は1人もいなかったのだ。
合計10回の連続射撃をした敵の騎士団は、いったん息を整えようと攻撃の手を緩(ゆる)めた。
その時、物見櫓(ものみやぐら)の中に隠れていたピエトロが立ち上がり、号令を発した。
「今度はコッチの番だ! 弓構えい! 」
城壁の裏に隠れていた警備兵20人が一斉に立ち上がる。
さらには、年老いた貴族や騎士、彼らの使用人、そして女でも―――力と勇気のある者は参加していた。その数は50人に近い。
彼ら全員が弓を構えていた。
ただ、彼らが敵と違っていたのは、矢の先端が燃えていた事である。それらの矢尻には、油を染み込ませた布が巻かれており、それに火が着けられていたのだ。
「撃て! 」
ピエトロが豪声を上げた。
放たれた火矢は、真っ直ぐ敵兵に向かって飛んでいった。
ヴィルヘルムは、襲いかかる2本の火矢を剣で叩き落とす。
他の者も、手にした剣や盾、弓でそれを払った。だが、突然の攻撃だったので、中には矢を受けて落馬する者もいた。
「怯(ひる)むな、怯(ひる)むな! 奴らは大した腕ではないぞ! 矢は当たらん! 」
ヴィルヘルムが余裕の激励(げきれい)を発した。
しかし、途端に彼らの足元が燃えだしたのである。
叩き落とした火矢で地面に火が着いたのだ。
敵は何が起こったのかわからず、慌(あわ)て始めた。
「二の矢、放(はな)て! 」
ピエトロの号令とともに、第二の火矢が放たれた。
今度の矢は、敵を大きくはずれ、その背後にある屋敷の茅葺(かやぶ)き屋根や荷車に積んであった藁(わら)などに引火した。
たちまち大きな火の手が上がる。
各家々にあった照明用や食用の油がすべて集められ、屋根やアチコチにおかれた藁(わら)、『領主の館(メヌア)』前の大路などにタップリと撒(ま)かれていたのである。
敵の騎士団は、退路が燃え出した事で大きな混乱が始まろうとしていた。
そこへ第三の矢が放たれた。
もはや、狙う必要などなかった。より遠くへ飛ばすだけでよいのだ。
ファレーズの街はしだいに、大きな炎に包まれていった。
ヴィルヘルムは唖然(あぜん)とした表情でピエトロを見上げた。
「ま‥ まさか、お前達は‥ 自分達が住む街を、みずからの手で焼き払おうというのか―――? 」
これまでルール無用で戦ってきた傭兵団(ようへいだん)であったが、このような奇策は見た事も聞いた事もなかったのである。