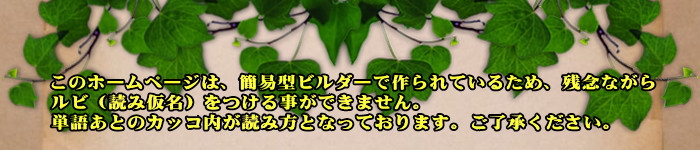
32
1026年 ファレーズ城内
「祝宴(しゅくえん)じゃ! 祝宴の準備をいたせい。 殿のご帰還を祝う宴(うたげ)を催(もよお)すのじゃ。 街の者達を城内に招き入れてもかまわぬぞォォ‼ 」
ファレーズ城の執事(アンタンダン)であるティボーがそう叫んでから、三日三晩、ロベールの無事帰還とドラゴン退治の成功を祝う宴(うたげ)が執(と)り行(おこな)われた。
街の有力者達は城内に招かれ、貧しい者達にもリンゴ酒(シードル)と鱒(ます)のパイが振る舞われた。
エルレヴァは伯爵の恋人として正式に招待されていた。
彼女が城の門をくぐった時、中庭(ヴァレ)に集まっていた多くの人々からどよめきが上がった。それは、彼女があまりにも美しかったからである。
本来の美貌(びぼう)は無論の事、彼女は貴族や富豪の娘達とも引けを取らない美しいブリオー(袖口が広くなったドレス)を身にまとっていた。
一見質素に見える淡い若草色のブリオーは、一流の仕立て人による総絹製である。上半身はぴったりとして、彼女の見事な体の輪郭(りんかく)を浮かび上がらせていた。その裾は、後ろが少し長くなっていて、下半身に流れるような動きをつけている。
腰の低い位置に着けられた白いベルトは、彼女の細い腰をさらに強調させている。
多くの貴婦人達は、丁寧(ていねい)に三つ編みにした髪に、リボンを幾重(いくえ)にも巻き、その頭上に宝冠(クラウン)やトーク帽(つばのない丸い帽子)などを被(かぶ)っていた。
一方、エルレヴァは髪を後ろで一カ所だけ縛り、その上からドレスと同色の薄いヴェールを被(かぶ)っただけであった。

ブリオーとサークレット(イメージ) © 中世衣装の販売 ARMSTEET
それは無造作で飾り気がないように見えた。だが、細(こま)かな刺繍(ししゅう)が施(ほどこ)されたヴェールとそれを留める額(ひたい)の金の輪(サークレット)は、彼女のゆるやかに波打つ見事な金髪をよりいっそう際立たせていた。
エルレヴァの完璧に計算された衣装は、その場の誰よりも慎(つつ)ましやかに見えるのに、彼女の魅力を二倍にも三倍にも膨らませていたのだ。
すべての女性が、彼女の美しさに羨望(せんぼう)と諦(あきら)めの溜息を漏らした。
もはや、誰もエルレヴァに後ろ指を差す者はいなくなっていた。
宴会(えんかい)には、家臣達と共に、110人の兵士達も参加していた。
彼らは大いに酒を飲み、バカ騒ぎに興(きょう)じたのだ。そして、酔っ払って、つい口を滑らせる者達もいた。
「いやいやいやいや‥ ティボー殿がいくら、伯爵様こそがドラゴンを退治なさった方だとおっしゃっても‥ 実際にやったのはあの異教徒に違(ちげ)えネーんだよ! ロベール様は関係ないに決まってるさ‥! 」
「まったくだ! 伯爵様は良い方だが、ドラゴン退治をしたってーのは言い過ぎだよ。 ありゃ、ウソだな! 」
そんな話をしていた二人の兵士の首に、突如ナイフが突き付けられた。
「おい‥ 誰がウソをついたって!? 」
思わず振り返った二人は、その犯人を確認してホッとした。兵士仲間であるエルリュインとダヴィドだったからである。彼らは、ドラゴン退治の生き残りの兵士達であった。
「おいおい‥ 冗談はよせやい! 」
右側の兵士が笑いながら、相方の喉にナイフを当てるエルリュインの肩を叩いた。
「いくらふざけてたって、ナイフはまずいだろう! 下手すると切れちまうんだぞ! 」
しかし、エルリュイン達は笑っていなかった。彼らはふざけているわけではないのだ。
「だから‥ 誰が関係ないって? 何がウソなんだよ? 」
「お前ら、もしかして伯爵様を馬鹿にしてんのか!? 」
「え!? 」
凍り付いた二人をエルリュインは睨(にら)み据(す)えた。
「だったら、その口が二度ときけないように、喉(のど)を掻(か)き切ってやろうか!? 」
二人の兵士達は、脅(おび)えた顔を横に小刻(こきざ)みに振った。
「わ‥ 判った‥! 判ったって! 俺達が悪かったよ‥‥ 」
「もう二度と、伯爵様の悪口は言わないから! 約束する 」
謝る兵士の喉(のど)からナイフを放(はな)したエルリュインは、忌々(いまいま)しげに鼻を鳴らすと、ダヴィドとともにその場を立ち去った。
残された兵士達は気味が悪そうに顔を顰(しか)め、エルリュイン達の後ろ姿を無言で見詰めていた。
ドラゴン退治の旅で生き残った23人の兵士達は、出発した時とは違う人間になっていた。
まず、彼らは酒を飲まなかった。
それは、彼らが毒で苦しんだからだけではない。
もし、ロベールのタメに戦わなければならなくなった時、酒で意識が朦朧(もうろう)としていたのでは、差し障(さわ)りがあると考えたからだ。
それで、彼らは禁酒の誓(ちか)いを立てたのである。
娯楽の少ないこの世界では、酒は大いなる楽しみであった。男なら、歳(とし)の十四や十五ともなれば、いっぱしの酒飲みとなる時代である。にもかかわらず、その大切な娯楽を断(た)とうというのは、彼らに並々ならぬ決意がなければできない事であった。
彼らの心には、『後ろめたさ』が巨大な重しのようにのしかかっていた。
『ドラゴン退治の御一行様』という事で、人々から多くの賞賛を受ければ受けるほど、彼らの重しは増していった。
さもありなん。実際にドラゴンを倒したのは頼純一人だけなワケだし、自分達は騙(だま)されて毒を飲み、意識のないまま眠っていたにすぎないのだ。
―――あまりにも間抜けすぎる。彼らは心の底から恥ずかしかった。
それなのに、周囲からは妙に持ち上げられ、それを否定する事も出来ないのである。
それゆえに、彼らは自分達のプライドを守るタメ、『行かなかった者達とは違う』として、他者に対して必要以上に武張(ぶば)るのである。
もちろん、頼純に対して、嫉妬(しっと)やねたみなどあろうはずもない。
あれほどのドラゴンを倒した頼純を、間近に知る者達である。途切れ途切れの意識の中だが、その戦いを見ていた者もいた。
だから、他の者らよりも彼らの方が、はるかに頼純を英雄視していたのだ。それは、神に対する畏敬(いけい)の念に近いほどの尊敬であった。
一方で、ロベールに対しては、それ以上の心のつながりを感じていた。
命を救ってもらった恩義だけでなく、さらに大きな愛を感じていたのだ。それは、主従(しゅじゅう)関係における『忠誠』というよりも、母親に対する『盲目(もうもく)的愛』に近い感情であった。
また、死をともにした事で互いの仲間意識も強かった。それが逆に、『行かなかった者達』に対して、排他的になってしまう原因にもなっていた。
こうした彼らの思いは、やがてロベールへの『歪んだ忠誠心』へと発展しつつあった。
そんな彼らの中でも最も忠誠心が高かったのが、ロベールの近習(きんじゅう)であるエルリュインであった。
25歳の彼は、ロベールの山賊襲撃事件の際に亡くなった警備隊長ジャックの息子である。伯爵の命を守るために死んだジャックへの恩賞(おんしょう)として、息子である彼は新米騎士に取り立てられたのだ。もちろん、まだ貴族ではない。
貴族となるためには、必ず騎士(シュヴァリエ)の称号(しょうごう)を持たねばならなかったが、騎士(シュヴァリエ)だからと言ってそのすべてが貴族になれるワケではなかった。
エルリュインは、今回の旅からロベールの身の回りの世話をする近習(きんじゅう)に任じられたのだ。
そしてこの旅でも、彼は父と同じように、ロベールの命を狙う者によって死にかけたのである。
その事が、彼に大きな思い込みを生(しょう)じさせていた。
『我が一族は、伯爵様およびそのご子孫のために死ぬ栄誉(えいよ)を神から与えられている』―――それが自分の運命だと信じ込んでしまったのである。
その強い思いは、イエス・キリストに殉(じゅん)じた聖エチエンヌらとなんら変わりはなかった。
エルリュインは、ロベールの命令なら、火の中でも水の中でも飛び込むだろう。たとえ教会の教えを破ろうとも、ロベールの命令を遂行(すいこう)するに違いなかった。
この怒濤(どとう)の20日間は、このような若者にも、それほどの覚悟を抱(いだ)かせる、波乱に満ちた冒険であったのだ。
夜も更(ふ)けてくると、人々からずっと賞賛を浴び続けた頼純は、かなり疲れてきた。彼は酒の入った木のコップを手に、人混みを避(さ)けて城の塀につけられた回廊(かいろう)に昇り、ひとり星を見上げていた、
「いたいた! もう‥ 探しちゃったよん♡ 」
声を掛けてきたのはジョルジュ伯であった。
「俺‥ 明日、ルーアンに戻るから! 」
「へえ‥ さっそく、リシャール大公にご報告かい? 」
「うん! おそらくは、近日中に大公様からの呼び出しがあると思う。 ロベール伯は『ドラゴンの頭』と『胴体の皮』を持って、公都(こうと)ルーアンに行くと思うけど‥ できれば、アンタも来て欲しいな 」
頼純は苦笑いで答えた。
「ああ‥ 考えとくわ。 けど、これでオメーもお役御免だな。 もう、俺にまとわりつく必要もなくなったワケだ 」
「え!? まとわりつくって? 」
「だから‥ 俺の事を探るために、友達になりたいなんてウソをついて近づかなくてもよくなったって事さ 」
いつもヘラヘラしているジョルジュ伯がスッと真顔になった。
「はあ!? なんで、アンタと友達になりたいって言ったコトがウソになるワケ? そりゃ、ホントでしょう! そんなコト言われたら、ボクもちょっと怒っちゃうよ 」
「‥‥‥ 」
「俺はアンタの事が気に入った! だから、友達になりたいって言ったんだ。 それのどこが悪いの!? 」
ストレートなジョルジュの物言いに、頼純は若干の照れくささも手伝って、口を尖らせ反論しようとした。
「い‥ いや‥ 悪いとは言ってネーけどさァ‥ けど、オメーが俺を気に入るタイミングってなかっただろう! 」
「それは‥ アンタが厳重に縛られて、館の広間に連れて来られた時さ! 」
ジョルジュ伯はあっさりと答えた。
「え!? そんな早い段階‥? 」
驚く頼純に、ジョルジュ伯はしたり顔で頷(うなず)いた。
「普通なら泣いてひれ伏すような状況なのに、アンタは恐れる素振(そぶ)りをいっさい見せなかった。 それどころか、圧倒的に不利な場面で、アンタは大公様に喧嘩まで売ってみせたんだ。 俺はアンタが、よほどの愚か者か、喧嘩(けんか)っ早いバカか―――そのどちらかだと思ったね 」
「いや‥ アレは―――」
口ごもる頼純の目をジョルジュは覗(のぞ)き込む。
「けど、アンタの目を見て判ったよ―――それが怒りにまかせての事じゃないって! アンタの目はいたって冷静だった。 怒ったフリをしていただけなんだ。 大公様に噛(か)み付いたのは、蛮勇(ばんゆう)からでも、喧嘩好きだからでもない。 すべて計算ずくの事さ。 どうしたら、この危機から脱出できるのかってネ! 」
見破られた頼純は、悪態をついて誤魔化(ごまか)そうとする。
「け‥ 計算ずくってよォ―――オメー、人聞きの悪(わり)ィコト言いやがんなァ。 馬鹿のクセしやがって、ナニが目を見て判っただよ! 笑わすんじゃネーぞ! 」
「まァた、馬鹿とか言っちゃってェ! 何度も言うけど―――俺、こう見えても貴族ですから! ちゃんと教育も受けてるし、人を見る目も教わってんですゥ。 だから、大公様も俺を間者(かんじゃ)として送り込んだんでしょ!? 」
「ま‥ まあ‥ そりゃ、そうだけどよォ‥ 」
頼純はさらに言い訳しようとする。
「けど‥ あの時だって、オズバーン伯に三日三晩引きずり回されて、俺の体はボロボロだったんだぜ。 なのに、あんな百戦錬磨(れんま)の巨兵と―――しかも、二人と戦うなんて言い出したんだ。 そんなモン、どう考えたって、ムチャクチャだろう!? 頭がおかしいと思わネーのか!? 計算してたってーのは、俺を買いかぶりすぎなんだって! 」
頼純は賢いと思われる事を避(さ)けているようだった。蛮勇(ばんゆう)の輩(やから)と思われていた方が相手に警戒されず、都合がよいからであろう。
だが、ジョルジュ伯も持論を譲(ゆず)らない。
「いいや‥ アンタにはアンドレ兄弟に勝つ絶対の自信があったんだ。 そして、仲間達が助けに来る事も―――彼らがいつどこに、どういうふうに布陣(ふじん)するのかまで知っていた。 一見、無茶(むちゃ)に思えるアンタの行動は、すべて冷静に計算された上のモノなんだ 」
「‥‥‥ 」
完全に見抜かれてしまった頼純は、返す言葉がなかった。
「まあ‥ あんなドラゴンを前にして、逃げ出さずに戦おうって考えるような人ですからねェ。 そりゃあ、ちょいと頭がおかしいってーのも、事実なんだろうけどォ―――♡ 」
からかうようなジョルジュ伯に、頼純は舌打ちをした。
「テメー‥ 上げたり、下げたりしてんじゃネーよ! 」
「けど‥ そこが、メチャクチャかっこいいと思ったんじゃん。 だから、俺はアンタに惚れたの。 友達になりたいって思ったんだよ! それはホント、信じてよ! 」
ジョルジュ伯は急に猫なで声になって、
「だからさァ‥ 俺と友達になってェん! お願い♡ 」
頼純は意地悪な顔をして、ジョルジュの申し入れを拒否する。
「やなこったい! それとこれとは話が別だ! 」
だが、ジョルジュもしつこく食い下がる。
「そんなコト言わないでさ‥ 友達になってよん 」
「ならネーよ! ならねェって何度も言っただろう! 」
すがりつくようなジョルジュをすげなく振り払う頼純。その様は、二人がふざけあっているようにさえ見えた。
そこへ、回廊(かいろう)を昇(のぼ)ってきたロベールが声を掛けてくる。
「ジョルジュ伯、大丈夫ですよ! 我々は、もうすでに友達なんですから 」
「はあ!? 」
頼純がしかめっ面をロベールに向けた。
だが、ロベールはニッコリとほほ笑んで続けた。
「だってそうでしょう!? ワタシ達は全員、死ぬような思いで20日間も旅をともにしたんですよ。 その中で、ワタシ達には共通の思いができあがったハズです。 だったら、ワタシ達はすでに仲間でしょう!? 友達なんですよ!」
我が意を得たりとばかりに、ジョルジュ伯は目を輝かせた。
「そっかァ‥! そうだよね、俺達はもう友達なんだ! なんだよォ‥ 仲間じゃん! 」
ジョルジュ伯に肩をポンと叩かれた頼純は、
「え~~~え! もう‥ じゃあ、そういうコトにしといてもいいや‥ 」
と、面倒臭そうに頷(うなず)いた。しかし、彼の心の中では、それはまんざらでもなかったのだ。
次の日の朝、ジョルジュ伯は足取りも軽く、ルーアンへと戻っていった。
祝宴(しゅくえん)はさらに続いていたが、その間にも、ロベールは一行を苦しめた毒入りリンゴ酒(シードル)について調べさせていた。
だが、ついにその出所(でどころ)はつかめなかった。
リンゴ酒を運んできた農夫のアルノーはすでに死亡しており、依頼をしたとされた村長も、そんな話はまったく知らなかったからである。
ただ、何者かが暗躍(あんやく)し、ロベールの命を狙っているコトだけは間違いなかった。