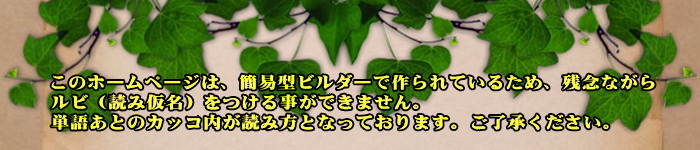
31
1026年 ファレーズ街道
ロベール伯爵一行は、シュザンヌの道案内で『アンデーヌの森』から脱出しようとしていた。
彼女をどこまで信用してよいものか―――いまだ判然としなかったが、彼らにはそれしか生き残る方法がなかったのである。
毒で死にかけていた兵士らも日々回復し、一行の状況は悪くなかった。
ただ、巨大な『ドラゴンの頭』を乗せた輿(こし)が、彼らの進行速度をやや落としていた。
ワニとの戦いで全身に傷を負(お)った頼純は、出発して3日ほどは担架(たんか)に乗せられて運ばれていた。兵士全員が代わる代わる4人態勢で担(かつ)いでくれたのだ。
『ドラゴンの頭』を乗せた輿(こし)とその『巨大な皮』を運ぶ輿(こし)、そして頼純を乗せた担架(たんか)である。病み上がりの兵士達にとって、それはかなりの重労働であっただろう。だが、それに文句を言う者は誰もいなかった。むしろ、嬉々(きき)としてその苦役(くえき)をこなしていた。
彼らにとって頼純は『勇者』であり、その世話をする事は名誉な事であったからだ。また、退治したドラゴンを運ぶ事も、彼らにだけ許された特権なのである。
それゆえに、兵士達は率先(そっせん)して、頼純や『ドラゴンの頭』を担(かつ)いだのであった。
それでも、頼純は4日目には担架(たんか)を下(お)り、自分の足で歩くようにした。杖をつきながらではあったが、歩けるまでに回復していたのだ。
その驚くべき治癒(ちゆ)力は、頼純の体力によるモノというよりも、シュザンヌの治療の功績(こうせき)が大きいと思われた。
頼純は、あばら骨が3本折れ、左の二の腕の骨にもヒビが入っていた。
擦(す)り傷、切り傷、打撲傷(だぼくしょう)は全身に数限りなくあった。
シュザンヌはそれらひとつひとつの傷に、症状にあわせてそれぞれ違う薬草を磨(す)り潰し、丹念(たんねん)に塗(ぬ)り込んでくれたのだ。そのせいで、頼純の全身は、様々な緑色でまだらに染まるほどであった。
さらに、毎日数種類の薬湯(やくとう)も飲まされた。
彼女は薬草について、町の医者などよりもはるかに多くの知識を持っていたのだ。
また、理髪師よりもずっと上手(うま)く傷口を縫(ぬ)い合わせる事が出来た。
当時のヨーロッパ世界では、キリスト教会が『血』を嫌ったため、外科は『汚(けが)らわしく、野蛮な行為』として蔑(さげす)まれていた。それゆえ、外科的処置は、医者ではなく、理髪師が行っていたのだ。その処置も、傷の外側を糸で縫(ぬ)い合わせる程度の事にすぎなかった。
さらにシュザンヌは、骨折などの治療に見た事もない処置を施(ほどこ)した。
左腕の骨折は、腕に棒を二本添(そ)えて布で縛り上げ、動かないように固定した。肋骨(ろっこつ)の骨折にも、7枚の板で胴体を囲み、それを布で縛り上げて動かないようにした。板は水汲(く)み用に持って来た桶(おけ)をバラしたモノである。
ただ、なぜそれほどまでに、シュザンヌが頼純の治療に熱心であったのかは謎であった。彼女もドラゴンを倒した頼純を英雄視していたのかもしれない。
彼女は、手当の間もけっして顔を見せないよう、頭巾を深く被(かぶ)っていた。だが、頼純は薬を塗る彼女の手を見てある事に気づいていた。
4日目の夕食も、ドラゴンの肉の燻製を火で炙(あぶ)ったモノだけだった。
一行は、脱出前から毎日三食この肉しか食べていなかった。もう6日目になる。
全員が、ドラゴンの肉にはもううんざりしていたが、それでも文句をいう者はほとんどいなかった。あと少しで森を抜けられると信じていたからである。
森さえ抜けてしまえば、人里があり、温かいパンや野菜たっぷりのポタージュ、油の滴(したた)る厚切りのベーコンも食べられるはずだった。
みんなその事に胸を膨(ふく)らませ、ドラゴンの肉を無心に囓(かじ)っていた。
頼純も緑色の体に着物を羽織(はお)ると、焚(た)き火の前でワニ肉を食べていた。全身の痛みはほぼ取れ、食欲もかなりある。体調が元に戻りつつある証拠であった。
そんな頼純の元へジョルジュがやって来た。
「ヨリちゃん‥ 調子はどうよ? 」
頼純は苦笑いで答えた。
「悪くない。 婆さんの薬が効(き)いているようだ 」
「そっか‥ よかった! 実はね――― 」
ジョルジュ伯はいつもと違い、神妙(しんみょう)な顔で頼純に告(つ)げた。
「この森も、明日か明後日(あさって)には抜けられると思うんだよね。 それでも、ファレーズに戻るまでには、途中の村で一泊か二泊はしなきゃならないワケじゃん。 そして、そこの村人達はその時はじめて、本物のドラゴンを見るコトになるんだ! 」
「‥‥‥」
「みんな、最初はパニックだよネ!? そして次に、そのドラゴンは誰が倒したのかって話になる。 その時から、ヨリちゃんは『勇者』になっちゃうんだ! 世間はアンタを崇(あが)め奉(たてまつ)るに違いない。 必ず、道中は大騒ぎになるだろう。 だから、今の内から心の準備をしておいた方がいいと思う! 」
「う‥ うん‥ 」
頼純はジョルジュをポカンとした顔で眺めていた。
「ナニ? 」
「いや‥ オメーでも、まともな話ができるんだなァと思ってさ――― 」
その言葉にジョルジュ伯はムッとした顔を返した。
「おいおい‥ 俺は貴族なんだぜ! それなりの教育は受けてるし、お偉いさんと話す事だってあるんだ。 そこいらのバカと一緒にすんなよ! 」
「はいはい‥ 判った、判った 」
彼に知性がある事を納得していない頼純に、ジョルジュ伯は
「だからさァ‥ ホント、お願いしますよォ‥ 」
と、げんなりした顔でつぶやいた。
それを無視して、頼純はワニ肉を囓(かじ)る兵士達に視線を送ると、面倒くさそうに顔を顰(しか)めた。
「けどさァ‥ アレはドラゴンなんかじゃなくて、アジアに住むワニってー動物なんだけどねェ‥。 コイツらにもさんざん説明したけど、誰も信じちゃくれネーし―――世間の人達も同じように、ドラゴンだって大騒ぎするんだろうなァ‥!? 」
「そうだよ‥! だって、人々にとってドラゴンはドラゴンじゃん! あの頭は、間違いなく『ドラゴンの頭』なのだ 」
「う~~~ん‥ 」
頼純は視線を落とすと、しばし燻製肉を奥歯で弄(もてあそ)んだ。そして、ふいにジョルジュに顔を向け、尋(たず)ねたのだ。
「でェ‥ オメーはその事を、リシャール公爵になんて報告するつもりだい? 」
「え!? な‥ 何のコト? 」
ジョルジュはとぼけようとした。だが、その顔は引きつっている。
頼純はそんなジョルジュにまくし立てた。
「しらばっくれてんじゃネーよ! オメーがリシャール大公から命じられて、俺達の様子を探りにきた間者(かんじゃ)だってェコトぐらい、こちとら先刻(せんこく)ご承知なんだよ! 素直に白状しやがれ! 」
「や‥ やっぱりバレてた? 」
愛想笑いで頭を掻(か)くジョルジュに、頼純は勝ち誇ったように語った。
「あったりめェだ! 伯爵の位(くらい)を持つオメーが、供(とも)も連れずにこんな道中(どうちゅう)についてくる事自体、おかしいだろうが! だとすれば、誰かに命じられたに違(ちげ)えねェ。 そして、アンタに命じる事が出来る者といえば、リシャール大公か、オズバーン伯ぐらいしかいネーじゃねェか! 」
「ご名答! いつから気づいてた? 」
「ファレーズ城で巨兵兄弟と戦った時だよ! みょうになれなれしく近づいてきて、おかしいと思ってたんだ。 アレもすべて、リシャールの差し金なんだろうが!? 」
ジョルジュは両手で頼純を指差した。
「さすがヨリちゃん! なんでもお見通しィ~~~い♡ 」
そのふざけた態度に頼純はイラッとくる。
「テメー、ブッ殺すぞ! 」
次の日も、シュザンヌを先頭に、ロベール達は暗い森の中をひたすら歩き続けた。
そして昼を少し過ぎた頃、一行は突如、明るい日差しに充ち満ちた野原へと抜けたのだった。
やっと、『アンデーヌの森』から脱出できたのである。それは魔法にでもかかっているかのような、唐突(とうとつ)な感じであった。
一行に歓喜(かんき)の声が上がった。
森へ迷い込んで、2週間以上が経っていた。不安と空腹の日々がやっと終わったのである。
身分の隔(へだ)たりなく、誰もが抱き合って脱出を喜んだ。

シュザンヌはいつの間にか消えていた。
ロベールも頼純も彼女に感謝の言葉を告(つ)げたかった。一行の命を救った真の功労者(こうろうしゃ)はシュザンヌだったからである。しかし、それはかなわなかった。
ただ、何の根拠(こんきょ)もなかったが、頼純は彼女と再び出会うような気がしていた。
ジョルジュ伯の予想通り、最初の村に辿(たど)り着いた時、村人達はその巨大な『ドラゴンの頭部』を見て、腰を抜かした。
対応に出た村長は驚きのあまり物陰に隠れ、しばらく出てこなかった。やがて、村人達に背中を押され、及(およ)び腰で現れた村長は震える声でロベールに尋(たず)ねた。
「こ‥ このようなモノは初めて見ました‥! これが『ドラゴンの頭』ですか‥? 」
「ええ‥ そうなんです‥! 」
おっかなびっくり『ドラゴンの頭』に近づいた村長は、アングリと口を開けたまま、色々な角度からその頭を眺めていた。次第になれてきたのか、ふむふむと納得顔を作った。
「これまであの森に迷い込んだ者で、戻ってきた者はほとんどおりませんでした。 その多くが、このドラゴンに喰(く)われていたのでしょう。 そのような悪魔の使いを退治してくださった事を心より感謝いたします。 お礼と言っては失礼ですが‥ お望みの事があれば、なんでもおっしゃってください 」
「では、お言葉に甘えて‥ 」
ロベールはニッコリした顔で自分達の願いを伝えた。
「ありったけの材料で、我々にたくさんの料理を振る舞ってください。 そして、よく乾燥した藁(わら)をたっぷり敷いた寝台を人数分用意していただけませんか。 もちろん、料金はお支払いいたします。 どうか、願いをお聞き入れください 」
「そのような事、お安い御用でございます 」
なにせ、彼らはドラゴンを倒した英雄である。
村長は自分の村はもちろんの事、近在(きんざい)の村々にも声を掛けて食材を集め、村の女達が総出で料理を作った。
兵士達は久しぶりに食べる、温かく美味(おい)しい料理に感動し、涙を流す者さえいた。それは、何人も死んだ者達がいる中、自分が生き残れた事に対する喜びであり、神への感謝でもあったのだ。
みな、腹がはち切れそうになるまで、食事をたっぷりと楽しんだ。
しかし、何樽(たる)も用意されたリンゴ酒に手をつける者はいなかった。さすがに、あのひどい腹痛と下痢を思い出すと、恐ろしくてとても飲む気にはなれなかったのだろう。
一行はその夜、ふかふかの寝台でゆっくり手足を伸ばし、温かい毛布にくるまってグッスリと眠る事が出来たのだった。
次の日は朝から、噂を聞きつけた近在(きんざい)の人々が『ドラゴンの頭』を一目見ようと押し寄せ、一行の周囲は黒山の人だかりとなった。
頼純は、自分と伯爵の二人でドラゴンを倒したと公言(こうげん)したので、ロベール伯の元にも多くの野次馬が集まり、その話を聞きたがった。
頼純としては、ウソをついているつもりはない。
ワニが出現した時、真っ先に音を鳴らして注意を引きつけたのはロベールであったし、ワニの攻撃で何度も気を失い掛けた頼純に繰り返し声を掛けてくれたのも彼であった。
ロベールの存在がなかったら、自分は喰(く)われていたに違いない―――頼純は純粋にそう思っていたのである。
話し下手な頼純は、興味津々(しんしん)の人々をロベールに任せた。
一方、ロベールは、ドラゴンを倒したのは頼純だと考えていたので、それに沿(そ)って彼の活躍を語って聞かせた。
「始まりは、わたくしとわたくしの恋人が山賊に襲われたところまで遡(さかのぼ)ります――― 」
話は少々長くなったが、ロベールは頼純との出会いから、巨兵兄弟との戦い‥ そしてドラゴンを倒すところまで、みなが興味を持つように語って聞かせた。
意外にもロベールは話し上手で、人々は目を輝かせ、『ドラゴンの頭』と伯爵を見比べながら、その話に聞き入った。
娯楽に飢えた人々にとって、これほどワクワクする話を聞くのは久しぶりであった。
さらに、普段なら声を聞くどころか、その姿さえ見る事を許されない伯爵様が、気安く自分達に語り掛けてくれるのである。その喜びは大きかった。
人々は伯爵一行に供物(くもつ)を献上(けんじょう)し、神へ感謝の祈りを捧(ささ)げた。
その噂はまたたく間に拡がり、次に宿泊する村に着くともっと人が集まってしまった。
翌日は、さらに大量の人々がロベールの話を聞こうと、一行の後をついてきた。その数は千人を超え、大行列となってファレーズへ到着したのだった。
ロベール達がドラゴン退治のタメにファレーズを出発して、ちょうど20日目―――彼らはふたたびこの街へと戻って来た。
ファレーズにもすでにドラゴン退治の噂は伝わっており、すべての領民は沿道に列をなし、一行の頭上に花びらをまいた。そして、大いなる祝福とともにその帰還(きかん)を喜んだのだ。
多くの人々に囲まれたロベールは馬を下(お)り、徒歩でファレーズの街へと入ってきた。
人々が必要以上に伯爵に詰め寄らぬよう、沿道は城の兵士達によって警備されていた。
その警備の目をかいくぐって、一行へと走り込んでくる者がいる―――エルレヴァであった。
彼女は勢いよくロベールに抱きつき、その赤い唇を彼の唇にギュッと押しつけた。
衆人環視(しゅうじんかんし)の中、二人は熱烈なキスを交(か)わしたのである。
「アナタ様はわたくしが想像していたよりも、はるかに偉大な人物でした。 アナタ様の事を過小評価したわたくしをどうかお許しください 」
唇を離したエルレヴァは嬉(うれ)しそうに謝罪した。
ロベールははにかんだ顔でそれに返した。
「いや‥ すべては、君の忠告とヨリ殿の働きのお陰だ! 二人には大いに感謝している 」
その時、どこからともなく現れたティボーが、エルレヴァの腕を掴(つか)みロベールから引き離すと、代わりに彼に抱きついた。
「おお、若‥ 若、よくぞご無事で! しかも、このような大手柄(おおてがら)‥ じいは嬉(うれ)しゅうございます 」
彼は恭(うやうや)しくロベールにそう言いながら、人前で抱き合う事は許さんとばかりに、兵達を使ってエルレヴァを連れて行かせようとした。
その時、ロベールが厳(きび)しい声を発した。
「無礼者! その手を放せい。 彼女は我が子を身籠(みご)もっておるのだぞ。 ノルマンディー公家の血を引く貴族の母である。 気安く触るでない! 」
「はは―――あ! 」
怒鳴られた兵達は慌(あわ)ててエルレヴァの手を放し、片膝(ひざ)を立てて跪(ひざまづ)くと、ロベールに深々と頭(こうべ)を垂(た)れた。
いつもの優柔不断さを微塵(みじん)も感じさせないロベールに、ティボーは戸惑いながらも彼を諫(いさ)めようとした。
「まあまあ、若‥ その話はまた後日ということで――― 」
だがロベールはティボーにもキッパリと言い放(はな)った。
「黙れッ! このワタシに指図(さしず)するでない。 彼女を敬(うやま)うのだ! 」
今度は周囲の領民達に向かって吼(ほ)えた。
「皆の衆も、心せよ! わが内縁の妻であるエルレヴァに敬意を払うのじゃ! 」
その言葉に領民達は沈黙し、しばしポカンとなった。
だが、意地悪げな笑(え)みを浮かべたティボーが、ロベールの耳元で囁(ささや)く。
「若‥ そのような事を申されるのなら、兄上にご報告させていただきますぞ♡ 」
いつもなら、ティボーからちょっと脅(おど)されるとすぐに困った顔をしていたロベールも、その日は一切屈(くっ)しなかった。
「好きにせい。 お前がワタシではなく、兄上の家臣として勤(つと)めを果たしたいと思うのなら止(と)めはせん。 だが、その時はこの城から出て行ってもらうぞ。 ルーアンに戻るがよい 」
「い‥ いや‥ それは‥ 」
逆にティボーが脅(おど)され、言葉を詰まらせた。
その変わりように、ティボーのみならず、領民達も驚いていた。
そして、それはやがて歓喜(かんき)の声へと変わったのだった。
ロベールの兵達への献身(けんしん)は、噂としてすでに知れ渡っており、その身分の隔(へだ)たりなく人々に接する彼の態度は、ほとんどの領民から好感を持たれていた。
その彼が身分低き革なめし職人(ペルティエ)の娘と恋をしているという事は、むしろ好事(こうじ)として迎(むか)えられたのだった。
そして、そんなロベールの変わりように一番驚いていたのが、他(ほか)ならぬエルレヴァであった。