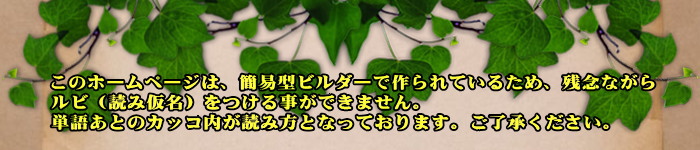
8
1023年 カラコルム山脈
「うう‥ ううう‥ 」
目映(まばゆ)い日の光を浴び、頼純は意識を取り戻した。
体の節々(ふしぶし)が痛い。切られたところも数カ所あるようだ。しかし何と言っても、こめかみに締め付けるような激痛がある。頭を金槌(ハンマー)でガンガンと殴られているようだった。
そんな頼純の顔を覗き込む者がいた―――ロレンツォである。
彼はげんなりした顔で、寝台に横たわった頼純に何かを語り掛けてきた。
傍(かたわ)らのアハメッドがソグド語でそれを通訳する。
「警備隊に死んだ者は一人もいない。 だが、腕を折られたり、足を折られたり、顎(あご)の骨が砕かれた者から背骨をやられた者―――全員が負傷している。 もはや、我が隊商の警備隊は壊滅(かいめつ)状態だ。 隊長を始め警備隊すべてを雇い直すまで、旅は続けられなくなったんだ。 お前は、この責任をどうとるつもりだ? 命を助けてやった恩人に、何という仕打ちをするんだ 」
頼純はその問いに答えず、弱々しい声で尋ねた。
「サミーラは‥ サミーラは無事か? 」
その時、もう一人が寝台に駆け寄り、頼純の手を握り締めた。
「はい。 ここにおります 」
サミーラだった。彼女は何度も何度も手を握り締め、ほほえみながら涙を流していた。
「ありがとう‥ ありがとうございます。 ヨリ様のお力で、ワタシは無事でございます 」
「そうか‥ よかった‥ 」
頼純はポツリと呟(つぶや)いた。
苛(いら)立った表情でサミーラを睨(にら)むロレンツォの話を、アハメッドは淡々と通訳した。
「この女奴隷は高貴の出身で、しかもまだ処女だ。 どこへ行っても高く売れる―――そう思って買ったのだが、こんな事になるなんて‥‥ 大失敗だったよ 」
ロレンツォはふたたび頼純に顔を向けるとまくし立てた。それをアハメッドが訳していく。
「そもそも、奴隷は売り買いされる商品だぞ。 彼女の処女はその特典にすぎない。 そしてそれは、この女を買った私のモノ、彼女のモノではないのだ。 もし、ミーカーイールが有り金をはたいてこの女を買ったのなら、その特典も新しい所有者に移動する。 誰も文句は言えなかったハズだ。 そんなコトにどうしてお前は命を賭けた? 愚(おろ)かとしか言いようがない 」
一瞬の間を置いて、ロレンツォとアハメッドはしまったという顔になった。
本当の雇い主が誰であるのかをバラしてしまうような物言いだったからである。
サミーラに手伝ってもらい、上半身を起こした頼純は、ロレンツォ達に薄ら笑いを返す。
「色が白い方―――ロレンツォとか言ったっけ? 奴隷のアンタが本当の雇い主だって事は知ってる。 このサミーラから聞いたからな 」
「サ‥ サミーラから? 」
ロレンツォは、なぜだと言わんばかりに顔を曇(くも)らせた。自分が雇い主である事は誰も気づいていないハズ―――そう信じていたからだ。
頼純はそんなロレンツォの目を見詰めて、キッパリと言い放った。
「俺は彼女に命を救われた。 だから、何があっても彼女にその恩を返さなきゃならない。 それが今回はたまたま、操(みさお)を守るって事になったダケさ。 そしてそのタメになら、俺は死をも厭(いと)わない。 たとえ自分が死んだとしても、それで恩が返せたのなら本望だ。 それが俺の生き方であり、哲学だ 」
ロレンツォが怒りをぶちまける。
「だったら、私も救ってくれよ。 お前を救ったのはこの私だぞ! 彼女は私の命令で世話をしただけ。 ならば、私にも恩を返してもらう権利があるハズだ 」
その言葉に頼純は、ああ、なるほど‥と思った。たしかに、恩義(おんぎ)の量はロレンツォの方が大きい。
「うむ‥ 」
頼純は唸(うな)ると、腕を組みしばし思案した。
やがて、名案が浮かんだとばかりに、その笑顔をロレンツォに向ける。
「よし! だったら、この俺を雇(やと)えばいい! 俺が警備をしてやるよ! 」
ロレンツォは、頼純の言葉の意味がわからず、眉を顰(ひそ)めた。
「え? 奴隷のお前を―――? 」
それに対し、頼純は得意げな顔で答えた。
「そうだよ。 俺の腕前は判ってるはずだ。 アンタの警備隊をたった一人でぶっ潰せるほどの腕前さ。 けど、給料はミーカーイールと同じでいいや。 だったら、お買い得だろ? 」
だが、ロレンツォは呆れ顔で、その申し出を一蹴(いっしゅう)する。
「いやいやいや‥ なんで、奴隷のお前に給料を払わなきゃならないんだよ? 」
途端に頼純は、これまで見せたことのない凶暴な表情になる。先ほどまで疲労困憊(ひろうこんぱい)し、気を失っていた人物と同一には見えないほどである。
「おいおい‥ いつ、俺がテメーの奴隷になるって言った。 テメーが勝手に決めたダケだろう。 そんなモン、俺の知ったコッチャねェわ! 」
「け‥ けど‥ 」
事態を根底からひっくり返す頼純に、ロレンツォは返す言葉がなかった。
頼純は眠たそうに目を細めた。その目はあきらかにロレンツォを恫喝(どうかつ)していた。
「ほ~~~う‥ じゃあ、テメーは―――『力』ある者は『力』無き者を屈服させてもいいって‥ そう信じてるワケかい? 」
「う‥ うん、まあねェ‥ 普通、そうなんじゃないの? 」
「じゃあ、聞くが‥ テメーがいま持ってる『力』ってなんだ? 金か? それぐらいしかネーだろう。 けど、そんなモンがこの砂漠のど真ん中で『力』になるとでも思ってんのかい? 」
「あ‥ 」
ロレンツォは思わず絶句してしまった。
『力』とは、『金』と『暴力』と『権力』によって構成される。そしてこのような辺境(へんきょう)の地において、もっとも重要なのは『暴力』なのである。
だが、ロレンツォはその『暴力』機構を昨晩失ってしまった。
頼純はあせった顔のロレンツォとアハメッドを、意地悪な微笑(えみ)で交互に覗(のぞ)き込んだ。
「だったら、いまは俺の方が『力』はあるぜ! いくら体が弱り切ってたってテメーらぐらいなら、あっという間にぶっ倒してやる。 んなモン、朝飯前さ 」
頼純の笑顔に殺意が色濃くにじみ出す。
「テメーを本当の奴隷にしてやろうか♡ 」
「‥‥ 」
この男はやりかねない―――そう思ったロレンツォとアハメッドは完全に言葉を失ってしまった。
なんという胆力(たんりょく)であろうか。先ほどまで呻(うめ)き声を上げ、水を飲ませてもらっていた男が、いまは自分達を脅迫している。しかも、それは成功しているのである。
両者の立場は完全に逆転していた。ロレンツォはもはや、下手(したて)に出るしかなかった。
しかしその一方で、この男が素直で真っ直ぐな人物である事にも気づいていた。
数々の難(むずか)しい局面で、商談を自分に有利に成立させてきたロレンツォである。まだ事態をひっくり返すことは可能であると考えていた。
「ちょ‥ ちょっと、待ってよ。 話を戻そうよ。 私はアンタの命の恩人じゃないのか。 そしてその恩は、死んでも返すって言ってたじゃないか。 なのに、この私を奴隷にするって―――そんなひどい話はないだろう 」
頼純は天井に目をやるとフムフムと頷(うなず)く。
「ああ‥ そっかァ‥ そうだったよねェ‥ 」
「いやいや‥ 『そうだったよね』じゃなくてさ――― 」
やはり、彼の思惑どおり、頼純はかなり単純な男であるようだ。
そんなロレンツォを頼純は満面の笑みで覗き込む。
「じゃあ‥ やっぱり、警備隊長って事でいいや。 部下も4、5人ほど雇(やと)ってくれたらいいからさ。 それって、逆に安上がりじゃない? 」
手のひらを返すようなその態度にロレンツォは呆れるばかりである。
頼純はなれなれしい笑顔を作った。
「ね♡ 」
少々、悔しい気もしたが、この男もそう悪い人間ではなさそうだし、なによりロレンツォにはそれしか方法がなかった。
「はいはい‥ 判りました。 じゃあ、そうさせていただきますよ。 そうすればいいんでしょ! よろしくお願いいたしまァす 」
ロレンツォは、投げやりな態度で頼純を警備隊長にする事を了解したが、心の中ではこれが悪い取引だとは思っていなかった。
そんな両者のやり取りを、サミーラはクスクス笑いながら聞いていた。
1023年 カラコルム山脈
藤原頼純が警備隊長となったロレンツォの隊商(キャラバーン)は、ヤルカンドの市場(バザール)で四名の武者を雇(やと)うと、六月の下旬に彼(か)の地を出発した。
ロレンツォは渋々ながらも、頼純に太刀(たち)を返していた。
一行は、カラコルム山脈を目指して、砂漠地帯を南へと進んでいく。しだいに彼らの視界には、万年雪を冠(かん)した山々が一杯に広がっていった。この美しい連山が、彼らの旅の最大の難所なのだ。
タクラマカン砂漠の西縁(せいへん)へ辿(たど)り着くと、すぐに石ころだらけの山道へと入る。砂漠地帯よりもさらに植物の少ない不毛な山道は、やがて断崖絶壁(だんがいぜっぺき)の隘路(あいろ)となる。
切り立った山肌からの落石も多く、数十丈(当時の1丈=10尺=2メートル96センチ=約3メートル 数十丈は100~200メートルぐらい)上で転がった小さな石ころが、やがて大量の岩石となって降り注ぐ事も日常茶飯事であった。
石につまずいて坂を転がれば、手足は簡単に折れ、または奈落の底へと墜落(ついらく)していく。

さらに、山の天候は変わりやすく、夜と昼の寒暖差も激しかった。
突然の雨でずぶ濡れになったあと、着替えずに夜を迎えようものなら、夏とはいえど間違いなく凍死するのだ。
やがて隘路(あいろ)は広い渓谷(けいこく)となり、川に沿って進めるようになった。
このあたりまで進むと、標高はかなり高くなっている。呼吸が苦しくなり、高山病になる者が続出した。ロレンツォや頼純も何度か激しい頭痛や吐き気、めまいに襲われた。放っておけば死ぬ事もある。
そのタメ、山道をいったん戻って低地で体を慣らし、再度前進するという事を繰り返さねばならなかった。
彼らは山越えをしているのではない。山の麓(ふもと)を抜けているに過ぎないのである。
しかし、周囲は『世界の屋根』と呼ばれている高山地帯である。彼らの道程(どうてい)は登山となんら変わらなかった。
また、このような『死の世界』にも山賊はいた。
獣も通らぬ山道で、一行は二度も盗賊の待ち伏せにあったのだ。
しかし、さすがに少人数であったタメ、頼純率いる警備隊によってあっさり蹴散らされた。
警備隊は以前のそれと比べて、ずいぶんと規模が小さくなったにもかかわらず、戦闘力は逆に上がっていた。それは頼純の剣の腕前もあったが、部下達の働きがミーカーイールの時よりも格段によくなっていたからであった。敵に対する位置取りや戦闘方法がまったく違っていたのである。すべてが、頼純の指導力と統率力の賜物(たまもの)であった。
ロレンツォ一行が、渓谷からチョゴリ山(K2の中国名 世界第二位の高山=8611メートル)の絶景を見上げる頃には、笑顔や鼻歌が出るまでに隊商は一体となっていた。
山へ入ると、ロレンツォは自分が本当の雇い主である事を一同に明かした。ここまで来れば、もはやイスラム勢力も手が届かない。奴隷であると嘘をつく必要がなくなったのだ。
しかし、仲間である剛力(ごうりき)達も、ヤルカンドまではロレンツォが奴隷であると信じていたのである。
さあ今からは、自分を主人だと思え、自分を敬え―――と言われても、そう簡単に気持ちを切り替える事はできない。
ところが、頼純はあの隊商宿(キャラバーン・サライ)の夜以来、ロレンツォに対等の口ぶりで話す事はなかった。主従関係とまではいかなかったが、命の恩人として、礼節をもって彼に接していたのだ。
やがて、隊商の全員がロレンツォを敬うようになった。
最も強く、最も頼りになる男が敬意を払う人物だったからである。
× × × × ×
こうして彼らは、4ヶ月もの艱難辛苦(かんなんしんく)の末、山脈の横断を果たし、インドのカシミール地方へと辿(たど)り着いたのだった。
彼らが取ったインドへの侵入方法は、異常であり、危険極(きわ)まりないルートである。
地形の情報をほとんど持たないヴェネツィアの商人が、机上で作った素人計画にすぎない。
しかし、ロレンツォがこのルートにこだわり、奴隷に扮(ふん)してまで―――ある時は鎖につながれ、またある時は檻(おり)の車に乗せられてまで―――旅を続けたのは、ひとえに凶暴なガズナ国のイスラム兵士と遭遇(そうぐう)しないタメであった。
だが、安全だと思っていたカシミールはすでにガズナ国の手に落ちていた。
どの街もイスラム兵士であふれていたのである。
こんな事ならば、素直にカシュガルからカイバル峠へと向かえばよかった。そうすれば、あれほどしんどい思いでカラコルム山脈を越える必要もなかったのに―――ロレンツォは己(おのれ)の情報不足を呪(のろ)いながら、南へと敵中横断をせねばならなかった。
安全地帯までは遥かに遠く、普通に旅をしても最低一ヶ月はかかる道のりである。そこまでたどり着くタメには、無数にある検問所と幾多(いくた)の砦(とりで)を突破し、莫大な数の敵の目をかいくぐらねばならない。となると、三ヶ月以上は必要となる。
そして現実には、三ヶ月以上も無傷で敵陣を逃げ回る事など不可能なのである。
ロレンツォは、『主(しゅ)もついに自分をお見捨てになったのだ』と覚悟した。
その時、『大丈夫! 安心してください』と勇気づけてくれたのは頼純だった。
だが、それは根拠のない励(はげ)ましではない。
頼純には、危機を察知する『嗅覚』と、それを回避する『知恵』‥ さらには、回避できなかった場合に対処する『高い戦闘力』―――それらのすべてを兼(か)ね備えていたからだ。
頼純はまず、最小限の人員を残して隊商を解散させた。
ロレンツォと頼純を除けば、全員がイスラム教徒であり、彼らにはさほどの危険が及ばないからであった。
そして、彼が先頭となって活路(かつろ)を見いだし、また激しい戦いを繰り返しながら一行を南へと導いたのである。それはまさに八面六臂(はちめんろっぴ)の大活躍であった。
頼純の戦いぶりは、鬼神のようであり、また舞踊家のようでもあった。見る者に『美しい』とまで感じさせる動きなのである。
ロレンツォは敵に囲まれながらも、その姿を惚(ほ)れ惚(ぼ)れと眺(なが)めていた。
彼が頼純と出会った時、その刀を強く欲しいと願ったのは、この男がそれを振るう姿が見たかったから‥‥無意識の内にそう願っていたに違いない―――ロレンツォは確信した。
彼が本当に欲しかったのは、この藤原頼純という男だったのだ。
こうして頼純は、命からがらながら、ロレンツォ達を仏教国であるパーラ国のパータリプトラまで脱出させる事に成功したのである。
安全なパーラ国へと入った一行は、緊張を解き、刀傷を癒(いや)すタメに、しばしの休息を取った。
その後、ふたたび旅の体制を整えると、さらに南下を続けた。
そしてついに、目的の地・ガンガ国のカリンガナガラへ到着したのだった。