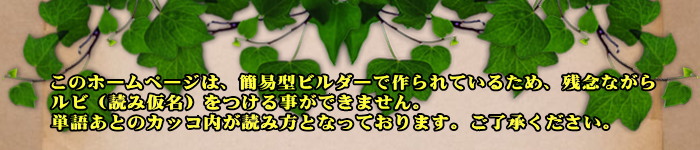
69
1016年 イングランド・ウィンチェスター
ゴドウィンは、クヌート王子が陣を張るイプスイッチから、ウィンチェスターへと馬を走らせていた。きこり時代に、材木を運ぶため馬車を使っていたおかげで、馬の扱(あつか)いはそれなりに馴(な)れていたが、このように早駆(はやが)けしたのは初めての事であった。
元はといえば、妻マーガレット伯爵夫人殺害の嫌疑(けんぎ)から逃(のが)れるため、エマ前王妃についた嘘がはじまりである。ところが、口からスルスルと出てくる言葉(でまかせ)は、しだいに大きな話となり、国運を左右する事態となっていった。
そんな、自分ですら結末の見えない筋書きを、ゴドウィンは大いに楽しんでいた。数年前まで、きこりで殺人鬼だった青年が、いまこのイングランドを動かそうとしているのだ。
ウェセックスには、再起を賭けて兵を募(つの)っていたエドマンド剛勇王(ごうゆうおう)がいた。ゴドウィンはそのイングランド王に会いに行ったのである。
街道のアチコチにはデンマーク軍による関所が設(もう)けられていたが、ゴドウィンはクヌート全軍司令官による通行許可証を手に入れていた。
おかげで、すべての関所で止められる事はなかった。
やがてウィンチェスターに近づくと、今度はイングランド軍が増えてくる。彼らの検問には、エマ前王妃の手紙をみせればよかった。兵士達は封筒につけられた王室の紋章に気づくと、丁重(ていちょう)に道案内さえしてくれるのだった。
ゴドウィンは、途中で立ち寄った農家で、馬から馬車に乗り換え、その荷台に大きな樽(たる)を5つ乗せた。ここでクヌート王子の通行許可証は燃やして捨てる。
この先は完全にイングランド軍の支配地域となるからだ。イングランド兵に身体検査でもされて、デンマークの書類が発見されようものなら、反逆者と見なされ、その場で首を刎(は)ねられる可能性もある。
馬車を走らせたゴドウィンは、やがてウィンチェスターに設(もう)けられたエドマンド王の陣幕(じんまく)にたどり着いた。彼は、警備兵に大金を渡し、エマ前王妃からの手紙を国王に届けるよう頼んだ。
エドマンド王はゴドウィンとの接見をすぐに許可してくれた。いくら不快に思っていようとも、義母からの手紙である。相手の話ぐらいは聞いてやらねばならなかった。
ゴドウィンは、クヌート王子の時と同じように恭(うやうや)しく挨拶(あいさつ)をすると、
「兵を募(つの)るにも、武器を買うにも資金が必要でございましょう。 エドマンド国王陛下のために―――いや、このイングランド王国のために、ぜひともそのお手伝いをさせていただきたいのです 」
ゴドウィンは運んできた大樽(おおだる)のフタを次々と開けていった。中には、鈍(にぶ)い光を放つペニー銀貨がぎっしりと詰まっている。
ウィンチェスター近郊の農家に隠してあった資産の一部である。そこはマーガレット伯爵夫人の農地であった。いまはゴドウィンのものとなったその農家を、彼は隠れ家のひとつとして使っていたのだ。
大量のペニー銀貨を見るなり、国王の目の色が変わった。
「お~~~お‥ これはありがたい。 感謝いたします 」
ゴドウィンの言う通り、この戦争のせいで王家の財政は逼迫(ひっぱく)していた。王にとって、目の前の男の申し出は本当にありがたい事であった。
山と積まれた銀貨はかなりの額であったが、ゴドウィンが持つ全資産からすれば、5分の1にもすぎなかった。
「援助はまだまだいたします。 ただ、その代わりと言ってはなんですが‥ このわたくしを会計の相談役として、陛下の戦争に参加させていただく栄誉(えいよ)を頂戴(ちょうだい)したいのです 」
「相談役―――? 」
「はい‥ わたくしは剣を使った事がないので、兵士として闘う事はできません。 しかしながら、デンマーク軍の非道なる侵略には、もはや我慢がならないのです。 それは我がイングランド国民の総意でございましょう。 ですから、わたくしも国王陛下とともにデンマーク軍と戦わせていただきたい! 後方支援となりましょうが、陛下のお役に立ちたいのです 」
「なるほど‥! さすがの義母(ははうえ)殿も、今回ばかりはわたしに味方しようと考え、あなたを送りつけたというワケだ。 なにせ、このわたしがデンマーク軍に敗れてしまえば、あの人の命だとて危(あや)うくなるのだからな!
」
「ええ‥ エマ様は、それはもう‥ この国の行く末をご心配になっておられます 」
「しかしそのお陰で‥ あなたのような力強い味方を手に入れる事ができた。 それはそれでけっこうな事です 」
「では―――? 」
「大いに歓迎いたしましょう。 あなたはイングランド軍の参謀(さんぼう)の一人として、これから我が陣幕(じんまく)に自由に立ち入る事を許可いたします 」
「おお‥ なんという事でしょう。 陛下のありがたいお言葉に感謝いたしますとともに‥ あなた様とイングランド王国に永遠の忠誠をお誓い申し上げます。 これからは粉骨砕身(ふんこつさいしん)、陛下のお役に立てるよう努力いたしましょう 」
エドマンド王はゴドウィンを迎(むか)え入れる証(あかし)として、王主催の会食を催(もよお)してくれた。その席には多くの将軍や騎士(ナイト)らも招かれていたのだ。
高貴な人々と交(まじ)わり、盃を交(か)わしたゴドウィンは大いに感動し、エドマンド国王に対するさらなる忠誠を誓った。己(おの)が命が尽(つ)きるまで、国王陛下を支え続けると約束したのだ―――あくまでも、口先だけの事であったが‥‥。
彼は翌日からエドマンド剛勇王に仕(つか)える側近の一人として、各地への従軍にも付き添(そ)ったのであった。
だが、ゴドウィンが参謀(さんぼう)にくわわった途端、戦局は悪化していった。
その主たる原因は、マーシア伯エアドリクと『長身のトーケル』‥‥この二人の裏切り者のせいであった。守りの両翼(りょうよく)が敵方となった事は、エドマンド王にとって致命(ちめい)的だったのだ。
『長身のトーケル』は元々デンマークバイキングであったし、マーシア伯エアドリクはエドマンド王の義弟だったが、これまで何度もイングランドを裏切ってきた男である。そのような人物を軍の中枢(ちゅうすう)に置き、信頼していたエドマンド剛勇王は間抜けであったとも言えようが、彼らを重用(ちょうよう)せねばならないほどに、イングランド軍は人材不足だったのだ。
ただその裏には、ゴドウィンの働きも大いにあった。
イングランド軍の布陣やエドマンド王の戦略などを、彼はデンマーク軍のクヌート王子に逐一(ちくいち)報告していたのである。
エドマンド剛勇王は、10月18日の『アサンダンの戦闘』においても大敗を喫(きっ)し、もはや後がなくなってしまった。
ところが、グロスターシアまで追い詰められたエドマンド王のもとへ、敵方の総司令官・クヌート王子から和議の申し出があったのだ。
優位にある側から和議を申し込むなどおかしくはないか―――エドマンド王は不審に思ったが、戦局に打開策がない彼は、ゴドウィンの勧(すす)めもあって、とりあえずその協議に乗ってみる事にした。
両者の会談は、ディアハースト島の『ディーンの森』でおこなわれた。
協議に出席したのはイングランド側、デンマーク側それぞれ4名づつ。エドマンド王の信任厚いゴドウィンは、この席にも出席する事ができた。
エドマンド王27歳、クヌート王子21歳―――イングランド、デンマーク両国の若き総司令官が対峙(たいじ)したのである。
まず、口火を切ったのはクヌート王子であった。
「もはや、戦局は明らか! イングランドの8割を支配下に置いた我が軍の勝ちです。 もう、あきらめられてはいかがですか? 」
だが、エドマンド王は強張(こわば)った笑顔でそれを否定した。
「しょ‥ 勝負は時の運ですぞ! 追い詰められてから、本領(ほんりょう)を発揮する場合もございます。 我が軍には、勝利をあきらめた兵士など一人としておりません 」
それはウソであった。イングランドの兵士達は連日の敗戦によってボロボロに疲れ、敵に剣を振りあげられるかどうかさえも怪しい状態にあった。
そしてそれは、ゴドウィンからの密書によって、クヌートも承知の事なのだ。
「はっきり申し上げて‥ このままいけば、我がデンマーク軍はイングランド軍を全滅させる事となりましょう。 しかしながら、人は死を前にすると思わぬ力を発揮するもの。 イングランド軍による最後の抵抗は、予想以上に大きなものになるやもしれません。 わたしは我が軍の将兵が、そのような無駄な戦闘によって失われる事を避けたいのです 」
「だ‥ だから‥‥? 」
「ここらで停戦といたしませんか? 」
「て‥ 停戦? どのような条件で? 」
「テムズ川を挟(はさ)んで、南側をイングランドの領土とし、その北側は我がデンマークがすべていただく―――それで、いかがですかな? 」
それはかつてアルフレッド大王が統一したウェセックス王国―――『ディーンロー』を除く、イングランド王国が実効支配していた地域の、さらに半分以下の領土に過ぎなかった。
一方、クヌートの領地はイングランド全体の7割近くとなる。
だが、すべてを奪われるよりははるかにいい。いや、むしろ現在イングランド側がもつ支配地域よりも、それはずっと広いのだ。
クヌートの領土は、そのほとんどが『ディーンロー』である。その『ディーンロー』は、『セントブライスデーの虐殺(ぎゃくさつ)』以来、イングランドの支配を完全に拒絶し、デンマーク側についていた。
つまり、この和議によるイングランド側の損失は大きなものではないのだ。むしろ、エドマンドにとっては破格の条件とも言えた。
剛勇王(ごうゆうおう)は、小声で副官としばしやり取りをした後、その和議に応じる旨(むね)をデンマーク側に伝えようとした。
その時、ゴドウィンが一同を前にして、大きな声を上げた。
「そのような条件では、我が軍は和議など結べませんぞ! 」
「なんとな!? 」
エドマンド王は驚いた。
「だってそうでしょう!? 現在の戦況からすれば、この和議は我がイングランドにとって好条件すぎます! これは何かの罠(わな)に違いない! エドマンド国王陛下‥ このクヌート王子を信用してはなりませぬ。 絶対に署名をなさらないでください 」
クヌート王子は呆れ顔をゴドウィンに向けた。
「どこのどなたか存じませんが‥ これが罠(わな)とは心外ですな! ディーン人をもう少し信用していただきたい 」
だが、ゴドウィンは勝者の将に対して、臆(おく)する事なくそれを否定した。
「信用しろですって? そんな事、できようはずがないじゃないですか! あなた方はこれまで何度、我がイングランドとの和議を破ってこられたとお思いですか? 」
「そ‥ それは‥ 」
一瞬、気色(けしき)ばむクヌート王子に、ゴドウィンはさらにたたみ掛けた。
「そりゃね‥ バイキングなんぞは、しょせん盗賊ですから、約束を反故(ほご)にするのも仕方ないでしょう‥。 しかしながら、あなた様のお父上・スヴェン1世国王陛下は伝統あるデンマーク王国の長であらせられたのですぞ。 そのような方が、『セントブライスデーの虐殺(ぎゃくさつ)』の報復として、我が国を4回も侵略し‥ そのつど『もう二度と侵略はしない』と約束して、我がイングランドから多額の退去料(ディーンゲルド)を奪っていったのです。 にもかかわらず‥ 和議は毎回破られ、半年から一年で再び攻め込まれました。 そのようなデンマークの約束など、我らが信用できましょうか? 」
そこまで言われたクヌート王子は、憮然(ぶぜん)として席から立ち上がった。
「そうですか‥ まぁ、ご信用いただけないというのなら、この和議の話はなかったという事で――― 」
立ち去ろうとするクヌート王子に、エドマンド剛勇王(ごうゆうおう)は慌てた。
「ちょ‥ ちょっと、お待ちください! この者は、わたしの家臣ではなく――― 」
これまで、『命もいらぬ』と覚悟して、戦い続けてきたエドマンド剛勇王(ごうゆうおう)であった。だが、いったん好条件で身の安全を保証されると、緊張の糸は切れ、その覚悟も大いに揺(ゆ)らいでしまった。彼はこの和議を潰(つぶ)される事が急に怖くなったのだ。臆病風(おくびょうかぜ)に吹かれたのだろう。
しかし、弱気になったエドマンド王の言葉を無視して、ゴドウィンはさらなる条件を提示した。
「今後20年間、デンマーク王国は絶対にイングランド領内に攻め込まないとお約束ください。 そして、もしそれを破った場合には、イングランド王の資格を失うという罰則(ペナルティー)も添(そ)えていただきたい。 それを『国政審議会(ウェテナイェモート)』に承認してもらうのです。 そこまでしていただければ、クヌート殿下のお言葉も信用いたしましょう 」
「‥‥‥ 」
クヌート王子は立ったまま、しばしゴドウィンを睨(にら)みつけた。
陣幕(じんまく)内は緊張に静まり返った。息を呑(の)む音さえ聞こえるかのようである。
やがて、クヌート王子の口がゆっくりと開かれた。
「いいでしょう。 その条件、飲もうじゃないですか! 」
エドマンド王とその副官は、ゴドウィンを見詰めて感嘆(かんたん)の声を漏らした。それは、ゴドウィンの交渉(こうしょう)があまりにも見事であったからだ。
これで、今後20年間はデンマークからの侵略はない。国内経済を立て直し、軍備を増強するには願ってもない猶予(ゆうよ)だった。
だがゴドウィンは、再び着席したクヌート王子にさらに迫った。
「ならば、もう一つ提案をさせてください。 我がエドマンド王様、あるいはクヌート殿下―――どちらかが先にお亡くなりになられた場合は、その領土を相手方にすべて譲与(じょうよ)するという条件はいかがでしょうか?」
その言葉に、エドマンド王はさらなる驚きの声を上げてゴドウィンを振り返った。
「そ‥ それは、この二人の内、長生きした方がイングランド全土の国王になれるという事か? 」
「はい‥ さようでございます。 さすれば、その後も無益な争いを交(か)わす事はなくなるでしょう‥ 」
ゴドウィンはエドマンド王にニヤリとした顔を返した。
クヌート王子は腕組みをすると、しばらく渋い顔で考えていた。彼以外の5人は、王子が何と返答するのか固唾(かたず)を呑(の)んで見守っている。
「いかがでございましょうや‥? 」
ゴドウィンが促(うなが)すと、クヌートは苦々(にがにが)しげながらもそれに頷(うなず)いた。
「まあ‥ いいでしょう。 その条件も盛り込めばいい。 その上で、署名した宣誓書(せんせいしょ)を3通作成し、一通を我がデンマーク王国が、もう一通をイングランド王国が‥ そして、最後の一通を『国政審議会(ウェテナイェモート)』に提出する事といたしましょう 」
エドマンド剛勇王(ごうゆうおう)は、ゴドウィンの外交による大いなる勝利に歓喜(かんき)した。
× × × × ×
イングランド軍の陣幕(じんまく)に戻ったエドマンド王とゴドウィンらは、将兵を集め、先ほど取り交わした和平条約の内容について報告をした。
兵士達はやっと長い長い戦いが終わる事を知り、大きな歓声を上げた。それはいつまでも続く喜びの声であった。そして、祝宴(しゅくえん)が始まったのである。
ゴドウィンは最も重要な家臣として、エドマンド王の隣に席を設(もう)けられた。本日、最大の功労者だからである。
エドマンド王はガラスの盃(ゴブレット)を手に、満面の笑顔でゴドウィンを褒(ほ)め称(たた)えた。
「ゴドウィン殿‥ 本日はじつにあっぱれであった! よくぞ、あの場であのような条件を思いつき、交渉(こうしょう)してくれた。 心より、感謝しておりまするぞ! 」
「そのようにお褒(ほ)めいただけるとは、光栄の極(きわ)みにございます 」
ゴドウィンははにかんだ微笑をエドマンド王に返した。
「とはいえ‥ デンマークははじめから弱腰でした。 領土の分配で、あれほど我らに有利な条件を提示したのは、彼らが早急に和平をなさねばならなかったからでしょう。 おそらくは、デンマークの国内外に何らかの事態が発生したと思われます。 内乱か、あるいは他国から侵略されたのか――― 」
「なるほど‥! 」
「ともかく、クヌート王子は一刻も早くこの戦争を終わらせたかったに違いありません。 ですから、わたくしも少々強気になって、我らにより有利な条件を押しつけてやったのです 」
「とにもかくにも‥ すばらしい交渉(こうしょう)であった! 私さえ長生きできれば、イングランド全土が我が物となるのだからな。 これは、アルフレッド大王様以来の快挙(かいきょ)―――いやそれ以上の大偉業となる。 我が名は永遠に歴史に刻まれるであろう。 なんと、めでたき事じゃ! 」
「おっしゃる通りでございます。 せいぜい、長生きにおつとめくださいませ♡ 」
その日からゴドウィンはエドマンド剛勇王(ごうゆうおう)の片腕として、常にその傍(かたわ)らにあった。
それから3日後には、イングランド軍は移動を開始し、ロンドンへと戻ったのである。
『ディーンの森』の和平条約が、『国政審議会(ウェテナイェモート)』によって承認されたのは2週間後の事であった。
だが、エドマンド王はロンドンに戻った頃から体調を崩していた。
医者は、長い戦闘の疲れが出たのであろうと診断し、精力剤を処方していた。
彼はしだいに食欲がなくなり、頭痛で睡眠も十分に取れなくなっていった。下痢、腹痛もなかなか治まらないようである。やがて、青白い顔となり、汗が止まらなくなっていった。さらには、少しでも身体を動かすと息が荒くなり、立っていられない状態となったのである。
ベッドに臥(ふ)せったエドマンド剛勇王(ごうゆうおう)は、傍(かたわ)らに跪(ひざまず)くゴドウィンの手を握り、
「わたしはこのまま死んでしまうのだろうか‥? 友よ、なんとも悔しい事だ‥‥ 」
そう弱々しい声で呟(つぶや)くと、悔し涙を流した。
「気をしっかりとお持ちください。 陛下は、全イングランドの国王とならねばならないお方なのですぞ‥! 」
ゴドウィンもポロポロと涙を流した。
1016年11月30日、エドマンド剛勇王(ごうゆうおう)はついにこの世を去った。
『ディーンの森』の和平交渉からわずか6週間後の事である。
これにより、クヌート王子はついに全イングランドの国王としてロンドンで戴冠(たいかん)する事となった。12月24日、降誕祭(クリスマス)の事である。
翌年の1017年1月6日、『国政審議会(ウェテナイェモート)』は、『ディーンの森の条約』に基づき、侵略者・クヌートを新しいイングランド国王として認めざるを得ず、オックスフォードに貴族を集めこれを承認した。
これによって、すべてのイングランド国民が新王に従い、それに異を唱(とな)える者、反逆する者は誰もいなかった。
これらすべての事は、ゴドウィンとクヌートとの間で綿密(めんみつ)に計画された陰謀である。
エドマンド王が日々飲んでいた精力剤には、カラバル豆から抽出された毒が混入されていたのだ。