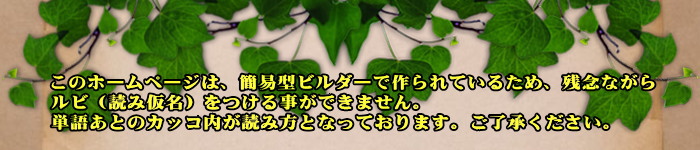
72
1018年 イングランド・ウィンチェスター城
『ノルマンディーのエマ』は、クヌート王と結婚するやすぐに懐妊(かいにん)した。
この事を大いに喜んだクヌート王は、生まれてくる子が男子であれば、自分の後継者にすると宣言してしまったのだ。
だが、エマは4ヶ月で流産してしまう。
この噂は、元妻であった『ノーサンプトンのエルギフ』の耳にも入った。
彼女は首都ウィンチェスターから東へ120マイル(190㎞)ほど離れたエクセターに居を構えていたが、すぐに馬車を飛ばしてウィンチェスター城へと乗り込んできた。
「わたくしがあなたの正式な妻となれず、イングランド王妃になれなかった事はいたしかたありません。 残念ではありますが、それはあきらめましょう。 しかしながら、わたし達の息子であるハロルドヘアフットやスヴェンが、王位から遠ざけられる事は我慢なりません。 それはいくらなんでも、あまりのお仕打ち! 神とてお許しにはなられませんよ 」
彼女はクヌートをなじった。
「エマ王妃とて、もはや32歳。 これから子供が―――男子が生まれるとは限りません。 ならばまずは、我が息子達に王位をお与えくださいませ! 」
そういう彼女に、クヌートは言い返した。
「いやいや‥ お前が申しておるのは、初産(ういざん)の場合の話。 エマは32歳とはいえ、すでに三人の子供を産んでおる。 ならば、可能性はまだ十分にあるだろう 」
だが、エルギフも後には引かなかった。
「そうです! その三人の子供こそが問題なのです。 その内の二人は男子なのですよ。 彼らは前王の息子であり、アナタ様に次ぐ王位継承権を持つ者達なのです。 アナタ様がお亡くなりになれば、アナタ様の子達と前王の子達との間で必ずや諍(いさか)いが起きるでしょう。 禍根(かこん)を残すに違いありません 」
「な‥ なるほど‥‥! 」
クヌートはエルギフの意見にも一理あると思った。もし、自分が死んだなら、エマが産んだ前王の息子達と、エルギフが産んだ自分の息子達、4人全員に王位継承権が発生するのだ。 争いごとになるのは火を見るよりも明らかであった。これには、あらかじめ手を打っておく必要があるだろう。
さらに彼には、『ノーサンプトンのエルギフ』を裏切ったという後ろめたさもあった。
そこで、クヌート王はエルギフとの長男・ハロルドヘアフットにイングランドを継承させる事を決意した。
これに対し、『賢人会議』とも呼ばれた王室諮問機関(ウェテナイェモート)は大いに賛成した。
エルギフはノーサンプトン領主(エアルドルマン)の娘で、アングロサクソン人の血を引いていたからである。一方、エマはフランスのノルマン人であった。
王室諮問機関(ウェテナイェモート)は、サクソン人の血を引く王ならば国民も大いに安心するだろうと考えたのだ。
中世のキリスト教会では、庶子(しょし)(正妻以外から生まれた子供)に相続権は認められていなかった。ただ、この当時くらいまでは、さまざまな規制もまだ厳格には行われていなかったのである。それゆえ、庶子(しょし)であるハロルドヘアフットも王位継承の権利を得る事ができたのであった。
ところが、エマは再び王の子を妊娠したのだ。そして、翌年の春、今度こそ玉のような男子を出産したのである。彼は父の名を受け、ハーディクヌーズと命名された。
これは大いなる慶事(けいじ)のはずである。だが、王妃エマの心は暗澹(あんたん)たる気持ちでいっぱいだった。
かわいいハーディクヌーズの行く末が案じられたからである。彼は正妻の子であるというのに、イングランド王を継承する事ができないのだ。
ノルマンディーに預けた先王エセルレッドとの子―――エドワードやアルフレッドは無論の事、クヌート王との間にできたハーディクヌーズでさえも、イングランド王にはなれない。王位継承権のある息子を三人も産んだというのに、エマの子は誰一人として国王になれないのだ。
産後の精神の不安定さも手伝ってか、彼女はかなり憂鬱(ゆううつ)な気分になっていた。
そんなところへゴドウィンが訪(おとず)れたのである。
「王妃様‥ ご機嫌麗(うるわ)しく存じ上げます♡ 」
玉座に腰掛けたエマは、いかにも不機嫌そうであった。
「フン‥ なにを申すか! わらわの気分はいっこうにすぐれぬ。 気分がめいる事ばかりじゃ‥ 」
彼女のゴドウィンに対する言葉遣いは、以前のような横柄(おうへい)なものに戻っていた。
ゴドウィンは、彼女の命を助けたばかりか、クヌート王との結婚までも万事手配してくれた人物である。いわば、エマにとって大恩人なのだ。にもかかわらず、彼女は手のひらを返した。
確かに、彼がいろいろと画策した事を、他の者に絶対に悟られてはならなかった。そのためには、王妃と家臣のけじめをはっきりさせる必要もあったであろう。
だが、本当のところは、ふたたび権力を得た彼女が、驕(おご)り高ぶっていただけであった。
さらに、ゴドウィンは、エマが思っていたほど出世していなかったという事もあった。クヌート王は彼の言葉によく耳を傾けたが、彼には爵位があるわけでも、領地があるわけでもなかった。宮廷を賑(にぎ)わす道化(どうけ)や吟遊(ぎんゆう)詩人の立場と大して変わらないのだ。
そのため、エマはゴドウィンを軽んじたのである。
しかしそれは、しかたのない事であった。イングランド征服の最後の『詰め』において、ゴドウィンの果たした功績は大きなものであったが、現王が前王を毒で謀殺(ぼうさつ)したなど、けっしてあってはならぬ話。ゴドウィンの手柄(てがら)はあってないようなものなのだ。
そんな彼の活躍を知らないデンマーク貴族達は、
「イングランドを裏切ったような者は、今度はデンマークも裏切るに違いない! 」
「あやつは、優勢な方にすぐ転ぶ、卑怯者(ひきょうもの)である! 」
「何を身につけようと、どう着飾ろうとも、生来(せいらい)の育ちの悪さはすぐに出るもの! 」
「王はなぜ、あのような下賤(げせん)な者の言葉に耳を傾けるのだろうか?」
などと、自分達とて『強盗団(バイキング)』上がりのくせをして、ゴドウィンへのあからさまな陰口を叩くのであった。
彼らは、クヌート王の信任が厚いゴドウィンに対して、嫉妬(しっと)していたのであろう。
ただ、ゴドウィンに明確な手柄(てがら)がない事も事実である。
それゆえ、クヌートも彼に高い地位を与えるわけにはいかなかったのだ。
となると、王妃に返り咲いたエマと無役のゴドウィンとでは、身分に大きな開きがあった。
それで、大恩人であるにもかかわらず、エマはゴドウィンを粗略(そりゃく)に扱ったのだ。彼女はそういう浅はかな女だった。
「なるほど‥ それはご心配でしょう‥! 」
ハロルドヘアフット王子をイングランド王の後継者に指名する際、クヌート王は珍しくゴドウィンに相談をしなかった。王はウルフ伯と協議して、後継者問題を決定したのであった。
ゴドウィンはそれがおもしろくなかった。
王妃の悩みを聞いたゴドウィンは、部屋に彼女と自分二人しかいない事を確認した。そして、王妃のそばへと近づいたのである。
ゴドウィンの接近に、驚いたように身を引いたエマを、彼は意地悪な微笑で覗(のぞ)き込んだ。そして、軽い口調で申し出たのであった。
「ならば、ハロルドヘアフット殿下とスヴェン殿下‥ ついでに、『ノーサンプトンのエルギフ』様もまとめて殺して差し上げましょうか? 」
「え!? 」
冗談めかして耳元で囁(ささや)かれたその恐ろしい言葉に、エマはドキリとした。
確かに、ゴドウィンならば―――ハロルドヘアフット王子ら三人をいとも容易(たやす)く、確実に殺してくれるに違いなかった。
そしてそうなれば、イングランドの王位は我が息子ハーディクヌーズのものとなるであろう。
しかし、彼女はすぐに笑ってそれを否定した。
「な‥ なにを申すか。 そのような事をすれば、誰もがわらわが殺害を命じたと疑うであろう。 クヌート様にそれがバレたなら、わらわの首は刎(は)ねられてしまうではないか‥ 」
少しは知恵が回るのだな―――とゴドウィンは鼻を鳴らした。
だが、手の甲で口元を隠すようにして笑うエマの顔は、いささか引きつっている。
その些細(ささい)な変化を見逃さなかったゴドウィンは、しばらく考えるフリをして、さらなる『悪魔の囁(ささや)き』を口にしたのだ。
「ならば、デンマーク王にいなくなっていただくというのはいかがでしょうか? 」
その言葉にエマは驚愕(きょうがく)した。
「い‥ いや‥ ま‥ まさか、ハーラル義兄様(おにいさま)を殺すというのか? 」
「エマ様のお悩みは、王位が足りないから起きる事なのです。 ならば、継承する王位の数を増やせばいい。 ハーラル王亡き後、クヌート王様にデンマーク王となっていただき‥ その上で、その継承者としてハーディクヌーズ殿下をご指名いただくのです 」
「‥‥‥ 」
「よいですか‥ デンマーク王国は王様の母国なのですぞ! そのデンマークの王となるという事は、イングランド王をもさらに支配する、上級王になられるという事を意味しているのです! こちらの方がずっと価値があるとは思いませんか? 」
「そ‥ そんな‥‥ 」
エマは口に両手を当て、漏れそうになる声を押し殺した。
だが、彼女はしだいにその言葉の持つ魅力に引き込まれていく。
デンマーク王―――なんと素晴らしき響きなのだろうか。 ああ、我が息子ハーディクヌーズをデンマーク王にしたい。 そのためなら、何をしてでもかまわない―――エマはそう強く思った。
1年半前の彼女は、水面(みなも)を漂(ただよ)う枯れ葉のような自分の運命を案じ、神に懸命に命乞(いのちご)いをしていた。そのエマが、今では義兄の命を奪う算段(さんだん)をしているのだ。
「いかがいたしましょうや? 」
ゴドウィンが返答を促(うなが)すと、エマはそれにかすれた声で返した。
「そ‥ それがよいと思う‥ 」
「ほ~~~お‥ そのような重大な事、ゆっくりと考えてから決められなくともよいのですか? 」
「い‥ いくら考えようとも、悩み苦しむ時がふえるだけ。 結論は同じじゃ‥ 」
「なるほど‥! 」
ゴドウィンは王妃の目を覗(のぞ)き込んで念を押した。
「では、アナタ様の命により‥ デンマーク国王のお命を頂戴(ちょうだい)いたしまするぞ! よろしいですかな!? 」
エマは顔を伏せ、ゴドウィンの視線から逃げた。そして、コクリと頷いたのだ。
産後の不安定な精神だったとはいえ、それはけっして許される事ではなかった。
ゴドウィンは、エマの心が徐々に悪魔に蝕(むしば)まれていく様子を見て、嬉(うれ)しかった。楽しかったのである。
―――何とあさましい女なのだろうか。 自分の首が、真綿(まわた)でジワジワと絞(し)められていく事にまったく気づいていない愚か者だ。 この女はまだまだ楽しめる―――ゴドウィンはほくそ笑んだ。
かつて、殿上人(てんじょうびと)だったエマ王妃は、いまや自分と同じ汚物となったのである。
ゴドウィンは不敬(ふけい)にも、王妃エマの両頬(りょうほお)に手を添(そ)えると、俯(うつむ)いていた彼女の顔を自分の方にグイッと向けた。
「よいですね!? これは、バレれば―――わたくしのみならず、アナタ様までも、重い罰を受けねばならないご命令ですぞ。 その事を十分にご覚悟ください。 我々は一蓮托生(いちれんたくしょう)なのです♡ 」
「は‥ はい‥! やって‥ やってくだ‥ さい‥ 」
エマは小さく震えながら、ゴドウィンに頼み込んだ。
× × × × ×
ゴドウィンは、今度はクヌート王の下(もと)へと向かった。
彼は広間の玉座に坐るクヌートの前に進み出ると、
「王様‥ ハーディクヌーズ王子様誕生のおり、デンマーク国王ハーラル陛下より頂戴(ちょうだい)いたしましたお祝い―――そのお礼の使者はいかようにいたしましょうか? 」
と申し出た。
クヌートはその問いに顎髭(あごひげ)を触りながら考えた。
「うむ‥ そうじゃな‥? ウルフ伯にでも頼むとするか。 奴ならば兄上とも旧知の仲じゃからのォ。 妹エストリドともども里帰りをさせてやるとよい 」
「しかしながら‥ ウルフ様は王様の右腕として、政治のサポートに忙しくされておられます。 先日も、ロンドンから15000ポンドの税金を徴収するよう、お命じになられたばかりではありませんか 」
「そうであった‥ 奴には、デンマーク兵帰還のための報奨金(ほうしょうきん)を集めさせていたのだったな‥ となると、別の者に出向いてもらわねばならないが―――」
「いかがでしょうか‥ このわたくしめにお使者の任(にん)、まかせてはいただけませんでしょうか? 」
「お前をデンマークへ送れというのか? 」
「はい、さようでございます。 イングランドからの新参者であるわたくしは、ご重鎮(じゅうちん)の皆様からいささか軽んじられております。 ここいらで、わたくしにも名誉あるお仕事を賜(たまわ)りたいのです 」
「うむ‥ なるほど‥! 」
「それに、クヌート王様がお生まれ、お育ちになったデンマーク王国をぜひとも見てみたいのです。 これから長く仕(つか)える身といたしまして、王様の事をもっともっと存じ上げたいのです。 どうかこの願い、おかなえくださいませ 」
「わかった! よかろう、お前に頼む事としよう 」
クヌート王はゴドウィンの企(たくら)みも知らず、その願いを快諾(かいだく)したのであった。
× × × × ×
クヌート王の兄であり、デンマーク国王であるハーラル2世は、普段は物静かであったが、なかなかに肝(きも)が据(す)わった人物だった。
スヴェン1世の死によって、クヌートがイングランドを追われデンマークへ逃げ帰った時、彼は地位確保のため、兄ハーラルにデンマーク王国の共同統治を申し出た。だがハーラルはそれをキッパリと拒否し、単独で国王の継承を受けたのだ。
それは父スヴェン1世の遺言であったのだが、弟クヌートをこのまま敗戦の将として終わらせたくなかったのである。
だが、クヌートはハーラルから王位を奪うに十分な軍隊を持っていた。敗軍とはいえ、イングランドから連れ戻ったデンマーク軍は、先王スヴェン1世がイングランド侵略のために編成した精鋭部隊である。ハーラル2世が支配する国内兵団よりもはるかに強大であったのだ。
しかし、ハーラルはその脅威に恐れをなす事なく、自分の権利をはっきりと主張し、その一方で、クヌートが改めてイングランドを攻略できるよう遠征軍の増強に協力した。下手をすれば、さらに強大化したクヌート軍に攻め滅ぼされるかもしれなかったのにである。
こうしたハーラル2世の誠実な姿勢に、クヌートも頭が上がらなかったのだ。
1018年9月、ゴドウィンは2週間の船旅を経て、デンマークのロスキレ宮殿についた。
彼はハーラル王に丁重(ていちょう)な挨拶(あいさつ)をすると、クヌート王からのお礼の手紙やたくさんの土産物などを届けた。
王は大いに喜び、盛大な祝宴(しゅくえん)を三日間催(もよお)してくれたのだった。
しかし、祝宴が終わった四日目の朝、ハーラル2世は突如体調の乱れを訴え、五日目からは寝込んでしまった。
彼はしだいに食欲がなくなり、下痢、腹痛もなかなか治まらない。やがて、身体を動かすと息が荒くなり、立っていられない状態となった。顔は青白く、汗も止まらない。
王の主治医は毎日薬を与え続けたが、ハーラルの体調はますます悪化していった。
そして2週間後、デンマーク国王ハーラル2世はついに逝去(せいきょ)したのだった―――それは、29歳という短い生涯であった。
その直後、王の主治医と一人娘が屋敷で首を吊って自殺しているのが発見された。
二人の死は、王を快癒(かいゆ)させられなかった事を悔(く)いての殉死(じゅんし)だろうと判断された。
だが、その真実は―――ゴドウィンから一人娘を誘拐された主治医が脅迫に屈し、ハーラル2世の薬にカラバル豆の毒を混入させていたのだ。
そして、国王が亡くなった後、毒殺の証拠を隠滅(いんめつ)するために、ゴドウィンは二人を自殺に見せかけて殺したのであった。