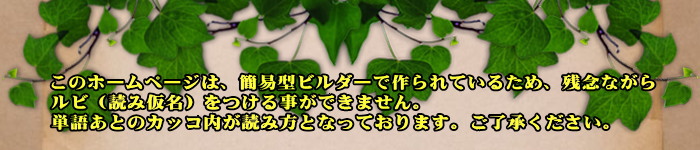
15
1026年 ファレーズ城・中庭(1)
あたりはすでに真っ暗になっていた。
領主の館(メヌア)の広間からは送別会の明かりが漏れていたが、先日の歓迎(かんげい)会とは打って変わって、にぎやかな声は聞こえてこない。
ロベールの家臣(かしん)達は皆(みな)、意気消沈(いきしょうちん)していた。
頼純が、ロベールの家臣となる事を断ったからである。
誰もが望む貴族の地位を、『くだらない』と一蹴(いっしゅう)したからであった。
さらには自分達の国が、世界から見ると取るに足らない、ちっぽけな存在であるとまで言われた。
そして、そのような暴言(ぼうげん)を吐く頼純を取り押さえようとした多くの兵士達が、頼純のひと睨(にら)みで動けなくなったのだ。その事が、彼らをいっそう惨(みじ)めな気分にしていた。
その暗澹(あんたん)たる思いは、もはや怒りに近い感情にまで変質し、広間に充満(じゅうまん)していた。
そんな険悪な空気の中、やはりロレンツォはたいしたもので、前回と同様、ロベールの隣に堂々と坐り、何食わぬ顔で食事をしていた。その上、ティボーと世間話までして笑っているのである―――まさに大物であった。
一方、頼純の席は今回、他の家臣達と同じテーブルであったが、その席は空(あ)いていた。
いくら肝(きも)の据(す)わった頼純でも、さすがにその場の空気は耐(た)えがたかった。
つい先刻(せんこく)、彼らの主人を怒鳴りつけ、彼らの仲間と大立ち回りを演じたのである。居心地(いごこち)がよかろうハズはない。
一同の前でエルレヴァの悪口を言った事も、自分の失態だったと反省していた。ロベールに恥をかかせ、申し訳ないと思っていたのである。
だがその一方で、彼らがどう思おうと知ったコッチャない―――と開き直っている部分もあった。
もう二度とこの地に戻ってくる事はないのだ。
「せぇ―――のッ!! 」
男奴隷達と一緒に、大きなチェスト(長持ち)を持ち上げた頼純が、荷車へと向かう。
彼は部下であるイタリア人傭兵(ようへい)にロレンツォの警護を任せ、自分は、明日の出発のために中庭で慌ただしく準備をしている仲間達を手伝う事にしたのだ。
その時、隣の荷車の影からサミーラが現れた。彼女は積み終わったチェストの山に防水用の布を被せている。
その姿を見た途端、頼純は『あ! 』―――と息を呑んだ。
サミーラも頼純の姿に気付き、頬(ほお)を染めた微笑(えみ)で会釈してきた。
頼純は棒立ちとなり、チェストから手を離してしまう。
奴隷達は慌(あわ)ててそれを支(ささ)えようとしたが間に合わず、大きな音を立て、チェストはひっくり返ってしまった。
中からたくさんの商品がこぼれ、周囲は大騒動となった。
サミーラも驚いている。
そんな中、頼純はただただ立ち尽(つ)くしていた。
あまりの恥ずかしさに、真っ赤になった顔で天を仰ぐと、そのままそれを戻す事ができなかった。今日は、サミーラと目を合わせるなど絶対に無理な状況なのだ。
頼純は昼間、多くの人の前で、サミーラに好意をいだいている事を認めた。開き直っての事だったが、それは告白も同じであった。
そしてその話は、すぐにファレーズ中に広まっていった。もちろん、ロレンツォの隊商(キャラバーン)にもである。
それゆえ、仲間達にからかわれながらも、必死にサミーラを避(さ)けていたのだ。彼女は今夜、宿舎の片付けをしていると教えられたから、頼純は外の荷運びを手伝う事にしたのである。
なのにバッタリ彼女と出会い、クスリと笑われてしまった。
頼純は星々を見詰めながら、絶望的な気持ちに襲われていた。
いい年をして、ちょびっと涙まで出た。
そんな頼純の背に声がかかる。
「あ‥ あのォ‥ ヨリ殿―――? 」
「ひぃ―――い! 」
てっきり、サミーラが声を掛けてきたと思った頼純は、処女(おとめ)のような声を上げた。
だが、声の主は領主のロベール伯であった。彼は食事会を抜け出して、ここへやって来たのだ。
「少し、お話をしてもよろしいでしょうか‥? 」
頼純は、さらに気が重くなった。
× × × × ×
「いや~~~ァ‥ 今日のお話しには、ガツンときました 」
一枚が5プース(1プース=1インチ=2.7センチ。5プースは約13センチ)はあろう分厚い板で作られた、高さ20ピエ(1ピエ=約30センチ。20ピエは約6メートル)ほどの城壁には、その壁に沿って見張り用の回廊(かいろう)が巡(めぐ)らされている。頼純とロベールはその回廊(かいろう)を歩いていた。
回廊(かいろう)は、地面から15ピエ(=約4.5メートル)の高さに設(もう)けられ、幅は1ウナ(=約1.2メートル)ほど。 あちこちに松明(たいまつ)が灯(とも)され、そこから中庭全体が見渡せるようになっていた。
ロベールはその中庭を眺(なが)めながら、ゆっくりと歩(ほ)を進めた。その後ろに続く、頼純は少々ばつが悪そうな顔をしている。
「でも、まぁ‥ もしかしたら、そうじゃないかなァ―――とは思っていたんです。 東方の国々の方が、我々よりも進んでいるんじゃないか‥ 豊かに暮らしてるんじゃないかってね‥! 」
「はあ‥ 」
「もちろん‥ それは、わたくしだけじゃありません。貴族や僧侶(そうりょ)など、ある程度の教育を受けた者は、みな気づいているハズです。 だって、このフランス国内でさえ、アチコチにローマ時代の遺跡(いせき)が残っていて‥ その驚異的な技術は、まだ誰も解明できていないのですから‥ 」
この時代の知識人は、漠然(ばくぜん)とした不安を抱えていた。
遠い過去にギリシャ・ローマという時代があり、その時代はいまの自分達よりもずっと優(すぐ)れた技術や文化を持っていた―――という事は、知識人達の間では常識となっていた。
しかし、自分達はその文明を受け継ぐ事ができなかった。
だから、もし他の世界がその文明を受け継ぎ、さらに発展させていたら‥‥ 自分達よりも圧倒的に強大な世界となっているかもしれない―――という不安である。
だが、その事を口にする者は誰もいなかった。
その事を認めてしまえば、自分達は外の世界に比べて、劣(おと)った民であり、貧しい社会である事を認めなければならなかったからである。
教会の権威(けんい)は失墜(しっつい)し、王の威厳(いげん)は損(そこ)なわれ、その王によって任命された貴族の名誉も地に落ちてしまう。
それは、キリスト教社会の仕組みが崩壊(ほうかい)する事を意味していた。
頼純は驚いた顔でロベールに尋ねた。
「じゃ‥ じゃあ、あの執事(しつじ)のおっさんが異教徒を馬鹿にしてたのも‥ その事を知った上で―――? 」
ロベールはそれにゆっくりと頷(うなず)いた。
「ええ‥ ティボーはわたしよりもずっと多くの知識を持っている人ですから‥‥。 それだけに、我々の世界は、じつは負けているのかもしれないという強い強迫観念を持っているのでしょう。 その思いが、東の人々をより憎むようにさせているのかもしれません 」
それから、ロベールは頼純をあらためて振り返った。
「そして‥ そんなティボーの言葉を真(ま)に受け、サミーラ殿を買い取るなどと、大変失礼な事を申し上げてすみませんでした 」
「そ‥ そんな‥ とんでもねェ! コチラこそ、みんなの前でエルレヴァさんの悪口なんか言っちまって‥ 反省してたんだ。 この通り、勘弁してくれ! 」
深々と頭を下げる頼純に、ロベールは目を伏(ふ)せ首を振った。
「いいえ‥ エルレヴァに一番失礼な事をしたのはこのわたしなのです。 彼女の言葉を信じられなかったわたしが悪いのです。 本当に後悔(こうかい)しています 」
そんなロベールを、頼純はつくづく感心したように眺(なが)めた。
「ふ~~~ん‥ アンタって貴族なのに、謙虚(けんきょ)な人なんだなァ‥! 」
そう言われて、ロベールは照れくさそうに笑顔を作った。
「へへへ‥ それって、褒(ほ)めてます? 」
「もちろん、褒(ほ)めてますよ! そして、エルレヴァさんは相当の知恵者(ちえしゃ)のようだ。 俺達が惚(ほ)れた女は二人とも頭がいい 」
「じゃあ‥ サミーラ殿も―――? 」
「ああ‥ 頭の回転はかなり早い! 俺の3倍は回るね! 」
「さ‥ 3倍ですかァ‥ ハハハハ‥ 」
二人は夜空を見上げて笑った。
「あ~~~あ‥ でも、よかったァ。 ヨリ殿と仲直りができて♡ 」
少年のような喜び方をするロベールに、頼純は少々面映(おもは)ゆく感じていた。
「じゃあ‥ アンタの話ってーのは、この俺と仲直りがしたかったから‥ それで、呼び出したのかい? 」
「い‥ いえ‥ それは、そうじゃなくて‥ 実は、昼間の話の続きを―――」
「おいおい‥ 俺はアンタの家来(けらい)になるつもりはないぜ。 それとこれとは別の話だ 」
ロベールはいたずらっ子のような表情で、上目遣(うわめづか)いに頼純を覗(うかが)った。
「それは残念なんですが‥ お聞きしたいのは、もう一つの方なんです―――」
「え? 」
「ですから‥ ヨリ殿って、石の城の作り方を知ってるんですか? 」
「あ‥ ああ‥ その事‥! 」
頼純は後頭部をポリポリとかきながら、恥ずかしそうに説明をした。
「いやァ‥ もう十年以上も前の話なんだけどさァ‥。 俺は『宋』にいる頃に、不法入国者として捕まっちまってな‥ それで、三年ほど苦役(くえき)をさせられてたんだ。 で、それが城壁の修理工事だった。 だから、設計とかってーのは無理なんだけど‥ 建築方法ぐらいなら、判(わか)らねェわけじゃない! 」
「ホ‥ ホントですか? 」
「けど‥ こりゃあ、簡単に教えられる事じゃネーし‥ 俺達は明日、この街を出発しちまうんだから――― 」
ロベールは悔しそうに顔を顰(しか)めた。
「そっかァ‥ もっと早くに、話を聞いておけばよかったなァ‥‥ 」
何かに気づいたロベールは、胸倉を掴(つか)まんばかりにして頼純に迫った。
「で‥ でも‥ 二、三年もしたら、またこのファレーズに戻って来ますよね? ヨリ殿は、しばらくはロレンツォ殿の下で働かれるのでしょう? ですよねェ!? だったら、その時に必ず作り方を教えてください! 絶対ですよ!」
「わ‥ 判った、判った! まあ、その時には教えられると思うよ‥‥ 」
しかし、それは嘘(うそ)であった。
彼らの計画では、この地を訪(おとず)れる事はもう二度とないのだ。
キラキラと目を輝かせて、その約束を信じているロベールを見ると、頼純は後ろめたい気持ちになった。
そして自分の気持ちを誤魔化(ごまか)すように、ロベールに問い掛けた。
「けどな‥ このファレーズを石の城にしようと思ったら、莫大(ばくだい)な金が掛かるんだぞ。 その金はどうするつもりだい? 」
石の城の建造費は、彼の領地の何年分もの歳入(さいにゅう)に匹敵(ひってき)するだろう。
それだけの資金を調達するとなれば、方法はおのずと限られてくる。その答えによって、ロベールの力量もはかる事ができるのだ。
彼の力量が不十分であれば、石の城など作る資格はない。そしてそうであれば、自分の嘘(うそ)も関係なくなる―――頼純は無意識の内にそう考えていたのかもしれない。
莫大(ばくだい)な資金を工面(くめん)する上で一番簡単な方法は、兄のリシャール3世ノルマンディ大公に出資を願い出るという方法である。
ノルマンディー公国はかつて、バイキング達の略奪品(りゃくだつひん)を換金(かんきん)する『市(いち)』を開催し、その税から巨万(きょまん)の資産を作り上げていた。
それゆえ、その建造費を捻出(ねんしゅつ)する事もさほど難しくはないだろう。
しかし、己(おのれ)の好奇心や欲望を満たすために、兄に泣きつくようならば、この男はクズである。相手にする価値はない。
二番目に簡単なのは、税率を上げ、庶民(しょみん)からさらに金をふんだくるという方法である。誰でも一番最初に思いつく方法だ。これは愚(おろ)かな領主という証(あかし)であろう。
さらには、他国へ攻め入り、その国の財を略奪(りゃくだつ)し、あるいは領土を広げる事で税収を増やすという方法もある。
これは、頼純の嫌いな方法ではなかったが、戦争は金もかかり、失敗も少なくない。
けっして、賢者(けんじゃ)のやり方ではなかった。
一番良いのは、この街の経済を活性させる事であろう。
無税で『市(いち)』を開くのだ。そうすれば、人々が集まり、物流も活発となる。その人達は多くの金を使い、それが税収となるのだ。
頼純は、四番目の方法だけが正解だと考えていた。
それ以外の答えを出せば、ロベールに石の城を造る資格はない。そして、彼が正解を答えられるとはとても思えなかった。
つまり、頼純は明日、心置(こころお)きなくこの地を出発できるのだ。
頼純は、ロベールが答えを出すまでに、少々時間がかかると思っていた。しかし意外にも、彼は即答(そくとう)した。
「その資金なら、税収を上げればよいと思います 」
頼純は少しガッカリした。ロベールに好感を持っていたのに、やはり彼は愚(おろ)かな領主だった。
「そうかい。 つまり、アンタは自分の個人的な興味のために、領民達を苦しめようってワケだ? 」
「え!? どうしてですか? 」
「だって、アンタは領民に重税を課(か)すんだろう? 」
ロベールは呆(あき)れたように笑った。
「違いますよ。 領民の収入を上げてやるんです。 そうすれば、彼らから税をたくさん取れるじゃないですか 」
思いも寄らぬ方向から答えが返ってきたタメ、頼純はかなり面食(めんく)らっていた。
「りょ‥ 領民の収入を上げるゥ―――? ど‥ どうやって? 」
ロベールは、ニンマリとした微笑(えみ)を浮かべて、頼純の目を覗(のぞ)き込んだ。
「―――農業改革ですよ♡ 」
ロベールは5番目の選択肢(せんたくし)を提示(ていじ)した。