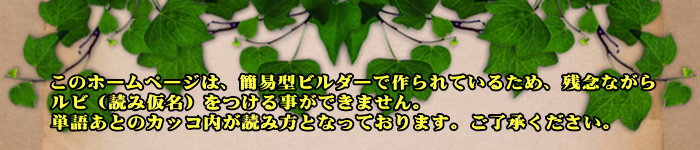
66
1004年 イングランド・フックの森
ゴドウィンは、妻や子、周囲の者らに、自分はサセックスの没落貴族、『ウルフノースチルド』の息子だと話していた。
だが本当は、フックの森に住む『きこりのジョン』の一人息子として、990年に誕生していた。
父親のジョンは大酒飲みで怠(なま)け者、母や幼いゴドウィンにいつも暴力をふるうような男だった。
一方、母親のアンはいつも笑顔を絶やさない、料理上手な女性だった。
だが、ゴドウィンは成長していくにつれ、母親の笑顔がいつも引き攣(つ)っている事に気づいた。
毎日、働きもせず酒を浴(あ)びるジョンは、アンが少しでも不満げな顔をすると、『酒がまずくなる』と言っては、執拗(しつよう)に殴る蹴るを続けるのだ。
それで、彼女は本心とは裏腹に、いつも笑いの仮面を被(かぶ)っていたのである。それはそれは、不気味な笑顔であった。
一家の家は、ロンドンとウィンチェスターを結ぶ街道から、3マイル(4.8キロメートル)ほど入った森の奥にあった。街道の近くとは言え、周囲は鬱蒼(うっそう)とした木々に囲まれている。
その家は、小屋に毛が生えた程度の粗末な建物であったが、道標(みちしるべ)を見落として森に迷い込んだ旅人が、一夜の宿を求めて頻繁(ひんぱん)に扉を叩くのだ。そこでジョンは、彼らに食事も提供する代わりに、宿代を取る事にしたのだ。
食堂や宿屋のような生業(なりわい)を始めたのである。
もちろん、それらすべての仕事は妻のアンにやらせ、自分は頂戴(ちょうだい)した金で酒を喰(く)らった。
幼い頃から、父親に暴力を受け続けたゴドウィンは、その恐怖と痛みを忘れるためなのか、あるいはそんな父親の血を受け継いだせいなのか、やがて虫や魚、小動物であるネズミやリス、ウサギなどを殺すようになっていった。
そんな少年時代を送ったゴドウィンが14歳になった春、彼の悲惨な人生に突如大きな転機が訪れた。
母から命じられて薪割(まきわ)りをしていた彼の元に、泥酔(でいすい)した父が現れ、いつものように彼を殴る蹴るしはじめたのだ。
それは、なれた痛みのはずであった。
だがその日に限って、ゴドウィンは耳の奥で何かが切れる音を聞いたのだ。そして次の瞬間、目の前を大量の血が舞っていた。
しばらくして、母の金切(かなき)り声に彼が正気を取り戻すと、目の前にはバラバラになった父ジョンの骸(むくろ)が転がっていた。
ゴドウィンとその右手に握られた斧(おの)には、大量の血と頭髪が付着している。
切断された父の手足、グジャグジャに潰(つぶ)された頭部を見た時、彼に巨大な恐怖が襲いかかった。だがしばらくすると、体の奥底から、ジワジワと痺(しび)れるような陶酔感(とうすいかん)が滲(にじ)み出してきたのだ。
彼はその快感が、初めて手にした自由による歓喜(かんき)であると思っていた。
それまでずっと霧(きり)が掛かっているようだったゴドウィンの頭の中は、ナニもかもが鮮明になり、あらゆる事柄の輪郭(りんかく)をハッキリと感じる事ができるようになったのである。
惨劇(さんげき)に悲鳴を上げ続ける母を落ち着かせ、彼は裏庭に穴を掘ると、バラバラに切断された父の死体を埋めたのだった。
それから数日間、ゴドウィンは最高に幸せな日々を過ごした。
だが間もなくすると、今度は母が彼の『父親殺し』をなじりはじめたのだ。
母親のアンは、ゴドウィン以上に父の被害者であり、自分の味方であると信じていたのに、彼女はあんな男を愛していたのだ。
いつまでも繰り返される母の声がうるさく、ゴドウィンは苛立(いらだ)ちがつのっていった。そしてそれが頂点に達した時、彼は彼女の首を絞めて殺してしまったのである。
驚く事に、愛していると思っていた母親を殺しても、ゴドウィンにはなんの感情も湧(わ)いてこなかった。もっと悲しんだり、後悔したりするのかと思っていたが、むしろ心から余計な重しがとれ、楽になっていた。
ただ困ったのは、その日からの食事の用意であった。
家に置いてあった食材をすべて食べ尽(つ)くし、そのあと三日間は水だけで過ごさなければならなかった。彼は大いなる空腹に苦しんでいたのだ。
そんなところへ、たまたま1人の旅人が立ち寄った。
ゴドウィンは有無(うむ)を言わさず彼をナイフで刺し殺し、持っていたわずかばかりの食料に喰(く)らいついた。そして腰のベルトから金の入った袋を奪(うば)ったのだ。
ゴドウィンはその金を持って、すぐに近くの村に行き、さらに食事をした。そしてこう思ったのだ―――なんだ、簡単じゃないか。
ゴドウィンはあの時確かに空腹ではあったが、餓死(がし)寸前だったわけではない。飢えを満たす方法は他(ほか)にいくらでもあったはずである。しかし、彼は殺人という手段をとった。それが簡単であったからである。
それからの彼は、一人できこりの仕事を続けながら、時折立ち寄る旅人を殺しては、その荷物を奪(うば)って生活したのだ。
ゴドウィンは人を殺す事に何の罪悪感も感じない少年だったが、だからといって、殺人に快楽を感じているわけでもなかった。
生活のため木を切り倒すのと同じように、川で魚を釣って食べるのと同じように―――彼は人を殺した。それは食い扶持(ぶち)なのである。
ゴドウィンは自分が、目的のためならどんな悪行でも行える人間だという事に気づいていった。それが、たとえ神の道に反し、地獄に落ちるような行為であってもまったく平気なのだ。
きこりのジョンとその妻アンがいなくなったというのに、近在の人々は意外にもその事に気づかなかった。森の奥に住む、飲んだくれのきこり一家の事などどうでもよかったのだ。
当時は、スヴェン1世率(ひき)いるデンマーク王国軍の侵攻で、イングランド社会は騒然としており、そのような事にいちいち気を留める者など誰もいなかったのである。
ましてや、多くの旅人が行方不明になっている事など知るよしもなかった。
何人もの旅人を殺してきたゴドウィンだったが、武術などの修行を積んだわけではない。
時には、大したことないと思っていた旅人が、とてつもなく格闘に長(た)けている場合もあった。また、何度ナイフで刺そうとも、斧(おの)で斬りつけようとも、簡単に死んではくれず、激しく抵抗される場合もあった。
それでゴドウィンの身体には、無数のひっかき傷やナイフの傷跡、歯形などが残っていた。ひどい場合には、腕や肋骨(ろっこつ)を折られて、何日も動けなくなる事さえあったのだ。
ただし、どんなに負傷しようとも殺し掛けた旅人を逃がした事はなかった。全員を確実に殺してきたのだ。
16歳の冬に、ゴドウィンのきこり小屋に薬の研究をしている医者が一夜の宿を求めてきた。
彼は囲炉裏(いろり)の火に当たりながら、様々な薬について説明をしてくれた。
そしてゴドウィンはその時はじめて、毒薬なる物があり、それで人を殺せるという事を知った。
旅の医者は薬について書き記(しる)された分厚い本を持っていた。
夜中になると、ゴドウィンはいつものように彼を殺して、その本を盗んだのだ。
文字は母から教えてもらっていたが、本の実物など見た事もなく、さらに難しい内容だったので、それを理解するにはかなりの努力が必要とされた。
だが、彼は高い知能を持ち合わせており、そのお陰で何十回と読むうちに、その内容をほぼ理解したのであった。
本には、数々の毒薬や幻覚剤の作り方が記載されていた。
毒薬の材料は、その多くが森の中に自生している。
毒薬作りにおおいに興味を持ったゴドウィンは、その後、何人もの旅人を実験台にしては、その技術を磨(みが)いていったのである。
毒はやがて、ゴドウィンのお気に入りの殺害方法となった。
なんといっても、無駄な格闘をしなくてすむ。自分が傷ついたり、痛い思いをしなくてよいのだ。
さらに、刃物による殺害と違って血が流れない。これも大きな要因だった。大量の血で床や地面を汚してしまうと、その掃除も大変なのである。
そして、毒を使えば相手の服に刃物によるかぎ裂きも、血による染みもできない。つまり、服を町へもっていけば高く売れるのだ。
布地の大量生産ができなかった時代、服は庶民の平均年収の何倍もする、たいへん高価な物であった。
素材は羊の毛や麻(リンネル)などで、糸を紡(つむ)ぐところから始まり、その糸で布を織り、その布を裁断(さいだん)・縫製(ほうせい)してやっと完成するのである。そのすべての工程が手作業であった。
貴族や富豪の財産目録には、土地や金銀、宝石と同様に、ドレスが何枚、クロークが何着と記載されるほどの価値があった。
新品の服が着れるのはそうした金持ちだけで、庶民のほとんどは古着や家族から譲られた服を着て一生を過ごすのだ。
また、イスラム国家によって中国との貿易がほぼ途絶えていた時代、絹織物はビザンティン(東ローマ)帝国で作られるわずかな物があるばかりで、貴族でさえもなかなか手が出せない超高級品であった。
それゆえに、死んだ旅人達の服や靴などはいい商売になったのである。
だが、なによりも彼が毒殺を好んだのは、毒を飲まされたと気付いた時の旅人の表情にあった。呼吸困難な中、目を白黒させてゴドウィンの顔を見詰めるその表情がゴドウィンは最高に好きだった。腹を抱えて大笑いできるのだ。
ゴドウィンが21歳になった頃、彼の家に自分と同じ名前―――『ゴドウィン』という男が宿泊した。
男はサセックスの元従士(じゅうし=国王や貴族に仕える戦士の事)である『ウルフノース・チルド』の一人息子だと自慢し、その証(あかし)である指輪を見せびらかした。
『ああ、自分も貴族や従士(じゅうし)の子息だったらどんなによかっただろう 』
ゴドウィンはうっとりと夢想した。
そして、自分こそがこの指輪を持つにふさわしい人物であると考え、この男をトリカブトの毒で殺害したのだった。
もっとも、彼が指輪を持っていなかったとしても、おそらく殺していたに違いないのだが‥‥‥。
彼が森のきこり小屋でこの8年間に、刺殺(しさつ)、撲殺(ぼくさつ)、絞殺(こうさつ)、毒殺などで殺した旅人の数は、すでに50人を上回っていた。
そして、その被害者から盗み取った貴金属や服の代金、銀貨などはかなりの額になっているはずだった。だが、そのほとんどが残っていなかった。
材木や盗んだ服を近在の町に売りに行った時、飲食と女に使ってしまったのである。
飯を食いに行けば酒を勧(すす)められ、酒を飲むと女をあてがわれる。
彼の初体験は15歳の時、相手は20歳以上年上の売春婦であった。
それからは、ちょくちょく商売女を買うようになっていった。
材木を売りに行く小さな町である。売春婦はみな、最下層に生きる者達ばかりで、汚れたチュニックに頭巾を着け、顔はあちこちが煤(すす)で汚れていた。虫歯だらけの汚い口にべっとりと口紅を塗るだけの醜い女達である。時には、母親よりもはるかに年上の女もいた。
だが、美しい女などほとんど見た事のなかったゴドウィンは、そんな女達でもさほど気にはしなかった。
ゴドウィンは殺人鬼だったが、女性に対して加虐的(かぎゃくてき)嗜好(しこう)があったわけではない。女性を犯したり、殺したりする事に快感を感じる性癖ではなかった。
ただし、女性にちやほやされると妙に嬉(うれ)しかった。単純にモテたかったのである。
そんな時、自分は元貴族の息子だとウソをつき、あの指輪を見せるのだ。すると、売春婦達の目の色が変わった。歓声が上がり、おべんちゃらやお世辞が飛び交った。
そうすると、ますます嬉(うれ)しくなって、さらに金を使ってしまうのである。
だが、この1、2年、きこり小屋を訪(たず)ねてくる旅人はめっきりと減っていた。あの『ゴドウィン』も久しぶりに訪(おとず)れた旅人だったのだ。
デンマークの侵略がますます激しくなり、街道を通る者達は軍の関係者ばかりで、呑気(のんき)に旅をする者などほとんどいなくなっていたからである。
そのせいで、ゴドウィンの家計は大赤字になろうとしていた。
そこで彼は一念発起(いちねんほっき)し、ロンドンに移住する事を決めたのだ。
どうせ強盗殺人を行うのなら、人口が多い場所に行った方が効率がよいと考えたのである。
こうして、凶悪な殺人鬼が大都会に放(はな)たれたのであった。
だがこの時点で、この恐ろしい殺人鬼が将来イングランド一の大貴族になろうなどとは、誰も―――本人のゴドウィンさえも、予想だにしなかった事であった。