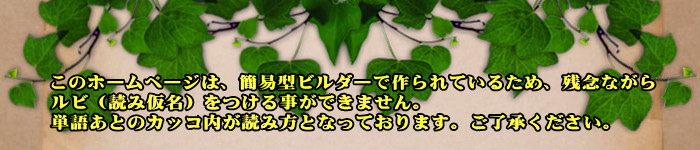
63
1027年 ファレーズ城(1)
「本年は、1月早々にも兄リシャール大公とフランス国王ロベール2世陛下の御公女(ごこうじょ)―――アデル殿とのご成婚が執(と)り行(おこな)われます。 さらに7月には、わたくしとエルレヴァとの子供も産まれるのです。 めでたい事ばかりが続く、良き1年となる事でしょう 」
ファレーズ領主ロベール伯爵は、大広間に集まった家臣や騎士などの前で挨拶をした。
「戦士、家政の隔(へだ)たりなく、この場にいる全員が本年もノルマンディーとファレーズに忠誠を誓(ちか)い、各人がその本領(ほんりょう)を十分に発揮(はっき)される事を切に望みます。 ―――では、乾杯! 」
一同は、歓声とともに木製のゴブレットを掲(かか)げ、中身を一気に飲み干した。
この乾杯より、1027年『新年の宴(うたげ)』が始まったのだ。
その宴席は、降誕祭(クリスマス)などとは違い、兵士や家臣などごく限られた身内だけで催(もよう)された慎(つつ)ましやかなものであった。
だが、いくら規模の小さな催(もよお)しとはいえ、酒を出すタイミング、料理を出すタイミングなど、そう簡単なものではない。にもかかわらず、はじめて差配(さはい)を任(まか)されたエルレヴァの手腕(しゅわん)はなかなかのものであった。
大半の準備はティボーが事前に行(おこな)っていたとはいえ、最初からここまで出来るというのは、彼女の聡明(そうめい)さあっての事だろう。
広間の壁には、ピンクのリボンが何本も巡(めぐ)らされ、燭台(しょくだい)の蝋燭(ろうそく)も外側を赤く塗られた物が使用されていた。それはちょっとした事であったが、宴席に女性らしい華(はな)やぎを醸(かも)し出していた。
× × × × ×
この当時の『新年初日』は、1月1日とは限らず、キリスト教各宗派や国、都市によってバラバラであった。
ローマキリスト教会ではユリウス暦を使用していたが、基本的には、主イエスの降誕祭である12月25日を新年初日としていた。
ユリウス暦とは、紀元前45年、ガイウス・ユリウス・カエサル(英=ジュリアス・シーザー)が導入した太陽暦で、1月1日を新年初日としていた。
だが、国によっては、受胎告知(じゅたいこくち)である3月25日や、復活祭(イースター)である4月上旬などを新年初日とするところも多かった。
受胎告知は、処女であった聖母マリアが、天使ガブリエルから主イエスを身ごもった事を告げられた日である。
復活祭(イースター)は、ゴルゴダの丘で磔刑(たっけい)に処された主イエスが復活した日であり、3月22日から4月25日の間に行われる。
イエスの処刑から三日後の日曜日に、聖母マリア、マグダラのマリア、サロメの三人の女性が彼の墓を訪ねると、そこに主イエスの遺体はなく、中にいた青年が『彼は生き返ってここを立ち去った』と告げたのだ。
キリスト教会では、その日をイエス・キリストの復活の日とし、『春分の日のあとの、最初の満月の次の日曜日』と定めたため、年によって日付が変わる移動祝日となったのである。
また、ヴェネツィアなどイタリアの都市国家では18世紀まで、一年が10ヶ月=3月から始まり12月に終わる古代ローマ暦が使用されており、3月1日を新年初日としていた。
つまり、ユリウス暦における1月1日は、理論上の新年初日であり、各国共通ではあったが、キリスト教がすべての事象の最上位にあった中世ヨーロッパにあって、それは行事としてさしたる意味を持ってはいなかった。
その日を祝日とする国や都市もあったが、そうではない国や都市も多かったのである。
ノルマンディーでは降誕祭(クリスマス)からを新しい年としていたが、1月1日も暦(こよみ)上の新年初日として祝う事にしていた。
× × × × ×
宴もたけなわとなり、5度目の乾杯が行われた。
頼純はリンゴ酒(シードル)を呷(あお)りながら、『またひとつ歳をとった。 今年はもう三十四か‥ 思えば遠くに来たもんだ‥‥ 』などと、感慨(かんがい)にひたっていた。
その時、広間の扉が開かれ、鎖帷子(オベール)と兜(カスク)で武装した3人の男が登場した。
「ロベール殿‥ 祝いの宴(うたげ)のさなかであろうが、邪魔をするぞ! 」
突如、侵入してきた招かざる客に、ロベールの騎士達はいっせいに立ち上がり、剣に手を掛けた。
「おお‥ これは弟殿ではございませんか‥! 新年早々、どうなさいました? 」
ロベールは席から立ち上がり、笑顔でその不審者を迎(むか)え入れた。
3人の先頭に立つのは、ブルゴーニュ伯の嫡男(ちゃくなん)ルノーであった。現在40歳である彼は10年前、ロベール伯爵の妹アデレイドと結婚していた。つまり26歳のロベールにとって14歳も年上の義弟だったのだ。
不審者でないと判り一同がホッとする中、兜(カスク)を小脇にかかえた彼だけが、ひとりマントを翻(ひるがえ)してメインテーブルへと進み出た。
「貴公は我が父、オットー・ギヨーム伯爵の行方(ゆくえ)について、何かご存じではないか? 」
ルノーの唐突(とうとつ)な質問に、ロベールは困惑(こんわく)した表情を浮かべた。
「い‥ いいえ! お父上様がパリのロベール国王陛下に、年末、会いに行かれたという―――噂話ていどならお聞きしておりますが‥‥ 」
オットー・ギヨーム伯爵は、身分はロベールと同じ伯爵であったが、イタリア王を父に持つ名門の出身である。フランス国王とも姻戚(いんせき)関係にあった。
「それが、3週間ほど前‥ パリを出発した後に消息(しょうそく)不明となったのだ! 」
「そうですか‥ それはご心配の事でしょう。 しかし、なにゆえにそのご消息(しょうそく)を、わたくしにお尋(たず)ねになるのです? 」
ルノーの眉間(みけん)には深いしわが刻(きざ)まれていた。
「伯爵がいなくなったと連絡をしてきた父の家臣はカーンにいた。 父、オットー伯の一行は、わずかな供回りだけを率(ひき)いて、ノルマンディーのカーンに行っていたのだ 」
「カ‥ カーンに‥!? 」
カーンはファレーズの北側にあり、公都ルーアンに次ぐノルマンディー第二の都市であった。
「ああ‥ 彼らが言うには、父は船でパリからセーヌ川を下り、外洋に出てからオルヌ川へ入ると、カーンに向かったそうだ 」
ルノーを招き入れようとメインテーブルで立ち上がったまま話を続けていたロベールは、やっと納得顔となった。
「なるほど、カーンとなれば我がノルマンディー公国領ですからね。 それで、わたくしに―――? 」
しかし、テーブルの前に立つルノーは、ゆっくりと首を振った。
「そうではない‥ 父はその数少ない供回りさえも残して、ひとり出掛けたらしい。 そして、そこからの消息(しょうそく)がプッツリと途切れたのだ。 ただ昨日、ある船頭から、父らしき身なりのいい貴族を船で運んだという証言を得る事ができた 」
その言葉に、頼純が嫌な顔でルノーを振り返った。
「‥‥‥ 」
「船頭はその貴族を、トレノ村という場所まで運んだと語ったのだ‥! 」
「え!? ト‥ トレノ村―――? 」
驚いた声を上げるロベール伯爵。
その場にいた家臣達からも、『トレノ村‥ トレノ村‥‥ 』と、さざ波のように言葉が繰り返され、やがて広間はシーンと静まりかえった。
ルノー以外の全員が、オットー・ギヨーム伯爵が何をしたのか想像がついたのだ。
そんな気配に気づかないルノーは、さらに話を続けようとした。
「そこで、私がトレノ村まで行くと――― 」
ロベールはルノーに手のひらを向け、彼の話を制した。
「ちょっと、お待ちください! そのお話は別室でお伺(うかが)いいたしましょう 」
ルノーは『やはり』と言わんばかりに、眉を顰(しか)めた。
「つまり‥ 貴公は、なにか知っておるという事だな? 」
その問いには答えず、ロベール伯爵は奥への扉を手で示した。
「ともかくこちらへ――― 」
領主の館(メヌア)の中は部屋数がたいそう少なかった。それゆえ、そこに住む者達に、プライベートな空間などほとんどない。
ロベールはルノーとの話を寝室でするか、礼拝堂(シャペラ)でするか迷ったが、けっきょく彼を寝室に通す事にした。
ロベールの寝室はそれなりの広さがあった。今後、正室となる夫人のベッドや彼女から産まれてくる子供達のベッドなどもその部屋に置かれるからであった。むろん、正室にはなれないエルレヴァやその子供は、この部屋で寝起きする事はできない。
あいた空間にはテーブルも置かれ、椅子(いす)が6脚ついていた。
ロベールはルノーをそこに腰掛けさせ、その対面に自分と連れてきた頼純も座らせた。
「では‥ お話の続きをお伺(うかが)いいたしましょう 」
ルノーはゆっくりと頼純に顔を向けると、その目を見詰めたまま、話し始めた。
「父が消息(しょうそく)を絶った翌日、トレノ村近くの食堂で火事があり、たくさんの人が焼死したと聞いた 」
「ええ‥ その事は承知しております。 あそこまでが、我が領内ですからね 」
「では‥ それらの焼死体すべてが、無残にも手足をバラバラにされていたという事も―――貴公はご存じか? 」
「はい‥ 存じ上げております 」
「食堂が火事になった朝、トレノ村には多くの少年と血まみれになった青年達が訪(おとず)れたそうだ。 その少年達は誘拐された被害者であり、彼らを救い出したのは、血まみれの青年達と『勇者ヨリ』だったとか―――! 」
「ああ‥ その『ヨリ』てーのが、この俺の事だよ! 」
頼純は、ルノーが自分の事に気づいていると知った上で、彼に名乗り出た。
「では、聞こう。 お前は私の父を殺したのか? 」
「さあ‥ そいつは知らネーな! 」
ルノーはテーブルをドンッと拳(こぶし)で叩いた。
「とぼけるでない! おのれが我が父を殺したのであろう!? 」
だが、頼純はシレッとした顔で答えた。
「この俺が、食堂にいた者全員を殺した事は事実だ。 だが、殺されたのが誰だったかは、一切確認していない。 こいつは、誰に聞いてもらってもそう答えると思うゼ 」
しらを切るような頼純の態度に、ルノーの苛立(いらだ)ちがつのる。
「貴様ァ‥ とぼけるつもりかッ! 」
なんとかルノーの誤解を解こうと、ロベールが声を掛けた。
「まあまあ‥ まずは、こちらの事情を説明させてはいただけませんでしょうか!? 」
ルノーは言い訳だけは聞いてやると言わんばかりに、その申し出を受け入れた。
「よかろう! さっさと申し開きするがよい。 ただし、その物言いによっては、我がブルゴーニュとの戦争も覚悟されよ! 」
だが、ロベールの表情は硬く、その口は重かった。
これから彼に、あそこで起こった恐ろしい事件について告げなければならないからだ。そして、もし彼の父がその事件に関与していたのであれば、それは彼に巨大な衝撃を与えるだろう事も承知していた。
「い‥ いま、なんと申された‥? 」
ルノーは、彼の年若き義兄が何を言っているのか、その意味がまったくわからなかった。
それも無理はないと思ったロベール伯は、神妙(しんみょう)な面持(おもも)ちでもう一度ゆっくりと説明した。
「ですから、あの食堂は‥ 子供をさらっては、その子達を殺し、料理として出していた人肉食堂だったのです。 そして、そこの客は全員、その料理の材料が子供である事を知った上で、好んでそれらを喰っていました 」
「‥‥‥ 」
ルノーは固まったまま、何も語らなかった。
親族にとって、それはにわかには信じ難(がた)い話であろう。
頼純が重々しい口調でさらに付け加えた。
「だから、この俺はその悪魔全員を斬り殺して、焼き払ったんだ。 ふたたび蘇(よみが)える事ができないようにね! 」
頼純は、ゴルティエら『カラス団(コルブー)』達に累(るい)が及(およ)ばぬよう、すべて自分がやったと語ったのだ。
その時、それまで言葉を失っていたルノーの口が、ゆっくりと動いた。
「な‥ なにが――― 」
ひと言目をなんとか絞(しぼ)り出すや、ルノーは激しい口調で反論し始めた。
「何が悪魔だ! 父はけっしてそのような人物ではないッ‼ 領民を慈(いつく)しみ、領民からも慕(した)われる心優しき領主なのだぞ。 そのような父が、幼き子供を喰らう悪魔だったなんて絶対にあり得ない! 」
父を守ろうとするルノーに、頼純は否定も肯定もしない。ただ、事実だけを伝える。
「だから‥ 俺は別に、あんたの父親が、『子供を喰った』だの、『悪魔だった』だのと言ってるわけじゃネーんだ。 ただ、あの食堂にいた者は全員が人食いの悪魔だった。 それだけは間違いない! 」
しかし、頼純も心の中では、ルノーの父親が『カラス団(コルブー)』達に殺された一人であろうと思っていた。
ルノーは、木で鼻をくくったような頼純の態度が許せなかった。激しい怒りが湧(わ)き上がってきたのだ。
「き‥ 貴様ァァァァア‥‥‼ 『勇者』だか、なんだか知らないが‥ 下郎(げろう)の分際で、この私に口答えするとは、ただではすまさんぞ‼ 」
ルノーは怒鳴り続けた。
しかし、彼のこの『怒り』は、『不安』と『恐怖』に由来していた。
―――はたして、自分は父親の事をどれほど知っていたのであろうか‥? 自分が知っていたのは、父のほんの表面部分だけで、もしかしたらその内側にはどす黒い心が隠されていたのではないだろうか?―――ルノーは口とは裏腹に、父が絶対に潔白であるという確信が持てなかったのだ。
さらにもし、父が『悪魔』だったら、自分はどうなってしまうのだろうか‥‥自分や家族が世間から受けるであろう激しい糾弾(きゅうだん)など、恐ろしい未来が頭の中をグルグルと駆け巡(めぐ)っていた。
その『不安』と『恐怖』が、逆に『怒り』となって爆発したのだ。
ロベールはそんなルノーをなだめようとした。
「ともかく‥ 落ち着いてください! お父上、オットー・ギヨーム伯爵が、その食堂にいたとは限らないでしょう。 似た人物がカーンからトレノ村まで船に乗ったと言うだけで、お父上の消息(しょうそく)はカーンまでしか立証されておらぬのですぞ 」
「だ‥ だが‥‥ 」
「似たような顔はよくある事ですし、船頭の勘違いかも知れません。 金目当てにウソをつく事だってあります 」
「‥‥‥ 」
「しかも、食堂の焼け跡に残された死体は完全に炭化し、彼らがどこの何者だったのかまったく判らないのです―――身分を明らかにするような物もすべて無くなっておりました。 おそらく近在の村人らが、そういった金目の物を盗んでいったのでしょうが‥‥ 」
「‥‥‥ 」
「つまり、オットー・ギヨーム伯爵がその場にいた―――『悪魔の料理』を食べていたという証拠は何もないのです。 存外(ぞんがい)に、ひょっこりお父上がお戻りになるやもしれませぬぞ 」
ルノーはゆっくりと首を振ると、憎しみのこもった目で頼純を指差した。
「いいや‥ この男の顔を見て確信したよ! 父はこの男に殺されたに違いない。 満足な取り調べも行(おこな)われず、あらぬ疑いで父は処刑されたのだ! 」
もはやそれは言いがかりに過ぎなかった。
「貴様は絶対に許さんぞ‼ 」
「ったく‥もう! 」
頼純はふてくされた顔をルノーに返した。