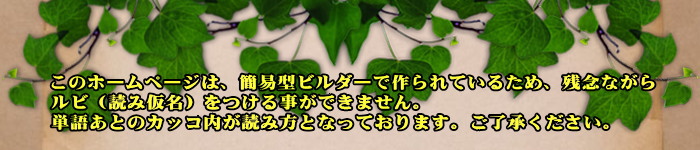
18
1026年 ファレーズ城内・広間
× × × × ×
何度も繰り返し登場するが―――ヨーロッパ諸国の歴史は、西ローマ帝国がゲルマン民族によって崩壊(ほうかい)させられたところから始まる。
西暦476年に西ローマ帝国が滅ぼされると、ヨーロッパには幾(いく)つものゲルマン王国が興亡(こうぼう)を繰り返した。
西ゴート、東ゴート、ヴァンダル、ブルグンド、ランゴバルド‥‥
そんな中、ヨーロッパ北部、フランドル周辺に定住していたゲルマンの小部族サリ・フランク族は、西暦481年にクロヴィス1世が族長になるや、またたく間に周辺のフランク族を統一、メロヴィング朝フランク王国を建国するのである。この時、クロヴィスはわずか16歳にすぎなかった。
その後も、彼は幾多(いくた)の戦いに勝利し、また他国と政略結婚をかさね、さらにはアタナシウス派キリスト教(カトリック)に改宗するなどして西ヨーロッパに盤石(ばんじゃく)な基礎を築いていく。
そしてクロヴィスが41歳となった西暦507年、ガリアに居座っていた巨大国家「西ゴート王国」をついに破り、彼らをイベリア半島まで駆逐(くちく)するのである。
やがてフランク王国はガリア全土を得、その版図(はんと)を大きく広げる事となる。
このメロヴィング朝は、その後270年間十四代にも渡って続いた。
だが、メロヴィング朝宮廷内では、しだいに国王よりも宮宰(きゅうさい=マヨル・ドムス)の権力が増大していく。
宮宰(きゅうさい)とは、本来は王家・公家(こうけ)の私的な管理人―――『執事』的な立場の者の呼称であった。しかし、彼らは王家・公家(こうけ)の財務管理から騎士団の長までをも務めたため、実質的には家老・大臣のような、王に次ぐ最高職となっていた。
そして、メロヴィング朝において宮宰(きゅうさい)の影響力を決定づけたのがカール・マルテルであった。
西暦732年、西ゴート王国を征服したウマイヤ朝のイスラム勢力が、勢いに乗じてフランク王国にまでなだれ込んできた際に、カールは『トゥール・ポワティエ間の戦い』でこれを破り、彼らをイベリア半島まで押し戻したのだ。
強力な兵力を持った異教徒ウマイヤ朝からフランク王国を守った事は、国内の貴族達に高く評価された。
そしてその子、ピピン3世はローマ教皇(きょうこう)やフランク族貴族らの推挙(すいきょ)を受け、西暦751年ついに国王となるのである。
これがカロリング朝フランク王国の始まりとなった。
メロヴィング朝最後の王であったキルデリク3世は、新王となったピピンに幽閉(ゆうへい)され、3年後に獄死(ごくし)する。これによって、始祖(しそ)クロヴィスの血筋は途絶(とだえ)える事となる。
さらに、ピピン3世の子、シャルル・マニュー(カール大帝)は、53回もの軍事遠征をおこなった結果、最大領土(現在のフランス、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、チェコ、スロバキア、イタリアなどなど)を保有する事となる。
イベリア半島、イングランド、スカンジナビア半島をのぞく、全ヨーロッパを国土としたカロリング朝フランク王国は、ビザンティン(東ローマ)帝国に匹敵(ひってき)するほどの超大国となったのである。
しかしながら、シャルルマニューの子、ルイ(ルードリッヒ)1世は、ゲルマン族の習慣にならって、その領地を三分割し、東フランク王国、中央フランク王国、西フランク王国として、三人の息子達に分け与えたのだ。
この西フランク王国が、フランスの原初(げんしょ)となった。
西暦843年、シャルル2世から始まった西フランク王国は、5代目のルイ5世が亡くなると、教会から「王位は世襲(せしゅう)ではなく、気品と英知で選ばれるべき」として、その継承に介入される。
そして、ルイ5世の摂政(せっしょう)であったユーグ・カペーが推挙(すいきょ)される事になる。
諸侯(しょこう)貴族らもこれに反対しなかったため、西暦987年、フランク公であり、パリ伯であったユーグ・カペーが王位を継いだのである。
これがカペー朝の始まりであった。
しかし、当時のフランク王国は各地で諸侯(しょこう)が群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)しており、国王であろうとも、彼らを統治する事は不可能だった。
新国王・ユーグ・カペーの直轄(ちょっかつ)領は、彼がパリ伯だった頃の領地―――イル・ド・フランスと呼ばれたシテ島周辺とオルレアンしかなかった。
彼は脆弱(ぜいじゃく)な権力と、ちっぽけな経済基盤しか持ち合わせていなかったのである。
人々は彼を、『名ばかりの王』―――と呼んだ。
だが、このカペー朝をもって、この地は西フランク王国からフランス王国と呼ばれるようになる。
そして彼の血は、マリーアントワネットとともに断頭台(だんとうだい)の露(つゆ)と消えたルイ16世まで約八百年間、国王として君臨(くんりん)し続けるのである。
1026年頃のフランス王国は、ユーグ・カペーからその子、ロベール2世へと国王の座が引き継がれていた。
しかし、いまだに『力』を持たない王国宮廷内は、さらに前年に亡くなった長男ユーグに代わって、次男アンリと三男ロベールのどちらを皇太子(こうたいし)にするかで大いにもめていた。
そのような混乱した宮廷を、諸侯(しょこう)貴族が重んじるわけもなく、彼らは自分達の領地を思うがままに支配していた。
ノルマンディー大公リシャール3世もそのような支配者の一人だったのである。
× × × × ×
ファレーズ城の『領主の館(メヌア)』内は、兵士から料理人、野良猫にいたるまで、張り詰めた空気の中、ビクビクとしていた。
館の広間入り口ドアが荒々しく開かれると、二十人ほどの兵士達がドカドカと入ってくる。
その中央には、厳重に緊縛(きんばく)された頼純がいた。
後ろ手に幾重(いくえ)にも縄(なわ)で縛(しば)られた頼純は、兵士達に無理やり引きずられている。
全身から砂埃(すなぼこり)を巻き上げる彼は、髪は千々(ちぢ)にほつれ、裸足(はだし)の足は傷だらけになっている。
力無く俯(うつむ)くその首にまで、二本の縄(なわ)が掛けられていた。それぞれの縄(なわ)の端は、二人の兵士が手のひらに巻き付けて握っている。
頼純が無理に逃げようとすれば、その首は呼吸ができないほどに締め付けられるであろう。
頼純の周囲に付き添った8人の兵士は、抜き身の剣を握り締めたまま、彼を強引に玉座の前に跪(ひざまず)かせた。
それはもう、冥府(めいふ)から這(は)い出てきた怪物でも相手にするかのような物々しい警備であった。
そこには、サミーラをはじめとする隊商(キャラバーン)の人々の姿はなかった。あの森に置き去りにされたのである。
彼らの目的はあくまでも頼純の捕縛(ほばく)にあったのだ。
頼純から十数ピエ(4~5メートル)前方にある玉座(ぎょくざ)には、この地の領主ロベール伯爵ではなく、その兄、ノルマンディー大公リシャール3世が腰掛けていた。
頼純の逮捕・連行を任(まか)されたノルマンディー公国家宰(セネシャル)・オズバーン伯が声を上げた。
「大公様のお申しつけ通り‥ 異教徒・ヨリズミを召(め)し捕(と)ってまいりました。 どうか、存分(ぞんぶん)にご検分(けんぶん)を! 」
玉座(ぎょくざ)にふんぞり返ったリシャール3世は、険(けわ)しい表情で頼純を睨(にら)むと、
「下郎(げろう)‥ 面(おもて)をあげい! 」
けっして大きくはないが、誰もが一瞬息を止めてしまいそうな、威厳(いげん)に満ちた声を放(はな)った。
だが、頼純は俯(うつむ)いたままピクリともしない。
リシャールが坐る玉座(ぎょくざ)の右横には、心配そうに頼純の様子を覗(うかが)うロベールが立っている。
「ヨ‥ ヨリ殿‥ 」
反対側には、ニヤニヤ顔で頼純を見下ろすティボーの姿もあった。おそらく彼が、自分の都合(つごう)のいいように大公に吹き込み、それに怒ったリシャールが頼純の逮捕を命じたと思われた。
また広間の両側には警備の兵士達と共に、リシャールの近習(きんじゅう)であるアンリやフェルディナン、シャルル、ジョルジュなどの上級騎士の面々もいた。
頼純を連行したオズバーン卿は、彼が頭を上げる力さえないのも無理はないと思っていた。
そのように仕向けたのはオズバーン自身だったからである。
用心深い彼は、頼純についての聞き取り調査を行い、その圧倒的強さを知るや、通常の五倍の人員(じんいん)で捕縛(ほばく)に向かった。頼純の逮捕後も、気を緩(ゆる)めることなく護送(ごそう)したのだ。
頼純が暴れる事ができないように、捕らえてから二日間、いっさい水を与えていなかった。
そしてその間、頼純は馬に牽(ひ)かれて、駆け足でこの地までやって来たのだ。
喉がカラカラというよりも、すでに死にかけていた。頭を上げるどころか、声すら出す事ができないだろう。
顔を上げる事ができない頼純に業(ごう)を煮(に)やしたリシャール3世は、頼純の傍(かたわ)らの兵士へ声を掛けた。
「おい‥ 」
「はッ! 」
剣を構えた兵士は頼純に慎重(しんちょう)に近寄ると、その髪を鷲掴(わしづか)みにして、頭を無理やり上げさせた。
その時、広間の一同がどよめいた。
クタクタになっているハズの頼純が、笑っていたからである。
「お‥ おい‥ や‥ やめろって‥ か‥ 髪が‥ 髪が乱れるだろうが‥‼ 」
パサパサに干涸(ひか)らびた唇が動いた。
「ムム‥ 」
死にかけてもなお悪態(あくたい)をつく頼純の剛胆(ごうたん)さに、リシャールはむしろ怒りが湧(わ)き上がってきた。
リシャールは、彼が脅(おび)え、涙を流し、自分の足元にひれ伏(ふ)して許しを請(こ)うに違いないと思っていたからである。にもかかわらず、頼純はその期待を裏切ったのだ。
頼純は疲れ切った顔で周囲を見回すと、かすれ声で一同に毒づいた。
「な‥ なんだ、テメーら‥ 雁首(がんくび)揃(そろ)えやがって‥ 俺に殺されるために集まってきやがったのか‥? あん‥!? 」
頼純の目は死んでいなかった。爛々(らんらん)と輝いているのだ。
「強がりを申すでない! お前の方こそ、死ぬ寸前なのだぞ! 」
オズバーンが頼純をきつくたしなめた。これ以上、事態を悪化させないためである。
オズバーンとて、この捕縛(ほばく)はさすがにやり過ぎたと反省していた。そして、なんとかこの男を助ける方法はないかと、考えていたのである。
その場の空気を和(なご)ませるためか、近習(きんじゅう)のアンリやフェルディナンが軽口を叩いた。
「なるほど‥ 異邦人にしては、じつに見事なフランス語だ‥! 」
「しかし、言葉使いに品(ひん)がない。 下賤(げせん)の者にでも習(なろ)うたか? 」
「きっと、女郎(おなご)に違いなかろう♡ 」
その侮蔑(ぶべつ)とも冗談ともつかぬ会話に、数人の家臣がクスクスと笑った。
だが二人を無視したリシャール3世は、厳しい表情で頼純を見据(す)えた。
「お前が捕らえられたのは‥ そのように、貴族に対して無礼な口をきくからだ! いくら弟を助けたとはいえ‥ 我がノルマンディー公国、我がフランス王国を侮辱(ぶじょく)する者は、けっして許されない! 」
それに何か言い返そうとした頼純を遮(さえぎ)って、リシャールは彼への判決を申し渡した。
「我がノルマンディー巡回(じゅんかい)裁判所は、我らが名誉を傷つけた罪と、この館(やかた)内にて乱暴狼藉(らんぼうろうぜき)を働いた罪に対し、鞭(むち)打ち十回の刑を与える。 心して罰(ばつ)を受けよ! 」
その判決に一同は驚いた。皆が予想していた以上に重い処罰だったからである。
鞭(むち)打ちの刑は、長い長い鞭(むち)によって行われる。
その鞭(むち)で打たれると、一回目で打たれた背中には巨大なミミズ腫れが走り、三回目にはその皮が裂(さ)ける。五回も打たれると背中や首の肉が爆(は)ぜ、七、八回目には骨にまで達するだろう。
十回も打たれようものなら一生消えぬ障害が残り、悪ければ命まで落としかねない―――非常に過酷(かこく)な刑罰なのである。
だが、頼純はせせら笑った。
「へ‥ へへへ‥ おい‥ おいおい‥ そ‥ そんなモンで、いいのかい‥ ああ? ここで俺を確実に殺しといた方がいいと思うゼ‥! じゃネーと、アンタは一生、俺から命を狙われるコトになる‥! これから先、ずっと‥ この俺がいつ殺しに来るのかって―――ビクビク脅(おび)えて暮らさなきゃならねェんだ‥! そうなっても、いいのかい♡ 」
「!! 」
たどたどしい口調ながらも、鋭い眼光(がんこう)の頼純に睨(にら)まれ、リシャールは一瞬気圧(けお)された。
頼純はリシャールのそのわずかな『脅(おび)え』を見逃さない。
「し‥ しっかし‥ さすがはバイキングの子孫達だ‥ 罪もない隊商(キャラバーン)を襲い‥ 女子供を人質にして、俺を強制連行し‥ あらぬ疑いで半殺しにしようっていうんだからよ‥! ご‥ 強盗団やってたご先祖様も大喜びしてるだろうゼ‥! 」
先ほどまで死にかけていた彼も、幾分(いくぶん)元気を取り戻したかのようだった。
「コ‥ コラ‥! 」
オズバーンが、頼純の悪態(あくたい)を止めようとした。ノルマンディーでは、ご先祖様が強盗団(バイキング)であった話は御法度(ごはっと)なのだ。
だが、時すでに遅し。リシャールの怒声(どせい)が広間に響いた。
「よォ~~~し! お前の望み通り‥ お前に死罪を申し渡す! 即刻、その者の首を刎(は)ねよ! 」
リシャールは、頼純の『脅し』に一瞬でもドキリとしてしまった自分を恥じていた。そして、その羞恥(しゅうち)が頼純への怒りへと転嫁(てんか)されたのである。
「じょ‥ 上等じゃネーか! この素首(そっくび)‥ 刎(は)ねれるモンなら、刎(は)ねてみやがれ! 」
頼純がリシャールに怒鳴り返した。
なぜこの状況にあって、わざわざリシャールを怒らせるような無礼な言葉を並べ立てるのか―――誰も頼純の胸中を理解できなかった。
しばし、呆気(あっけ)にとられている一同の耳に、リシャールのさらなる命(めい)が飛び込んでくる。
「やれ‼ 早く、首を刎(は)ねるんだ! 」
その声にしたがって、さきほど頼純の髪を掴(つか)んだ兵士が、長剣をゆっくりと振り上げた。
この危機をまったく無策(むさく)で迎(むか)える頼純であるとは思えなかったが、彼が絶体絶命である事は間違いなかった。
その時、悲痛(ひつう)なる声が広間に響き渡った。
「お‥ お待ちください! 」
声を上げたのは、ロベールだった。
「兄上‥ 兄上はおかしいですよ。 このヨリ殿は、わたくしを山賊から助けてくださった方ですよ。 兄上はお礼を申し上げねばならない立場なのではありませんか? なのに、いきなり首を刎(は)ねよとは―――このロベール、納得がいきません! 」
ゆっくりとロベールを振り返ったリシャールは、見下した態度で語った。
「お前は、何も分かってはおらぬ。 このように、貴族や騎士を恐れぬ者を放っておいてはいかんのだ。 それでは民に示しがつかんだろう。 また、近隣(きんりん)や配下の貴族達から、このノルマンディーが侮(あなど)られる事にもなろう。 それが、反乱や戦争の原因となるのだ! 今後の諍(いさか)いを防ぐためにも、ここはこの男を厳しく処罰せねばならない。 それこそが、我らの生き残る道なのだ 」
だが、それでも納得がいかないロベールは、いつになく兄に食い下がった。
「け‥ けどォ‥ どうか、お願いします‥! 今回だけは、わたしの願いを聞いてください‥ どうか、彼を許してやってください。 」
そこへティボーが割って入る。ロベールをしたり顔で諫(いさ)めるのだ。
「兄上の申されるとおりでございます。 先日のこの者による乱暴狼藉(ろうぜき)の噂(うわさ)は、すでにノルマンディー中に広まっております。 その噂(うわさ)を治めるためにも、一罰百戒(いちばつひゃっかい)―――我らが、この者を罰したという事こそが重要なのでございます 」
その言葉とは裏腹に、ティボーは腹の中で『ざまぁみろ』とほくそ笑んでいた。寝小便の秘密をバラされた恨(うら)みは深かった。
だが、この期(ご)に及んでも頼純の口は止まらなかった。
「でェ、今度は‥ リシャール大公は‥ たかが悪口を言った程度の旅人一人を捕まえるために‥ 大量の兵士を出し、罠(わな)まで使わなきゃならなかったって―――騎士達は誰一人、剣を振ることもなく、コソコソ隠れてた―――って噂(うわさ)されるんだろうぜ‥! よかったな♡ 」
リシャール3世は声を荒げた。
「ナ‥ ナニィ! 」
「で‥ でもまあ‥ しょうがねェか‥!? ノルマンの騎士はどいつもこいつもへっぽこばっかりで‥ 俺とまともに剣で戦ったんじゃ、勝てネーんだしな‥! だから、俺が怖い! 怖いから、いろいろな理由をつけてこの俺を殺さなきゃならねェんだ! リシャール3世は臆病者なのさ‥ 」
リシャールは憤然(ふんぜん)として頼純を叱責(しっせき)した。
「なにを申すか! 農奴(のうど)や博打(ばくち)打ち上がりの山賊を、少々退治したからと言って大口を叩くでない! 我がノルマンの騎士ならば、一人でももっと多くの山賊を退治したであろう。 」
「ケッ‥ ナニ言ってやがる! その農奴(のうど)や博打(ばくち)打ち上がりに‥ ここの警備兵達は皆殺しにされたんじゃねェのかい‥! 」
「ええい、黙れい! 貴様とて、一人として山賊を殺せなかったではないか! もし、ワザと殺さなかったのなら‥ 人を殺す事にためらいがあるお前の心は弱い! 敵に情けを掛けていては、戦場では生き残れぬのだぞ! 」
「違うね‥! 戦場では、敵から戦闘力を奪うだけでいいんだ。 殺さずに傷つければ、そいつを救い出そうと数名の仲間達が戦列から離れる。 逆に殺しちまえば‥ 仲間を殺された怒りと、自分が死にたくない恐怖で、敵はムキになって挑(いど)んでくるんだ。 そうなれば、こちらの勝機(しょうき)も逃してしまう。 アンタこそ、『用兵』の何たるかをまるで判かっちゃいない! 」
「ギギギ‥ 」
ああ言えばこう言う頼純に、リシャールの苛立(いらだ)ちはますます募っていく。
頼純は、小馬鹿にしたような微笑を浮かべた。
「もちろん‥ それは俺が強いからできるのであって‥ ノルマン騎士のような‥ 弱い奴らには至難(しなん)の業(わざ)だろうがな‥! 」
「き‥ 貴様ァァァァ‥! 」
湧き上がる大きな怒りに、リシャールは玉座から立ち上がった。
そのリシャールの前に、ロベールが両手を広げて立ちふさがる。
「もう、お止(や)めください。 たとえ兄上とて、我が城内でこれ以上の勝手な振る舞い、許しませぬぞ! 」
「なにィィィィィィィい‥‼ 」
家臣の前で散々恥をかかされたリシャールは、激しい怒りに包まれていた。もはや、ロベールごと殺しかねない勢いだった。
そこに、やっと頼純の言いたい事を理解したオズバーンが声を上げる。
「ならば、ヨリズミ‥ お前が我が戦士と戦ってみよ! そうすれば、どちらが強いかハッキリするだろう。 」
オズバーンは、ロベールを睨(にら)むリシャールに向かって尋(たず)ねた。
「ねェ、大公様‥ 我がノルマン騎士が、このような風来坊(ふうらいぼう)に負けようハズがありません! この者は、我が戦士に斬り殺させるコトといたしましょう 」
「あ‥ ああ‥ 」
赤々と充血させた目でオズバーンを振り返ったリシャール大公は、噛(か)み締めた歯の隙間(すきま)から声を漏らした。
「そ‥ そうせい! 」
× × × × ×
城の中庭には、多くの兵士や家臣達が見物人として集まっていた。
ファレーズ領の兵士が120人ほど、城の召使い達は50人くらいで、リシャールが連れてきた騎士・兵士が約50人はいた。さらに、噂(うわさ)を聞きつけた街の医者や商人達も、何かと理由をつけ、衛兵に金を渡してでも、中庭へ入らせてもらおうとしていた。その数が100人ほど―――総勢300人を越える観衆が、この一戦を見逃してなるモノかと、期待に胸を膨(ふく)らませていた。
彼らは、頼純達が戦うタメの直径25ウナ(1ウナ=約1.2メートル。25ウナは約30メートル)ほどの空間を空けて、その周囲にびっしりと立っていた。
中には入れぬ一般の町民達は『領主の館(メヌア)』を囲み、その声や音だけでもいいからと―――塀の外から聞き耳を立てていた。
リシャール大公の御前(ごぜん)という事もあって、中庭は静かであったが、物凄(ものすご)い熱気に包まれていた。
縄(なわ)を解かれた頼純は、木のコップに入れられた水を2杯だけゆっくりと飲み干した。
喉(のど)はまだ渇(かわ)いていたが、飲み過ぎると体が動かなくなる。しばしの我慢であった。
続いて、体を動かしてみる。
腕の動きは悪かった。ずっと縛(しば)られていたせいか、筋肉が硬直して上手く回せない。
傷だらけの足も動きを鈍らせていた。
いつもの半分ほどしか、彼の力は発揮できないだろう。
それでもこの場で戦うしか、彼に生き残る道はないのだ。
頼純は、オズバーンから返してもらった太刀(たち)を静かに抜き払った。
その時、中庭にざわめきが起きた。
人垣が割れて現れたのは7ピエ(約2.1メートル)近い大男が二人。
一人は、両手にそれぞれ戦斧(せんぷ)を握っている。
もう一人は、右手に巨大な長剣、左手には分厚く大きな盾を構えていた。
誰が見ても、頼純に勝てる要素はなかった。