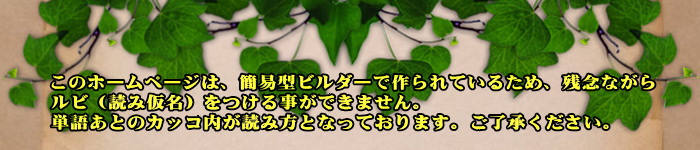
21
1026年 ファレーズ城・中庭(3)
兄エノーの大楯(おおだて)で吹き飛ばされた頼純は、起き上がろうと四つん這(ば)いになった。
その時、ふと目の前が真っ暗になる。
それが、盾(たて)の衝撃によるモノなのか、それともここ数日の過労によるモノなのかは判らなかった。
その頼純の背中めがけて、アンドレの戦斧(アシュ)が振り下ろされる。
背後の殺気を察知した頼純は、咄嗟(とっさ)に仰向けになってその刃(やいば)を躱(かわ)した。
ドゴンッ!と地響(じひび)きを立て、アンドレの斧が地面に突き刺さる。
いまだ地面に倒れたままの頼純に向かって、今度は兄エノーの長剣(エペ)が何度も突き立てられた。
「クソッ! 」
悪態をつきながらも、地面をゴロゴロ転がってその切っ先を躱(かわ)していくしかない頼純。
なかなか起き上がるきっかけが見つからない。
その時、エノーの攻撃に若干(じゃっかん)のためらいが生じた。
その隙(すき)を見逃す事なく、頼純は素早く立ち上がった。
さっと正眼(せいがん)に構えると、頼純は次の攻撃に備えた。
だが、二人は襲いかかっては来なかった。
先ほどまで、嵐のように剣や斧を振るっていた巨人兵の兄弟は、中庭中央に戻ると、手招(てまね)きするように長剣(エペ)と盾、戦斧(アシュ)と戦斧(アシュ)を打ち鳴らした。
「ホレ‥ 逃げてばかりいないで、かかって来いよ! 」
「どうした? 二人とも倒すんだろ? 」
頼純は静かに腰を落とすと、太刀(たち)の切っ先を斜め下におろす。
そのままゆっくりとした足さばきで、広場の外周に沿(そ)い、左へと移動していった。
そこへ再び、アンドレの斧による連続攻撃が襲いかかった。
「ホレ、ホレ! 」
だがその攻撃をも、頼純は上半身を左右に振る事で見事に躱(かわ)していく。
アンドレの左右の戦斧(アシュ)による攻撃は、頼純の上半身に絶え間なく降りそそぐのだが、たまにタイミングがずれ一瞬の切れ間ができる事もあった。
頼純はそれを見逃さず、斬り掛かろうとする。
だが、兄のエノーがそれを許さない。必ず、長剣(エペ)による攻撃を加えてくるのだ。
次々と襲いかかる刃(やいば)に、頼純は押し戻されていった。
二人の複合(コンビネーション)攻撃は素晴らしかった。
だがそれも、一人一人の戦闘力の高さゆえになせる技(わざ)であろう。
そもそも、二人を相手にすると言い出したのは頼純である。
本来ならば、一人を選んで戦えばよかったのだ。
つまり、リシャール大公は、どちらか一人だけでも十分に頼純を倒せると踏んでいたのだ。
戦場では、いつも二人一緒というわけにもいくまい。彼らは、それぞれで戦い、それぞれの武勲(ぶくん)を上げてきたのだ。
それだけに、一人を倒せば、もう一人も何とかなるという話ではなかった。
ただ、二人をいっぺんに倒す方法がない以上、どちらかを先に倒さなければならない。
今の頼純の体力では、彼らの絶妙(ぜつみょう)な複合(コンビネーション)攻撃をこのまま躱(かわ)し続ける事などできないのだから‥‥。
巨兵兄弟の激しい連続攻撃に押され、頼純は右へ左へとめまぐるしく移動していった。
だが、彼は相手の斬撃(ざんげき)を決して太刀(たち)で受けようとはしなかった。
すべて、足さばきと上半身の捻りダケで、二人の刃(やいば)を躱(かわ)しているのだ。
そんな頼純を見詰めたまま、ジョルジュは溜息を漏らした。
「ス‥ スゲェ‥ アイツ、あれだけ打ち込まれてるのに、それをすべて躱(かわ)してる‥! 」
「ああ‥ ワタシもこんなの初めて見た‥! しかも、あんなボロボロの体で―――だ! 」
オズバーンも驚きを隠せなかった。
一般の観衆は、逃げてばかりで攻撃できない頼純を笑っていたが、戦いを生業(なりわい)とする者が見れば、彼がいかにとんでもない事をしているのか一目瞭然であった。その驚異的な動きから、一瞬たりとも目が離せない。
それは恐ろしいとさえ思える光景なのだ。
また、二人の攻撃がピタリと止まった。
そして先ほどのように、こちらへ来いと挑発(ちょうはつ)するのだ。
「さあ来い! 」
「堂々と勝負しろ! 」
何かがおかしい―――そう感じた頼純はゆっくりと後ずさり、決闘場の縁(ふち)まで来ると、今度は外周に沿って右へと移動していった。
再び、斧と長剣と大楯(おおだて)による激しい攻撃が開始される。
その凶刃(きょうじん)をよけながら、今度は左へ戻っていく。
ある程度のところまで来ると、やはり彼らは攻撃をためらった。
間違いない―――兄弟はこの位置で攻撃を止めるのだ。
頼純は気づいた。
そう、彼の背後には観覧席に座るリシャール公がいるのだ。
彼らは勢い余って、戦闘の刃(やいば)がリシャール公に向かう事を嫌っていたのである。
それは弱点というよりも、礼儀作法や配慮(はいりょ)といったたぐいの小さなためらいである。
だが、頼純はそんなモノでも突破口にするしか方法がなかった。
連日、長距離を走らされ、限界まで体力を消耗(しょうもう)させられた頼純は、いつものような俊敏(しゅんびん)な動きができなかった。
斬り込もうと一歩踏み出す間(ま)が、一瞬遅れてしまうのである。
そのために、彼らの攻撃からこちらの反撃へと移る事ができなかった。
だが、彼らに躊躇(ちゅうちょ)する一点があるとすれば、その間(ま)を埋める事ができる。
頼純は太刀(たち)を上段に構えると、ルーアンの巨兵兄弟の挑発(ちょうはつ)に乗ったフリをして、リシャールを背にしたまま中庭中央へと進んだ。
5ウナ(約6メートル。1ウナ=1.2メートル)ほど前進すると、再びアンドレの斧攻撃が始まった。
その太刀筋を躱(かわ)しながら、頼純は後ずさっていく。
連続攻撃を続けるエノーやアンドレは内心あせっていた。
長剣(エペ)も戦斧(アシュ)も空(くう)を斬るばかりで、頼純の体にまったく当たらないからだ。
いとも容易(たやす)く攻撃を躱(かわ)される事は、子供扱(あつか)いされているようで、二人には大きな屈辱であった。彼らは多数の観衆の前で恥をかかされているように感じていた。
その精神的ダメージは、空振りによる体力の消耗(しょうもう)をさらに増加させていった。
そして、さすがにここまで来ると、一般の観衆も頼純のやっている奇跡(きせき)を理解したようだった。笑顔を消した人々は、息をこらしてその戦いを見守っている。
中庭から歓声は消えたが、その熱気は逆に増していった。
ヨーロッパ人が使う長剣(エペ)は、幅広く、分厚い。
その切れ味はよいとはいえず、『斬る』というよりも、強い力で『叩き切る』といった感じである。
まさに、斧の切れ味だ。
そして、敵の刃(やいば)から身を守るために、彼らは鉄製の鎖帷子(オベール)を着用し、その下に鎧下(ガンベゾン)まで着けていた。分厚い綿を入れ、キルティングされた鎧下は、打撃による骨折を防ぐためのモノである。
ここまで装備をしておけば、多少斬りつけられても大した被害にはならないのだ―――彼らの長剣(エペ)ならば‥‥。
完全防備した巨兵兄弟は、相手の攻撃から身を守る絶対の自信があった。
彼らの全身を覆(おお)う鎖帷子(オベール)は、その巨体にあわせて特注のモノである。しかし、それを構成する一つ一つの鉄の輪は、他の鎖帷子と変わりがなかった。
後ずさる頼純をリシャール公爵の方へ向かわせまいと、アンドレはその左に回り込んだ。
次なる攻撃のためアンドレが左手の斧を大きく振り上げた時、頼純は素早くその体を右側に逃がした。
頼純を追って、斧の振り下ろす方向を変えようとしたアンドレは、その先にいるリシャールを見て一瞬ためらう。
頼純はその機を逃さなかった。
公爵まではまだ距離があると確認したアンドレが、頼純の側頭部を狙って斧を横に払った。
だが、そこに頼純はもういなかった。
身を低くして太刀(たち)を構えた頼純は、アンドレの足元へと滑(すべ)り込んでいたのだ。
戦斧(アシュ)の刃(やいば)が真一文字に空(くう)を切った時、アンドレの下半身でジャラリと音がした。
彼の鎖股引(ショース)の右太股(ふともも)部分が斬れた音だった。
鎖はスッパリと切れ、下に履(は)いていたズボン(ブレー)に赤い滲(にじ)みがひろがっていく。
「ウッ! 」
鋭い痛みに襲われるアンドレの右脇をくぐって、頼純は背後に回り込んでいた。
咄嗟(とっさ)に、右手の斧を横に振りながら、アンドレは頼純に体を向けようとする。
だがそれよりも早く、頼純はその背中めがけて袈裟懸(けさが)けに太刀(たち)を振り下ろした。
アンドレを救うため、エノーの長剣(エペ)が頼純の頭蓋(ずがい)を襲う。
瞬間、頼純は再び転がって、その場から逃(のが)れた。
「バ‥ バカな‥! 」
エノーは愕然(がくぜん)としていた。
なぜなら、弟の鎖帷子(オベール)の背中が大きく切り裂けていたからである。
それは致命傷(ちめいしょう)ではないが、よもや鉄製の鎖帷子(オベール)があのような細い剣で斬れようなどとは思ってもいなかったのだ。
一方、アンドレは慌(あわ)てていた。
鎖帷子(オベール)が切れた事実よりも、その事で重い鎖帷子(オベール)の重量バランスが狂い、前方に移動したそれが体にまとわりついて、腕の動きを鈍くしていたからである。
彼はもはや素早く斧を振る事ができなくなっていた。
再びアンドレの足元に潜(もぐ)り込んだ頼純は、靴も兼ねた鎖股引(ショース)の上からその左足の甲に深々と太刀(たち)を突き刺した。
地面にまで深く刺さった太刀(たち)を引き抜くと、そこから鮮血が吹き上がる。
「ギャ―――ア‼ 」
アンドレは激痛に絶叫しながら、めったやたらと両手の戦斧(アシュ)を振り回した。だが、彼はもう歩く事さえままならなくなっていた。
弟アンドレから十分な間合いをとった頼純は、今度は兄に向かって正眼(せいがん)に構えた。
弟が傷つけられたエノーは、怒りに燃えていた。
「貴様、許(ゆる)さん! 」
盾(エキュ)でガードしながら、大きく振りかぶった長剣(エペ)を振り下ろす。
「死ね‼ 」
だが、体をわずかに右に傾(かたむ)け、その切っ先をかわした頼純は、長剣(エペ)を握るエノーの右手めがけてストンッと太刀(たち)を当てた。
「グァァァァァア‥ 」
再び叫び声が上がる。
大きな長剣(エペ)を落とした巨兵兄が、高々と右手を挙(あ)げた。鎖の手袋で覆(おお)われたそこからは大量の血が滴(したた)っている。
彼の右手の親指がなくなっていたのだ。
もはや彼が右手で剣を振る事は二度とないであろう。
頼純はさらに、そのエノーの大盾めがけて太刀(たち)を振り下ろした。
巨大な木の盾は、真っ二つに切断されてしまう。
頼純は直(す)ぐさま後ずさると、兄弟と十分な間合いをとった。
それはあまりにもあっけない幕切れだった。。
中庭にいた誰もが、声ひとつ上げる事ができない。
ただただ、巨人兵二人の呻(うめ)き声だけが響き渡った。
たしかに、兄弟に戦闘力はまだ残っている。現にアンドレは、動けないまでも斧を振り回し続けているのである。
だが、これ以上戦えば、二人は確実に殺されてしまうだろう。
誰がみても勝敗は決していた。
あとは、審判がそれを認めるかどうかに過ぎなかった。
だが、その結果に腹を立てたティボーが、観衆の半分以上を占める兵達に怒声(どせい)を浴(あ)びせた。
「皆の者‥ こやつを殺すのだ! 一斉に斬り掛かれ! さっさとやるんだ‼ 」
その声に、170人近いノルマン兵が長剣(エペ)を引き抜いた。
だが頼純はそれに臆(おく)する事なく、平然と太刀を構える。
「へへへ‥ そう来やがったか♡ 」
彼は四方(しほう)を幾重(いくえ)にも囲んだ大量の兵士相手に、戦う気満々であった。