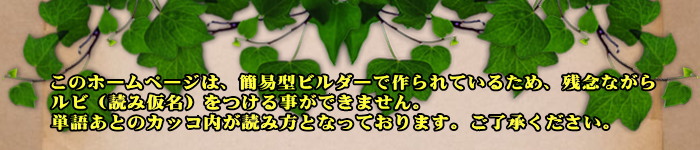
5
1026年 ファレーズ城内
「殿のお帰りだァァァ! 開門、開門ォォォン! 」
衛兵の声と共に、ギィ──イッと軋(きし)む音が響き、第二の城門がゆっくりと開かれていく。
ロベール一行は、空壕(からぼり)に架(か)けられた跳ね橋を渡り、開かれた城門をくぐると、領主の館(メヌア)の中へと進んでいった。城内の最上層に建てられた領主の館は、その周囲をさらに板塀(いたべい)で囲まれていた。
高さ20ピエ(1ピエ=1フィート=約30センチ。20ピエは約6メートル)ほどの板塀には、上部内側に回廊(かいろう)が巡(めぐ)らされ、常に4、5名の兵士が周囲を巡回している。
丸太の原木から、楔(くさび)で裂いたり、鋸(のこ)で引いたりして、一枚一枚切り出される『板』は、非常に高価なモノであった。
館の周囲すべてを、その『板』囲むタメには、何千枚もが必要であり、費用は莫大な金額となる。領主ならではの贅沢(ぜいたく)な造りなのだ。
しかし、金を掛けただけあって、その出来上がりは丸太の塀(へい)よりもずっと優美に見えた。
塀の内側には広々とした城庭(ベリー)が拡がり、館をはじめ、礼拝堂、兵舎、馬舎、使用人の住居など、様々な建物が建てられている。
そして、城庭(ベリー)を挟んで一番奥にそびえ立つ巨大な山が、『土塁(モッド)』であった。
それは空壕(からぼり)を掘った際に出た残土など積み上げ、しっかり地固めして作られた山である。
高さ60ピエ(=約18メートル)はあろうそそり立つ土塁(モッド)の頂上には、『物見の塔』とも、『避難所』とも言える建物が建っている。
その建物も周囲を板塀(いたべい)で囲まれ、土塁(モッド)と城庭(ベイリー)を結ぶのは、同様に塀で守られた長い階段と連絡用の跳(は)ね橋しかなかった。建物は最後の『砦』として、敵の侵入を厳重に防いでいたのだ。
この小山の上に建つ『避難所』こそが、ノルマンディ式の城塞(じょうさい)の特徴であり、のちにヨーロッパ各地に建つ城の原型となった。
一行が中庭に入ると、馬から降りたロレンツォは、ゆっくりと城内を見回し、感嘆(かんたん)の声を上げる。
「お~~~お‥ これはこれは、立派なお城ですなァ‥。 深くて幅の広い壕(ほり)と、金字塔(ピラミッド)かと見まごうばかりの高い土塁(モッド)―――その上には堅牢な『物見の砦』を持っている。 その偉容(いよう)は、遙(はる)か遠くの森からでもハッキリと窺(うかが)う事ができます。 素晴らしい! 」
ロレンツォは見え透いたお世辞(せじ)を言った。彼は数年に一度、ロベールに会いにくるのだが、そのたびにこのような社交辞令でおだてるのだ。
「え? そ‥ そうですかァ‥? 」
しかし、毎度ロベールはこの世辞(せじ)を真(ま)に受ける。しかも、伯爵はこの城の佇(たたず)まいにかなりの自信を持っており、自慢であった。
その事に気づいたロレンツォはさらに褒(ほ)めちぎった。
「ええ、そうですとも。 これほどの城はなかなかありませんぞ! フランス国王のおわしますパリ城や兄上の居城・ルーアン城に次ぐほどの名城です。 これなら、敵もこのファレーズを襲おうとは考えますまい 」
「フフ‥ フフフ‥ や‥ やっぱり、そうですかねェ? いやいや‥ ボクもそうじゃないかなァとは思っていたんですけどォ…… やっぱり、そうかァ‥ そうだよなァ‥ へへへ‥ 」
ロレンツォから自慢の城を賞賛され、ロベールはすっかりいい気分になっている。
そんな二人のやりとりを、荷車の荷ほどきを手伝いながらチラリと眺(なが)めた頼純は、小馬鹿にするかのように鼻を鳴らした。
その時、騒々しい声が中庭に響いた。
「わ‥ 若ァ──あ! 」
そこには、何度も何度もロベールの名を叫びながら、転げんばかりにして駆け寄ってくる初老の男の姿があった。
「若‥ ロベール様ァ! ご‥ ご無事で‥ ご無事でございましたかァ―――? 若ァ―――あ! 若ァ―――あ! 」
彼はこのファレーズ城を取り仕切る執事(アンタンダン)のティボーである。
「おお‥ 爺(じい)か‥! 」
ティボーは、ロベールに勢いよく抱きつくと、ポロポロと涙を流し始める。
「若ァ‥ 若ァ‥ 爺は‥ 爺はもう、心配で、心配で‥ 心の臓が止まるかと思いましたぞォ‥ 」
「うん‥ うんうん‥ 大丈夫だって‥ そんなに心配するな‥ 心配するなって―――い‥ 言いたいところだけどさァ‥ 」
ティボーを安心させようと、彼の背中をさすっていたロベールの笑顔がどんどん崩れていく。ティボーの顔を見た途端、それまで懸命に堪(こらえ)えていた緊張の糸がプツリと切れてしまったのだ。
再び、死の恐怖が蘇(よみがえ)ってきたロベールは、大粒の涙を流して泣き始める。
「いやいやいやいや‥ ホントにホントに‥ もう‥ もう、今回ばかりは、絶ッッ対―――絶対にダメだと思ったよォ‥ 」
そんなロベールをひしと抱きしめるティボー。
「若ァ‥ 若ァ‥ 」
「怖かった‥ 怖かったよォォォォ‥ 」
いい年をした大人二人が、広場で抱き合って泣いている姿に、周囲の人々は呆気(あっけ)にとられていた。

ティボーは、リシャール大公とロベール伯爵が幼い頃から、その教育係を務めていた人物で、早く父母から引き離された二人にとって親代わりといえた。
それ故(ゆえ)、ロベールにとっては、自分の感情をさらけ出せる数少ない存在なのであった。
しかし、ティボーはハッと我に返ると、ロベールから体を離す。
「若、なりませぬ。 泣いてはなりませぬぞ! 」
何を言われているのか判らないロベールは、泣きべそ顔でキョトンとする。
そんなロベールの目を、ティボーは真っ直ぐに見詰める。
「このようにひと目の多いところでは、決して涙を見せてはなりません 」
「だ‥ だって‥ いま、ティボーだって泣いてたじゃないか 」
ティボーは厳(きび)しい口調で諭(さと)す。
「いいえ。 わたくしと、若では身分が違います。 貴方様(あなたさま)は多くの民を治める伯爵―――貴族なのですぞ 」
「そ‥ それは、そうだけど‥‥ 」
「そして、人の上に立つ者は、下々(しもじも)の者に決して感情を悟られてはなりません。 侮(あなど)られてはならぬのです。 弱き姿を見せてはいけません 」
ティボーの言う事はもっともであった。
しかし、このような人前で彼を諭(さと)す事こそが、ロベールが人々から侮(あなど)られる原因になっている事を彼は理解していなかった。
だが、ロベールは、
「うん‥ わかった。 これからはそうするよ 」
とティボーの言う事をあっさりと受け入れた。
ロベールは、じつに純粋で素直な性格であった。
だが言い換(か)えると、従順(じゅうじゅん)なのである。彼は人に逆らえなかった。
そこに年相応の反抗心や自我をうかがう事はできない。ある種のいびつささえ感じさせられた。
それはおそらく、この執事――ティボーとの擬似親子関係に起因していると思われた。二人は、『幼子』と『母親』の関係なのだ。
彼が実年齢より若く見えるのも、その従順さゆえに、大人を感じさせないからであった。
ティボーは、ロベールの答えに満足したのか、ニッコリとほほ笑んだ。
「さすが、ロベール様! 聞き分けがおよろしい 」
そこへロレンツォがやってくる。上得意であるロベール伯爵家の金庫番、ティボー殿に挨拶(あいさつ)するためだ。
「どうもどうも、執事殿‥ ご無沙汰(ぶさた)しております。 ヴェネツィアのロレンツォでございます。 今年もどうか、よいお取引をお願い申し上げます 」
ティボーはロレンツォを見るや、両手を大きく開き、大袈裟(おおげさ)に喜んでみせる。
「おお‥ ロレンツォ殿、ロレンツォ殿‥ あなた様のお陰で、我が主人・ロベールは窮地(きゅうち)を救われました。 このお礼、どのようにお返しすればよいのでしょうか 」
「いやいや、執事殿‥ 我々がたまたまあそこを通りかかったのも神の思し召し(おぼしめし)でございましょう。 ロベール様の日頃の信心(しんじん)の賜(たまもの)です。 お礼など、心配ご無用! 私どもには、お取引でよりよい価格をおつけいただければ、それで十分でございます 」
ロレンツォは、救出の功(こう)をひけらかさず、控えめな態度をとりながらも、『商品は高値で買ってもらうぞ』という婉曲(えんきょく)な圧力を掛けてきた。
その意味をしっかりと理解したティボーは、押し寄せるであろう高額な請求書を考えると笑顔も強張った。
「またまた‥ そのように、ご謙遜(けんそん)なさいますな 」
無邪気(むじゃき)なロベールは、火花散る二人の会話を額面(がくめん)どおり受け取り、ロレンツォの功績をさらに讃(たた)えた。
「爺‥ 今日はホントに死ぬと覚悟させられた。 ロレンツォ殿御一行が現れなければ、この命失っていたに違いないのだ。 皆様への感謝の念、あだや疎(おろそ)かにしてはならんぞ! 」
「さようでございましょう、さようでございましょうとも! しかし、ここで立ち話も何でございます。 館(やかた)の中へ入ってごゆるりとご歓談(かんだん)くださいませ 」
ティボーはこの話題を中断すべく、ロレンツォを館の中へ招き入れる作戦に出た。ここでロベールに不用意な発言をされて、さらに商品の値を上げられては堪(たま)らぬと考えたからだ。
「おう‥ それがよい、それがよい。 ささ、どうぞこちらへ 」
改まった口調のロベールに案内されて、ロレンツォと番頭、さらには頼純とイタリア人傭兵(ようへい)二人が領主の館へと進む。
「ところで‥ お連れのサラセン人は、ロレンツォ殿の奴隷ですかな? 」
慇懃(いんぎん)な口調で、ティボーが背後から声を掛けてくる。
その声に、頼純は憮然(ぶぜん)とした表情で振り返った。
「ここは神聖なる領主の館(メヌア)です。牛馬同様、奴隷は外にお留(とど)めおきいただきたい。 多少、雨漏(あまも)りはいたしますが、屋根のある小屋がございます。 そこなら、水とエサはタップリお与えできますので‥‥なにとぞ、ご容赦(ようしゃ)くださいませ 」
ロレンツォは、ティボーの発言にニッコリとした笑顔で答えた。
「何をおっしゃいますやら、執事殿‥ この者は我が隊商(キャラバン)の警備隊長でございますぞ 」
「え? サラセン人が‥ 警備隊長―――? 」
ロレンツォの顔は笑っているが、ティボーを見詰める目は冷ややかである。
「そして、この身は―――たとえ、お得意様のお館(やかた)内であろうとも、常に危険にさらされております。 以前にも何度か、取引の最中に襲われた事がございましてね‥ よって、この者を連れずに私が動く事は一歩たりともあり得ません。 執事殿が、ヨリを館に入れぬとおっしゃるのなら、私はこのまま帰るしかないでしょう。 それでも、よろしいですかな? 」
ビザンティン(東ローマ)帝国を始め、地中海の各地、そして遠くアラブの港にまで足を伸ばすロレンツォにとって、異教徒もまた商売仲間であり、友人であった。時には、命の恩人とさえなりうる。それゆえ、彼は肌の色や宗教でその人物を計(はか)るような事はしなかった。
ましてや奴隷などというものは、その人物に運がなかったというだけで、明日は我が身の話である。盗賊に襲われそれを撃退できねば、誰もが奴隷として売られるのである。
彼は、奴隷も商品として扱(あつか)っていたが、逆に自分が奴隷として売られる日が来るかも知れない事を覚悟していた。
それゆえ、身分や階級などというモノは立場の違いに過ぎず、人としての能力になんら関係がないと考えていた。
そんなロレンツォにとって、異教徒や奴隷を必要以上に軽んじるティボーの態度は前々から癪(しゃく)に障(さわ)っていた。そこで、本日は少し意地悪を言ってみたのだ。
帰ると言い出したロレンツォに驚いたロベール伯爵は、あせった様子でティボーをたしなめる。
「爺‥ ダメだよ、ダメ。 ロレンツォ殿御一行を追い返すなんて、絶対にダメだって! そんなコトしたら、命の恩人を疎(おろそ)かにしたって、諸国の人々にどれだけ笑われるか―――いや、兄上にどれだけ叱られるコトか―――! 」
本当は、人々から笑われる事も、兄・リシャール3世から怒られる事も、ロベールにとってはどうでもいい事であった。それよりも、ロレンツォが持ち込む遠隔地の珍しい品物や香辛料が手に入らず、さらにその旅での冒険譚(ぼうけんたん)が聞けなくなる事の方が遙かに心配であった。数年に一度の大きな楽しみを奪われたくなかったのだ。
いくら従順な彼であっても、そのタメならば、『母親』に逆らう事をためらわなかった。
「それから‥ その方こそが、ボクを直接助けてくださったヨリズミ殿だぞ! 十数人の盗賊を斬り、二十人以上いた奴らを退治してくれた武人だ。 サラセン人でもない! サラセンよりも遙か遙か東の国―――『日本国』というところからお越しの方だそうだ 」
ロベールの真意を見透(みす)かしたティボーは、必死に説得する主人に皮肉たっぷりの口調で返す。
「へ~~~え‥ そうですか! そりゃ、驚きですな、若♡ 」
頼純は、そんなやり取りを理解しているのか、していないのか、げんなりした表情で眺(なが)めていた。
× × × × ×
ベリー内でもひときわ大きい領主の館(メヌア)は、柱や梁(はり)が外側にむき出しとなった木骨造り(コロンバージュ)で、柱と柱の間をふさぐ土壁の上には白い漆喰(しっくい)が丁寧(ていねい)に塗られていた。屋根は分厚い茅葺(かやぶ)きである。
ロレンツォ達五人が通された大広間は、内壁にまで板が張られ、床には不揃い(ふぞろい)ながらも平らな石が敷かれていた。その床には、二つの大きな囲炉裏(いろり)が切ってある。
囲炉裏(いろり)は暖房器であり、夕食時には豚の丸焼きやスープの大釜(おおがま)を掛けるコンロにもなった。
広間の正面奥は一団高くなっており、領主の玉座(ぎょくざ)が設けられていた。
天井は高いが、明かり取りの窓が少ないため、内部はかなり暗い。
玉座の背後の壁には、すきま風を遮(さえぎ)るための大きなタピストリーが掛けられている。
館は大きくても、中は細かく仕切られていなかった。部屋数が少ないのである。それゆえ、プライバシーはほとんどない。
ロベールでさえひとつの寝室しか持たず、家族が増えてもその寝室をみなで使う事になる。家臣達は全員同室で寝起きしていた。
また様々な報告や決断・謁見(えっけん)、場合によっては裁判までもがこの大広間で行われ、家臣らとともに毎晩この部屋で夕食をとった。
それは、彼のやり方というワケではなく、ヨーロッパのほとんどの貴族がそうやって暮らしていたのだ。
玉座に腰掛けたロベールは、傍ら(かたわら)で苦々しい表情をしたティボーの事などお構いなしで、前に立つロレンツォに目を輝かせて尋(たず)ねた。
「それで‥ ロレンツォ殿はどうやってヨリズミ殿を召(め)し抱(かか)えられたのですか? 」
ロレンツォは苦笑しながらそれに答える。その横には、仏頂面でティボーに目をやる頼純も立っていた。
「う~~~ん‥ 召し抱えたと言うよりも、召し抱えさせられたと言った方がよいのでしょうか? 元々、ヨリは私の奴隷だったんですよ 」
その言葉にティボーは、『ほら、やっぱり』といわんばかりの顔を作った。
かたやロベールは、ロレンツォの話しぶりに、ますます好奇心を募(つの)らせていった。
「え? ど‥ 奴隷から警備隊長ですって―――? それはどうしてです? なんでそんな事になるんです? いったい、何があったんですか? 」
矢継ぎ早(やつぎばや)に尋ねてくるロベールに、ロレンツォは遠くを見詰める目でゆっくりと語り始めた。
「私達の出会いは3年前―――たしか、4月の事でした。 遙か東の事でございます 」