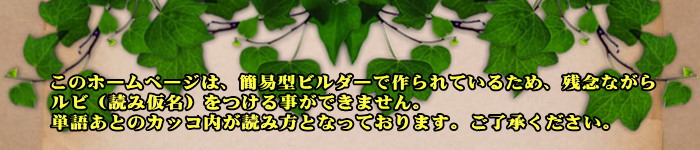
序 章
1066年 ヘイスティングス
イングランド・グレートブリテン島の南東に位置するピヴェンジィの海岸には、異様な光景が広がっていた。
砂浜一面に、おびただしい数の軍船(ぐんせん)が打ち上げられていたのである。
ロングシップと呼ばれる全長50~70フィート(1フィートは約30センチ。70フィートは約21メートル)級の無蓋長船(むがいちょうせん)だけでも700隻以上、小さな食料輸送船まで含めると、3000隻を越える巨大船団であった。
それらは、わずかな海峡を挟んで目と鼻の先にある、フランスの港・サンバレリーを出発した軍船団(ぐんせんだん)だった。
ただ、その光景が異様に見えるのは軍船の数ではなかった。その全ての船が、真っ黒に燃え尽(つ)きていたからである。
海を渡ってきた侵略者達には、もはや逃げ帰る方法はなかった。この戦いに勝利しなければ、彼らはこの地で死ぬしかない。
だが、船団に火を放ったのも、彼ら自身であった。
この戦いに必ず勝つという彼らの決意の表れなのだ。
それは、彼らが生きる時代からさらに1200年以上も昔―――遥(はる)か遥(はる)か東方の国、漢の将軍・韓信(かんしん)が用いた『背水の陣(はいすいのじん)』と同じ戦術であった。
1066年10月14日早朝、ノルマンの大軍団は、ピヴェンジィの浜から北東へ11マイル(約18キロメートル)ほどの、『テルハムの丘』と呼ばれた丘陵(きゅうりょう)地帯に陣取っていた。

騎士3000人、弓兵1000人、歩兵ですら2000人にも及び、工兵(土木作業員)からコックまで含めると、総勢一万人を越える大軍団が、その丘を埋め尽くしている。
しかし、そこに喧噪(けんそう)はなかった。
みな、間もなく発せられるであろう『戦闘開始』の合図を、息を潜めて待っているからである。
丘の尾根(おね)には、すでに三千の騎士達が整列していた。
静寂(せいじゃく)の中、気をはやらせた軍馬が放つ鼻息や足踏みの音のみが谷間(たにあい)を渡っていく。
この侵略者達は、騎士が乗る3000頭もの軍馬を、わざわざ船でノルマンディから運んできていた。
軍馬を落ち着かせようと手綱を操(あやつ)る騎士達は、みな鎖帷子(くさりかたびら)で全身を覆(おお)い、頭には鼻当て付きの兜(かぶと)をかぶっている。
そんな騎士達の中央に、ひときわ立派な軍馬に跨(またが)った男がいた。
彼は他の騎士達とは違って、兜を被(かぶ)っていない。代わりに、宝冠(ほうかん)が頭上に載(の)せられていた。
鷹(たか)のように鋭く前方を見詰めるその双眸(そうぼう)からは、高い知性と深い徳、そして岩のように堅い意志をうかがう事ができる。
彼こそが、フランス王国のノルマンディ大公(たいこう)ギヨーム2世であった。
彼が見詰める先、小さな沼を挟んで500ヤード(1ヤード=約90センチ。500ヤードは約450メートル)ほど前方にある『センラックの丘』には、一万六千人を超すサクソンの軍勢が布陣(ふじん)している。
敵は自軍より遙かに多かった。しかし、彼は負ける気がしない。勝利を確信していたのだ。
そしてこの戦いに勝てば、フランス国王の家臣であるギヨーム公爵が、イングランドの国王となる。
「オニマール! 」
ギヨーム2世は厳しい表情で家臣に声を掛ける。
オニマールと呼ばれた上級騎士が、ギヨームの真横へと馬を寄せる。
彼の風体も、その名前同様、他の騎士達とは少々違っていた。
鎖帷子(くさりかたびら)の上に奇妙な胸鎧(むねよろい)をつけ、腰には通常の半分ほどの幅しかない湾曲(わんきょく)した剣を紐(ひも)で吊っている。面立ちもサラセン人のそれに近い。
しかし、その見た目の違和感とは裏腹に、彼の醸(かも)し出す雰囲気は周囲の空気に溶け込んでいる。
ギヨームがオニマールに何事か耳打ちすると、
「承知! 」
オニマールは頷(うなず)くや否や、馬を駆(か)り、延々と伸びたノルマンディー騎士団の前を大声で走り抜けていく。
「おのおの方、戦の準備をォォォ! 戦闘準備でござるゥゥゥゥ‼ 」
その声に、騎士達は一斉に腰から長剣を引き抜く。
「弓兵、弦(つる)引けェ────イ‼ 」
弓兵長の号令とともに、騎士達の背後にいた弓兵達が前へと進み、朝日に輝く空に向かって弦をキリキリと引き絞っていく。
辺り一帯が固唾(かたず)を呑(の)む。ほんの数秒が永遠のようにさえ感じられた。
その時、ギヨームの鋭くも威厳(いげん)に満ちた豪声(ごうせい)がテルハムの丘に響き渡る。
「矢、撃てェェェェイ! 」
一斉に放たれた千本の矢は、大きな弧(こ)を描いて上空に達すると、一瞬の静止の後、真っ逆さまに敵陣へと降り注いでいく。
一の矢、二の矢に貫かれたサクソン兵達は、悲鳴と怒号(どごう)上げながら次々と倒れていく。
「全騎士軍団、全速前進! 」
騎士の指揮を任されたオニマールが、細く湾曲(わんきょく)した剣を敵方向に振り下ろして叫ぶと、三千の騎兵は鬨(とき)の声と共に一斉にテルハムの丘を駆け下りていった。
丘の上に残ったのは、ギヨーム大公と彼を護衛する二百人ほどの親衛隊だけであった。
イングランド国王―――ギヨームは心の中でそう呟(つぶや)いてみた。
しかし、そこには何の感慨(かんがい)もなかった。喜びも感動も湧(わ)いてはこないのだ。むしろ、これまでの38年間の生涯で、勝ち抜いてきた数々の戦(いくさ)―――産まれてから、いや、産まれる以前から始まっていた数え切れぬほどの『戦い』の事が思い出された。
ギヨームは、本来ならば国王どころか、ノルマンディーの公爵にさえなれぬ立場であった。
母親が平民だったからである。母の父――彼の祖父は身分卑しき革(かわ)なめし職人だったのだ。
当時の平民は、貴族達から汚物(おぶつ)を見るかのように眉(まゆ)をひそめられるのはまだよい方で、たいていの場合、路傍(ろぼう)の石と同じ様に無視される存在だった。そこにいる事さえ認知(にんち)されない存在なのだ。
彼の母はそんな階級の出身だった。
しかし、人々から蔑(さげす)まれるギヨームを心より愛し、あまたの敵から彼を守り、ついには大国ノルマンディの公爵の地位にまで押し上げた人物がいた。
彼の父・ロベール1世とその家臣ヨリである。
二人に思いを巡(めぐ)らすと、四十に近い威厳(いげん)に満ちたギヨーム大公でさえ、ふと涙腺(るいせん)がゆるんでしまう。
ましてや、そんな出自(しゅつじ)である彼の子孫達が、その後一千年にも渡ってイングランドの国王であり続けようなどとは、ギヨーム自身も思いも寄らぬ事であった。