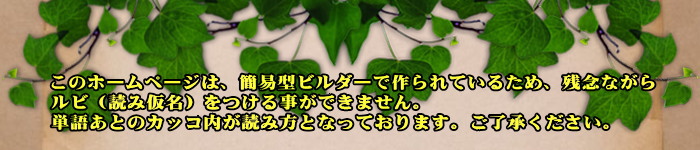
17
1026年 モン・サン・ミッシェル
ロレンツォ一行の道中(どうちゅう)は天候にも恵まれ、2週間後にはモン・サン・ミッシェルに到着した。
明日はモン・サン・ミシェル島の修道院へと赴(おもむ)き、院長と謁見(えっけん)する予定となっている。
彼らはその晩、近在(きんざい)の宿屋へ泊まる事とした。
ファレーズからモン・サン・ミッシェルに到着するまでの間に、ロレンツォの隊商(カラバンヌ)はノルマンディー中の噂(うわさ)の的になっていた。
道行く人々はロレンツォ達を見つけるや、ニヤニヤと笑ったり、反対に苦虫を噛(か)み潰(つぶ)したような顔になったりする。
ニヤニヤ顔の者は、『ファレーズ伯爵ロベール1世を山賊の襲撃から救った異教徒』の話を聞いた者達で、そのとてつもない強さを賞賛(しょうさん)していた。
一方、苦虫顔の者は、『その異教徒がファレーズのお城で、伯爵を怒鳴りつけ、さらにはキリスト教徒まで馬鹿にした』という話を聞いた者達で、その行(おこな)いを不快に思っていたのだ。
しかし、どのような噂(うわさ)話が広まろうと、頼純をはじめとする隊の者達はさほど気にしてはいなかった。
なぜなら、彼らはあとひと月もすれば、イスラム教徒が支配するイベリア(現スペイン王国)に入ってしまうからである。
× × × × ×
(この解説は少々長くなっております。歴史に興味のない方は、とばして先をお読みいただいても大丈夫です )
中央アジアの騎馬(きば)民族であったフン族は4世紀半ば頃から西へと移動を始め、紀元370年頃には東ヨーロッパに迫ろうとしていた。
このフン族の侵攻(しんこう)が、約千年にも及(およ)んだローマ帝国の終焉(しゅうえん)の第一幕となるのである。
最初に襲われたのは、ローマ帝国国境の東―――黒海(こっかい)北部沿岸(=現ウクライナ南部)に住み着いていたゲルマン人の東ゴート族であった。
馬を使って村々を急襲(きゅうしゅう)し、勇猛(ゆうもう)かつ苛烈(かれつ)な攻撃を繰(く)り出すフン族に、東ゴートの人々は反撃する術(すべ)を持っていなかった。
戦いに敗れた東ゴートの村は、すべての女が犯され、すべての財―――家畜(かちく)から種籾(たねもみ)にいたるまで、あらゆる物が奪(うば)われ、その後に生き残った村人全員が殺された。そして最後に家屋(かおく)に火が放たれるのである。
フン族が通った後には、黒焦(こ)げとなった死体の山しか残っていなかった。
そのあまりの残忍さに、難(なん)を逃れたわずかな者達もみずからの土地を捨て、西へと逃げ始めた。
その数は雪だるま式に膨れ上がり、やがて十数万人となった難民が黒海西岸へと移動するのである。
身ひとつで、命からがら南カルパチア山麓(=現ルーマニア南部)にまでたどり着いた東ゴートの難民は、激しい飢(う)えと恐怖から、精神的に追い詰められていた。
彼らは、そこに住んでいた同族の西ゴート族に襲(おそ)いかかり、無理やりその居住地を奪(うば)ったのだ。
紀元375年の秋、東ゴート族によって故郷を追われた西ゴートの民は、一方で迫り来るフン族にも恐れをなし、国境線であるドナウ川を越えてローマ帝国内に侵入(しんにゅう)した。そして皇帝に自分達の庇護(ひご)を求めたのである。
ローマ皇帝ウァレンスは彼らの救済(きゅうさい)を承諾(しょうだく)したが、10万人と予想していた西ゴートの難民は30万人を越え、用意していた居留地の食糧(しょくりょう)ではとても足りない状態となってしまう。
冬になると、ローマ帝国領内で西ゴートの難民による略奪(りゃくだつ)と殺戮(さつりく)が始まった。大量の餓死者(がししゃ)を出した彼らには、それしか空腹を満たす方法がなかったからである。
その後もフン族はヨーロッパ東部を荒らし回り、襲われたブルグンド族、ヴァンダル族、ランゴバルド族などのゲルマン民族も、次々とローマ帝国内へ逃げ込んでいくのだ。そして彼らは、西ゴート族と同様に略奪(りゃくだつ)と殺戮(さつりく)を行(おこな)うのである。
玉突き状態で、次々とローマ帝国領内へ弾(はじ)き出された彼らは、自分達になされた残虐非道(ざんぎゃくひどう)な犯罪行為を他国の民に対して行(おこな)っていく事となる。
これが『ゲルマン民族の大移動』である。

フン族による略奪/ジョルジュ・ロシュグロス
紀元395年、分割(ぶんかつ)統治(とうち)を目的としてローマ帝国が東西に分裂する頃には、西ローマ帝国の領土内は避難民であるはずの蛮族(ばんぞく)達に蹂躙(じゅうりん)され尽(つ)くしていた。
西ゴート族もその例外ではない。彼らは移動しながら略奪(りゃくだつ)と殺戮(さつりく)を続け、ついにローマの街を包囲するのだった。
これを脅威(きょうい)と感じた西ローマ帝国・初代皇帝ホノリウスは、属州(ぞくしゅう)ガリア(=ほぼ現フランス共和国)と属州ヒスパニア(=現スペイン王国)を領地として与える代わりに、イタリア半島から出ていくように彼らを説得した。
ガリアとヒスパニアは、ゲルマン蛮族(ばんぞく)による混乱で、すでに帝国の支配が及ばなくなっている土地だった。さほど惜(お)しくもなかったのだ。
これに素直に従った西ゴート族は、紀元415年、ガリア西部のトロサを首都として巨大国家『西ゴート王国』を建国する。
ここから、1492年の『グラナダ陥落(かんらく)』に至るまで、1000年を越える長いイベリア半島の興亡(こうぼう)史が始まるのであった。
彼らは国内の抵抗勢力である他部族を殲滅(せんめつ)し、全土を掌握(しょうあく)した。
ほどなくして、西ローマ帝国と連合軍を作り、紀元451年にはパリ西方のカタラウヌムでフン族を撃退(げきたい)するのだ。
80年にも渡って全ヨーロッパを恐怖のどん底に落としめたフン族も、その2年後に、王であったアッティラが急死するとあっさり滅亡(めつぼう)してしまう。
そして紀元476年、ついに西ローマ帝国が崩壊(ほうかい)する。
その後の西ゴート王国は、クローヴィス率いるフランク族に敗れてガリアの地を奪(うば)われたりもしたが、キリスト教国家となり、イベリア半島を統一して、他の蛮族(ばんぞく)国家が次々と滅亡していく中、繁栄(はんえい)を誇(ほこ)ったのだった。
しかし紀元711年、ほんのわずかな距離しかないジブラルタル海峡を渡って、アフリカ北部からイスラム人らがイベリア半島に攻め込んできた。
怒濤(どとう)のごとく攻め寄せるイスラム教国家『ウマイヤ朝』に、西ゴート王国はなすすべもなく、簡単に滅ぼされてしまうのだった。
それは、建国から296年後、東ゴート族に南カルパチア山麓の故郷を追われてから336年後の事であった。
一方、シリア・ダマスカスに首都を持ち、中東アジアから北部アフリカまでの広大な国土を誇った『ウマイヤ朝』は、イベリア半島までもその支配下においたのだ。
だが、この『ウマイヤ朝』も、紀元750年にはアッバース革命によって滅ぼされてしまう。
新政権となった『アッバース朝』は、旧体制の一族を一人残らず処刑しようとしていた。
追い詰められたウマイヤ王族の一人、アブド・アッラフマーン1世は、イベリア半島のアンダルシアへと逃げ込む。
彼らはやがて半島を征服(せいふく)し、紀元756年にイスラム国家『後ウマイヤ朝(コルドバのウマイヤ朝)』を再興(さいこう)するのだった。
それから270年が過ぎていた。
『ウマイヤ』、『アッバース』、『後ウマイヤ』まであわせると、イベリア半島はじつに315年間もイスラム教国家に支配されていたのである。
しかしキリスト教徒も、この屈辱(くつじょく)の歴史をただ指をくわえて見ていたワケではない。
再征服運動(レコンキスタ)によって、少しずつ彼らから自分達の国土を取り返していたのである。
ただし、1026年の時点では、ナバラ王国がカスティリア伯領を併合(へいごう)し、半島の北部三分の一ほどを奪還(だっかん)したていどに過ぎなかった。
片や、『後ウマイヤ朝』はカリフ(=国家最高権威者)であるヒシャーム2世の摂政(せっしょう)アル・マンスール・ビッ・ラーヒが1002年に亡くなると、継承者(けいしょうしゃ)争いで国内は長期に渡って混乱をきわめた。
その混乱に乗(じょう)じて、イベリア半島の西岸部にイスラム諸王国(しょおうこく)『バダホス』が興(おこ)っていたのだ。
× × × × ×
頼純らの目的地は、そのバダホス国の港町リスボンだった。
そこから今度は船に乗り、大海原(おおうなばら)をさらに西へと向かう。
意外であるが、中世ヨーロッパにおいて、『地球が丸い』という事は知識人らの間では常識であった。
ギリシャ時代のピタゴラスからプラトン、アリストテレスら多くの哲学者や科学者が、『地球は球体である』という事を唱(とな)えていた。それは、ローマ時代のプトレマイオスらを経(へ)て、中世に入ってからも天文学として研究されていたのだ。
これをキリスト教教会も支持し、多くの教会の学者達がこの研究に携(たずさ)わっていた。ただしそれは、プトレマイオスが提唱(ていしょう)した天動(てんどう)説―――『地球が宇宙の中心である』という考えを元にしたモノであったのだが‥‥。
頼純は、東の果ての日本から、西の果てのイベリア半島リスボンまで旅をするのである。地球が球体ならば、一周ぐるりと回って、東の果ての日本はすぐそばだと思われた。
サラセン(=イスラム)の商人仲間も、リスボンを真西に向かうとアジアの東岸があり、そこまでは船で二、三ヶ月の距離だろうと教えてくれた。
ただそれが判っていても、その航海を成(な)し得(え)た者は誰もいなかった。
なぜなら、いくら星を読んだとしても、長期間真西に向かい続ける方法がなかったからである。
ところが、ロレンツォはインドのカリンガナガラで、中国『宋』から渡来(とらい)した『指南針(しなんばり=羅針盤)』なる物を手に入れていた。
それは、常に北を指す針がついた画期的な道具であった。
これさえ使えば、いつでも船が進んでいる方角を知る事ができるのだ。
長い長い旅だが、方角さえ分かればあとは何とかなる。
すでに心は大冒険家となっていたロレンツォは、はるか東の国・日本へ西回りで旅をする事を決意していた。
当時、日本は『ワクワク』という名の黄金の国として、中国(スイーン)の東方にあるとイスラム商人達の間で信じられていた。
『ワクワク』とは、『倭国(わこく)』がなまったものらしい。
その日本、中国への航海は、再び戻ってくる事のない一方通行の旅となる。
だが、頼純は祖国へ帰る事に異存(いぞん)はなく、サミーラも行動を共にすると決めていた。
隊商(カラバンヌ)の他の者達も、生きては帰れないと知った上で、黄金の島『ワクワク』へ行きたいと志願した者達ばかりであった。
それは、ローマ教会に見つかってはならない、史上最大の冒険なのだ。
リスボンはイスラム教徒が支配する土地であったが、サラセン商人を通じて船や食料の手はずはすでに整っていた。
もちろん、彼らが日本にたどり着く事はない。
なぜなら、そこにあるのはアメリカ大陸だからだ。彼らはその事を知らなかった。
そして、日本までの距離もはるかに遠かった――彼らが考えているよりも、地球はずっと大きかったのである。
× × × × ×
夜も深い刻(とき)となっていた。
宿屋の食堂でリンゴ酒をしこたま飲んだ頼純が、自室の寝台(しんだい)に転がってしばらくたった頃、表から馬のひずめの音が響いてきた。
イビキをかいて熟睡(じゅくすい)していた頼純だったが、その音に敏感(びんかん)に反応し、パッと目を覚ました。かすかな異常にも、直ぐさまに反応する武人(ぶじん)の性(さが)である。
起き上がった頼純は、太刀(たち)を掴(つか)んで自室から静かに出ると、入り口周辺の様子を窺(うかが)った。
しばらくすると、大きな音で入り口のドアが開けられ、身なりのよい男が階段を駆(か)け上がってきた。
男の名はジュリオ。ヴェネツィアのロレンツォの屋敷で働く従者(じゅうしゃ)の一人で、頼純も面識(めんしき)があった。
ロレンツォの寝室に入ったジュリオは、無理やり主人を起こすと、寝ぼけ眼(まなこ)の彼に耳打ちをした。
その瞬間にロレンツォは完全に覚醒(かくせい)し、やがて表情を曇(くも)らせる。何か重大な知らせであったに違いない。
ロレンツォはしばしの間、寝台(しんだい)に腰掛けてジッと考えていたが、やがて横になり毛布を被(かぶ)った。
その様子を確認した頼純は、主人に習(なら)い、寝台(しんだい)に戻ったのだった。
日が昇りかけた頃、ジュリオが頼純を起こしに来た。
彼の言葉にしたがって食堂に降りると、ロレンツォが神妙(しんみょう)な顔で立っていた。
目が赤い。あの後(あと)も眠れなかったのであろう。
やがて、隊商(カラバンヌ)の仲間も寝起き顔で集まってきた。
最後に番頭のマルコが降りてくると、ロレンツォはおもむろに切り出した。
「1週間ほど前、母が倒れた。 容体(ようだい)はあまりかんばしくないそうだ‥ 」
その言葉に、隊商の全員が固まった。
長年、ロレンツォの家に仕(つか)えてきたマルコは悲鳴にも似た声を上げる。
「お‥ 奥様が‥ そんな‥ 」
「この大冒険に出る時‥ 明るい母の笑顔に送り出されてわたしは家を出た。 もう二度と、母に会う事はないと覚悟を決めて旅立ったのだ。 それは皆も同じであったと思う 」
一同は頷(うなず)いた。
「だが、わたしはダメだった。 母が重病だと聞いた途端、彼女に会いたくなってしまったのだ。 あの決意は、彼女が元気である事を前提(ぜんてい)にした話だった―――こんな情けない主人を笑いたくば笑ってくれ。 しかし、一晩考えてみたが、やはりこの思いを断(た)ち切る事はできなかった 」
誰も口を開かなかった。ロレンツォの気持ちが痛いほど判るからだ。そう簡単に親を捨てる事などできようはずがない。
「ヤンチャだったわたしは、幼い頃から彼女にたくさんの迷惑をかけてきた。 何度も何度も心配させ、また悲しませてきたんだ。 それだけに‥ 死ぬ前に謝りたい事や、言い訳したい事が山ほどある。 最後ぐらい、彼女の手を握ってやりたい‥ そばにいてやりたいんだ! だから、このわたしをヴェネツィアへ帰してくれ! お願いします! 」
ロレンツォは『主人』として、隊商(カラバンヌ)の部下達に命令はしなかった。『仲間』として、彼らに真摯(しんし)に願い出たのである。
その場の全員が、ふたたびコクリと頷(うなず)いた。
警備の武人から奴隷にいたるまで、ロレンツォに心酔(しんすい)してついてきた者ばかりである。彼らもまた、仲間としてその申し出に賛同(さんどう)したのだ。
「ぜひ、そうなさいませ! わたくしもお供させていただきます 」
マルコがそう言った。彼は五十をとうに過ぎており、体力的にも今回の旅は無理であった。そのため、イベリアのキリスト教国家、ナバラ国で別れる予定となっていたのだ。
ロレンツォは、一人一人の目を見詰めて語り掛けた。
「とはいえ、我々の冒険を中止するワケではない。 ただ、もしかしたら、しばらく延期(えんき)する事になるやもしれん。 それから、隊商(カラバンヌ)ごとヴェネツィアに戻るのは時間もかかるし、金もかかる。 そこで、皆はこの地に残り、私が再び戻ってくるまで待っていて欲しいのだ! 」
「了解しました、御主人様! 」
一同は声を揃(そろ)えて了承(りょうしょう)した。
その時、頼純が申し出た。
「ならば、我々はファレーズまで戻って、待っていてもよろしいでしょうか? わたくし、もう一度あの伯爵(コント)と話してみたいと思っておりましたゆえ 」
ロレンツォはニコリとほほ笑んで答えた。
「いいだろう。 お前の好きにするがよい。 ただし、ロベール伯の家来になってもらっては困るぞ。 お前はわたしと一緒に日本へ行くのだから! よいな? 」
頼純は大きく胸を叩いて応(こた)えた。
「ご安心ください。 それは肝(きも)に銘(めい)じておりますから。 我々の冒険はここで終わりはいたしません! 」
× × × × ×
その後、ロレンツォは手早く荷物をまとめると、マルコとジュリオを引き連れ、早馬(はやうま)でヴェネチアへと戻っていった。
頼純達は彼らの帰郷(ききょう)を見送ると、遅い朝食をとった後、ロレンツォから申し渡された詫(わ)びの言葉をモンサンミッシェルの修道院長へ伝えに向かった。
それからゆっくりと準備をし、宿を出発したのは、すでに昼近くになっていた。
今夜はアヴランシュの町で一泊し、明日はヴィルデュ村、明後日はそこから街道を東に折れて、カーンではなく、ヴィール村へと向かう。そこから、二日ほど街道沿いに東へ向かうと、ファレーズの町に到着する。それは、じつにのんびりとした旅だった。
隊商(カラバンヌ)には、少々拍子(ひょうし)抜けした感があった。
これまでは、まもなく訪(おとず)れるであろう苦難(くなん)の旅への緊張や不安、まだ見ぬ新天地に対する希望や期待で、日々ドキドキ、ワクワクしていたのだ。
それが急に、無期限の停止となったのである。
隊商(カラバンヌ)内の空気が、散漫(さんまん)になった事も致(いた)し方なかった。
彼らは、木漏(こも)れ日が差し込む巨大な森の中を、街道沿いにゆっくりと進んでいった。
森の中をしばらく行くと、前方から明らかに騎士、兵士と思われる一団が現れた。
彼らは、鎧下(ガンベゾン)の上に鎖帷子(オベール)を着け、兜(カスク)も装備している。その手には抜き身の長剣(エペ)と盾(エキュ)が握られていた。
明らかに戦闘態勢をとっている。
気がつけば、一行の左右の林にも、その仲間と思われる兵士達が槍(ラーンス)を構(かま)えて隠れている。
前方から、ゆっくりと近づいてくる20名ほどの騎士達は、明らかに頼純達を狙っていると思われた。
緊張の欠如(けつじょ)は頼純達に大きな油断を作らせ、これだけ多くの兵士達の気配(けはい)を気づかせなかったのだ。
それは、あってはならない失態であり、そんな自分を頼純は心の中で罵(ののし)った。
頼純はすぐさま状況を分析した。
彼らはあきらかに兵士である。山賊や盗賊のように、自分達の荷物を奪(うば)いに来たわけではないと思われた。
では、兵士達の目的は? 自分達の捕縛(ほばく)なのか、殺害なのか―――そのどちらかに違いない。
また、現在の頼純達の陣容(じんよう)ならば、この武装集団を追い払う事も可能であろう。
だが、これだけの兵士と闘えば、コチラにもかなりの死傷者が出る事は間違いなかった。
大冒険を前に、仲間達を危険にさらす事はできない。
隊商(カラバンヌ)は逃げ場を求めて、ジリジリと後退していた。
そんな中、意を決した頼純だけがその場に留(とど)まった。
腰を落とし、太刀(たち)の柄(え)に手を掛けると、先頭の騎士に丁寧(ていねい)なフランス語で誰何(すいか)した。
「そちらは、いずれのご家中(かちゅう)にあられるか? 我々はヴェネチアはロレンツォ家の隊商(カラバンヌ)‥ これより、ファレーズへ向かう途中にございまする。 なに用にございましょうや? 」
「‥‥‥ 」
だが、騎士達は何も答えない。
この場では、頼純が太刀(たち)を抜く事はできなかった。彼が抜けば、それは戦闘開始の合図となってしまうからだ。
しばしの睨(にら)み合いが続く。
と、背後で女の叫び声がした。
頼純がハッとして振り返ると、隊商(カラバンヌ)最後尾にいた女奴隷が兵士に捕まえられている。
太刀(たち)の柄(え)を握り締めたまま、頼純は彼女の元へ駆(か)け寄ろうと踏み出した。
その刹那(せつな)、
「いまだ! 」
と大きな声が掛かった。
『しまった! 』
心の中でそうつぶやきながら、頼純は太刀(たち)を抜き掛けたが、すでに遅かった。
足元の地面が持ち上がると、そのまま体が宙に浮いたのだ。
罠(わな)に掛かった頼純は、大きな網(あみ)で吊(つ)り上げられ、身動きが取れない状態になっていた。
頼純が捕まるや、周囲から多くの兵士が飛び出してくる。
彼らはすぐさま、背後の傭兵(ようへい)達も制し、隊商(カラバンヌ)全員を拘束(こうそく)していた。
尻を下にして、体を『く』の字に折られた頼純に、正面の騎士団が慎重に近づいてくる。
頼純の下に立った彼らが一斉に剣を突き上げれば、宙にぶら下がった頼純はその場で死ぬだろう。
「クソ! なに奴か! 名を‥ 名を名乗れ! 」
少々、焦(あせ)った声で頼純は叫んだ。
その時、頼純を囲んでいた兵士達の輪が割れ、一人の上級騎士が登場した。
「わたしは、ノルマンディー大公家の家宰(セネシャル)であるオズバーン卿(きょう)である。 リシャール3世大公の命(めい)により、ヴェネチアのロレンツォが警備隊長―――藤原頼純なる者を捕縛(ほばく)しにまいった。 神妙(しんみょう)に縛(ばく)につけ! 」
「はあ!? リシャール3世ィ‥? 」
その言葉に、頼純は戸惑(とまど)うばかりであった。