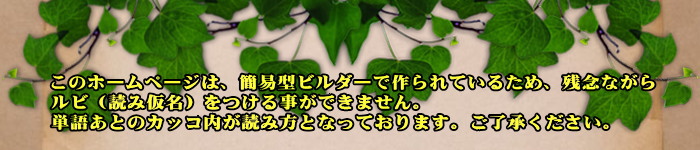
70
1017年 イングランド・ウィンチェスター城
イングランド王国の前王妃である『ノルマンディーのエマ』は、幽閉(ゆうへい)されていたウィンチェスター城の自室で一人脅(おび)えていた。
あのゴドウィンとかいう怪しげな男の言った通り、イングランド軍は敗北し、エドマンド剛勇王(ごうゆうおう)は急死した。そして、新たに国王となったクヌートの命令によって、ウェセックス王家につながる者やエドマンド剛勇王(ごうゆうおう)を支援した者達は次々と逮捕・処刑されていったのである。
エドマンド王の妻、『イーストアングリアのエディス』王妃もすでに首を刎(は)ねられていた。
エドマンド王とエディスの子供、エドワードとエドモンドも捕らえられ、処刑のためスウェーデン王国へ送られたと聞いた。
噂では、スウェーデン国王・オーロフ・シェートコヌングは、1歳児と産まれたばかりの赤ん坊だった二人の王子を不憫(ふびん)に思い、一人をポーランド王国に、もう一人をキエフ公国へ送還(そうかん)したらしい。彼らがその後どうなったのか、宮廷の誰一人として知らなかった。
ウェセックス家の血を継ぐ者で唯一、確実に生き残っているのは、エマとエセルレッド前王との子供達―――現在ノルマンディー公国に預けられているゴーダとエドワード、アルフレッドの姉弟だけであった。
ゴドウィンは、『アナタ様を必ず助けて差し上げましょう 』などと言っていたが、そんな口約束はあてにならない。
次は自分が殺される番ではないかと、恐怖に苛(さいな)まれる毎日であった。
彼女は心底(しんそこ)、後悔していた。夫・エセルレッド2世が死んだ時に、さっさと実家であるノルマンディー公国へ戻ればよかったのだ。
ゴドウィンとかいう男の口車に乗って、つい欲を出したばかりに、戻る機会を失ってしまった。
ただ、あれから彼女は彼女なりに、その後の生き残り方について真剣に考えたのだ。そしてやはり、クヌート王と結婚する事が最善の策であろうという結論になった。
たとえノルマンディー公国へ戻ったとしても、その後の彼女の人生はどうであろうか?―――出戻りの厄介者(やっかいもの)として生涯(しょうがい)を終えるか、フランスの中小貴族へでも嫁(とつ)ぎ、ずっと格下の伯爵夫人として一生を過ごすぐらいしかないだろう。一度、国王妃として、強大な権力や絶大な服従を得た者にとって、伯爵夫人ていどの力など屈辱でしかなかった。
それゆえ、あの男の言葉が頭の中にこびりついて、他の考えが思いつかなかったのかもしれない。
だがその一方で、クヌート王子との結婚がいかに難しいかも十分に分かっていた。
彼は敵の総司令官である。しかも、彼女より10歳も年下で、さらにはすでに妻と子供までいるのだ。
エマがクヌートを籠絡(ろうらく)する事など不可能に近かった。
そんな事をあれこれ悩んでいる内に、事態は何度も急展開を繰り返し、それについていけないエマはロンドンからの脱出の機会さえも逸(いっ)してしまったのだ。
ロンドンウォールの宮廷にいた彼女は、3週間ほど前に先遣隊(せんけんたい)として入場したデンマーク兵によって捕らえられ、このウィンチェスター城に閉じ込められたのである。
いつ死刑執行人が現れるのかと、エマは毎日ビクビクしながら暮らしていた。髪を掴(つか)まれて無理やり広場へ引きずり出され、そこで首を刎(は)ねられる―――そのような悪夢に毎晩うなされていた。
そんな或(あ)る日、彼女が幽閉(ゆうへい)されていた寝室の扉が突如開かれる。
エマは『ついに来たか!』と心臓が止まりそうになった。だが、彼女の目の前に立っていたのはニコニコと微笑(ほほえ)むゴドウィンであった。
彼はエドマンド剛勇王(ごうゆうおう)の一番の家臣であったにもかかわらず、唯一生き残っていた。いや、今ではクヌート王の重臣なのだ。
イングランド国民はこの男を裏切り者とみていたし、エドマンド王はゴドウィンに暗殺されたのではないかと噂する者さえいた。
「どうも‥ ご無沙汰(ぶさた)しておりました 」
ゴドウィンが丁重(ていちょう)に頭を下げた時、エマは暗黒の中に一条の光が差し込んだようで、涙があふれるほど安心した。
「あなたはもう戻ってこないとばかり思っていました。 だって、あなたはクヌート王の家臣になられたのですもの。 今は支配する側の人間! 今さら、何の権限も持たない元王妃の側近となる必要もないし‥ ましてや、妻殺しの疑いを晴らす必要さえなくなりました‥ 」
「何をおっしゃいますか。 わたくしは約束は守りますよ。 あなた様をクヌート王の妃(きさき)にしてみせましょう 」
「ど‥ どうして、そんな事を? 何のために―――? 」
エマは驚いていた。いまの彼女にとって、生き延びる事だけが望みであった。それ以上の事は期待していなかったのだ。
「そうですねェ‥‥ 」
エマから理由を尋(たず)ねられたゴドウィンは、ちょっと考えてからそれに答えた。
「だって‥ そっちの方がおもしろそうじゃないですか♡ 」
× × × × ×
早速、ゴドウィンはエマとクヌート王を結びつける準備に取り掛かった。
クヌート王は1013年、父王(ふおう)スヴェン1世の命令により、18歳で『ノーサンプトンのエルギフ』と結婚した。マーシア攻略のための政略結婚であった。
だが、この結婚は教会が認めた正式のものではなく、仮祝言だったのだ。その後、クヌートは戦争に次ぐ戦争で、彼女との『結婚』をきちんと神に誓(ちか)うヒマはなかった。
それゆえ、いまエマとクヌート王が正式に結婚すれば、彼女の方が正妻となれるのだ。
とはいえ、二人がまず知り合わなければ何も始まらない。
そこで2週間後に、クヌート王戴冠(たいかん)の祝宴(しゅくえん)を、エマ前王妃が主催者となって開く事にした。ゴドウィンが口を利(き)けば、クヌート王は招待に応じてくれるだろう。彼はすでにそれほどの信用を王から得ていた。
その祝宴(しゅくえん)の際に、二人を結びつけるのだ。
そのためには、それまでに男をたらし込む手練手管(てれんてくだ)を、エマに憶(おぼ)えさせねばならなかった。
ゴドウィンは、ロンドンの高級娼婦(しょうふ)の中でも最高ランクの者数名を密かにウィンチェスター城に呼び寄せ、彼女の指導に当たらせた。
まずは、その容姿(ようし)をより魅力的にみせる方法からはじまる。
当時、化粧はキリスト教会が禁じていた。神から与えられた素顔を、化粧をする事で偽(いつわ)ってはならないとされていたのだ。
だが、それでも娼婦(しょうふ)達は化粧をしていた。より美しく見せなければ、客を他の女に取られてしまうからである。彼女達にとって、『神』よりも『金を稼ぐ』事の方が大切だったのだ。
紅(べに)の差し方や、睫毛(まつげ)を黒く塗る方法をエマは教えられた。また、目の周囲も黒い線で縁(ふち)取るのだ。これで目元の印象が強くなり、より魅力的に見えるらしい。
ただし、美しく変身させながら、自然であるようにとゴドウィンは指示していた。化粧が濃すぎては、男は逆に引いてしまうからである。
さらに、男を引きつける笑顔の作り方やポーズの取り方、衣服の着崩し方なども娼婦(しょうふ)達に指導させた。
そしてもちろん、ベッドの中での愛情表現も‥‥。
下品にならず、優美でありながらも、男の身も心も溶(と)かし、虜(とりこ)にするような技術であった。
毎日、ほとんどの時間がその過酷(かこく)な訓練にあてられたが、お肌のために睡眠だけはタップリとるようにしていた。
そして、ついに祝宴(しゅくえん)の日は訪(おとず)れたのだ。
ウィンチェスター城はその準備におおわらわであった。大広間には30台以上のテーブルが並べられ、3人掛けの椅子は70脚近く用意されていた。大量の食器が並べられ、何トンもの酒が準備された。その一番奥、一段高くなったテーブルには、中央にクヌート王の玉座が設(もう)けられ、その右隣には主催者であるエマ前王妃の席、左隣が古将エイリーク・ハーコナルソン伯爵の席となっていた。ゴドウィンは彼女らの目の前、主賓(しゅひん)の席に一番近いテーブルに陣取る事にしていた。
招待客は、デンマークの貴族や有力戦士などが大半だったが、かろうじて生き残ったイングランドの貴族や有力者なども呼ばれていた。
厨房(ちゅうぼう)では、30人を越える料理人が慌(あわ)ただしく、その腕を振るっている。
間もなくクヌート王が到着するとの連絡が入る中、寝室に控えていたエマは不安な気持ちで一杯だった。
『やっぱり、無理! アタシなんかが見初(みそ)められるはずがない』―――彼女の頭の中は否定的な思いばかりがよぎっていく。
様子を見に来たゴドウィンが、そんな彼女を励(はげ)ました。
「何を心配されておるのです。 あなた様ほどの美貌(びぼう)なら、クヌート王が恋に落ちぬはずはないじゃないですか。 訓練も十分に積みましたし‥‥ もっと、自信を持ってください 」
ゴドウィンは、懐から2つの薬を取り出すとエマに差し出した。
「しかしながら‥ それでも不安ならば、万全の態勢にしておきましょう♡」
彼はエマの目を覗(のぞ)き込むと
「あなた様とクヌート王が二人きりになられたら、王の飲み物の中にこの粉薬を入れてください。 さすれば、王は必ずあなた様の体に触りたくなります。 さらに寝室に入ったら、今度はこちらの丸薬を香炉の中に入れるのです。 そこから出る煙は、和合(わごう)の感度を何倍にも増幅させ、快楽の極致(きょくち)へと誘(いざな)いましょう♡ 」
使い方を伝授した彼は部屋から出て行った。
いよいよクヌート王が城に到着した。
エマは城門まで出迎え、臣下(しんか)の礼を取った。
「これはこれは、クヌート王様‥ この度(たび)は新国王の御継承まことにおめでとうございます。 陛下の臣民(しんみん)として、お祝いの宴(うたげ)を精一杯催(もよお)させていただきます。 どうか、お楽しみくださいませ 」
「ああ‥ 」
クヌートは素っ気なく返事をすると、広間へと続く回廊(かいろう)を足早に進んでいった。
エマは意外だった。
クヌートは恐ろしい男だと聞いていたが、華奢(きゃしゃ)な体とあどけなさを残す顔をしていた。それも当然であろう。義理の息子であったエドマンド剛勇王よりも6つも年下なのである。夫エセルレッド2世と比べれば親子ほども歳が離れていた。
彼のそんな幼さに、エマはちょっと安心した。そして、今度はドキドキしはじめたのだ。
彼女は31歳の今日まで、恋をした事がない。
17歳の時、34歳のエセルレッド王と結婚し、その後13年間、夫を慈(いつく)しみ、愛し続けた。だがそれは恋愛感情などではなく、子供達の父、家族としての愛であった。
だから、甘く切ない思いや胸のときめきなどを、これまで味わった事がないのだ。
もちろん今夜、彼女が企(たくら)んでいる事は恋愛などではない。自分が生き残るための『色仕掛け』にすぎない。
だが、これからこの若者と何かがあるかと思うと、彼女は胸の高鳴りを押さえる事ができなかった。
× × × × ×
「少し酔ったみたいですわ。 よろしかったら、外の風に当たりながら、お話しませんか‥? 」
エマは隣のクヌート王に耳打ちした。彼女としては、かなり積極的な行動であった。
「あ‥ ああ‥ いいだろう! 」
二人は席から立ち上がった。
宴席では食事も終わり、お菓子と食後酒の時間となっていた。大いに飲み、楽しく盛り上がったデンマークの貴族達は、ノルド語で歌を唄いはじめた。古代の英雄を讃(たた)えた歌謡集(エッダ)のようであった。
喧噪(けんそう)を抜け出したエマとクヌートは中庭を散歩した。しかし、外は最も寒い2月である。マントを羽織(はお)っていた事、風がなかった事、酒を飲んでいた事で、なんとか寒さを我慢できたが、それでも少し歩くと酔いが覚めてしまうほどであった。
「寒い! やはり、ちょっと無謀でしたかね 」
「そ‥ そうだな‥ 」
エマはマントの内側から酒の入った素焼きのボトルを取り出した。
「飲みますか? 体が温まりますよ‥ 」
「ああ‥ いただこう‥! 」
クヌート王は口数が少なかった。彼はエマの提案を承認する言葉しか語らなかったのだ。いつもの陽気さや、剛胆(ごうたん)さ、そして時に見せる残虐(ざんぎゃく)さなどはすっかりなりを潜(ひそ)めていた。
クヌートは緊張しているのだ。
彼はエマから差し出されたボトルを受け取るとグイと飲んだ。
「あ‥ 美味い! 」
驚きの声が上がる。
「じゃあ、わたくしも♡ 」
今度はエマがボトルを奪い、媚薬(びやく)入りの酒を呷(あお)った。そして、再びボトルをクヌートに戻したのである。
「陛下は今後イングランドをどう統治なさろうとお考えなのですか? 」
クヌートはボトルの酒を飲みながら、それに答えようとした。
「統治とか、政治とか言われても――― 」
その時、彼の目の前に火花が飛んだ。視界が歪み、真っ暗であるはずの中庭に黄色や桃色の光が浮かび上がる。苦しくはないが、毒を飲まされたのかもしれない。そう思ってエマを振り返ると、彼女は楽しそうに微笑(ほほえ)んでいる。その笑顔がたまらなくかわいらしかった。彼自身もどんどんと楽しくなっていく。
いつの間にか、何かを話し、笑っているようだった。さきほどまでの緊張はもはやない。
さらには、これまでデンマーク軍総司令官として、またイングランドの新国王として、自分を律してきた『戒(いまし)め』も、一気に砕け散ったような気がした。
クヌートはエマのバラ色の唇にどうしても口づけがしたくなったのだ。 そして、その均整の取れた体を抱きしめたくなった。
これは酒のせいなのか‥毒薬のせいなのか‥そんな事はもうどうでもよくなっていた。
二人はどちらからとなく、クヌートの寝室へと向かっていったのだった。