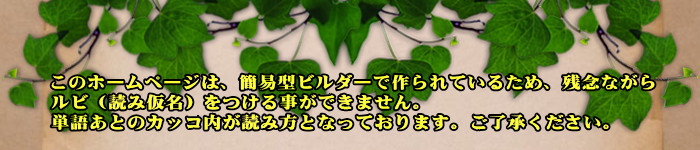
11
1026年 ファレーズ城・中庭(2)
「いいか? この俺様が、『おおそれながら―――』って、お上(かみ)にタレ込みゃあ‥ オメーだって死刑になっちまうんだぞ! それでもいいのかよ‥ああ!? 」
「‥‥ 」
箱からトマを見上げているジャンには、その顔がよく見えていなかった。
ただトマの沈黙は、彼が答えに窮(きゅう)しているからだと判断したジャンは、さらに強気に出た。
もし、ジャンがトマの表情を見ていたなら、そのまったく感情のない目を不気味に思い、別の言葉を使っていたに違いない。
「死刑が嫌なら‥ この俺様を逃がすんだ。 どんな手を使ってでも、必ず逃がせ! いいな!? 判ったか、クソ坊主!! 」
ジャンは居丈高(いたけだか)に命令した。
「‥‥‥ 」
「おい! 聞いてんのか? 返事ぐらいしろや! 」
「それはお断りいたしましょう。 」
トマは鼻で笑うとキッパリと拒絶した。
「え? 」
「アナタがあのコトをバラしたいとお思いなら、どうぞお好きになさってください。 わたくしは、自分が死罪になる事など‥ アナタに仕事を依頼した時から覚悟しておりますから 」
「い‥ いや‥ あの――― 」
まさか、そんな答えが返ってくるとは予想だにしていなかったジャンは、完全に言葉を失ってしまう。
「そもそも‥ わたくしが大金を積んで依頼した仕事を‥ アナタは失敗したのですよ。 なのに、アナタはなぜ、そのように偉そうな口を利(き)くのですか? 」
「だ‥ だって、それは――― 」
トマは冷淡な口調で、ジャンが抱(いだ)いている『仲間意識』のようなモノを打ち砕いていく。
「ともかく‥ アナタはこの地の領主を襲ったのです。 これはもっとも重い罪だ。 ですから、取り調べや裁判でアナタがナニを白状しようとも、アナタは間違いなく死刑となります―――おそらく、『火あぶりの刑』でしょう 」
「ひ‥ 火あぶりの刑‥‥! 」
トマは薄笑いを浮かべてその恐怖心をさらに煽っていく。
「ええ‥ それはそれは、熱いそうですよ。 なにせ、足下から体が焼かれていくのですからねェ。 その苦しみといったら、アナタのような不信心な者でさえ、天を仰ぎ‥ 『どうか、早く死なせてください』と祈るほどだそうです 」
ジャンはゴクリと喉を鳴らした。
中世終盤の15世紀に『魔女狩り』が始まるまで、『火あぶりの刑』は罪人を杭(くい)に縛り付け、そのまわりにびっしりと薪(まき)を積み上げて、火をかける方法が一般的であった。
薪(まき)は小枝が多く、その炎は一気に燃え上がる。そこから大量に発生した高温の煙は、罪人を一酸化炭素中毒、あるいは気道熱傷(ねっしょう)によって瞬時に窒息死へと至らしめた。
つまり、本当は熱さを感じる前に死んでしまう事の方が多かったのだ。
「しかしながら‥ アナタにはその前に、取り調べという名の『拷問(ごうもん)』が待っていますけどね 」
トマの楽しそうな顔には、聖職者にあるまじき残忍さが宿っていた。
恐怖心が膨(ふく)らみ始めたジャンではあるが、精一杯の虚勢(きょせい)を張ってみる。
「へ‥ へへへ‥ そ‥ そっちは、大丈夫だ。 俺ァ、痛みにはかなり強ェ方だからさ‥ 何とかなると思う♡ 」
何も判っていないジャンをトマは嘲笑(あざわら)った。
「あれあれあれェ‥ アナタは取り調べが、拳(こぶし)で殴られたり、せいぜいがムチで打たれる程度だと勘違いしていませんか? 『拷問(ごうもん)』はそんな生やさしいモノではありませんよ 」
「‥‥‥ 」
トマは箱の中に向かって楽しそうに話し掛けた。それはまるでジョークでも語っているかのようである。
「まずは‥ 両手両足すべての爪が剥(は)がされるそうです。 そして、そのあまりの痛みに絶叫し続けたアナタの声がかれ果てた頃‥ 今度は、その血まみれの指を一本一本切断していくのです 」
その言葉を想像し、ジャンの心に黒い染みがジワジワと広がっていく。
「もちろん‥ たくさんの血が出ますが―――そのせいでアナタが死なないように、切断面には焼きごてが押しつけられ、止血されるそうです。 拷問(ごうもん)部屋は血の臭いと肉の焼ける臭いで充満します。 やがて、何杯もの水を掛けられたアナタがやっと意識を取り戻すと、次は歯が一本一本抜かれていくのです。 そして、その次には目も…‥ 」
「ああああ‥ 」
それは、ジャンを絶望に導くに十分であった。彼の頭の中で真っ黒な光が大きく瞬(またた)いた。
トマはサディスティクな微笑(えみ)でジャンを見下ろしている。
「しかし、それでもアナタが死ぬことはありません。 拷問番は、相手に痛みだけを与え、死なせない技術を持っているからです。 ですから、アナタは来る日も来る日も‥ 眠る事も休む事も、気を失う事さえ許されず‥ ひたすら激痛の中を漂(ただよ)いながら、ジワジワと死へ近づいていくのです。 それは、すぐにでも『火あぶり』にされた方がどれほど楽かと思うほどでしょう」
「い‥ いやだ‥ いやだ、助けてくれェェ‥ 」
ジャンはおこりにでも罹(かか)ったかのようにガタガタと震えながら、首を左右に振り続ける。彼もやっと、これから自分の身に降りかかる不幸を理解したようだ。
「やだやだやだやだ! 」
そう叫ぶと、ジャンは檻(おり)の鉄棒と鉄棒の間に涙目の顔を押しつけ、トマに必死に懇願(こんがん)した。
「た‥ 助けて! 助けてくれェ。 助祭様、この俺を助けてください! 」
大声を上げるジャンに、トマは自分の唇に人差し指を当て静まるように指示した。
それから彼は抱えた聖書の表紙を優しくなでながら、ジャンにそっと語り掛けた。
「もし―――アナタがその地獄のような苦しみから逃れたいと思うのなら‥」
「お‥ 思うのなら―――? 」
トマは檻(おり)に顔を近づけ囁(ささや)いた。
「拷問(ごうもん)が始まる前に死んでしまうのです! そうすれば、少なくともその苦痛からは逃(のが)れられる―――それが唯一の方法でしょう 」
その言葉に、ジャンは目を大きく見開いたまま、固まってしまう。
「し‥ 死ぬ―――? 」
「そうです。 わたくしはアナタを救うタメに、薬を持って来て差し上げました 」
トマは、懐から素焼きの小瓶(こびん)をゆっくりとつまみ出す。
「これさえ飲めば‥ アナタは天国にいるような幸せな気分になれます。 そして、やがて大きな睡魔に襲われ‥ そのまま眠ってしまえば、アナタの心臓はやがて静かに止まってしまうのです 」
トマは妖しげな目でジッとジャンを見つめている。先ほど年嵩(としかさ)の警護兵にしたように、ジャンにも催眠術をかけているようだった。
その視線に魅入(みい)られ、ジャンはしだいにトロンとした目になっていった。だが、最後の理性が必死にそれを押しとどめようとした。
「そ‥ それは自殺じゃないのですか‥? 自殺をすれば、死者の魂は永久にこの世をさまようのでしょう―――? 」
「そうはいっても‥ このまま火あぶりになってしまえば、アナタの肉体は焼けてなくなり‥ どちらにしても、『審判の日』に復活する事はできないのですぞ 」
「そ‥ そんなァ――― 」
今まで、散々悪事を働いておきながら、この期に及んで復活もクソもないだろう‥‥と、トマは思ったが、それでもジャンを安心させるように穏やかな声で囁(ささや)いた。
「大丈夫! この薬さえ飲めば、アナタは神の仕事を手伝った者となり‥ これまでのすべての罪悪が許され、天国に召(め)される事になるでしょう 」
「か‥ 神の仕事‥? 」
「そう! アナタは主(しゅ)の僕(しもべ)であるこのわたくしの仕事を手伝ったのです。 だったら、それは主に仕(つか)えたのも同じ事! きっと主もお喜びになるハズです 」
その思いもよらぬ言葉に、ジャンは恍惚(こうこつ)の微笑(えみ)を浮かべる。
「ホ‥ ホントに? ホントに、この俺が‥ わたしが天国にいけるのですか? わたしのように、愚(おろ)かで罪深い者が―――天国に‥? 」
「そうです。 だから、この薬をお飲みなさい‥ 」
「は‥ はい‥ 」
完全に術に掛かったジャンは、うっとりした顔で頷(うなず)いた。
トマは嘘をついていた。
ジャンがいくら悔(く)い改めようとも、このような悪党が天国に行けようはずはない。
さらに、トマの薬を飲んでも、ジャンがすぐに死ぬ事はなかった。
拷問(ごうもん)が始まる朝にジャンが死んだのでは、唯一の接見者であるトマが疑われてしまう。だから、ジャンには数日間生きていてもらわなければならなかった。しかもその間にどのような拷問(ごうもん)を受けようとも、真実を語られては困るのだ。
ジャンに飲ませた薬液は、遅効(ちこう)性の猛毒であるタマゴテングタケと、速効性で幻覚や酩酊(めいてい)・多幸(たこう)感・健忘(けんぼう)を及(およ)ぼすベニテングタケから抽出した毒を複雑に混(ま)ぜ合わせ、さらに薬効(やっこう)を強めたモノであった。
それは、半日ほどで効力を発揮(はっき)し、泥酔(でいすい)したかのような意識消失状態が2、3日も続く。まともに口がきけない状態で、やがて激しい嘔吐(おうと)と下痢(げり)が始まり、心臓を衰弱(すいじゃく)させて確実に死へと導くのだ。
ジャンは、どんなに厳(きび)しい拷問(ごうもん)を受けようとも、決して口を割る事なく、3日目に突如心臓が止まるだろう。
それはそれは恐ろしい毒薬であった。
このような毒物を扱う者は、いつの時代も『邪悪なる者(マレフィキウム)』と呼ばれたが、この時代はとくに―――『魔女(ソルシエ)』という名称が与えられた。
トマは神に仕える身でありながら、そのたぐいの人種だったのである。
× × × × ×
紀元476年、西ヨーロッパ全土を治めていた西ローマ帝国が崩壊すると、北部ヨーロッパのスカンジナビア人達はしだいに南へと移動を始め、6世紀の初頭には本格的な侵攻(しんこう)を開始した―――バイキングである。
彼らは農民であり、漁師であり、商人でありながら、盗賊であり、殺戮者(さつりくしゃ)であり、破壊者でもあった。
彼らが歴史の表舞台に登場するやいなや、ヨーロッパは恐怖のどん底へと突き落とされる。それほどまでに、彼らの殺戮(さつりく)と略奪(りゃくだつ)はすさまじかったのである。
紀元885年には、三万人のデンマーク人を引き連れたバイキングの首領・ロロが西フランク王国(後のフランス王国)の都市パリを襲った。当時、パリ要塞には二百人ほどの騎士しかおらず、瞬(またた)く間に町は炎に包まれ、何百と立ち昇る黒煙は天空を覆(おう)い尽(つ)くすほどであった。
それでも、騎士達は数ヶ月の籠城(ろうじょう)に堪(た)えたが、完全な囲い込みによる食糧不足はやがて城内に飢餓とペストをもたらし、パリは陥落(かんらく)寸前にまで追い込まれていくのである。
一方、ロロが率いるバイキング達は、セーヌ川下流域に定住し、ここを拠点(きょてん)にフランス各地を荒らし回った。
彼らバイキングによる国土の荒廃(こうはい)―――ひいては、西フランク王国の簒奪(さんだつ)をも懸念(けねん)したシャルル単純王は、911年に首領であるロロと『サン・クレール・シュル・エプト協定』を結ぶ。
西フランク国王に対する絶対的忠誠とキリスト教への改宗(かいしゅう)を条件に、彼らにフランス北部・ネウストリアを領地として与えたのである。
これがノルマンディー公国の始まりであった。
首領のロロは教会の洗礼を受け、名をフランス風にロベールと改(あらた)めた。また、ベランジュ伯の娘ポパと結婚する事で、仲間達にもフランス人との婚姻(こんいん)を促(うなが)した。
罪のない人々を殺し、犯し、奪ったかつての強盗集団は、こうしてキリスト教的フランス文化を取り入れ、しだいに異郷(いきょう)になじんでいったのである。
それから115年後、ロロから数えて5代目となるリシャール3世の時代には、ノルマンディー公国はフランスでも五本の指に入るほどの名家であり、大国となっていた。
× × × × ×
『山犬のジャン』は、拷問(ごうもん)が始まってから三日目の朝に死んだ。
その死因が、苛烈(かれつ)な拷問(ごうもん)によるモノなのか、病によるモノなのかは医者も判断がつかなかった。
ましてや、教会の助祭トマを疑う者など誰一人としていなかったのである。
その日は、夜明け前から激しい雨が降りだした。
あちこちで旅ゆく人々を襲っては、荷を盗み、殺害していたジャンだけに、その死を悼(いた)む者は誰もいなかった。
しかし、重要な容疑者の死に、拷問(ごうもん)官や兵士達は大いに慌てた。彼らは雨に打たれながら、ぬかるんだ館の庭を走り回って大騒ぎをしていた。
そんな中、朝から馬小屋の軒下(のきした)に腰を下ろした頼純は、右往左往する兵士達を眺(なが)めるワケでもなく、ただ無心に木の枝を削っていた。
そもそも、『ジャンの背後には暗殺を依頼した首謀者がいる』とロレンツォに進言したのは、ほかならぬ頼純である。
だが、ジャンが死んで、その依頼人=真犯人が判らなくなったとしても、頼純の知った事ではない。
いや、そもそもロベールが死のうと生きようと、頼純にはなんの興味もなかったのである。
しょせんは、長い長い旅路の間に、ちょっと目を向けただけの異邦人(いほうじん)である。彼にはまったく関係のない人物であった。
そして、いまはジャンが死んだ事よりも、出来の良い箸(はし)を作る事の方が頼純にとっては重要であった。
そこへ、サミーラが雨に打たれながら走り込んできた。
彼女は、ヒジャブの頭や肩に着いた雨粒を払いながら、頼純にペルシャ語で話し掛けてきた。
「もう‥ すごッい雨! どこもかしこも、完全にぬかるんでます。 荷馬車も当分は動かせないみたい 」
「―――そうか‥‥ 」
頼純もペルシャ語で短く返した。
サミーラも、ジャンの死にまったく関心がないようである。むしろ、この雨で道中が難儀(なんぎ)する事の方が気がかりのようであった。
サミーラは頼純から少し離れた場所に腰を下ろした。
それっきり、二人の間には長い長い沈黙が続く。
しばらくして、やっとサミーラが口を開いた。
「あ‥ あのォ‥ こうして話すのは‥ ひさしぶりですね 」
彼女はそう言いながら、クスリと笑った。
「う‥ うん‥ ひさしぶりだ 」
なんとか返事を返した頼純は、小刀(こがたな)の手を止め、庭に打ちつける雨に目をやった。
サミーラも同じように雨を見詰めている。
「よく降りますねェ‥ 」
「ああ‥ よく降る‥ 」
再び、二人は黙り込むと、ゆっくりと流れゆく時を過ごした。
頼純はけっして寡黙(かもく)な男ではなかったが、サミーラの前ではなぜだか口が重くなってしまう。動悸(どうき)がし、頭に血が上って言葉が出なくなるのだ。
―――彼は恋をしていた。