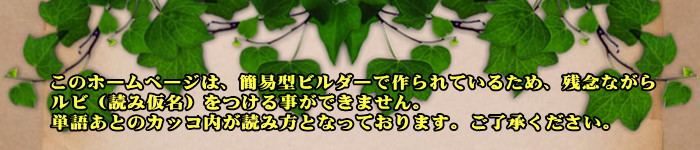
59
1026年 エレーヌの森(2)
「ティボー、どうした? 何だその傷は? 誰にやられたのじゃ? 」
エルキュールは、シュザンヌから手当を受ける弟、ティボーに駆(か)け寄った。
エルキュールの振り回した剣でティボーの二の腕が斬られてから、この庵(いおり)に運ばれてくるまで、かなりの時間が経っていた。その間、エルキュールは何も言葉を発さず、視線をティボーに向ける事もなかった。
それはまるで、自分の過ちを知っているのに、罪悪感からわざと無視をしているような素振りに見えた。
ところが、この庵(いおり)に着いて、本格的に手当を受ける段になって、大騒ぎしはじめたのである。
「おいおい‥ 今頃、気づいたのかよ? しかも、自分でやったくせに‥!」
頼純は小さな声で突っ込んだ。
エルキュールには、ボケている時の人格と、ボケていない時の人格が、それぞれ存在するようである。
だから、ボケている時の人格は、ティボーを負傷させたのが自分である事を知っているのだ。
ところが、ボケていない状態に戻った途端、彼は、ここがどこなのか、なぜティボーが怪我(けが)しているのかも判らなくなってしまう。その間の記憶がぷっつりと途切れているからだった。それは彼にとって、とてつもない恐怖だと思われた。
もちろん、多重人格とは違い、再びボケた状態になったからといって、以前ボケていた時の記憶が蘇(よみがえ)るわけではない。ボケた状態に記憶の一貫性はないのだ。
シュザンヌの庵(いおり)の中は、狭いながらもモノにあふれていた。
四方の壁には、乾燥させるため逆さに吊した薬草の束がたくさん掛けられている。
テーブルの上には、薬草を磨(す)り潰すすり鉢がいくつも載せられていた。
小屋の中央にきられた囲炉裏(いろり)には足つきの大鍋が置かれ、その上には奇妙な器具が載せられていた。そしてそこから出た管(くだ)は、床に置かれた壷(つぼ)へとつながっているのだ。
葡萄酒(ワイン)やリンゴ酒(シードル)などを蒸溜(じょうりゅう)して、中身から蒸留酒(ウォッカやテキーラ、焼酎など)を取り出す仕掛けらしい。葡萄酒(ワイン)やリンゴ酒(シードル)を蒸留させるとブランデーになるが、彼女はこれを数度繰り返し、アルコール濃度をさらに高めていた。
シュザンヌはその蒸留酒が入った細口の水差しを、診察台に横たわったティボーの上腕に傾(かたむ)けた。
中身の無色透明な液体が傷口に滴(したた)る。
「イイイイ‥ 」
水よりもさらに沁(し)みたのであろう、ティボーが呻(うめ)き声を上げた。
この時代には、まだ『消毒』の概念はなかったが、彼女は手をよく洗うとよい事を知っていた。さらに水よりはこの蒸留酒で洗った方が、手術後に患者が熱を出さない事も教えられていた。
「これを飲みなさい。 痛みがなくなるから 」
シュザンヌは、ティボーの口に丸薬を2個放り込み、白湯(さゆ)とともに飲み込ませた。
丸薬はアヘンであろう。ケシの果実から取り出した樹液を乾燥させた物で、ヨーロッパではローマ時代から鎮痛剤として広く使われていた。
しばらくすると、ティボーの目は虚(うつ)ろとなり、意識が朦朧(もうろう)としているようだった。
シュザンヌは消毒酒の入った桶で手を洗うと、その中に沈んでいた針と糸を取り出した。そして、それでティボーの傷口を手早く縫(ぬ)っていったのだ。
「むむ‥ やはり、傷はかなり深いのォ‥ 太い血管まで切れておるようじゃ! 」
少し離れていたところに立つ頼純は、つい心配そうな声を上げてしまった。
「それって、どうなるんです? 」
「どうにもならん! あとは自分の治癒力(ちゆりょく)で元に戻すしかない」
傷口の縫合(ほうごう)が終わったシュザンヌは、そこへ緑色のドロリとした薬を塗った。磨(す)り潰したいくつかの薬草を混ぜ合わせたモノである。
「でも‥ それじゃ当分は血が出続けるんですよね? もし、それが止まらなかったら? 」
ますます不安になった頼純が尋(たず)ねる。一昨日までは、『とっとと、死ねばいい』と思っていたティボーを、いまは心配しているのだ。
「血が大量に流れ出たら、人は死ぬ! 」
シュザンヌはティボーの傷口の上に折り畳んだ麻布をあて、その上から細長い麻布をグルグルと巻き付けていった。
「じゃから、血が止まるようにこうして布で押さえつけるのじゃ。 ちゃんと傷口を縫えば、たいていの場合はこの方法で血は止まる 」
「は‥ はい 」
シュザンヌは血まみれの手を蒸留酒の桶(おけ)で洗いながら語った。
「じゃが、それでも血が止まらぬ時は、腕の付け根を縛って血の流れを止めるのじゃ。 しかし、それを長く続けると腕が腐れてしまうので‥ その時は、焼きごてを使って患部を焼き固めるしかない 」
頼純はその光景を想像し、思わず顔を顰(しか)めた。
「ああ‥ 焼きごてですか‥ ありゃあ、熱いだろうなァ‥‥ 」
「さらに‥ それらすべてが上手くいかなかった場合は、左腕を切断せねばならんじゃろう。 その切断面も焼きごてをあてて止血する 」
こんな話、とても本人には聞かせられないと思った頼純が、ティボーの様子をこっそり覗(うかが)うと、彼は目をつむったままピクリとも動かない。気を失っているワケではないだろう。かすかに寝息が聞こえた。
「腕なんか切断されたら‥ ティボーのおっさん、悔(く)やむぞォ‥! なんだか、かわいそうになってきちゃったよ 」
「安心せい! 傷口はちゃんと縫(ぬ)い合わせたのじゃから、このように止血しておけばたいていは大丈夫じゃ! 」
治療が一段落したシュザンヌは、3つの木の椀(エキュエル)に乾燥した薬草の粉を入れ、そこへお湯を注(そそ)いでいった。やがて優しい薫(かお)りが立ち昇り始める。彼女はその椀を、頼純とエルキュールに渡してくれたのだ。
「さぁ‥ 飲んでみなされ。 気分の落ち着くハーブ茶じゃ♡ 」
熱湯の入ったお椀を両手で包むと温かさが伝わってきて、ホッとした気分になる。しかし中のお茶は熱々で、頼純にはすぐに飲めそうにもなかった。
とその横で、片手で椀を持ったエルキュールがそれを一気に飲み干した。
「うまい! もう一杯! 」
勢いよく椅子から立ち上がると、そう言って椀を差し出すエルキュールに、シュザンヌはクスクスと笑った。
「ほんに、面白いじいさんじゃこと‥! 」
そう言いながら、いったん席を立ったシュザンヌはティボーの顔色と出血の具合いを確認しにいった。そして、ふたたび椅子に腰を下ろすと、頼純にこれからの看護について説明をした。
「さっきも言うたように‥ この男の傷はけっして浅くない! じゃから、2週間ほどは仕事などさせず、自宅で寝て過ごすようにさせなさい 」
「は‥ はい‥! 」
「薬は、10日ほど続ける必要がある。 今日は5日分渡しておくが、あとの分は、誰かに森の入り口まで取りに来させるように! 用意して、置いておくから 」
「それで‥ 治療費の方は―――? 」
「そうじゃなァ‥ この男は金持ちそうじゃから、1リーブル(240ドゥニエ=約24万円くらい)も貰(もら)っておこうか! 」
シュザンヌは金持ちには高い料金をふっかけ、貧しい者には無料で治療を施(ほどこ)していた。それでも1リーブルというのは、治療費としてはさして高い値段ではなかった。
イタリアのサレルノやフランスのモンペリエなどの医学校を卒業したエリート医師ならば、富裕層への治療費は10リーブルを当然のように請求した。国王クラスの御典医(ごてんい)ともなれば、100リーブルをふんだくる時代である。
頼純と話すシュザンヌをエルキュールはマジマジと見詰めた。
「ところで、お前は誰じゃ? 本当にシュザンヌなのか? ワシはお前なんぞに会(おう)た事はないぞ! 」
そう言われたシュザンヌは、エルキュールに背を向け、顔を隠した。
シュザンヌはつねに頭巾(キャピュッシュ)を深く被(かぶ)っている。エルキュールにその顔がハッキリ見える事はできないはずである。大きく曲がった鼻としわだらけの顎(あご)、さらにはその間にある裂け目のような唇が見えるだけであろう。
頼純は呆れ顔で、失礼な事を言うエルキュールの肩を掴(つか)むと、椅子に座らせようとした。
「爺さん、爺さん‥ アンタ、初恋の人に失礼だぞ。 ともかく坐って、もう一杯お茶を飲もうや。 そして互いの思い出話でもすれば――― 」
頼純が話していると言うのに、エルキュールは肩に掛かった手を振り払い、シュザンヌの頭巾(キャピュッシュ)の尖端(せんたん)をグイと引っ張った。
「きゃあ! 」という声とともに、シュザンヌの頭部が露(あら)わになる。
とんでもない行動を起こしたエルキュールを取り押さえながら、頼純はシュザンヌに謝った。
「本当に申し訳ない! このじいさん、相当ボケていて――― 」
そこまで言いかけて、頼純は絶句した。
そこに若い女がいたからである。年の頃なら、30歳ぐらいであろうから、若いというのは言いすぎかもしれない。ただ、60代の女性でない事は間違いなかった。
彼女は顔の下半分に、何かの皮で作られた仮面を付けていた。
仮面は大きな鉤鼻(かぎばな)で、口は大きく裂け、顎(あご)は尖(とが)ってしゃくれている。
つまり、これまで老女であると思っていたシュザンヌは、仮面を付けて年齢を誤魔化(ごまか)していたのである。
シュザンヌが溜息(ためいき)とともに仮面を取ると、そこに美しい顔が現れた。
「もう‥ ホントに、こういうコトしちゃダメでしょう! 絶対にダメだからね! 」
曲がっていた腰をグイッと戻すと、彼女の身長は頼純とさほど変わらなかった。
「まぁ、バレちゃったんならしょうがないけど‥‥ でも、この事は絶対に秘密にしておいてくださいよ! 」
ずっとポカンとしていた頼純がやっと口を開いた。
「あ―――はい‥! 」
エルキュールは得意げに胸を張る。
「ホレ見ろ! やはりワシの言うた通りじゃないか。 この女は、シュザンヌではない! 」
「で‥ ですよねェ‥!? じゃあ、アンタはエレーヌの森のシュザンヌさんじゃないって事―――? 」
「いいえ、私はシュザンヌです。 ただし、私の母もシュザンヌ。 そして、祖母もシュザンヌです。 シュザンヌとは、我が家に先祖代々伝わる女医の名前なんです 」
「ああ、なるほど‥ そういう事だったんだ 」
「おそらく‥ ご老人がお探しなのは、わたくしの祖母―――マリー・シュザンヌなんでしょうけど‥ 残念ながら、彼女は20年ほど前に亡くなってしまいました 」
エルキュールは大きな嘆息(たんそく)とともに、肩を落とした。
「ああ‥ あの人は、もう死んでおったか‥! 」
彼は静かに目を伏せる。
「悲しくもあり、悔(くや)しくもあるが‥‥それも世の常。 ご冥福(めいふく)を祈る事にしよう 」
などとエルキュール達が話していると、なにやら庵(いおり)の外が騒がしくなった。
ガチャガチャと金属がぶつかる音がいくつも重なり、男達が怒鳴る声も聞こえてきた。
慌てて窓から外を覗(のぞ)くと、手に手に武器を持った男達がシュザンヌの庵(いおり)を取り囲んでいる。その薄汚いなりと下品な顔から、彼らが山賊である事はすぐに判った。さきほど退治した賊の仲間なのかもしれない。
その数は50人を越えている。その上、隠し扉のあるトンネルからさらに続々と侵入してきていた。
そのあり得ない光景に、シュザンヌは混乱した。
「何? 誰? どうやってここに入ったの? なぜこの場所が判ったの? 」
十重二十重(とえはたえ)に庵(いおり)を取り囲む山賊達の先頭には、偉そうに腕組みをする大男がいた。でっぷりと太ったその大男が、山賊達の頭目(とうもく)であると思われた。
男は頃合いだと思ったのか、小屋の中に向かって大声を掛けてきた。
「やっと見つけたぞ、魔女野郎! さっさと出て来やがれ! 」
頼純とシュザンヌは顔を見合わせたが、山賊達に返事を返さなかった。どう対応すればよいか、まだ判断がつかなかったからである。
するとまた、山賊の頭目(とうもく)が怒鳴った。
「テメー‥ お宝をたくさん隠し持ってんだってなァ‥!? それをすべて俺達に渡せば、命だけは助けてやる! 判ったら、出てくるんだ‼ 」
驚いた頼純が再びシュザンヌを振り返った。だが、彼女は手をプルプルと振るばかり。
「ないです、ないです! 祖母の時代からそういう噂はありましたが、お宝なんてこれっぽっちもありませんよ 」
返答がない事に苛立(いらだ)った頭目(とうもく)が脅(おど)しをかけてきた。
「出てこねェんだったら、この小屋に火ィ掛けてやる! それでもいいのか!? 」
このままでは黒焦(くろこ)げになってしまうと思った頼純が、シュザンヌに申し出た。
「とりあえず‥ 俺が表に出ていって、話を付けてくるよ! でェ‥ それがダメだった時には、また何か考えましょうや 」
「そんな‥ 行き当たりばったりで―――怪我(けが)をするだけですから、無視しましょう! 」
「大丈夫だって、俺は簡単な事じゃやられネーから! アンタだって、アンデーヌの森で俺の腕前は見たでしょう 」
「そ‥ それは、そうですけど‥‥ 」
だが、自信満々の頼純をエルキュールが鼻で笑った。
「テュロルドよ‥ お前がやられないじゃと!? 笑わせるな。 お前なんぞ、表に出ていけば、またたく間に山賊どもに斬り刻まれてしまうじゃろう! 」
頼純はその言葉を笑い飛ばした。
「ハハハハハ‥ やだなァ、じいさんまで‥ アンタだって、さっきこの俺が山賊を退治したトコは見てただろう!? それとも、忘れちゃったのかい? また、ボケた? 」
「ナニをぬかすか! お前は、敵の手足は斬り落とせても、その命まで奪う事はできんのじゃろうが! 」
頼純の顔が強張(こわば)った。
「だ‥ だから‥ それは、人は殺さない方が兵法上――― 」
「ウソをつくでない。 誤魔化(ごまか)すな! テュロルドよ、お前は人を殺さないんじゃない―――殺せないのじゃ! 」
「―――! 」
エルキュールは炯々(けいけい)とした目で頼純を睨(にら)み据(す)えた。
「ワシの目は節穴ではないぞ! 」
「な‥ なんで、その事を―――?」
誰も知らないはずの真実を言い当てられてしまい、頼純は言葉を失ってしまった。