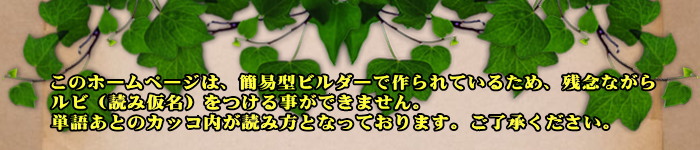
25
1026年 ファレーズ街道
ドラゴンが住むという『アンデーヌの森』は、ファレーズから2日ほど歩いたところから始まる。
『アンデーヌの森』は、大きな森というよりも樹海(じゅかい)といった方が適切であろう。行けども行けども、巨大な森林地帯が続くのだ。
外縁部(がいえんぶ)の木々をきこりが切る程度で、その奥に何があるのか―――誰も知らなかった。土地の者でさえその全容を把握できていないのである。
森の中は3、4マイル(4.5キロ~6キロ)も進むと、あとは獣道(けものみち)ていどしかない。
進むべき方向を示す道標(みちしるべ)も地図もないのだ。
ましてや、その森のどのあたりにドラゴンが住んでいるのか、知る者などいなかった。
ドラゴンが人を食うところを見た者は何人もいたという。だが、その中で、『アンデーヌの森』から脱出できた者はたった三人しかいなかった。
一人は老女、一人は四歳の男児、もう一人は、気のふれた若い女だった。そして、どこでドラゴンに襲われたのかを聞いても、三人ともはっきりとは答えられなかった。すべての証言がアテにならないのだ。
もし、仮にドラゴンがいたとして、それが森の中央に住んでいるとすれば、そこまでたどり着くのに一週間以上かかる可能性もあった。
しかも、間もなく寒い冬が始まるのだ。
日が落ちるのは速く、朝夕の気温の低下は著(いちじる)しい。さらに森に住む肉食獣たちは冬支度(じたく)のため食欲旺盛(おうせい)である。
夏の森よりも、危険度はずっと高くなるのである。
ロベールから三十人の兵士にいたるまで、全員が不安を抱えての行軍であった。
その中には、モン・サン・ミッシェルへと向かうサミーラやイタリア人傭兵のアンドレア、ジョヴァンニ、フィリッポ、ジャコモ達も一緒だった。
彼らとは途中の街道で別れる予定だったが、頼純と別れることが不安なようである。ロレンツォが不在の今、頼れるのは頼純しかいないからであった。
ただひとり陽気なのは、ジョルジュ伯だけである。
「いや~~~あ‥ 今日はいいお天気じゃん! 最高のドラゴン退治日和(びより)だぜェ! なあ、なあ‥ おい、なあ!? 」
何でこんな危険な旅に、供も連れずについてくるのか?―――と、みなは訝(いぶか)しがったが、彼は完全に物見遊山(ゆさん)の様子である。
ファレーズの街を出るとすぐに、街道の脇に女が立っていた。
エルレヴァである。
彼女の姿に気づいたロベールはすぐさま馬を下(お)り、エルレヴァの元へと駆け寄った。
「ゴ‥ ゴメン‥ 兄上から‥ ドラゴン退治を命令されちゃった‥ から‥‥ 」
彼女は冷静な表情で返した。
「ええ‥ 知っております 」
ロベールは部下達を気にしてか、小声で自分の不安を打ち明けた。だが、その顔は半泣きになっている。
「どうしよう? ボクにドラゴンなんて退治できないしィ‥ 森の中に入るのだって怖いよォ‥‥ 」
「何を弱気な事を! 」
叱咤(しった)するエルレヴァに、ロベールは力無く俯(うつむ)いた。
「だ‥ だってェ‥‥ 」
エルレヴァはロベールの両頬(ほお)に左右の手をギュッとあて、彼の顔を持ち上げた。そしてその目をジッと見詰めて、
「よいですか? このご命令で、兄上様があなたに何を求めていらっしゃるのか―――それをよくお考えください 」
「え!? 」
「それは、アナタを怖がらせるタメでも‥ あの中庭にいた兵士や領民達に、大公である自分の力を見せつけるタメでも‥ ましてや、本当にドラゴンを退治してもらうタメでもないハズです! 問題は、この旅でアナタが何を得(え)るのか、アナタがどう変わるかにかかっています 」
「何を得(え)て‥ どう変わるか‥? 」
ロベールはその言葉を噛(か)み締めるように復唱(ふくしょう)した。
「わかりましたか? 」
母親のような口ぶりでエルレヴァが確認すると、ロベールはコクリと頷(うなず)いた。
「うん‥ それが何かちゃんと考えてみ――― 」
言葉が終わらないうちに、エルレヴァは両手でロベールの顔をグイッと近づけ、口づけをした。
その情熱的なキスは、けっこうな時間続いた。
周囲の者達は、ただただポカーンとするばかりであった。
「エヘホンッ! 」
もういいでしょと言わんばかりに、頼純が咳(せき)払いをした。
ロベールから唇を離したエルレヴァは、再び彼に尋(たず)ねた。
「―――元気、出た‥? 」
ロベールはちょっと恥ずかしそうに頷(うなず)く。
「‥‥うん‥ すごく‥! 勇気百倍です! 」
先ほどまでの氷の女王のような表情を一変させ、女神のように優しくほほ笑むエルレヴァ。
「そう‥ よかった♡ 」
一同は、二人の熱烈なやり取りがちょっとうらやましいと思いながらも、伯爵は完全に尻に敷かれている―――そう確信した。
出発した彼らは、ほどなくしてモン・サン・ミッシェルと『アンデーヌの森』との分かれ道についた。
頼純はアンドレアにあとのことを託(たく)し、他の部下達にも一人一人挨拶(あいさつ)をした。
そして最後に、サミーラと向き合った。
「ご武運をお祈り申し上げます 」
「ああ‥ どうせ、ドラゴンなんていやしネーんだから、チャッチャッとかたづけて帰ってくるよ 」
そう言った後に、二人は目と目が合った。見詰め合ってしまったのだ。
「あ‥ 」
途端に、先ほどのロベールとエルレヴァのキスを思い出し、二人は顔を真っ赤にして視線を落とした。
「あ‥ いや‥ えっとォ‥ だから‥ そのォ‥‥ 」
「は‥ はい‥ なんでしょう‥? 」
頼純もサミーラも、何も言葉が出なかった。二人はただモジモジとしているダケである。
「ったく! だらしネーなァ‥♡ 」
ジョルジュ伯がなれなれしく頼純の肩に腕を回してきた。
「キスしたいんだろう? だったら、やればいいじゃん。 人の目なんか関係ねェって! バッカじゃネーの! 」
「うるさいッ‼ 」
頼純は鬱陶(うっとう)しげにジョルジュの腕を振り払った。
「出発だ、出発! さっさといくぞ! 」
サミーラに背を向けると、スタスタと行ってしまう。
ジョルジュは残されたサミーラの顔を覗き込んだ。
「ヨリちゃん‥ 恥ずかしいんだってさ。 よっぽど、アンタの事が好きなんだろうねェ。 でも、俺が言うのもナンだけど―――ありゃ、バカだね♡ 」
サミーラは、恥ずかしそうに頷(うなず)いた。
「はい‥! 」
× × × × ×
重装備の上に荷物も多く、一行の速度はかなり遅かった。
その日は、オルヌ川を越えたあたりで野営した。
二日目は、朝から曇(くも)りで風が強かった。
雨にならねばよいが―――と誰もがそう念じながら、『アンデーヌの森』への行軍が再開された。
兵達の士気は今ひとつだったが、指揮官であるロベールはあのキスでかなり元気になっていた。不安は残るものの、恐怖からは解放されたようだった。
「そういえば‥ 前から聞きたかったんだけど――― 」
本日は、徒歩で風景などを楽しんでいたジョルジュ伯が、ふいに頼純に質問をしてきた。
「ナンで、アンタって盾を使わネーの‥? ナンで? 」
「は? 」
「だ・か・らァ‥ 俺達の太刀(たち)筋ぐらいすべて躱(かわ)せると思ってんでしょ!? それでアンタは、盾なんかいらないって思ってる。 違うか? 」
先頭のロベールにもその声が届いたのか、彼は馬を引き返して二人の傍(かたわ)らについた。
「それ‥ ワタシもそのコト、気になっておりました。 ぜひ、お聞かせください 」
頼純はちょっと考えてから、それに答えた。
「いやァ‥ 盾を使わねェのは俺だけじゃないんだよネ‥ 日本の武士は、ほとんどが盾を使わない。 そういう習慣がネーんだな 」
「え!? マジで! 」
頼純の意外な答えに二人は驚いた。
「日本でも、合戦(いくさ)と言えば騎馬戦だ! ただ、日本人は守る事より、攻める事に重きをおくんだ。 だから、馬に乗って速く走り‥ 一気に攻め込んだら、太刀(たち)を振りやすくするタメ、邪魔な盾は使わない 」
「‥‥‥ 」
「また、太刀(たち)もそれにあわせて作られたってェ話だ。 片手で手綱(たづな)をしっかり操(あやつ)り‥ もう一方で太刀(たち)を自在に振れるように、軽く作られたんだって! 」
「騎馬にあわせて、剣(つるぎ)を作った―――? 」
「ホントかよォ!? 俺達なんか、左手で盾と手綱(たづな)‥ 両方握っちゃうよ 」
頼純はさらに語った。
「そして、軽く作った太刀(たち)に、さらに反(そ)りをいれる事で斬撃力(ざんげきりょく)を増し‥ 不安定な馬上でも、斬る、突く、受けるの三拍子を備えた武器となるよう、何度も何度も改良を重ねていったんだそうだ! 」
「へ~~~えェ‥ 」
「そのお陰もあってか‥ 太刀(たち)てーのは両手で握って振ると、もっとよく斬れる。 その切れ味は、この間の対決でもよく判っただろう。 鎖帷子(オベール)ていどならワケもねェ! 」
頼純はいったん腰の『小烏丸(こがらすまる)』に目を落とすと、その柄(え)を拳(こぶし)で軽くとんとんと叩いた。まるで、愛(め)でるかのような目つきである。
「まぁ、コイツは‥ ことさらに斬れるんだがね♡ 」
「しかし、無防備では――― 」
「相手の刃(やいば)は、太刀(たち)の刀身(とうしん)やこの鍔(つば)で受ける! さらに、鎧(よろい)にも盾の機能は充分にあるしな‥ だから、弓矢戦の時以外は、盾は使わネーのさ! 」
ジョルジュは頼純を指差すと、疑いの目で否定した。
「いやいや‥ そりゃウソだね! だってアンタは、エノーの剣やアンドレの斧を自分の剣じゃ受けずに、すべて体(たい)さばきだけで躱(かわ)してたじゃん 」
「ええ‥ あれは凄かった。 とても人間業(にんげんわざ)とは思えませんでしたよ。 まさに大天使ミッシェル様の動きです! 」
大天使ミッシェルの戦いぶりを見た事のある人間などいないハズなのだが‥‥
頼純は苦笑いした。
「それはね‥ いくら刀身(とうしん)で受けるっていっても、アンタらが使う剣は分厚くて重いからさ‥ そんな刃をまともに喰(く)らっちまうと、さすがにコッチの太刀(たち)も刃こぼれを起こす可能性がある。 小さい刃こぼれ程度なら、鍛冶屋(かじや)で研(と)げばいいけど‥ 大きく刃こぼれ起こしちまったり―――ましてや刀身(とうしん)が折れようモンなら、もう最悪だ! コッチの国じゃ修復できない 」
「‥‥ 」
「だから、よほどの場合でない限り‥ なるべく相手の斬撃(ざんげき)は受けずに、躱(かわ)すようにしてるのさ 」
「ふゥ~~~ん‥ なるほどねェ! 」
× × × × ×
よく斬れる刀の刀身(とうしん)は硬くできている。それを薄く鋭角に研(と)ぐ事で切れ味をよくするのだ。
だが、硬い刀身(とうしん)はどうしても折れやすく、薄い刃は刃こぼれを起こしやすい。
ただし、頼純の持つ太刀(たち)『小烏丸(こがらすまる)』は平安の世に作られたため、良質の鋼(はがね)をもちいた、古式鍛造(たんぞう)の丸鍛(まるぎた)えであった。
刃は厚く、刀身(とうしん)には粘りがある。曲る事はあっても、簡単に折れたりはしないはずであった。
そして、頼純の神業(かみわざ)のような―――まさに大天使ミッシェル様のような剣技(けんぎ)があってこそ、『小烏丸(こがらすまる)』は刃こぼれを起こすこともなく、よく斬れたのである。
× × × × ×
そうこうしている内に、ロベール一行は『アンデーヌの森』の入り口にまでたどり着いた。
森の入り口手前にはひらけた原っぱがあり、近くには小川も流れている。
陽(ひ)はまだ高かったが、一行は野営の準備に取りかかった。
その日は、温かい食事をたらふく食べて、天幕(テント)の中でたっぷりと寝るのだ。
近くの村で雇ったきこり(ティエボア)のアランの進言であった。
巨大な樹海に入ると、道はすぐになくなり、あとは獣道(けものみち)ていどの隘路(あいろ)を進まなければならない。
それは、巨木と巨木の隙間(すきま)を抜けていくようなモノだった。
地面は起伏が激しく、岩や木の根でゴツゴツとし、あるいは苔(こけ)でツルツルと滑(すべ)る。
倒木(とうぼく)を乗り越え、水たまりの中を進むのだ。
突如、数ピエ(1~2メートル)ある崖に突き当たり、そこをよじ登らなければならない事もあれば、谷をくだらなければならない事もあろう。
とんでもなく歩きにくい場所なのだ。
馬車で荷を運ぶ事など到底(とうてい)できない。
だから、水と食料は貴重品となる。自分達で運べる量しか持って行けないからである。
水ならば、近くの川で汲(く)めばいい―――というワケにもいかなかった。
正確な地図がない時代、森のどこに川や泉があるのか、ハッキリとは判らなかったからである。
行き当たりばったりで水を汲(く)みに行こうものなら、迷子になる可能性が高かった。
そして、深い森で迷子になった者には、たいていの場合、『死』が待っていた。
食事も、これからは固くなったパンを囓(かじ)り、干し肉の塩スープをすするていどで我慢しなければならない。
さらには、森の中は開(ひら)けた場所もほとんどないので、天幕(テント)は張れない。
木の根や岩を枕に、冷たい地面で寝なければならないのだ。
雨が降(ふ)れば、ずぶ濡れになって、凍えながら眠る事になる。
そのような生活がこれから一週間以上続く。温かい食事とやわらかな寝床とは、しばしのお別れなのである。
それゆえ、今夜は少し豪勢(ごうせい)に最後の夕餉(ゆうげ)をふるまった。
三匹の豚をシメて、丸焼きにした。鍋で焼いたほかほかのパンと、野菜がたっぷり入った熱いポタージュもあった。
だが、兵士達はその食事を無言で喉に押し込んでいった。
彼らにとって、いるかいないか判らないドラゴンよりも、不気味な森の奥深くへ入っていく事の方がよほど恐怖なのだ。
その恐怖が、みなを無口にしていた。
「皆様‥ おばんです 」
食事も一通り終わり、太陽が山の端(は)に少し掛かり始めた頃、近くに停(と)められた荷馬車から声を掛けてくる者がいる。
近在の農夫のようであった。荷馬車には六個の樽(たる)が載(の)せられている。
馬車を引いていた農夫はその手綱(たづな)を荷台に預け、近づいてきた。
「どんもどんも‥ ロベール伯爵様御一行でごぜェますだか? 」
ロベールは怪訝(けげん)な顔で答えた。
「ああ‥ そうだが‥! そなたは何者じゃ? 」
四十はとうに過ぎたであろうその農夫は、安堵(あんど)した顔で話し掛けてくる。
「こん近くの、ファヴロル村の者でごぜェますだ。 こん度(たび)は、伯爵様御一行がドラゴンの退治ばァしてくださるっちゅう事で‥‥ 我が村の村長もいっぺェ感激して、皆様になんぞ贈り物ばしてェと――― 」
「これはこれは、ご丁寧に‥ 」
「どんぞ、我が村の特産であるリンゴ酒をお受け取りくだせェ 」
× × × × ×
ロベール達が野営する様子を近くの物陰から窺(うかが)う人物がいた。
―――トマである。
彼は不気味な微笑(えみ)を浮かべて、ロベールを凝視(ぎょうし)していた。