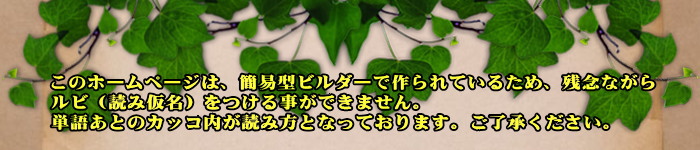
44
1026年 ファレーズ郊外・トレノ村
頼純とサミーラ、ゴルティエと『カラス団(コルブー)』達は馬を飛ばし、領地の最西端―――『トレノ村』へと向かっていた。
『カラス団(コルブー)』の不良達は半分以上の者が馬に乗れなかったため、彼らは2日分の食料とともに二台の馬車に分乗していた。
その馬と馬車はロベール伯から借りたモノであった。
少年達をさらった犯人が、トレノ村の『ひなげし食堂』の主人と妻ではないか―――と判明するや、頼純はすぐに城のロベールへ報告に行った。そして、これらの食料と乗り物を借りたのである。
ロベール伯は報告を聞くと、『トレノ村へ兵を送ろう』と言ってくれたのだが、頼純は『一刻を争うので、まずは我々が先に行きましょう。 ファレーズの兵達は急いで出撃の準備を調(ととの)え、遅くとも明日の朝までには出発させてください』と頼み込んだ。
頼純の頼み方は一見ロベールを急(せ)かせているようだが、本心はそうではなかった。
兵達が『ひなげし食堂』に到着するのは昼頃になる。それまでに、『カラス団(コルブー)』達で犯人を捕まえ、子供達を救出するつもりだった。
頼純は、どうしても『カラス団(コルブー)』達に手柄(てがら)を立てさせてやりたかったのである。
一同は風を切って進んでいた。
遠くの村から九時課(くじか)の鐘が聞こえてくる。正午と日没の中間だ。この分なら、日が沈むまでには『トレノ村』に到着できそうだった。
しかし、頼純にとって馬上は寒さがいっそう身にしみた。
サミーラからもらった襟巻(えりま)きがずいぶんと寒さを防(ふせ)いでくれたが、やはり風は冷たかった。
× × × × ×
生まれ故郷である日本の対馬や中国・宋の東京(トンキン)開封府(かいふうふ)にいた頃は、冬でも同じような格好をしていたが、さほど寒いと思う事はなかった。
頼純はその後、西域・敦煌(とんこう)へと向かい、それ以降ほぼ砂漠地帯を移動してきた。
寒暖(かんだん)差の激しい気候であるゆえに、日中は常に灼熱(しゃくねつ)であった。そして気温が低下する夜になっても、彼はあまり寒いとは感じなかったのだ。
さらに、高温のインド洋から海上路でイスラムの国々を回り、地中海に入ってもまだ温暖な気候は続いていた。
『冬はやっぱり寒い』と感じたのは、ヴェネチアに着いた頃からである。
対馬や開封府よりもずっと北に移動した事もあったが、なによりも彼自身が寒さに対する耐性を失っていたのだ。
そもそも、直垂(ひたたれ)と袴(はかま)は風通しがよすぎる。袖口(そでぐち)も、裾(すそ)も大きく口を開けている。その下は、単衣(ひとえ)(下着)にふんどしである。寒いのも当然であろう。
直垂(ひたたれ)には『袖括(そでくく)りの紐(ひも)』、袴(はかま)には『裾括(すそくく)りの紐(ひも)』というものが付いていて、それを絞(しぼ)るといくぶん冷気の出入りを押さえる事ができた。
しかしそれは、動きやすくするためのものであって、防寒として大きな働きをするものではない。
最近になってやっとヨーロッパの寒さにもなじんできたものの、最初の冬などは、高熱を出す風邪を三度も引いてしまうほどだった。
それでも、現在、頼純が着ている直垂(ひたたれ)と袴(はかま)は、ルーアンからファレーズに戻った直後に新品になっていたため、以前の穴だらけの着物に比べたら、寒さはぜんぜん違っていた。
これは、サミーラが作ってくれたモノだった。
頼純は日本の着物にこだわり、ヨーロッパに入っても、けっしてチュニックやブレーを着ようとはしなかった。その方がずっと温かく、入手も簡単で、目立たないにもかかわらずである。
それは、着物が頼純自身の自己証明(アイデンティティ)であるからだった。
彼が日本を離れてすでに20年近くが経(た)っていた。日本語を話す事はまったくなく、米を食べたのもインド以来である。
そうした生活は、自分が何者であるかをドンドンと見失わせていくのだ。
そんな彼にとって、己(おのれ)が『日本人・藤原頼純』であるという事を確認する上で、もっとも重要な存在が太刀と着物であった。
袴の腰紐(ひも)をギュッと締め、太刀を腰に吊(つる)すと、自分が何者であるのかを思い出させてくれる。
日本民族の誇りさえ感じさせてくれるのであった。
その直垂(ひたたれ)と袴(はかま)は、サミーラの二作目となる仕立てだった。
宋時代に、繕(つくろ)いながらも散々着たおした直垂(ひたたれ)と袴(はかま)は、さらに砂漠を彷徨(さまよ)った際にボロボロとなってしまった。それをサミーラが、ヤルカンドの宿屋で丁寧に繕(つくろ)ってくれたのだ。
だが、いくらあちこちに当て布をしても、元来の生地が擦(す)り切れてしまっていた。
だから、インドのカリンガナガラに到着した時には、着物は再びボロボロになっていたのだ。
そこで、サミーラはインドの木綿布(もめんふ)を使って、新しく直垂(ひたたれ)と袴(はかま)を作り直してくれた。
彼女はヤルカンドの宿で、頼純の着物にある無数の綻(ほころ)びを縫(ぬ)い合わせるため、その構造を完全に理解しなければならなかった。
お陰でインドでも、以前の直垂(ひたたれ)とほぼ同形のモノを作る事ができたのだ。ただ、生地が少々違っていたので、最初はゴワゴワとした着心地だった。
その後、インド洋で海賊と戦い、ヴェネチアに着いてからも、ファレーズに至るまでに何度も山賊に襲われ、彼らを退治している。
しかし、決定的に着物をボロボロにしたのは、ファレーズに着いて以降の事であった。
モン・サン・ミッシェルで捕まり、ファレーズへ強制送還されて以降、巨人兵士と戦い、深い森の中を迷走したあと、巨大ワニと戦ったのだ。
直垂(ひたたれ)と袴(はかま)は染めたのかと思うほどに汚れ、あちこちが破れ、綻(ほころ)びていた。
ルーアンに凱旋(がいせん)する際には、あまりにもみっともないので、頼純が自分でそれを洗濯し、綻(ほころ)びや破れを縫(つくろ)ってはいた。しかしながら、着物はやはりかなりくたびれており、男の針仕事は雑であった。
一方、モン・サン・ミッシェルにいたサミーラは、頼純の無事を祈りながら、無為(むい)に流れる時を使い、新しい直垂(ひたたれ)と袴(はかま)を縫(ぬ)っていてくれたのである。
彼女は、頼純が日本から着ていた着物もいまだ捨てずに取っていてくれたようで、それを参考に亜麻布(リンネル)で寸分違(たが)わぬモノを作ってくれたのだ。
それは、大変着心地がよく、頼純の気分を爽快(そうかい)にしてくれた。
一方、頼純もこの数週間、退屈なファレーズ城の生活の中で、麦藁(わら)を使って草鞋(わらじ)を編(あ)んでいた。
皮を縫(ぬ)い合わせただけのヨーロッパの靴は、太刀を振るう時に足が踏ん張れなくなるので、頼純には履(は)き慣れた草鞋(わらじ)の方がよかったのである。
彼は幼い頃に、育ての親である家臣から草鞋(わらじ)の編み方を習ってはいた。しかし、自分でそれを作れるようになったのは、中国・宋で捕まり、苦役(くえき)をさせられていた頃である。
当時は履(は)き物など与えられぬ立場であったが、さすがに真冬の大地に裸足はツラかった。そこで、役人から不要な藁(わら)をわけてもらい、必死に作り方を思い出して編(あ)んだのである。
自由の身になると、開封(かいふう)の街の商店にはいくらでも草鞋(わらじ)は売っていたが、頼純はその習慣を続けた。
そのお陰で、タクラマカン砂漠でロレンツォに助けられた時には裸足であった頼純も、カラコルム山脈に進入する頃には、十足以上の草鞋(わらじ)を持っていたのだ。
米を主食とするアジアでは、脱穀(だっこく)をすませたあとの稲藁(わら)が大量に余る。そこで、その藁(わら)を使って、縄や草鞋(わらじ)、笠(かさ)や蓑(みの)、筵(むしろ)など、様々な生活用品を作るのだ。
一方、ヨーロッパでは麦藁(わら)はほとんど余らない。むしろ貴重品なのである。
麦の収穫倍率が米に比べて極端に悪い事もあったが、麦藁(わら)の大半は馬や牛、豚などの冬場の貴重な餌となるからであった。
それゆえに、頼純は金を払って麦藁(わら)を買っていた。それでも、草鞋(わらじ)を作った方が靴を買うよりずっと安いのだ。そして、履(は)き心地(ごこち)もいい。
頼純は、着物を着て、太刀を腰に吊り、草鞋(わらじ)の紐(ひも)を結ぶと、全身に力が漲(みなぎ)ってくるのだった。
× × × × ×
『トレノ村』はカーンへ向かう街道の裏道に面していた。この裏街道は人通りも少ない。
頼純達が夕方に『トレノ村』へ着くと、村はすでに静まり返っていた。
元々、数世帯しかない小さな小さな寒村である。
頼純は『ひなげし食堂』の場所を聞くため、その一軒を訪ねてみた。
扉が細目に開かれると、中からやつれた女が覗(のぞ)き込んできた。
「な‥ なんだね? 」
「この村に『ひなげし食堂』があると聞いてきたのだが‥ それはどこなのでしょう? 」
女は一瞬ギョッとした顔になったが、
「『ひなげし食堂』なら‥ あの道を2、3マイル(3~5キロメートル)ほど森の中に入ったところにあるさ‥ 」
と、村の外れから続く道を指差した。それは何かに脅えているような表情だった。
「じゃあ、このまままっすぐに行けば――― 」
頼純の次なる問いに答えず、扉はバタンと閉まってしまった。
森の入り口まで辿(たど)り着くと、頼純は一同に命じた。
「全員、馬から下りろ。 手綱を木に縛り付けるんだ。 ココからは隠密行動を取る。 この先、私語は一切無用! 絶対にムダ口は叩くな。いいな! 」
「は‥ はい‼ 」
『カラス団(コルブー)』の面々は、頼純の指示に従い、静かに森の中を進んで行ったのだった。
日が沈みかける中、森の中はかなり暗い。
頼純は『また、森か‥ 』とうんざりしたが、それも仕方のない事だった。
フランス王国は、隣国ローマ帝国(神聖ローマ帝国=現ドイツなど)ほどではなかったが、まだまだ森林に充ち満ちていたからである。
それでも、平地の多いフランスは開墾(かいこん)されている方なのだ。
しばらく林道を歩くと、その建物は見えてきた。
木々に囲まれた『ひなげし食堂』は、暗闇の中にひっそりと佇(たたず)んでいる。
どこからか水の流れる音が聞こえてくる。どうやら建物の裏手に川があるようだった。
× × × × ×
この時代、宿屋は少なかった。本格的な宿泊施設となると14世紀まで待たなければならない。
なぜなら、交通機関がまったくない時代、軽い気持ちで物見遊山(ものみゆさん)の旅をする者などほとんどいなかったからである。
さらにどの家でも、難渋(なんじゅう)する旅人を三日間は泊めてやるという暗黙(あんもく)のルールがあった。とくに巡礼者などは温かく迎えられ、ちょっと怪しげな『さすらい人』であってもその軒先(のきさき)を借りるぐらいはできたのだ。
貴族や金持ち達は、その土地の領主や富豪の屋敷に泊めさせてもらう。教会や修道院でも旅人を庇護(ひご)した。
そのため、本格的な宿泊施設はあまり必要とされなかったのである。
ただ、大量の人々が集まる場所―――巡礼地や聖地、大きな市(いち)がたつ都市などでは、彼らを修道院や町の民家だけでは収容しきれない。そのため、数軒の宿屋が建てられていた。
また、ブドウ栽培の農家などでは、仕事のない冬場は兼業として宿屋をやる場合もあった。
彼らの客は、巡礼者、商人、そして移動する軍隊の騎士達である。
頼純達がモン・サン・ミッシェルで泊まった宿屋も、そんな数少ない宿泊施設のひとつであった。
× × × × ×
この『ひなげし食堂』はそういった宿屋ではなく、その名の通り食堂なのだろう。ただ、かなり大きな食堂であった。通りかかった者が宿屋と勘違いしてもおかしくはない。
頼純と『カラス団(コルブー)』達は林の中に身を隠し、食堂の様子をしばらく窺(うかが)った。
防寒のため、すべての鎧戸(よろいど)は閉じられていたが、その隙間から微(かす)かな明かりがもれている。
やがて、数人の男達の笑い声も聞こえてきた。
頼純は『カラス団(コルブー)』を二人一組にして、食堂の周囲に散開させていった。
不良少年達は、頼純から教えてもらった、手信号で連絡を取り合いながら、宿屋の回りの藪(やぶ)の中にひそんでいく。黒い服装をした彼らは、闇の中に溶け込んでいった。
しかし、真っ暗になってしまうと、もはや手信号さえも見えなくなる。弱々しい上弦(じょうげん)の月明かりだけが頼りなのである。
「ともかく‥ 中の様子を確認しねェと、どうしようもネーな‥ 」
頼純は隣に控えていたゴルティエとサミーラの肩を叩いた。
「俺とゴルティエの二人で中の様子を確認に行く。 サミーラはこの場に留(とど)まれ。 絶対に動くなよ! 」
小声で二人にそう伝えた。
そして、頼純とゴルティエは腰を落として、食堂の壁まで走ったのだった。
食堂の裏へ回ってみると、大きなヤナギの木が数本植わっており、その先は高さ10ピエ(約3メートル)ほどの崖(がけ)になっていた。そして予想通り、その崖の下には川が流れている。
川幅はそれなりに広く、おそらくはオルヌ川であろう。
そこには船着き場まで作ってあった。
ノルマンディーの中央にあたり、大きな街道からもはずれたこの地だが、船を使えばカーンからすぐである。水上路ならば、ルーアンやパリなどの大都市からでも、陸路よりずっと早く着く事が出来る。悪くない立地であった。
二人は船着き場へと続く階段を音を立てずに下りていった。
船着き場は十分な長さと幅があった。これなら大型船(ロングシップ)を使い、多くの人や荷物を運ぶ事ができる。
船着き場の奥の崖側には頑丈な木の扉がつけられていた。おそらくは荷物の搬入のため、地下道で『ひなげし食堂』とつながっているのだろう。
「あそこから中に入れるかもしれないな‥ 」
扉に近づくと、奇妙な事に閂(かんぬき)が外側につけてあった。
ゴルティエが訝(いぶか)しげに囁(ささや)く。
「これでは、侵入者に入ってくださいと言っているようなものです 」
「いや‥ 中にいる者を外に逃がさネーようにしているのかもしんねェぞ‥! 」
「え!? つ‥ つまり、『牢』って事ですか? 」
「ああ‥ ここに子供達が捕まっている可能性がさらに高まった‥! 」
頼純は静かに閂(かんぬき)をはずすと、鉄の環でできた取っ手をゆっくりと引いた。
微(かす)かな軋(きし)み音とともに、重い扉がゆっくりと開かれる。中は真っ暗だった。音から察するに、中は洞窟(どうくつ)か廊下なのか、ともかくかなり奥まで続いているようだ。
頼純は嫌な予感がした。
「暗いな。 だからといって、松明(たいまつ)を灯(とも)すわけにもいかねェし‥ こりゃ、危険すぎる 」
「いったん、戻りましょうか‥? 」
「ああ‥ そうしよう。 まずは、建物の周囲をすべて調べてからだ 」
とその時、空間の奥から子供の叫び声がこだまとなって聞こえてきた。
二人は目を合わせた。
「クッソ! 中に入らねェワケにはいかなそうだな‥! 」
「はい‥ 」
忌々(いまいま)しげにつぶやく頼純に、ゴルティエは意外にも脅えた表情を返した。
「仲間を呼ぶか? 」
頼純の問いに、ゴルティエはしばし考え込んだが、
「いえ‥ まずは、確認しましょう 」
二人は頷(うなず)くと、忍び足で暗闇の中へと入っていった。
扉は閉まらないように開け放っていたのだが、二人が5ウナ(約6メートル)ほど中に進入したところで、急にバタンと閉まってしまった。
慌てて入り口まで戻った二人は、必死に開けようとしたが、扉はウンともスンとも動かない。
「ダメです! 」
「もはや俺達には、前進するしか道は残されてネーようだ! 」
わずかな月明かりさえも奪われ、完全な暗闇となってしまった。目の前に手をかざしても、見えないほどの暗黒である。
頼純は側面の壁に手を当て、それに沿って慎重に進んでいった。
闇は二人の恐怖を増幅させていく。
小さな歩幅であったが、50歩ほど進んだ時、突如側面の壁がなくなった。
広い空間に出たようだ。
その時、再び子供の叫び声がした。
「ま‥ まただ 」
「な‥ なんでしょう‥? 」
二人は小声で確認し合いながら、叫び声がした方へゆっくりと進んでいく。
「た‥ たしか、コッチだ‥! 」
「いま‥ ヨリさんのブレー(ズボン)の腰紐(ひも)をつかんでいます 」
二人はすり足でさらに数歩進んだ。
「!! 」
頼純の背後に人の気配がした。それはゴルティエではない。
頼純が身構えようとした瞬間、彼の後頭部に激痛が走った。
「ガッ! 」
何か丸太のようなモノで強打されたようだ。相手がどこにいるのかさえ判らない。
薄れゆく意識の中で、頼純はゴルティエの頭が砕ける音を聞いたような気がした。