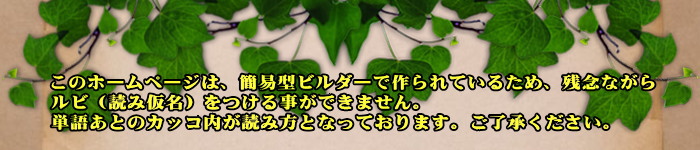
71
1017年 イングランド・ウィンチェスター
クヌートは不安で一杯だった。
イングランドの王となってすでに一ヶ月以上がたっていたが、彼はこれからどうしたらよいのかさっぱり判らないのだ。
父・スヴェン1世がイングランド王国との戦争をはじめたのは、クヌートが7歳の時であった。彼も15歳になると戦場へ連れて行かれる。そして、18歳で初陣(ういじん)を飾るや、それからの3年間、彼は冷静に、確実に、容赦(ようしゃ)なく人を殺し続けた。クヌートは戦士として非常に優秀な若者だったのだ。
父王(ふおう)や周囲の戦士達は、剣や盾の使い方、素手での格闘、人の殺し方、拷問(ごうもん)のやり方といった戦闘の方法から‥ 布陣(ふじん)の敷き方、兵站(へいたん)の確保、兵士の活用法、情報収集のやり方など―――戦争の方法にいたるまで‥ ありとあらゆる事を教えてくれた。
ただ、政治や統治については何も教えてくれなかったのだ。
齢(よわい)50を越え、いつ死んでもおかしくはないスヴェン王であったが、彼は自分が死ぬとはまったく考えていなかった。さらに、もし自分が死んだとしても、その跡(あと)は長男のハーラルに託(たく)すと決めていた。それゆえ、次男のクヌートには戦士として、将軍としての知識しか与えてこなかったのである。
クヌート自身も、戦場でどう生き残るか、仲間をどう勝利へ導くか‥‥ 日々、それしか考えてこなかった。
父王(ふおう)スヴェン1世が死んだ後はなおさらの事である。
デンマークに逃げ戻った彼は、軍を立て直し、ふたたびイングランドを攻略せねばならなかった。バイキングに敗北は許されないのだ。
クヌートは弱冠(じゃっかん)20歳で、数万人のデンマーク軍の総司令官として、彼らを率(ひき)いねばならない。そのためには、学ぶべき事が山のようにあった。
1015年9月、捲土重来(けんどちょうらい)を期してイングランドのサンドイッチに上陸してからは、昼間はほとんどが徒歩による進軍であり、突如イングランド兵と遭遇(そうぐう)しては、辺(あた)りが血の海になるような戦闘を繰り広げた。夜は各将と翌日の侵攻策についての軍議を行い、本日生き残った仲間達が神へ感謝する宴(うたげ)にも参加しなければならなかった。
休息は一切なく、戦闘による激しい精神の消耗(しょうもう)と、肉体の疲弊(ひへい)───クヌートの疲れは、もはやピークに達していた。彼には政治の勉強などやっているヒマはまったくなかったのだ。
ところが、ある日突然平和が訪(おとず)れ、彼はイングランドの統治者となった。
張り詰めていた緊張の糸が切れると、次に襲ってきたのは政治的判断の連続であった。
クヌートはかなり頭のよい方であったが、自分の下(くだ)した決断が正しいのか間違っているのかさえ判らなかった。
たとえば‥ デンマーク兵全員には、戦勝(せんしょう)の報酬(ほうしゅう)を与えなければならない。しかし、その原資(げんし)を捻出(ねんしゅつ)するために、イングランドの貴族や有力者の財産をすべて没収する方がよいのか、それとも国民に広く税を課す方がよいのか―――かなり難しい問題であった。
戦争であれば、どの戦場にどれだけの兵員を投入すればよいのかすぐに判ったし、間違える事もほぼない。また、たとえ間違えたとしても、さらなる兵員の移動、兵站(へいたん)の調達など次々と処理していく事ができる。
『戦争』には、『勝利』という明確な目的があるからだ。
ところが、『政治』にはそれがない―――様々な法律や、徴税(ちょうぜい)の方法、その再分配など‥‥下(くだ)した決断の正誤(せいご)がすぐに出ない場合が多く、5年10年と経って、それがよい政策であったか、失政(しっせい)であったかの結論が出されるのだ。
フランス王国やローマ帝国(神聖ローマ帝国=現ドイツ、オーストリア)では、すでに官僚組織に近い家政方(かせいかた)も存在していたが、『強盗集団(バイキング)』の延長として国家が成立したスカンジナビア諸国では、いまだ戦士が圧倒的な力を持っていた。
クヌートの周囲もほとんどが戦士・武将であり、政治には疎(うと)いものばかりであった。
それでも、王は家臣に判断の迷いを悟られてはならない。彼は内なる不安がばれないよう、冷徹な目で人々を睥睨(へいげい)し、尊大(そんだい)に振る舞ってきた。だが、精神と肉体の疲れは、すでに頂点に達しようとしていた。
そんな中、彼はゴドウィンという家臣を得たのだ。
彼には『度胸』があった。それは、戦士の『勇気』とはまた違うものである。彼は何をも恐れないのだ。己(おのれ)の死も他人の死も、虫けらのそれと同じくらいにしか思っていない。
さらに、ずば抜けて頭が良かった。
そして、欲がないのだ。報酬(ほうしゅう)や領地を求める事はほとんどなかった。むしろ、彼の方から財を供出(きょうしゅつ)するくらいなのだ。
彼は戦士でもなく、行政に精通(せいつう)しているわけでもなかったが、彼から提案される助言は常に的確だったのである。
そんな事もあって、イングランドの征服後、クヌートはゴドウィンをいつも傍(かたわ)らにおいていた。
そんなゴドウィンから、エマ前王妃主催(しゅさい)の祝宴(しゅくえん)に誘われたのである。
クヌートがウィンチェスター城に着いてみると、松明(たいまつ)が並ぶ中、エマが迎えに出ていた。
その姿を見た時、彼は息をする事も忘れてしまうほどであった。
この世にこれほど美しい人間が存在するのか―――彼は自分の目を疑うほどであった。
魔法にでも掛かったかのようにクヌート王はエマを見詰めていた。
「ささ‥ こちらへどうぞ 」
そう促(うなが)されて、はじめて我に返ったクヌート王は、見とれてしまった自分が恥ずかしくて、必要以上に憮然(ぶぜん)とした態度で歩き始めた。
食事中も、エマはあれこれと話し掛けてきたが、彼はそれにまともに答える事ができなかった。目を合わす事さえ緊張してしまうのだ。
クヌートの妻である『ノーサンプトンのエルギフ』とて、けっして醜女(しこめ)ではない。そばかすが多少あるものの愛嬌(あいきょう)のあるかわいい顔をしていた。政略結婚とはいえ、自分の子供を二人も産んでくれた女性である。クヌートは彼女を大切に思っていた。
1014年、父王(ふおう)スヴェン1世が亡くなり、王位を奪還(だっかん)したエセルレッド2世王からイングランドを追われた時も、クヌートは結婚したばかりのエルギフを見捨てる事なく、彼女をデンマークまで連れ帰っていた。
だが、エルギフに対する気持ちは家族愛であり、尊敬であり、優しさであった。
『ノルマンディーのエマ』はクヌートよりも10歳年上だったが、『ノーサンプトンのエルギフ』も彼より5歳年上だった。そして、エマの方がはるかに若く見えるのだ。
さらにエマは、気品と威厳(いげん)においてエルギフとは格段の差があった。
エマは大国ノルマンディー公国の公女として生まれ、13年間にわたってイングランド王国の王妃として君臨(くんりん)してきたのだ。小国の伯爵の娘であるエルギフではとても勝負にならなかった。
全身から醸(かも)し出されるその貫禄は、国王となったクヌートでさえも位負(くらいま)けしてしまうほどである。
ともすれば、萎縮(いしゅく)してしまいそうになる自分を誤魔化(ごまか)すかのように、クヌートはエマに仏頂面(ぶっちょうづら)で素っ気(そっけ)ない態度をとった。
だが、テーブルにつき酒宴(しゅえん)が始まると、酔いも手伝ってか、クヌートはますます彼女の美しさに魅了(みりょう)されていった。話しがうまく、話題も豊富である事もあったが、なによりも時折見せる流し目や軽く開かれた唇、そして動くたびに漂ってくる芳(かぐわ)しい香り―――それらがクヌートの心をかき乱すのだ。
食事が終わり、彼女に誘われるまま外へ出ると、その冷気でクヌートの昂(たか)ぶった気分も少しは落ち着いた。
だが、エマの懐(ふところ)から取り出された酒を飲むと、再びドキドキとし始めた。頭の中を閃光がいくつも走る。
クヌートは、それが恋であるに違いないと思い込んだ。
そして、二人は自然な流れで彼の寝室へと向かったのである。
くだらない事で大笑いしながら、千鳥足で寝室に入った二人は、はじめて向かい合った。部屋にはいい香りが立ちこめている。
クヌートとエマは見詰め合い、やがて沈黙した。
頭の中はフワフワとしているのに、心臓は早鐘(はやがね)を打つかのようで、クヌートの興奮は高まっていた。
彼女に触れたい、彼女を抱きしめたい、彼女の唇に吸い付きたい―――そんな考えばかりが頭の中をグルグルと回る。
ふいにエマから頭をなでられ、耳に吐息(といき)をかけられた瞬間、クヌートの全身に電流が走った。頭の中は、酔っ払った時のような、ぼんやりとした気分なのに、体中の感覚は研(と)ぎ澄(す)まされていくようだった。自制心は吹き飛び、クヌートはエマをベッドに押し倒していた。
彼女は抵抗するわけでもなく、みずから衣服を脱ぎ去り、彼の服を脱がせると、股間に手を伸ばしてきた。
次の瞬間、これまでに味わった事のない快感が、股間から脳髄(のうずい)へと走り抜けた。その快感はさらに増幅し続け、全身を駆(か)け巡(めぐ)る。頭の中はもう快楽の事しか考えられず、あらゆる雑念が全て消えていった。それはあらがい難(がた)い究極の快感だった。
そして、クヌートはエマにひたすら溺(おぼ)れていくのだ。
次の朝、クヌートが目を覚ますと、そこにはエマの瞳があった。彼女はクヌートを優しく見詰め、ささくれだった心を静めてくれた。
部屋には相変わらずよい香りが漂っている。その香りを吸い込むと、さらに気分が落ち着くのだ。
やがてクヌートは、彼女の前でなら、虚勢(きょせい)も見栄(みえ)もハッタリもまったく必要ない事に気づく。ただただ、ありのままの素直な自分でいればよいのだ。エマは彼の全てを包み込んでくれた。
それからの5日間、クヌートとエマは全裸のままベッドの上で過ごす事となる。食事もほとんどせず、水だけをがぶ飲みしながら、排泄さえ部屋の隅の壷で済ませ、ひたすら愛し合った。
6日目の朝、やっと我に返ったクヌートは、エマと結婚する決意をしていた。とても、彼女から―――その快感から離れられるとは思えなかったのである。
さらにもう一つ、彼女は元王妃である。政治や統治についても熟知(じゅくち)していた。当面の彼の業務に大いに役立つはずであった。
次男となるスヴェインを出産したばかりの『ノーサンプトンのエルギフ』と別れたクヌート国王は、教会の承認を得て1017年の2月、10歳年上の元王妃『ノルマンディーのエマ』と正式に結婚をした。
× × × × ×
ゴドウィンの思惑通り、エマとクヌートは結婚した。
やはり、媚薬(びやく)の効果と娼婦達に仕込まれた性技は絶大であったようだ。
ただ、なぜそのような事をしたのか、彼自身にもよく判らなかった。
何かの目的や計画があって行動しているわけではない。財産が欲しいわけでも、権力が欲しいわけでもなかった。行き当たりばったり、気の赴(おもむ)くままに動いているだけなのである。
ただ、少年時代から、彼が人を殺す目的は、金でも、殺人そのものでもなかった。ゴドウィンは人の運命を握る事が好きだったのである。
人々を生かす事も殺す事も思いのまま―――それは支配であり、神の存在に近づくような気がしていた。
特に、その人間の命の灯火(ともしび)が消える瞬間を観賞する事が、ゴドウィンは無類(むるい)に好きだったのである。彼らから金品を奪うのは副次的な事に過ぎない。
しかし、現在のようにある程度の『権力』を手に入れると、運命を握る人々の数も増えていく。一般人ならば、ゴドウィンが殺そうと思えば誰でも殺せた。
ゴドウィンがロンドンに出て来た時、酒場で彼を蔑(さげす)みながら金を放った金持ち達は、そのほとんどを『反逆罪』で捕縛(ほばく)し、処刑してやった。
だからといって、彼らを強く恨(うら)んでいたわけではない。ただ彼らは、ゴドウィンが『殺してもいい』と思えるだけの理由を持った者達だったのだ。
全財産を没収され、処刑台に立たされた元金持ち達は、涙を流しながらゴドウィンに命乞(いのちご)いをした。だがゴドウィンはその様子を見て、腹を抱えて笑うばかりであった。最高に楽しかった。
彼らから奪った財産はすべてクヌート王の国庫に入れられたので、文句を言う者は誰もいない。むしろ、戦費の回収に奔走(ほんそう)していた王家としては、賞賛(しょうさん)に値する処刑だったのだ。
やがて、イングランドの人々は、徐々にゴドウィンを恐れるようになっていった。
一方、ゴドウィンは運命を握る人々の数を増やすため、さらなる権力を握ってみるのも悪くないと考えはじめていた。
クヌートとエマを結びつけた理由も、権力の頂点にいた二人を彼が支配しようとしていたからかもしれない。
―――ゴドウィン、27歳の夏であった。