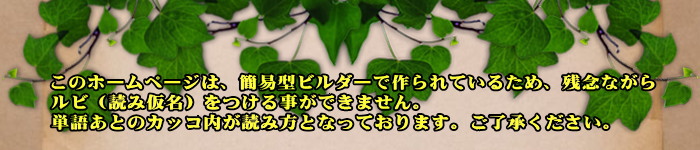
61
1026年 エレーヌの森(4)
「そんなに俺をブッ殺したいってんなら、好きにするがいいさ! ただし‥ それでオメーらがどうなっても、この俺は知らネーよ 」
薄笑いを浮かべてそう告げる頼純に、山賊達は訝(いぶか)しげに顔をしかめた。彼らは、たとえ相手が『勇者様』であろうとも、自分達の方が絶対に有利だと確信していた。にもかかわらず、頼純がいまだに余裕のある態度をとる理由が判らなかったのである。
「はあ‥ そりゃ、どういう意味だい? 」
山賊の頭目・ダミアンの問いに、頼純はしたり顔で地面を指差した。
「ホレッ‥ 足元を見てみろよ! 」
「え!? 」
どこから流れ出てきたのか、染(し)み出してきたのか、彼らが立つ地面は水でうっすらと覆(おお)われていた。
「あ‥ いつの間に!? 」
「お‥ おい。 あたり一面、水浸しだぞ! 」
やっと異変に気づいた山賊達が騒ぎ出す。そんな彼らに、頼純は状況を説明してやった。
「この水は、近くの川から引いてきた水だ―――ティーヴ川だよ。 その川の流れを完全に堰(せ)き止め、すべての水をこの砦(とりで)の中に流れ込ませてるんだそうだ。 だから、またたく間にここの水位は上がり、それはお前達の身長の三倍の高さにまで達するんだってさ! 」
「え!? 」
頼純はニコニコと楽しそうである。
「さっき聞こえなかったか? 俺がそこの扉から出て来た時、ガラガラと大きな音がしただろう!? あれは、お前達が入ってきたトンネルが崩れた音だ。 そして、ここにはあのトンネルしか出入り口はないんだよ。 そのたったひとつしかない出入り口が使えなくなったワケだ。 つまり、お前達はここから逃げられずに、全員が溺(おぼ)れ死ぬって事になるんだ♡ 」
頭目のダミアンは、引きつった顔ながらそれを否定する。
「そ‥ そんなバカな。 いくらなんでも、そんな事ができるはずネーだろう 」
しかし相手は、この森に百年以上住む『魔女のシュザンヌ』である。もしかしたら、そのような魔法が使えるのかもしれない。そう思うと、ダミアンは気が気でなかったのだ。
「俺の言ってる事が、ウソやはったりだと思うんなら調べてくりゃいい 」
頼純の言葉に、ダミアンは慌(あわ)てて手下を振り返り、大きな声を上げた。
「おい‥ 入り口を調べて来いッ! 」
「は‥ はい! 」
数名の者が、さらに水位の上がった中庭をビチャビチャと音を立てながら走っていった。
やがて彼らは、大声でダミアンに伝えた
「本当にトンネルが壊れています 」
「周囲の壁には、どこにも出口がありません! 」
この砦を作った古代ローマ人は、入り口隧道(トンネル)の上部に、それ全体を支えている楔石(キーストーン)をはずす仕掛けを施(ほどこ)していた。楔石(キーストーン)がはずれると、隧道(トンネル)は自重(じじゅう)で崩壊する。さらに、その上に積んであった大量の岩石までもが、降り注ぐようになっていた。しかも、外壁自体は崩れないため、栓(せん)がされたような状態になるのだ。
この砦(とりで)は、中心の庵(いおり)に向かってわずかに傾斜しているため、頼純やダミアン達の足元にまで水が届いたのはつい先ほどであった。
だが、後方にいた者達はかなり前から、自分達の足元が水浸しになっている事に気づいていたはずである。
トンネルの近くにいた者達は、それが崩れる大きな音も聞いていたに違いない。
だが、彼らは頼純の大胆な登場やダミアンとのやり取りに気を取られ、それらの事を言い出せなかったのである。
それがどれだけ重要な事か判断できず、ゆえに報告する事もなく、ただ漫然(まんぜん)と眺(なが)めていたのであった。
いつの世も、重要人物のそばにはそれなりに力ある者達が集(つど)うが、中心から離れれば離れるほどそれは有象無象(うぞうむぞう)の輩(やから)となっていく。もっとも今回の場合は、その中心にいるダミアン本人ですら充分に有象無象(うぞうむぞう)なのであろうが‥‥‥。
調べにいった手下の返事に、愕然(がくぜん)としていた頭目ダミアンがやっと声を発した。口の中が乾いているのか、かなりしわがれた声であった。
「け‥ けど‥ そんな事したら、アンタ達だって溺(おぼ)れるんじゃネーのか―――? 」
腕組みをした頼純がウンウンと頷(うなず)いた。
「そうなんだよ。 俺もそれを真っ先に尋(たず)ねたさ。 そしたら、さすが魔女だね‥ この小屋の中には、彼女専用の地下トンネルがあるんだって!」
「‥‥‥ 」
「ただし‥ 俺の仲間は怪我(けが)をしているから、そう簡単に移動はできない。 だから、この俺様がお前らとおしゃべりをして、シュザンヌや俺の仲間が逃げる時間を稼(かせ)いでたってワケさ♡ 」
ダミアンは大きく息を呑(の)む。
「じゃ‥ じゃあ‥ 俺達はお前に騙(だま)されてたってワケか? 」
「まあ、そういう事だな‥! ほれッ、壁の上を見てみろ。 脱出したシュザンヌが手を振っているぞ 」
「なに‥!? 」
ダミアンは、頼純が指差す方向を慌(あわ)てて振り返った。確かに、城壁の上には腰の曲がった老婆が、こちらに向かって手を振っている。
彼はあせった顔で頼純に命じた。
「だ‥ だったら、俺達もその地下トンネルで逃げてやる! そこをどきやがれ‼ 」
「そうはいかネーんだよ! んな事、この俺がさせるわけねェだろう。 俺だって、いまから小屋の中に戻って脱出するんだからな。 その間、追い掛けてくるお前らを何人かは斬るさ。 けど、それだけでいいんだ。 地下トンネルの中に入ったら、俺はそこにある操作棒(レバー)を引く。 すると、トンネルの分厚い扉が閉まり、外側からは二度と開けられなくなるんだとさ。 ホンット、すッげェ仕掛けだろう? 」
「ク‥ クソォ‥ 」
いくら人数がいても、庵(いおり)のような狭い場所に逃げ込まれてしまえば、簡単に頼純を殺す事はできなくなってしまう。その間に逃げられてしまう可能性が高かった。
山賊にとっては、かなり不利な状況となってきた。
それでも、ダミアンは精一杯の強がりを言おうとした。ここで弱気になってしまえば、味方は総崩れ―――大混乱が起きてしまうからだ。
「けど‥ 俺達の中にだって、泳げる者は何人もいるんだぞ! 俺もガキの頃はよく川で泳いだもんさ。 むしろ、泳ぎは得意なくらいだ 」
『俺も、俺も‥ 』と言わんばかりに、半分以上の山賊達が頷(うなず)いた。
「そうやって生き延びた者達は、仲間の復讐のためにも、全人生を賭けてお前らを狙ってやる! 必ず殺してやるからな‼ 」
ダミアンは悪魔のような微笑(えみ)を浮かべて、頼純を覗(のぞ)き込んだ。
「突然、どこからか矢が飛んできたり‥ 何気(なにげ)なく飲んだリンゴ酒(シードル)の中に毒が入っていたり‥ ベッドで寝ていたら首を掻(か)き切られたり‥ これからの一生、一時(ひととき)も安心して暮らせなくしてやる! 」
だが、頼純はさらに意地悪な笑顔を作って、頭目を覗(のぞ)き返した。
「へへへ‥ お前ら、燃える水って知ってるか? 」
「は‥ はい‥!? 」
「傷口を洗うための強烈に強い酒なんだが‥ これがとてつもなくよく燃えるそうだ! その燃える水―――強い酒と薬用の油がこの砦(とりで)のアチコチに貯蔵してあるんだって。 そして、それらを入れた樽(たる)は、水に浸(つ)かると一気に流れ出す仕掛けになっている! 」
「‥‥‥え‥ ええ‥? 」
「燃える水や油は、水よりも軽いから全部水面に漂(ただよ)うそうだ。 そこに火を着けてやれば、この砦(とりで)に満ちた水の表面はすべて燃え上がる。 泳いでようと、木にしがみついてようと‥ 溺(おぼ)れなかった者は全員、水面から上に出でいる部分がまっ黒焦(くろこ)げになるってェ寸法だ! 」
「そ‥ そんな‥ 」
「てな事いってる間に、水はもう膝(ひざ)まで上がってきてるぞ 」
山賊達のほとんどが頼純の話を信じたようで、急に右往左往しはじめた。一方、信じていない者は、頼純の説明を理解できない愚かな者達であった。そういう者は意味がわからなくても、他人の話に迎合(げいごう)する。つまり、全員がパニックを起こしたワケである。
「た‥ 助けてくれ‥! 」
「まだ、死ぬのはやだよ! 」
「逃げるんだ! 早く、早く! 」
「逃げるって、どこに逃げるんだ? 逃げ場所なんてネーぞ!」
山賊の中にはつかみ合いの喧嘩を始める者までいた。何がしたいのかさっぱり判らないが、慌(あわ)てている時は往々(おうおう)にしてそういうものであろう。
賢い者は、当面の恐怖である水没に備えるため、剣や斧、鎖帷子(くさりかたびら)などを捨てていた。それを見るや、愚か者達もすぐにマネをし始めた。そして、山賊のほとんどは愚か者ばかりなのである。
彼らは何の命令もなしに、勝手に武装解除してしまったのである。
手下達のそんな恐慌(きょうこう)ぶりに、頭目であるダミアンもどうしていいのか判らない。
ただ、怒りだけは湧(わ)き上がってくる。彼は頼純達のあまりにも無慈悲(むじひ)な行いに怒鳴り散らした。
「いくら何でも、そりゃやり過ぎだ! 皆殺しにするっていうのはひどすぎるだろう! そんな事は人間のする事じゃねェぞ! 」
「ナニ言ってやがる。 お宝ほしさにこの砦(とりで)にズカズカと乗り込んできたのは、お前らの方だろう。 この庵(いおり)を燃やしてやるとも言ってたよなァ‥!? 」
「そ‥ それは‥ 」
「そもそも‥ お前らは、森の通行人を襲っては、彼らが命乞(いのちご)いをするのを無視して皆殺しにしてきたんだろう。 なのに、その順番が自分達に回ってきたら、ひどすぎるだの何だのって―――そりゃ身勝手すぎやしないかい 」
「け‥ けどォ‥‥ 」
オロオロとし始めたダミアンを、頼純が怒鳴りつけた。
「だったら‥ テメーは、どうすんだよ! 」
ダミアンはついに観念したのか、ポロポロと涙を流しながら頼純に頼み込んだ。
「ゴメンなさい。 もう、二度としませんから‥ どうか、助けてください。 お願いします! 」
× × × × ×
シュザンヌは、城壁の上に取り付けられた大きな操作棒(レバー)に乗っかると、体重を掛けてそれを押し下げる。ローマ時代の機械は、ゴゴゴゴッと音を上げて反転しはじめた。砦(とりで)内に溜まっていた水が、徐々に排水されていく。
驚く事に、頼純が山賊達にした話はハッタリではなかったのだ。
本当に水は、砦(とりで)内が満杯になるまで注入され続けるし、消毒酒や薬用油もその水の中に流れ出す仕掛けになっていた。まったく、ローマ人達は恐ろしい事を考えたものである。
そして、いくら数々の人命を奪ってきた山賊とはいえ、80人もの人間を皆殺しにしようと本気で考えていたシュザンヌも恐ろしい女性だと、頼純は思った。
医者であるクセに、かわいい顔してそんな事をのたまうのだ。
ただし、この砦(とりで)の城壁がその巨大な水圧に実際に耐(た)えられたかというと、そこは甚(はなは)だ疑問である。完成した当時でさえも、おそらく城壁は注水の途中で決壊(けっかい)したと思われた。ましてや、この砦はそれから800年も経っているのである。とても保たなかったであろう。
山賊達は、板にでもしがみついて一定の水位まで頑張っていれば、やがて城壁は崩れ、水もろとも外へ放り出されていたはずである。
だが、そんな事など知らない80人の彼らは、早々に降伏したのであった。
山賊は頼純の指示に従い、全員が武装解除されると、順番にシュザンヌの庵(いおり)の中へと入っていった。そこにある床穴から、地下トンネルへと進んでいったのだ。
唯一の出入り口が塞(ふさ)がれてしまった現在、本当にそこしか外へ出る手段はなかったのだ。
ただし、彼らが向かう先はシュザンヌ達が出てきた城壁の上ではない。その通路はすでに閉じられていた。トンネルはそのまま延々と続き、森の奥へとつながっているのだ。
暗いトンネル内は、壁に灯明(とうみょう)がつけられており、点々と灯(とも)されたその明かりによって出口へと案内されるのである。灯明(とうみょう)はオリーブ油が入った小皿に芯を浮かべた物なのだが、今日はその皿の中に鎮痛用の麻薬であるアヘンとマンドラゴラの丸薬が投入されていた。油に溶け出したアヘンとマンドラゴラが甘ったるい煙を出している。
トンネル内はその煙で充満していたのだ。彼らはこの煙をかなり長い時間吸いながら、出口へと向かっていく事になる。
外へ出る頃には、山賊達も完全に陶酔(とうすい)状態に陥(おちい)っているだろう。気力がなくなり、幻覚を見続ける症状が2、3日は続くらしい。
このような状態で、真冬の森の中に放り出されるのだから、彼らの中には凍死する者も出るに違いなかった。だが、それは自業自得というものであろう。
その後、頼純達4人が換気された地下トンネルを脱出したあとは、その出口扉も完全に閉じられてしまう。扉の外側は上手くカムフラージュされており、よく目を凝(こ)らさなければ見落としてしまうほどであった。
さらに、彼らが頼純らを尾行して、砦(とりで)までたどり着いた迷路のような進入路も、束ねた木の枝などでその途中を塞(ふさ)ぎ、隠してしまうらしい。
ここまですれば、山賊達の砦(とりで)に関する記憶を完全に消す事まではできなくとも、それを曖昧(あいまい)にするくらいの事は可能であろうと思われた。
そもそも、ふたたび砦(とりで)を見つけたとしても、中に入る入り口はもうないのだ。
山賊達が、もう一度砦(とりで)を訪れる事はまずないだろうが、シュザンヌは当分の間、別の場所で生活する事にした。こんな時のために、彼女は長い間変装していたのだ。
シュザンヌはその引っ越しで、医学書や様々な薬剤、治療器具や薬の製造機器などを持ち出した。
そのせいで準備に時間が掛かってしまい、出発したのは次の日の昼過ぎになってしまった。
彼女の大量の荷物は、森の中につないでいた馬に乗せて運ぶ事にした。
頼純は来た時と同様、ティボーをおんぶし、エルキュールの長剣を持ってエレーヌの森を進んだ。エルキュールはシュザンヌが手を引いてくれた。
「すまない‥ アンタには一生感謝するよ‥ 」
ティボーが、頼純の背中でそう囁(ささや)いた。
「よせやい! おっさんらしくネーぞ! 」
頼純はクスリと笑った。
ふとエルキュールに目を向けると、頼純にはあれだけ虚勢(きょせい)を張っていたクセに、黙ってシュザンヌと手をつないでいる。
ちょっと頬(ほお)が赤い事とにやけた表情から、彼は若い女性とのふれあいを堪能(たんのう)しているようだった。
日没近くに森を抜けた一行は、近くの村でなんとか馬車を借りる事に成功した。
シュザンヌが手綱(たづな)を握る馬車は、荷台に横たえたティボーと彼女の荷物を載(の)せる事にした。それまでの馬には、エルキュールを乗せ、その手綱(たづな)を徒歩の頼純が牽(ひ)いた。
こうして、一行がファレーズに帰り着いたのは真夜中すぎとなってしまったのである。