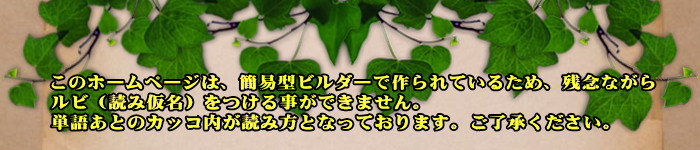
第88話
1027年 ファレーズ城(2)
頼純は渾身(こんしん)の力で、扉と扉の間に上半身をねじ込んだ。
「うォォォォォォォ―――ォお‼ 」
突如抵抗がなくなり、その体はすぽんと城門の中に転がり込む。
「ワッとととと‥‥ 」
その動きを追うようにして、ヴィルヘルムの弓矢が放たれた。
矢は正確に、起き上がろうとしている頼純の胸めがけて直進する。
だが、頼純の小烏丸(こがらすまる)が払われると、その矢は中ほどで真っ二つになった。
「おのれ! 」
ヴィルヘルムは次の矢をつがえようとした。
だが、身を低くして走り寄る頼純の方が早かった。
ヴィルヘルムの目の前を閃光(せんこう)が走る。
次の瞬間、弓を握ったままの左手が宙を舞った。
「グォ―――オ! 」
鮮血を噴(ふ)き上げる左手首を右手で押さえながら、ヴィルヘルムは膝から崩れ落ちた。
頼純は彼にかまわず、走り来る14人の騎士達に斬り掛かった。
騎士達が振り下ろす何本もの長剣(エペ)を見事に躱(かわ)しながら、頼純の太刀(たち)が一閃(いっせん)、二閃(にせん)する。
「とう! ヤッ! たッ! 」
いつもの鋭い太刀(たち)さばきは、敵の手足を次々と切断していった。
「グギャ! 」
「バボッ! 」
「ヒゲッ! 」
騎士達は悲鳴を上げながら、地面をのたうち回っている。その切断面からは大量の血が舞い上がっていた。
13人の騎士は、瞬(またた)く間に動けなくなった。
周囲は血まみれとなり、頼純も大量の返り血を浴びて真っ赤に染まっていた。
だが、今日も一人として敵は死んでいなかった。
それはじつに見事な剣技であった。いや、神業(かみわざ)に近い腕前である。このような離れ業(わざ)ができる者はそうそうはいないであろう。
しかし、その技(わざ)にはどこかいびつさが感じられた。
それは、頼純自身が一番気づいている事だった。
彼らは、理由(わけ)もなくファレーズを襲い、罪なき住民達を虐殺(ぎゃくさつ)した悪党どもである。サミーラまで、もう少しで殺されそうになったのだ。
頼純はいつにも増して、敵を憎く感じていた。
にもかかわらず、彼は一人も殺す事ができなかったのだ。
なぜだ‥ なぜ、殺せない?―――頼純は何度も自問自答した。
敵を『殺せない事』はお前のみならず、お前が大切に思う者まで死なせてしまう可能性がある―――エルキュールから何度も言われた説教が脳裏(のうり)をよぎった。
「ゲホゲホ‥ 」
敵の騎士達が上げる悲鳴に混じって、サミーラの咳(せ)き込む声が頼純の耳に届いた。
「し‥ しまった‥! 」
剣士からただの男に戻った頼純は、慌(あわ)ててサミーラのもとへと駆け寄る。
「大丈夫か? しっかりしろ! 」
それはほんのわずかな時間だったが、サミーラを忘れてしまった自分の事を、頼純は大いに悔(く)いた。
彼女をかかえ起こすと、その手にべっとりと血がついた。煙で咳(せ)き込むたびに、脇腹の傷口から血があふれ出ている。
「ちょっと待ってろ。 すぐに手当てをしてやるから 」
頼純は小烏丸(こがらすまる)を鞘(さや)に納めると、グッタリしたサミーラを抱きかかえて立ち上がった。
その時、
「―――! 」
頼純の背後に、ヴィルヘルムが立っていた。
その振り上げられた右手には長剣(エペ)が握られている。切断された彼の左手首からは、心臓の鼓動にあわせて血が噴き出していた。
普段ならば、その気配を感じぬ頼純ではない。
だが、サミーラの事が心配で、彼に一瞬の油断が生じてしまったのだ。
それはかなり危険な状況であった。
―――死ぬかも知れない。いや、死ぬ。
頼純は強く予感した。
彼がサミーラから手を放し、太刀(たち)を抜きながら振り返る間に、敵は長剣(エペ)を振り下ろすだろう。その刃(やいば)は確実に頼純の首に叩き込まれる。
誰かが何かを叫んでいるようだった。
頼純が声の方に目を向けると、門の外で弓を構えるドニとエルリュインがいた。しかし、手前にいる頼純達の体が邪魔をして、背後の男が狙えないようだ。
たとえ頼純が身を伏せたとしても、矢が飛んでくる間に男は斬るなり刺すなりするに違いない。男を殺す事はできても、頼純が助かる道はないのだ。
時間が止まったかのように、すべてがゆっくりと感じられた。
―――どうすればいい?どうすればいい?どうしてこうなった? いつもなら、こんな事にはならなかったのに‥ ああ、これがエルキュール爺さんが言っていた事か‥ 敵を殺さないとこうなるんだ‥ 相手にとどめを刺さなかったから俺は死ぬのか‥ 油断した俺が悪い‥ けど、サミーラが‥ 死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ―――いつになく弱気な思いが、頼純の頭の中を瞬時に駆け巡(めぐ)った。
そして、ヴィルヘルムは長剣(エペ)を振り下ろした。
頼純は死を覚悟した。
ただ、せめてサミーラだけは助かって欲しかった。自分のせいで彼女が死ぬのは堪えられなかった。哀(あわ)れに思ったのだ。
そんな3人の視界が一瞬陰(かげ)った。天空から影が舞い降りてきたのだ。
影は頼純を斬りつけんとするヴィルヘルムに襲いかかる。
―――ゴルティエであった。
屋根の上からヴィルヘルムめがけて飛び降りた彼は、俯(うつぶ)せに倒れた敵将の背中に跨(また)がり、握り締めた大型ナイフをその背中に突き立てたのだ。
「ぎゃ―――あ! 」
ヴィルヘルムが断末魔(だんまつま)の叫び声を上げた。
ゴルティエはそんな彼に何度も何度もナイフを突き刺す。
「死ね!死ね!死ね!―――死ね! 」
ゴルティエの顔に血の飛沫(ひまつ)が飛んだ。しかし、顔や手が赤く染まる事はない。
ヴィルヘルムは、すでに左手首からほとんどの血液を出し切っていたからである。
ヴィルヘルムはすぐに動かなくなった。
そして彼の死が、このすべての戦闘の最後となったのである。
× × × × ×
サミーラの治療はシュザンヌが施(ほどこ)してくれた。
弓矢によってサミーラの脇腹の肉はかなりえぐられており、出血もひどかった。
だが、矢尻は内臓に達していなかったため、死に至る事はないとの診断だった。2週間ほど安静にしていれば、歩けるようになるらしい。
息する事も忘れてシュザンヌの説明を聞いていた頼純は、安堵(あんど)のあまりその場にヘナヘナと崩れ落ちてしまった。
シュザンヌは、サミーラの傷を『医療用酒(アルコール)』で洗い、薬草を塗った布をあて、長い布を腰に巻きつけて患部を圧迫した。
頼純は朝昼晩、サミーラに煎(せん)じ薬を飲ませる事を約束させられた。
医者であるシュザンヌは、エルレヴァ達の低体温症を治療した後、ひそかに城門を出て『エレーヌの森』に入っていた。
ファレーズから逃げ出した下町や貧民街の人々が森の中に逃げ込んでいたからだ。彼らの多くはケガをしていた。その治療を行わなければならない。
一方、『領主の館(メヌア)』には金持ち専用の医師が2人もいる。何かあっても、自分が出張(でば)る必要はないと考えたのである。
それに『エレーヌの森』は彼女の本拠地であった。生まれ育った場所なのだ。だからこそ、そこで脅える人々を彼女は無視する事ができなかった。
夜が明け、頼純ら先発隊が到着してからは、治療拠点をファレーズの街に近い麦畑へと移動させた。これから大量に怪我人が発生する可能性があったからだ。
シュザンヌが治療する天幕(テント)周辺は、ケガをした人々でごった返していた。
ゴルティエと2人のレイモンは、麦畑の積み藁(わら)にもたれ掛かって坐ると、ぼんやりと燃え続ける街を眺めていた。
彼らは精も根(こん)も尽き果てていた。
筋肉はパンパンで、いたる所が痛かった。アチコチの関節がバキバキと音を立て、全身は燃えるように熱を持っている。
昨夜からファレーズの城内を走り回り、城壁に水を掛け、迷路を作り、何軒もの建物に火を着け、何十人もの敵に追い掛けられたのである。―――丸一日走り続けた彼らが、疲れていないはずがなかった。
彼らは逃げる途中、みずからつけた火に追われ、行き場を失ってしまった。
広がる炎は路地にあふれ、建物から吹き出す火の粉と煙で周囲が何も見えなくなってしまったのだ。
そこで、ゴルティエら3人は、ジャコモの指示に従って家屋(かおく)の屋根に登った。
すると、そこは地上よりもずっと見通しがよく、燃えていない場所もはっきりと判った。
あとは、屋根を踏み抜いて燃える室内に落下しないように気をつけながら、その上を走り続ければよいのだ。
やっと城門前までたどり着いた彼らは、地上に降りようと白煙立ち込める眼下に目を向けた。
するとそこには、敵に襲われようとする頼純の姿があるではないか。
次の瞬間、ゴルティエは屋根から飛び降りていた。何も考えていなかった。
あとは無我夢中である。
彼が我に返った時、敵将は背中の肉をズタズタに切り裂かれて死んでいたのだ。
そんな事を思い出しながら、3人は深い深い眠りに落ちていったのである。
昼過ぎには領主ロベール伯爵とその騎士団50余騎が到着した。
彼らは、ファレーズの街が燃えている光景に、大いに動揺(どうよう)する。
「バ‥ バカな‥‥ どうなってるんだ? 」
ロベールも先遣隊と同様に勘違いをしていた。だが、その反応は頼純達よりもはるかに大きかった。彼はかなりの興奮状態で怒鳴った。
「報告しろ! ファレーズは―――我が街は陥落(かんらく)したのか? 」
そんなロベールに、苦笑いで近づいてきた頼純が説明をした。
「大丈夫なんだってさ! ありゃ、敵を全滅させるために、こちら側から放った火だそうだ♡ 」
「え!? 」
「だよねェ‥ 信じらんネーだろう!? 敵を城下に閉じ込めて焼き殺すんだそうだ。 しかも、それを考えたのがエルレヴァさんだってんだから―――もう、俺もビックリしちゃったよ 」
「エ‥ エルレヴァが? 」
エルレヴァが何を考えたのか―――ロベールは、いまだ事態がよく理解できていなかったが、その言葉そのものが彼の心を落ち着かせた。
頼純は報告を続けた。
「それから‥ 1000人近い街の住民達も全員、『領主の館(メヌア)』に避難してるらしい 」
ロベールはいまだその話が信じ難(がた)いのか、もうもうと立ち昇る白煙を見ながら眉を顰(ひそ)めている。
「け‥ けど‥ あんなに燃えていて、『領主の館(メヌア)』は大丈夫なんですか? 」
頼純は、煙の奥に見える丘の頂上を指差した。
「ホレッ、あそこ! 『領主の館(メヌア)』で大きな旗が振られているだろう!? あれが振られている限りは、館の中は無事って事らしいぜ。 だから、安心しな! 」
「は‥ はあ‥‥ 」
いまだ不安が拭(ぬぐ)いきれないロベールに
「もう‥ 大丈夫だって! コイツはあのエルレヴァさんが考えた作戦なんだぜ。 そこらに抜かりはネーはずだ 」
頼純はロベールの肩を叩いた。
頼純に手足を斬られた14人の騎士達は、その部分をロープで縛るだけの簡単な止血しかしてもらえなかった。
とはいえ、たとえ手厚い治療を受けたとしても、彼らのほとんどは失血死やそれ以外の病気で死んでしまうのだ。
さらに、仮に生命力が強くて生き残ったとしても、彼らはその後全員が死刑となる。つまり、敵の騎士達は一人として生き延びる事はできないわけである。
しかも、エルリュインらによる拷問(ごうもん)はすでに始まっていた。
一人でも多く生きているうちに、色々と白状してもらわなければならない。
だが、彼らは意外にも簡単に口を割った。
ある者は激痛に堪(た)えかね、またある者は痛み止めの薬欲しさに、すすんで告白したのである。
彼らはローマ帝国(神聖ローマ帝国=現在のドイツ、オーストリア他)内のルクセンブルグ伯領に根城を持つ傭兵団(ゼルドナァ)『シュヴェールト』であるという事だった。
自分の名前、年齢、出身地、隊長の名前からどういう経路で移動してきたのか、1人あたりの報酬は幾らかまでありとあらゆる事を証言した。
だが、この襲撃を依頼してきた人物については、どのように厳しく責め立てても、誰も白状しなかった。本当に知らないようだった。
彼らは作戦内容と報酬は知らされるが、依頼主については聞かされない事が多かった。彼ら自身もそんな事に興味はなかった。
もしかすると、死んだヴィルヘルム隊長でさえ知らなかったのではないかという話だった。
頼純やエルリュイン達は、この事件の真相を究明する事はかなり難(むずか)しいという事を思い知らされた。
ロベール伯爵らはシュザンヌの指示に従い、何十もの天幕(テント)を張って、ファレーズの街から焼き出された人々の傷の治療や炊き出しをおこなっていた。
やがて、リシャール公爵も500の騎士・兵士を率いて、応援に駆けつけてくれた。
これにより、罹災(りさい)した多くの人々がひとときの安息を得る事ができたのである。
ファレーズの火事が収まったのは夕刻近くになってからだった。
城下町は、全体が燃え尽き、真っ黒な廃墟(はいきょ)となってしまった。
ただし、外城壁と『領主の館(メヌア)』だけは、大量の水を掛けたお陰もあってか、ほぼ完全な形で残っていた。
ロベール伯爵一行は急いで『領主の館(メヌア)』へと向かった。
だが、行く手はがれきだらけで、まだ火がくすぶっているところも多く、熱と煙がすごかった。
これでは、馬を走らせるどころか、徒歩でさえも前進が難しい状態である。
所々にかたまって敵騎士の死体と馬の死体が転がっていた。3、4人単位でちりぢりに分かれた彼らは、行く手を炎に遮(さえぎ)られ、行っては戻りを繰り返していく内に、やがて火炎に閉じ込められ、焼死したものと思われた。
騎士はほとんどが燃え尽き、炭化していた。
馬は沸騰(ふっとう)した体液で腹が膨(ふく)れ上がり、中にはそれが破裂して大量の腸を吐き出しているものもいた。
周囲には強烈な悪臭が漂い、嘔吐(おうと)する者は1人や2人ではすまなかった。
ロベールらに同行したノルマンディー大公は、その圧倒的な廃墟(はいきょ)といくつもの惨(むご)たらしい死体に呆然としていた。
「ほ‥ 本当に‥ このような恐ろしい計画を、一介(いっかい)の町娘が考えたというのか‥‥? 女だてらに、すべての町民を指揮し、この作戦を実行したのか―――? 」
リシャール3世はエルレヴァに驚かされるばかりであった。
「質・量ともに並外れた敵であるにもかかわらず‥ 彼らを相手に完全勝利をするとは―――とても信じられん。 それが本当ならば、わたしの軍師として雇いたいほどだ 」
そんなリシャール3世に、後からついていった頼純が声を掛けた。
「エルレヴァさんが傑出(けっしゅつ)した女性である事は間違いないでしょうね。 ただ、今回の勝利はそれだけじゃないようですぜ 」
「それは、どういう意味だ? 」
「話によると、街の全員が協力しあった事こそが勝利の要因だったみたいです。 誰もが強大な敵に屈せず、状況にあきらめる事なく、常に誰かが誰かを助け続けた結果です。 事実、わたしも仲間に命を助けられましたしね―――ひとりが全員のために‥ 全員が1人のために戦った成果でしょう 」
「‥‥‥ 」
「もちろん‥ そのように、強固な絆(きずな)で街をまとめ上げた彼女の政治力はすごいと思いますけどね♡ 」
「うむ 」とリシャールは頷(うなず)いた。
その頃、ロベール伯爵は黒い廃墟(はいきょ)の中を必死に進んでいた。
ともの者達がついていけないほどの早足だった。
煤(すす)と灰に覆われた地面は滑りやすく足を取られる。だから、ロベールは何度も転び、泥だらけの真っ黒けになっていたが、それでも必死に前進し続けた。
彼はエルレヴァの事が心配で、気が気でなかったからである。
君主(くんしゅ)たるもの、何があってもけっして動じず、でんと構えておれ―――あとで兄にそう怒鳴られるだろうと思った。
だが、今はそんな事どうでもいい。エルレヴァの元気な顔さえ見れれば、それでよかった。
彼がやっと広場までたどり着いた時、前方からぞろぞろと近づいてくる人々の姿が目に入った。
彼らも皆、全身が真っ黒になっていたが、それがファレーズの住人である事はすぐに判った。
彼らは、ロベールを発見するやその周囲に跪(ひざまず)いた。広場が埋まるほどに、何百人もいた。そして、彼らは神に祈りを捧げたのであった。
そんな人混みを割ってやって来たのは、何十人もの子供を引き連れたエルレヴァだった。
彼女の顔も煤(すす)まみれの真っ黒である。
「―――エルレヴァ! 」
ロベールは走り寄ると、エルレヴァを強く抱きしめた。
「よかったよォ‥ よかったよォ‥ 」
彼の目からはポロポロと涙がこぼれた。
「あらあら‥ そんなに泣かないの。 お腹の赤ちゃんに笑われちゃうぞ♡ 」
エルレヴァがクスクスと笑った。
ロベールもフフフと笑い返した。
それに吊られて周囲の人々も大いに笑った。だが、彼ら全員の目からは、とめどなく涙があふれ続けていた。
街が一体となった瞬間であった。
そんな光景をリシャール公爵は不思議そうな表情で眺(なが)めていた。
「領主と平民がともに笑(わろ)うておる‥‥! 」
頼純がそれに答えた。
「あれがロベール伯爵です。 街中の人々から慕(した)われる、いい領主様ですよ 」
「ほう‥ 」
リシャールはロベールがうらやましかった。
民心をまとめる事はひじょうに難しい。それは、『言葉』―――理屈や賢さで成せるものではない。ましてや、恐怖や暴力などではけっしてうまくいかないものだ。
そこに要求されるのは、民衆の心を動かす『人間力』だからである。
弟ロベールには、それが備わっているのかも知れない。
そしてもしそうならば、これまで気弱で頼りないと思ってきた弟の方が、自分よりも君主に向いているのではないのか―――ノルマンディー大公・リシャール3世は、そんな事を考えさせられた。
夕日に染まる彼らの姿は、それほどまでに美しい光景だったのだ。