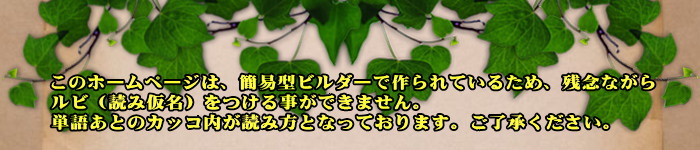
62
1026年 ファレーズ・ティボー邸
シュザンヌはしばらくの間、ティボーの屋敷で世話になる事となった。
住む場所がすぐに見つからない事と、ティボーの傷の具合をしばらく観察したいとの思いがあったからだ。
街の人々に不審がられても困るので、彼女はエルキュールの娘―――ティボーの姪(めい)という事にしておいた。
祖々父の代からノルマンディー公家(こうけ)に仕(つか)えるティボーは、52歳のこの年までずっと独身を通してきた。
それは、生来の皮肉屋でいじわるな性格が災(わざわ)いして、ほとんどの女性が彼に好感を持たなかった事も理由のひとつであったが、一番大きな原因はティボー自身が他の女性に対してまったく興味を示さなかったからである。
―――彼は20年以上もの長きに渡って、ただ一人の女性に思いを寄せていたのだ。
彼女はいつもティボーのそばにいたが、けっして手の届かぬ女性であった。
『彼女の事は諦(あきら)めて、違う女性と結婚しなくては――― 』と、いくら自分に言い聞かせてみても、彼女の笑顔を見てしまうと、そんな考えなど吹き飛んでしまうのだ。
ティボーの片思いは、苦しくも幸せな日々であった。
ところが、或る日突然、彼女は死んでしまう。10年ほど前の事である。
ひとりになると彼女を思い出し、涙が止まらなくなる日々が一年半も続いた頃、これではいけないと悟ったティボーはある決意をした。
彼は生涯(しょうがい)他の女性を愛さない事を神に誓(ちか)い、ひたすら仕事に邁進(まいしん)する事で、その深い悲しみの日々と決別しようと考えたのだ。
それからの彼は、彼女が残したリシャールやロベールの世話をする事で、心に空(あ)いた穴を埋めていったのである。
しかし、その熱心さが高じて、兄弟には疎(うと)まれ、他の家臣達からも『細かい事にうるさい』だの、『くだらない事に厳(きび)しい』だのと陰口を叩かれ続けたのであった。
それでティボーは、ますます依怙地(いこじ)になり、ひねくれ者となっていったのだった。
だが、そんな彼も今回の一件で、10年来の憑(つ)き物が落ちたかのようであった。
兄から自身の『死期』を告白された事で、ティボーも自分の『死』について思いを巡(めぐ)らしていた。そんなさなか、彼は大きな傷を負ってしまい、なおさら『死』というものを身近に感じたのだ。日もすがら、ベッドでジッとしていると、『人生とは何か?』などと、深く考えざるを得なかったのである。
傷快癒(かいゆ)のため、二週間ほどベッドで安静にしておくように言われたティボーは、新年の祝賀パーティーの準備を誰かに任(まか)せなければならなかった。
彼が家政方(かせいがた)の誰にしようかと悩んでいると、
「この際だから、エルレヴァさんに仕切らしちゃどうだい? 」
と頼純が持ちかけてきた。頼純はエルキュールに呼ばれて出向いたついでに、ティボーを見舞っていたのだ。
「いや‥ それは――― 」
二の足を踏むティボーを、頼純は流暢(りゅうちょう)なフランス語で説得した。
「いいかい‥!? あんたはもう、いつ引退してもおかしくねェ歳なんだぞ。 その一方で、エルレヴァさんは伯爵の子供を出産する事が決まってんだ 」
「しかし、その子は――― 」
「ああ‥ 俺だって、生まれてくる子供が世継(よつ)ぎになれねェ事ぐれェは知っているさ! 彼女が正妻になれねェ事だって判ってる。 だが、今後彼女の影響力が大きくなる事は間違(まちげ)ぇねェんだ。 すでに、このファレーズの住民達だってそれを認め始めてる。 だったらここで、アンタがエルレヴァさんに一歩譲(ゆず)ってやってさァ‥ 恩を売っておくってーのも、悪い考えじゃねェと思うけどなァ‥ 」
「‥‥‥ 」
「アンタだって‥ 彼女には、失礼な事を言ったり、認めなかったりして、散々イジメてきたんだ。 立場が逆転すると、彼女から仕返しされちゃうぞ 」
「ああ‥ そっかァ‥‥ 」
「なァに‥ 恩着せがましく譲(ゆず)ってやればいいんだよ! それでも、彼女は大いに感激すると思うゼ。 そりゃもう、アンタに感謝するだろうよ!」
「そ‥ そうかなァ‥ まあ、ヨリさんがそう言うのなら、そうしてみるか‥‥ 」
ティボーは、拍子(ひょうし)抜けするほどあっさりと頼純の意見を受け入れた。
これまでならば、頼純が言う事にはすべて反対してきたティボーであった。
だが、今は違っていた。それは彼が頼純に心を開いたせいもあったのだろうが、ティボーが性根(しょうね)から大きく変化したという表れであった。
そうでなければ、いくら命の恩人であろうとも、怪しげな森の魔女であるシュザンヌを自宅に招き入れる事など、絶対にあり得なかったはずである。
ティボーは、『新年の宴(うたげ)の進行はエルレヴァ殿に任せたい』とロベール伯爵に申し出た。そして、彼女を自分の屋敷に呼び出したのであった。
ティボーの枕元に立つエルレヴァは、彼から宴席に関する様々な指示を与えられていった。
「よいですかな‥ 」
「は‥ はい! 」
「まず、新年の宴(うたげ)においてもっとも重要な事は――― 」
ベッドで上半身を起こしたティボーは、それから料理のメニューや人数、テーブルの食器等の置き方、酒の追加、楽団への指示、玉座の後ろに掲げるタピストリーの選び方等々について、丁寧(ていねい)に教えていった。
もちろん、彼はクリスマス前からこの宴(うたげ)の準備も進めていたため、あらかたの発注―――客の招待や楽団、旅芸人への依頼、料理の材料、酒などの手配はすでに終わっていた。
さらに、賑々(にぎにぎ)しく行(おこな)われる降誕祭(ノエル)とは違い、厳(おごそ)かな新年の食事会は、規模もかなり小さく、手配するものも少なかった。
そもそも、細かい実務は執事(アンタンダン)の仕事ではない。各部署にはそれぞれ担当の給仕長(きゅうじちょう)がおり、彼の仕事はそれらを統括(とうかつ)する事なのだ。
「あ‥ あの‥ 騎士(シュヴァリエ)の方々の席順は―――いかように? 」
エルレヴァは張り切っていた。初めての城の仕事とあって、かなり緊張もしていたが、それ以上に家政の仕事ができる事が嬉(うれ)しかった。しかも、城のすべての使用人を差配(さはい)するのである。
いかに財産があろうとも、『卑(いや)しい者』とずっと蔑(さげす)まれてきた彼女が、やっと高貴な人々達の仲間入りをする時が来たのだ。それは彼女にとって長年の夢であった。
ベッドのヘッドボード(ドゥスレ)にもたれ掛かったティボーは、そんな彼女に淡々と説明をしていった。
「レオン兵士長はロベール伯爵様と同じ席に‥。 ただし、テーブル(ターブラ)の一番末席でけっこうです。 あとの、騎士(シュヴァリエ)達は左の列のテーブル(ターブラ)に勝手に坐りますから、心配ご無用! 」
「は‥ はい‥! 」
エルレヴァは不安から、親友であるサミーラにもこの場に付き合ってもらっていた。サミーラはエルレヴァの傍(かたわ)らで、ティボーの話をすべて蝋板(ろうばん)に記入していく。それを家に帰って、エルレヴァが羊皮紙に清書し直すのである。
ティボーは真剣な眼差(まなざ)しでエルレヴァを見上げた。
「よいですか‥ 上座のテーブル(ターブラ)はあくまでもロベール伯爵の席を中心にして、席作りをしてください。 そして、伯爵様から少しだけ距離をとった、向かって左隣がアナタの席です。 その反対側―――伯爵様の右側は、司祭様のお席となります。 ヨリ殿はアナタの左隣に――― 」
返事をしないエルレヴァに、どうしたのだろうとティボーは顔を曇らせた。
両手で口元を押さえたエルレヴァがおずおずと尋(たず)ねた。
「あ‥ あのォ‥ それって、つまり‥ わたくしが司祭様と同等の扱(あつか)いという事なのでしょうか‥? 」
「そういう事です‥! アナタ様もご出世なさいましたね♡ 」
ティボーはニッコリと笑顔で返した。
感動のあまり、エルレヴァの瞳からはポロポロと大粒の涙がこぼれ落ちた。ついに執事(アンタンダン)殿に認められたのだ。彼女は嬉(うれ)しくて嬉(うれ)しくてしょうがなかった。
エルレヴァは隣のサミーラの胸に顔を埋(うず)め、泣き始めたのだ。そんな彼女にサミーラももらい泣きした。
泣き続ける女性二人に、どうしてよいのか判らないティボーは、困った顔のままずっと固まっていた。
× × × × ×
押し迫った新年に向けて、城内もファレーズの町も人々が走り回り、慌(あわ)ただしかった。
そんな中、ティボーの屋敷の一室では、シュザンヌが持って来た医療機器を広げていた。そして準備が整うと、さっそく薬の製造を開始したのである。
彼女には降誕祭(ノエル)も新年も関係なかった。それよりも薬の方がはるかに重要なのである。
そんなシュザンヌの様子を、エルキュールは部屋の隅の椅子に腰掛けて、毎日眺(なが)めていた。
何かを言うわけでもなく、何かをするわけでもなく、ただジッと彼女の姿を見ているのである。
ティボー宅から帰ろうとしていた頼純が、そんな彼に声を掛けた。
「じいさん‥ シュザンヌさんに、えらくご執心(しゅうしん)のようだが‥ 大丈夫かね? 」
「うるさい! テュロルドよ‥ お前こそ、そのような心配をするヒマがあるのなら、もそっと剣を振れ! 無心になって、剣を振り続けよ。 そうする事で、己の心を強くするのじゃ! 」
頼純は二日おきにエルキュールから呼び出されていた。そして、長い長いお説教を聞かされるのである。剣士として、兵士として、また騎士として、どう生きるべきかを得々と訓示(くんじ)されるのだ。
だが、頼純はこの呼び出しに逆らえなかった。
自分が『人を殺せない』事を唯一見抜いた人物だったからである。
それに、彼はボケていたが、どこか頼純と波長が合うのだ。早くに死に別れた父を思い出させるのかもしれない。
「いやいや‥ アンタ、俺には『剣士とは何か』とか、『騎士とはこうあるべき』とか、立派な事ばっかりおっしゃってますけど‥ いま、シュザンヌさんのお尻見てたよねェ‥!? いやらしい目ェしてたぞ! 」
「な‥ 何を言うか‥! ワシは老い先短い身じゃぞ。 そのような邪念(じゃねん)など、ありゃせんわ! ただ美しいもの、汚(けが)れなきものを、最後にこの目に焼き付けたいだけなのじゃ! 」
頼純は、憮然(ぶぜん)とするエルキュールを、意地悪な微笑(えみ)で覗(のぞ)き込んだ。
「ウソだね‥ だってアンタ、股間が膨(ふく)らんでるじゃん♡ 」
「ウッ! 」
思わず股間を押さえてしまったエルキュールを、頼純は感心した様子で見下ろした。
「いやはや、じいさん‥ 歳をとっても、なかなかに男だねェ‥ 」
エルキュールは恥ずかしそうに頬を染めながらも、頼純に言い返した。
「もう‥! 死ぬ前にそれぐらいは良いではないか。 テュロルドよ‥ そのようにワシをイジメんでもよかろう 」
「え!? 死ぬって―――エルキュールさん、どこか具合でも悪いの? 」
突如、二人の会話にシュザンヌが割り込んできた。
「あ‥ いや‥ 」
エルキュールは言葉を失った。
彼は、シュザンヌが男二人の話をどこから聞いていたのかと想像し、顔を耳まで真っ赤にしてしまった。
そんなエルキュールの恥じらいなどおかまいなしに、頼純はズケズケと彼の身上(しんじょう)を語り出したのだ。
「あれッ‥ シュザンヌさんは知らなかった? このエルキュールじいさん、最近血を吐いちゃってさァ‥ それで、お医者さんに診(み)てもらったら、『間もなく死ぬ』って宣告されたんだって! 」
「え!? 」
「それで‥ 天国に召(め)される前に、もう一度初恋の人―――アナタのお祖母さんに会いたいと、わざわざここまで旅をしてきたってワケさ‥! 」
「んんうん‥‥‥まあ‥ そういう事じゃ‥! 」
エルキュールは寂(さび)しそうにつぶやいた。
「ちょっと失礼! 」
シュザンヌはエルキュールの目を覗(のぞ)き込んだり、まぶたの裏を見たり、舌を出させたりして確認していた。さらには、胸をはだけさせて、聴音機で胸やみぞおちの音まで聞いた。
「ここ、どんな感じですか? 痛くないですか? 」
胸を指先でトントンと数カ所叩き、次にみぞおちに拳を当てた。
「ああ‥ そこは痛い‥ 」
「ここ、キリキリと痛くなりますよね。 とくに、お腹がすいている時 」
「おお‥ そうじゃ、そうじゃ! よく判ったのう 」
「お通じはどうです? ウンチが黒くなる事はありますか? 」
「ああ‥ 時々あるな‥ 」
「ふむふむ‥ なるほどねェ‥! 」
シュザンヌはしばらく考えていたが、エルキュールの目を見て、ハッキリと言った。
「アナタはまだ死にませんよ! 」
「はあ!? 」
頼純とエルキュールは驚きの声を上げた。
× × × × ×
西洋医学の祖がギリシャのヒポクラテスなら、中世の医学を支配したのはローマのガレノスであった。
紀元129年生まれのガレノスは、ローマ皇帝マルクス・アウレリウス帝の侍医(じい)となるほどの名医であった。
その彼が提唱したのが『精気論』である。それは『精気(プネウマ)が肉体をどのようにして制御しているのか』が主題(テーマ)であった。
『生命活動は精気=プネウマによって制御されている』と考えたのだ。
彼は、人体が大きく分けて3つの臓器によって制御されていると推測した―――『脳』と『心臓』と『肝臓』である。
そして、それぞれの臓器で『精気(プネウマ)』は生成されるのである。
『脳』で作られる精神プネウマは脊髄(せきずい)や神経によって全身を駆(か)け巡(めぐ)る。『心臓』で作られる生命プネウマは動脈によって全身に運ばれ、『肝臓』で作られる栄養プネウマは静脈(じょうみゃく)によって体中を移動する。
そして、それぞれのプネウマは相互に影響し合い、この移動が上手くいかなくなった時、人は病気になると考えたのである。 ただし、彼には『血液の循環』という発想がなかった。
彼はそれらの理論を解剖(かいぼう)と実験によって検証し、自分の考えが正しいと確証を得たのだ。それは絶対の自信であった。
彼は「汝(なんじ)が医者としての名声を欲するのならば、我が研究のすべての業績に精通しなければならない」と語っている。
つまり、自分が導き出した『精気論』は完璧であり、絶対であると豪語したのだ。
ローマキリスト教教会では、この精気(プネウマ)を聖霊と解釈し、『精気論=ガレノス医学』はキリスト教の教えに離反(りはん)しないとして、これを認めた。そのため、後世の医者はこの『ガレノス医学』のみを学ばされ、ルネサンスに至るまで一千年以上もの間、医学はほとんど進歩しなかったのだ。
さらに、彼の実験重視、解剖(かいぼう)重視の考え方は間違っていなかったが、ローマ時代からルネサンス時代までは、人体の解剖(かいぼう)は許されていなかった。そのため、彼も猿と豚しか解剖(かいぼう)した事がなかったのである。
『ガレノス医学』は体液病理説であり、これを学んだ後世の医者は、尿を観察する事がその診療のほぼすべてであった。尿の濃さ、色、時には味まで確認する事もあった。糖尿の検査である。
また、血を不浄(ふじょう)のモノとした当時の医学界では、外科手術は理髪店の仕事とされていたのである。
一方、ローマキリスト教教会によって異端とされた科学は、すべて否定され、焚書(ふんしょ)された。
その滅び行くギリシャ・ローマ文明を保存したのは、意外にもイスラム教世界であった。彼らは、ギリシャ語やラテン語で書かれた書物を、丹念(たんねん)にアラビア語へと翻訳(ほんやく)していったのである。そして、それを元にさらに研鑽(けんさん)し、高い文明を築いていった。
医学も同様である。10世紀から11世紀にかけて、イスラム医学は絶頂期を迎えていた。
イベリア半島(現スペイン)の後ウマイヤ朝の首都コルトバは、50万人もの住民を抱える西欧最大の都市であり、ザフラー宮殿には40万もの書籍が集められていたという。
丁寧(ていねい)に書き写された科学書・医学書は、市中の本屋でも多く販売され、それらがピレネー山脈を越えて、禁書(きんしょ)としてフランスに入る事もあったのだ。
真面目なキリスト教医師は、そうした先進の医学を学ぶ事を拒否したが、どうしても真実が知りたい、なんとしても多くの人々を助けたいと願う者達は、その禁を破った。アラビア語の医学書を翻訳(ほんやく)し、むさぼるように読んだのである。
また、その内容を確認するため、戦場に出掛けたり、墓を暴(あば)いたりして、こっそりと死体を解剖(かいぼう)する者もいた。
そんな『神の教えに背く者』達をキリスト教教会は―――『魔女』と呼んだのだ。
それゆえに、苦労して手に入れた知識も次世代へ継承される事は難しく、たいていの場合は一代で終わってしまうのだ。そうなると、次なる段階へ進歩する事もできなくなってしまう。
だが、シュザンヌの一族はその研鑽(けんさん)を続けていた。
四代にもわたって、アラビア語の医学書を翻訳(ほんやく)し、解剖(かいぼう)も続けていたのだ。
それだけに、彼女の見立てはかなりのものであった。
× × × × ×
「血を吐いた事で、その医者はおそらくアナタが肺病であると診断し、余命を一年くらいだと予想したのでしょう。 しかしアナタは、お腹の病気です。 胃の腑(ふ)に穴が空いておると思われます 」
科学者の目をしたシュザンヌは、淡々と自分の診断を説明していった。
「この病気を治すには、様々な事に気を煩(わずら)わせたり、思い悩んだりしない事です。 先日のお茶のように、熱いモノは一気に飲まず、よく冷ましてから飲んでください。 たくさん食べ過ぎず、お酒も飲みすぎず、睡眠は充分に取る事。 そうすれば、すぐに死ぬ事もないでしょう。 まだまだ長生きできますよ♡ 」
口をポカンと開けたまま、しばらく息を止めていた頼純とエルキュールが、大きく息を吐き出した。
ホッとした頼純は、半笑いで軽口を叩いた。
「ハハ‥ ナンだよ、心配させやがって‥! 爺さんが診てもらった医者はとんだ藪(やぶ)だな! 」
エルキュールはムッとした顔でそれを否定した。
「そ‥ そんな事ないわ! リシャール公爵様の御殿医(ごてんい)殿じゃぞ。 金だって相当ふんだくられたわ! 」
しだいに込み上げてくる喜びを顔に出すまいと、エルキュールは顔面の筋肉を引き攣(つ)らせながら、笑顔を無理矢理押さえ込んだ。
「け‥ けど、まあ‥ そういう事なら、もう少し長生きしてやってもいいかな‥ そしたら、お前に剣の稽古(けいこ)だってつけてやれるしなァ‥‥ 」
だが、大いなる喜びを押さえきれなくなってしまったエルキュールは、ついに破顔してしまった。
「ムフフフフフフ♡ 」
頼純とエルキュールは大きな声を上げて笑った。
「ヒャハハハハ‥ ホホホホホ‥ ギャハハハハハ‥ 」
そんなこんなで、頼純の1026年は終わっていったのであった。