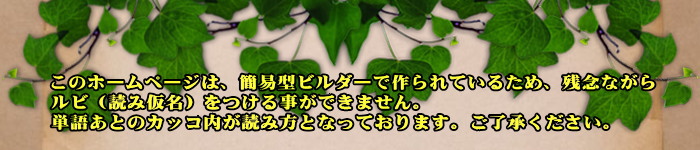
50
1026年 トレノ村・ひなげし食堂(6)
ゴルティエは、3人の老貴族と3人の富豪の両足を次々と切断していった。
彼らの悲鳴や絶叫が一段落する頃、ゴルティエも少々疲れたのか、残りの者達の処分をグラン・レイとプチ・レイに任せ、薪(まき)割り台に腰を下ろした。
血まみれとなった彼は、肩で息をしながら、8人の騎士達の両足が切断されていく様子をぼんやりと眺(なが)めていた。
すでに片足を頼純に斬られていた者は、残った方の足だけですんだが、手を斬られていた者は、さらに2本の足までも失った。
もはや、泣き叫ぶ声さえ聞こえてこない。彼らは声を上げる事に疲れ果て、かすかに呻(うめ)き声を漏らすばかりである。
グラン・レイ達の手際がよかったのか、人食い騎士達はまたたく間に両足を失っていった。
するとゴルティエが立ち上がり、『カラス団(コルブー)』達に声を掛けた。
「よし‥ コイツら全員、中に連れていくぞ! 」
ゴルティエを含めた12人の不良達は、二人で一人の客を抱きかかえ、あるいは引きずって食堂の中へと連れて行った。
切断した26本の足も運び込まなければならず、彼らは二度、三度と往復したため、かなりの重労働となった。
あまりの痛みと大量の失血(しっけつ)に、意識を朦朧(もうろう)とさせている13人の男達は声を上げる事もなく、なされるがままであった。
東の空が少し白み始めていた。
薄明かりの中、頼純はゴルティエ達の行動をジッと観察していた。
彼らは大量に血を浴び、もはや誰が誰なのか判らないほどである。
これほどの残酷な光景は、頼純も久しぶりであった。あたりに立ち込める血の臭いでむせびそうになる。
頼純は、ゴルティエ達が少々やり過ぎたかもしれないとは思っていたが、彼らの行動を止める事もなかった。
それは、彼らとの約束のせいもあったが、救出された子供達がその光景をジッと見ていたからである。
少年達の瞳(ひとみ)に、憐れみの光は微塵(みじん)もなかった。
牢屋のドアの隙間から、仲間が殺され調理されていく様(さま)を、毎日見せつけられた彼らである。
いま悲鳴を上げているのは、その料理を好んで注文し、嬉々(きき)として食べた者達であった。この客達さえいなければ、自分達が誘拐される事もなかったであろう。
そんな少年達にとって、彼らが悲鳴を上げるたび、『ざまぁみろ!』という思いしか浮かんで来ないのである。
邪悪なる悪魔は滅び、聖なる者達が勝利した―――少年らはそう確信していた。
そんな少年達の傍(かたわ)らに立つサミーラだけが、そのおぞましい光景から目を背(そむ)けている。ヒジャブー越しに、口元へと当てられた両手のひらが、微(かす)かに震(ふる)えていた。
やがて男達を運び終わったゴルティエが戻ってくる。彼は、今度は五人の売春婦の元へと向かった。
縛られて地面に正座させられた彼女達は、今度は自分達の番だと思い、大きく身を震(ふる)わせていた。早朝の厳しい寒さも手伝ってか、歯の根が合わず、カタカタとカスタネットのような音を鳴らしていた。
しゃがみ込んだゴルティエは、血まみれとなった顔で微笑(ほほえ)むと、彼女達を覗(のぞ)き込んだ。
いつもなら、ファレーズの娘達から黄色い声を浴びるその美しい顔も、今は殺人者のそれにしか見えない。
「でェ‥ おねえさん達も、あの汚(けが)れた料理を食べたんだよねェ‥?」
ゴルティエは判っていたが、あえて彼女達に質問した。
思った通り、売春婦達は大きく首を横に振り、必死にその事実を否定した。
「い‥ いえ‥ と‥ ととと‥ とんでもない‥! 」
「そそ‥ そ‥ そんな‥ お‥ 恐ろしい事は‥ しておりません 」
「で‥ ですから‥ 何でもします‥! どうか‥ どうか、許してください‥! 」
ゴルティエは、そんな彼女達を安心させるかのように、さらなる笑顔を作った。
「まあ‥ もし、おねえさん達が食べちゃったとしても‥ それは、あの悪魔どもにそそのかされた結果だろうからねェ‥ 愚かな行為だけれど、命だけは助けちゃおうかなァ‥♡ 」
「え!? 」
彼女達は一瞬戸惑い、そのあとに大いに狂喜した。
自分らはあの貴族達とは違い、貧しく卑しい身分の出身である。
いつもならば、まず真っ先にそのような者らから罰せられていくのが、この世の習(なら)いであった。
にもかかわらず、まさか自分らだけが助かろうとは‥ 思ってもみない事態であった。
「ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます‥」
「このご恩は一生忘れません! 」
「何でも言う事を聞きますから、おっしゃってください 」
女達はゴルティエの靴先に何度も何度もキスをした。
ゴルティエは笑顔を張り付けたまま、そう口走る女の顎(あご)を掴(つか)むと、開いた口にナイフを入れた。
「ガッ? 」
スッと手を引くと、口の内側からその頬(ほお)を切り裂いた。
「イギャ―――ア! 」
続いて反対側の頬(ほお)も切り裂く。
両頬(りょうほお)を切り開かれた売春婦は、口が三倍以上の大きさになった。
ゴルティエは、芋虫のように這(は)って逃げようとする女達を捕まえると、五人全員の口を裂いたのだった。
悲鳴を上げる女達は、二目(ふため)と見られぬ恐ろしい顔になっていた。
「これで‥ 今後、お前達に客がつく事はないだろう。 淫(みだ)らな事をして、男を惑(まど)わす事は二度とできネーぞ♡ 」
ゴルティエは冷酷な表情でそう言い放(はな)った。
このような顔では、売春婦として生きていく事はもうできない。彼女達は落ちぶれて、物乞(ものご)いでもするしかないのだ。
それはある意味、殺されるよりも恐ろしい処罰かもしれなかった。
頬(ほお)から空気を漏らしながら泣き叫ぶ女達を尻目に、ゴルティエは改めて食堂の中へと入っていった。
無数の呻(うめ)き声の中、フィリップ夫婦を始め、貴族や富豪達全員がまだ生きていた。
ゴルティエは、仲間に調理場から食用油を持ってこさせ、彼らに振りかけていった。
「もう判っているだろう。 お前達はこれから、焼かれるんだ。 お前達の言葉だと、『ローストする』って言うんだっけ? 焼かれる気分を、タップリと味わって死ね! 」
そう言うと、彼らに松明(たいまつ)を投げつけた。
火は燃え広がり、全員の衣服に点火したが、火力はさほど強くはない。
油が、食用油であり、掛けられた量もそう多くはなかったからだ。
公式の火刑ならば大量の薪(まき)がくべられ、罪人はあっと言う間に強烈な炎に包まれる。その炎や煙によって、気道熱傷や窒息を起こし、熱さを感じる前に死亡するのだ。
だが、彼らは一気に燃え上がらず、洋服や皮膚の表面が燃えているだけなのである。それは、ジワジワと焼き殺されるとてつもない苦しみであった。
「ひ‥ ひぃぃぃぃぃぃぃぃい‥‥ 」
貴族達は最後の悲鳴を絞(しぼ)り出した。
むろん、ゴルティエとてそこまで計算していたわけではない。ただ、男達が悶(もだ)え苦しむ姿を見ながら、殺されていった少年達の無念を思っていた。
そのうち、悪魔らは弱々しい悲鳴さえも上げる事ができなくなっていった。ただ、黒く炭化した彼らの手足が、ゆっくりと動くばかりである。
それが、苦しみもがいての結果なのか、筋肉や腱が熱で縮んでそう見えるだけなのかは判らなかった。
やがて、食堂の建物にも火が燃え移った。
ゴルティエ達は無言でその場から撤退(てったい)した。
勢いよく燃えさかる食堂を後にして、一行は森を脱出する事にした。
すでに、日は昇りかけている。
『カラス団』達は、店の横を流れる川に飛び込み、全身にこびりついた血を洗い流したかった。だが、彼らには拭(ふ)くモノもなければ、着替えも持っていない。ずぶ濡(ぬ)れのままで、寒風(かんぷう)吹き荒(すさ)ぶ森の中を歩くのは、まさに自殺行為となる。
彼らは我慢して、ガビガビと突っ張る顔のまま歩き始めたのだった。
食堂の客達を迎えに来るハズだった船は、けっきょくやってこなかった。いや、来てはみたものの、店の前で繰り広げられる阿鼻叫喚(あびきょうかん)の光景に恐れをなして、逃げ出したのかもしれなかった。
やっと木漏(こも)れ日が差し始めた森の中を、頼純ら一行はトレノ村に向かって歩いていた。
その道中、救出した少年達は一言も口をきかなかった。
『カラス団』達もまた、まったく話をする気分にはなれなかった。
彼らにとって、事件を解決したという達成感や満足感よりも、人を何人も殺してしまったという後悔や不快感の方が大きかったのだ。その鉛のような重く鈍(にぶ)い感情が、胸から腹へゆっくりと沈んでいき、彼らに口を開かせなかったのである。
二時間ほどの道のりを抜けトレノ村まで戻ると、頼純は『カラス団』に火を起こさせ、荷馬車に積んであった材料で少年達に温かい食事を作ってやった。
少年達は満足に食事を与えられていなかったのか、がっつくようにしてパンと野菜のポタージュをほおばった。だが、焼いたベーコンにだけは、けっして手を出そうとはしなかった。
おそらく彼らは、生涯肉を食べる事はできないだろう―――頼純はそんな少年達を哀(あわ)れむ事しかできなかった。
『カラス団(コルブー)』や子供達が食事をしている間、頼純とサミーラは村人に金を払い、頭を下げてなんとか十数枚の布きれを手に入れる事ができた。それを井戸の水で濡らし、ゴルティエ達の顔や手についた血を拭(ぬぐ)わせたのだ。
村人達はあの恐ろしい場所へ行った者達が、血まみれで戻ってきた事に、さらに脅(おび)えているようだった。
「頼純様―――! 」
火をかたづけ、出発の準備をしていると、伯爵親衛隊の騎士・エルルインが声を掛けてきた。ロベールの命により、誘拐犯の逮捕にやって来たファレーズの兵士がやっと到着したのである。
「もう、すべては終わったよ‥‥ 」
頼純は昨夜の状況を彼らに説明した。
それはある程度かいつまんだ話であったが、あまりにも衝撃的な事件の全容に、エルルインら全員が絶句してしまった。それほどに、おぞましく、悲惨(ひさん)な事件だったのである。
他人であるエルルインらがこれほどのショックを受けるのだ。ましてや、子供を食われた親達にこの事態をどう説明すればよいのか、頼純はますます気が重くなった。
一行がトレノ村を出発し、街道に出る頃、誘拐された少年達の親もやって来た。
誘拐された少年達の半分以上は親のない子であったが、それでも押しかけてきた母親や父親、兄や叔父で、一行は100人ほどにもなっていた。彼らは誘拐犯と戦うタメ、みな棒や斧(おの)、鎌などで武装をしている。
頼純は彼らに、子供達のほとんどが殺された事を伝えたが、食べられた事までは言わずにおいた。親達の心の傷をより深くしないタメの配慮(はいりょ)でもあったが、やけになった彼らが暴動を起こす可能性もあったからである。たとえ平民であっても、武装した100人となれば十分な脅威となる。
頼純は、子供達が食べられた事の報告は、後日改めてする事にした。
生き残った子供と対面できたわずかな親達は、彼らを抱きしめ、安堵(あんど)の涙を流した。一方、子供が死んだことを聞かされた親達は、地面に崩れ落ち、悲嘆(ひたん)の涙を流し続けたのだった。
一行は夕方近くになって、やっとファレーズに戻ってきた。
すでに、親衛隊によって連絡が入っており、教会の鐘と街中の人々が彼らを出迎えてくれた。
しかし、たくさんの子供を失った街は、頼純や『カラス団(コルブー)』達の行動を讃(たた)えながらも、大騒ぎする雰囲気ではなかった。
ただ、事件が解決し、誘拐犯が成敗(せいばい)された事を感謝するのみであった。
ゴルティエら『カラス団』は、顔や手、頭髪までは洗ったり、拭(ふ)いたりしたものの、その衣類には大量の血液が染み込んでいた。
全員が黒い衣装なので、色はまったく目立たなかったが、臭いの方はいまだに物凄(ものすご)い悪臭を放(はな)っていた。
頼純はそんな彼らを引き連れて、そのまま城へと向かったのである。事件について伯爵に報告するためであった。
ゴルティエはいったん家に帰り、着替えをしてから伯爵の御前(ごぜん)に立ちたかったが、頼純はそれを許さなかった。
「これでは、伯爵様に失礼なのでは? 」
不安げな顔で尋(たず)ねるゴルティエに、頼純は頭(かぶり)を振った。
「いや、それは違うね。 こういう事は真っ先に報告する事が大切なんだ。 それにお前達が汚れてる事、臭い事は仕事をした証(あかし)だ! 何を恥じる事がある 」
『カラス団(コルブー)』達はそんなものかと納得して、頼純の後ろについていった。
城の門番達は彼らが放(はな)つ悪臭にあからさまに嫌な顔をしたが、それでも止められる事はなく、一行は広間へと通されたのであった。
広間の扉が開かれると、すでに玉座(ぎょくざ)に着いていたロベールが立ち上がり、頼純達の仕事をねぎらった。
「ヨリ殿‥ 弟御(おとうとご)、そしてそのお仲間達―――本当にご苦労様でした 」
『カラス団』達は、ロベールの姿を見るや、慌(あわ)てて床に跪(ひざまず)いた。
ロベールは着座するなり、頼純に矢継ぎ早に質問をしてきた。
彼には、親衛隊の早馬によって、すでに事件の概要が説明されている。街の人々とは違い、少年達が喰われた事も知っているのだ。
「報告に寄れば、誘拐された子供達は悪魔どもに食い殺されたと言う事でしたが―――それは事実なのでしょうか? 本当に、子供達は食べられてしまったのですか? 」
『カラス団』達がジッと頭(こうべ)を垂れる中、立ったままの頼純は苦虫を噛(か)み潰(つぶ)した顔で頷(うなず)いた。
「ああ‥ ざんねんながら、それは間違いねェ。 助かった少年達もその事について証言するだろう 」
その信じられない凶悪な事件に、ロベールは困惑していた。
「その悪魔どもは、いったい何者なのです? 本当に悪魔なのでしょうか?」
「奴らが、アンタらの言う『悪魔』かどうかは、俺にも判らない。 そこには宗教観が含まれてるからな。 ちなみに、俺の国ではあのような者達を『鬼』と呼んでいる 」
「それで‥ ヨリ殿はその者達をすべて退治してくれたのでしょうか? 我が領内にもう悪魔はいないと思われますか? 」
「俺達はそこにいた全員を焼き払ったが‥ この国の人食いどもがすべて、昨夜あの場に集まっていたワケじゃネーだろう‥!? まだ残っている可能性はあるネ 」
「なるほど‥ 」
頼純はけっして嘘はつかなかったが、すべてを語る事もなかった。
「ただ‥ 奴らはファレーズ領の外から船で来てたようだ。 そして、食堂も料理人も燃えてなくなってしまった今‥ そんな恐ろしい料理を提供する店は当分できないだろう。 つまり、人食いどもがこのファレーズを訪れる事もないと思う! 」
ロベールはさらに核心に触れる事を聞いてきた。興味もあったのだろうが、領主としては当然の質問であった。
「で‥ 奴らはいったい何者なのです? 悪魔といえど、人の姿に化けていたのでしょう!? どういう人物になりすましていたのですか? 」
だが、頼純は小さく首を振った。
「さぁねェ‥ けど、伯爵さんは細(こま)けェ事は知らネー方がいい。 結果がよくても悪くても、厄介(やっかい)な立場になる可能性があるからな 」
しばらくの間、ロベールは頼純のことを見詰めていたが、やがてその意味を了解したようだった。
「たしかに! では‥ ひとまず、事件は解決したと言う事で――― 」
頼純は厳しい表情で付け加えた。
「とは言え‥ 今後は誘拐や失踪(しっそう)には、十分気をつけた方がいい。 人がいなくなる事を当然だとは思わず、何かの事件の前触れだと考えるようにした方がいいんじゃネーのか‥ 」
ロベールはその言葉に大いに反省していた。
「おっしゃる通りです。 本日生きて帰ってこれた16人の少年達も‥ 私が最初言ったように、来月になってから捜索を始めていたら―――みな食べられていた事でしょう。 まず私が立ち上がるべきだったのに‥ 本当に恥ずかしい限りです 」
「そういう事だな‥ 」
頼純もしばらくは、心の底から笑えそうになかった。あまりにも残虐な事件に、あまりにも凄惨(せいさん)な決着をつけたからである。
玉座(ぎょくざ)を前に、立て膝をついて跪(ひざまず)くゴルティエらへ、ロベールが声を掛けた。
「弟御(おとうとご)とそのお仲間達も、どうかお顔をお上げください 」
その言葉に、ゴルティエらは恐る恐る伯爵へと目を向けた。
ロベールは玉座(ぎょくざ)から下(お)り、不良達の前に進み出ると跪(ひざまず)き、ゴルティエの手を握(にぎ)った。
「今回の事件の解決はみなさんのお陰でした。 本当にありがとう 」
「い‥ いえ‥ 」
貴族である伯爵から手を握(にぎ)られたゴルティエは大いに感動していた。
ロベールはその後も、『カラス団(コルブー)』達の一人一人に言葉を掛けていった。
貴族から見れば平民など―――ましてや、自分達のようなチンピラ風情ではなおの事―――道に落ちているゴミや石ころと同じように扱(あつか)うのが普通である。
さらに、今日の自分達はとんでもない悪臭まで放(はな)っているのである。
にもかかわらず、伯爵は嫌な顔ひとつせず、その汚い手を握って『ありがとう』と感謝の言葉を掛けてくれたのだ。
それは、不良達にとってあまりにも恐れ多い事で、彼らの頭の中をグチャグチャにしたり、ボーッとさせたりしていた。
激しく感動する不良達の中には、涙を浮かべる者さえいるほどだった。
「ところで‥ 褒美(ほうび)についてなんだけどさ――― 」
唐突に頼純が口を開いた。
「え!? 」
「ちょっといいかな 」
頼純はロベールのマントの裾(すそ)を引っ張って、彼を『カラス団(コルブー)』達から少し離れたところへ連れて行った。
そこで、何やらヒソヒソと話し始めたのである。
その言動に、ゴルティエは大いに驚き、かなりガッカリしていた。
頼純が、このような深刻な報告をした直後に、報償(ほうしょう)を要求するような人物だとは思っていなかったからである。しかも、自分達には内緒で交渉(こうしょう)をしている。いったい幾(いく)ら貰(もら)うつもりなのだろうか‥?この人もしょせんはがめつい男だったのかと―――
「ふんふん‥ なるほど‥! 」
ロベールは、『カラス団(コルブー)』達の方をチラチラと見ながら頷(うなず)いている。
「わかりました! 」
やがて、ロベール伯爵はニッコリと微笑(ほほえ)んで、頼純の要求を呑(の)んだのであった。