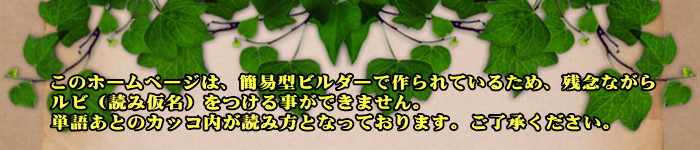
45
1026年 トレノ村・ひなげし食堂(1)
「まだかよ‥!? 」
藪(やぶ)の中にひそんでいた『カラス団(コルブー)』達も、そろそろしびれが切れる頃だった。
食堂の様子を確認しにいった頼純とゴルティエが、建物の裏手に回り込んでから、すでにかなりの時間が経っていた。
遠くの教会が知らせる終課(しゅうか)の鐘もずいぶん前に鳴り終わった。
一同の心に不安だけがジリジリと募(つの)っていく。
その苛立(いらだ)ちが、彼らの腰につけられた皮袋をよりいっそう重くしていた。
袋の中には十数個の小石が詰められている。頼純に命令され、森へ入る前に拾わされた石だった。
彼らは頼純から、『敵と遭遇(そうぐう)したら、ナイフや剣での接近戦ではなく、距離を取ってみんなで一斉に礫(つぶて)を投げろ』と指示されていた。
そこいらのゴロツキと喧嘩して勝ったぐらいの腕前で、調子に乗って訓練を受けた剣士の前に立とうものなら、あっと言う間に斬り殺されてしまうからだった。
そして、彼らは不良のクセに、頼純の言葉をちゃんと守っていた。それぐらい、頼純の事を尊敬しているのだ。
『カラス団(コルブー)』の面々は、意外にも心根は純粋なのであった。
一方、頼純を尊敬するあまり、その言葉を破ろうとする者もいた。
心配が極限にまで達したサミーラである。彼女は頼純の指示に背(そむ)き、行動する事を決意した。
藪(やぶ)から飛び出したサミーラは、身を低くして『ひなげし食堂』の建物へと走った。
建物の壁まで辿(たど)り着いた彼女は、施錠(せじょう)されていない鎧戸(よろいど)がないか、一個一個静かに確認していく。すると案の定、一つだけ鍵をかけ忘れた鎧戸(よろいど)があった。
サミーラは彼女の武器である小柄(こづか)(小さなナイフ)を使って、その鎧戸(よろいど)を少し開けた。内側は窓となっており、牛の角(つの)を薄くスライスした板が何十枚も張り付けてあった。
彼女はまず壁に耳を当て、中の様子を窺(うかが)った。
「こりゃうまい 」
「この店のロースト肉は絶品だな 」
「この茹(ゆ)でたヤツも、肉汁ソースをタップリつけると、ほっぺが落ちそうに美味い 」
「キャハハハハハ 」
などと、十数人の男女の声がした。
サミーラは小柄(こづか)の切っ先を使って、ガラス替わりの角板(つのいた)をほじった。角板(つのいた)は窓から脱落する事なく、そこに小さな穴が穿(うが)たれた。
サミーラはその穴から食堂の中を覗き込む。
そこには、やはり13人の男と5人の女がいた。
彼らは3,4人づつに別れて、5個のテーブルに坐っている。
男達は全員身なりがよく、貴族や富豪だと思われた。女はみな男達にしなだれかかり、下品な嬌声(きょうせい)を上げている。おそらくは売春婦かそれに準じる職業の者達であろう。
だが、いくら探しても、その室内に頼純やゴルティエの姿はなかった。
室内は、それぞれの柱に取り付けられたローソクと、各テーブルに1本づつ置かれたローソクしかない。そのため、サミーラの位置からは暗くてよく見えなかったが、彼らは手づかみで肉をむさぼり食っているようだった。
それは、いつもの食事風景である。
だが、暗くて彼らの詳細がよく見えないにもかかわらず、その光景は彼女を不快にさせるに十分であった。
それは、彼らが放つ『あさましさ』のせいであろうか。
食事に興じて楽しそうに笑う彼らは、高貴な人々であろうにもかかわらず、その顔が豚や野良犬のような『獣』にしか見えないのであった。
× × × × ×
「ウ‥ ウウ‥ ウウウウ‥ 」
頼純はやっと意識を取り戻した。
どれだけ気を失っていたのか判らない。
前方を見るため顔を上げようとすると、後頭部がズキズキと激しく痛んだ。先ほど殴られた所であろう。
さらに、胸がむかつき吐きそうになった。強烈に胃の内容物が押し上げられる。
頼純は、これも殴られた後遺症かと思った。しかしすぐに、それがとてつもない悪臭によるものだと気づいた。それはまさしく戦場の臭いだった。血と脂(あぶら)と糞尿の臭いが混ざった悪臭である。
その時になってやっと、自分の両手首が縄で縛られ、蓑虫(みのむし)のようにぶら下げられている事にも気づいた。
頑丈(がんじょう)に縛られた手首の縄が、鉄製のフックに引っ掛けられ、その先についた縄で天井の梁(はり)からぶら下げられているのだ。
足首もしっかりと縛られている。
ふと右横を見ると、3ピエ(約90センチ)ほど先に、同様の姿となったゴルティエがいる。彼はまだ気を失ったままであった。
周囲はかなり暗い。
だが、目が慣れてくると、先ほどの暗黒とは違い、徐々に室内の様子も判ってきた。
前方はかなり明るかった。
10ウナ(約12メートル)ほど先に大きな作業台があり、そこに燭台(しょくだい)が三台も置かれているからだった。
それぞれの燭台(しょくだい)には蝋燭(ろうそく)が三本ずつ立てられており、作業台は9本もの蝋燭(ろうそく)で照らし出されているのである。高価な蜜蝋(みつろう)の蝋燭(ろうそく)を9本も使うというのは、よほどの事であろう。
その作業台では、こちらに背を向けた男が何やら一心に仕事をしている。
頼純は腹筋を使って、縛られた両足をもたげると、隣にぶら下げられたゴルティエを数回蹴った。
「ア‥ アア‥ ア‥ 」
ゴルティエはやっと意識を取り戻したが、まだぼんやりとしている。事態が飲み込めてないようだった。
頼純は彼に声を掛けようとして、はじめて自分の口に猿ぐつわがはめられている事に気づいた。
何もかも気づくのが遅い。頼純自身もまだ覚醒(かくせい)しきれていないのであろう。
その時、ガスンッと大きな音が作業台の方から聞こえてきた。
蝋燭(ろうそく)に照らし出されたモノは、ナタのような巨大な包丁である。
作業台の男は振り上げた包丁を台に叩き付け、何かを切断しているようだった。
頼純は嫌な予感がした。
とんでもない恐怖が、下っ腹に重く溜(た)まっていく感じだった。
何度かガスンガスンと音が響くと、作業台の男は移動し、左手にしたモノをグツグツと煮立った鍋に、右手のモノをフライパンに入れた。
コンロはおろか、暖炉(だんろ)もない時代である。
調理は、土間の床に作られた『炉(ろ=囲炉裏)』で行(おこな)われる。
このような食堂ともなると、大きくてしっかりとした『炉(ろ)』が切られていた。
『炉(ろ)』には二つの焚(た)き口があり、それぞれに薪(まき)がくべられている。一つの焚き口には、フックにぶら下げられた大鍋が掛けられており、もう一つの焚き口には五徳(ごとく)が置かれて、その上にフライパンが載せられていた。
そのフライパンから、ジュージューと肉の焼ける音がし、いい香りが漂(ただよ)ってくる。
ここは『ひなげし食堂』―――料理を作るのは当然である。
だが、その肉の焼ける香りは、頼純の胃にあった内容物を一気に口まで上昇させた。そして、それが猿ぐつわで堰(せ)き止められたのだ。頼純の口はゲロでパンパンになってしまった。
このままでは、吐瀉物(としゃぶつ)が鼻や気管に逆流し、窒息してしまうかもしれない。頼純は頑張って、それをもう一度呑(の)み込むしかなかった。
本当は、男が何をしているのか、頼純もなんとなく判っていた。
ただ、そんな恐ろしい事を認めたくなかったのだ。
しかしながら、男がそれを確信させる行動にでた。
作業台に戻った男が何かを持ち上げたのだ。
それは切断された人間の『腕』にしか見えない。それも小ぶりの『右腕』である。おそらくは、誘拐された少年の『右腕』なのだろう。
それでも、頼純は―――男が、殺してしまった少年の遺体を埋めやすくするためにバラしているのだ―――と思い込みたかった。
ただ、現実がそうでない事も知っていた。
男は少年を『調理』しているのである。
そして、ここの客達はそれが人間である事を知りながら―――その料理を『喰(く)っている』のであろう。
気がつけば、作業テーブルの隅には、少年の頭部らしきモノも載(の)せられていた。
それは、とてつもなくおぞましい世界だった。
幼い少年を喰(く)らうなど、頼純には絶対に許せる事ではない。
頼純は、込み上げる激しい怒りで荒くなる呼吸を、何とか調(ととの)えようとつとめていた。
その時、左側奥の扉が開かれ、中年の女が入ってきた。ジョアンであろう。
「モンデール伯爵様のテーブル‥ 内臓の煮込みを二つと、股肉(ももにく)のステーキを追加で! 」
「あいよ! 」
注文を告げたジョアンは頼純の方を振り返った。
彼女は作業台にあった包丁を握ると、頼純に近づいてくる。そのエプロンは血まみれであった。
頼純はいつからか、『やめろ―――おッッ‼』と言葉にならない叫び声をあげ続けていた。
そして、そんな事にも気づかせないほど、彼の怒りは頂点を突破していたのだ。
ジョアンは、あちこちに飛び散った血が乾き、黒い斑点(はんてん)となった顔で頼純を覗(のぞ)き込み、微笑(ほほえ)んだ。
「おやおや‥ お目覚めかい♡ 」
そう言いながら頼純の猿ぐつわをはずしてくれた。
頼純は、いまだ口の中に半分ほど残っていた吐瀉物(としゃぶつ)を吐き出すと、怒りに充ち満ちた目でジョアンを睨(にら)んだ。
「き‥ 貴様たち‥ 許さんぞ! 絶対に許さん‼ 」
ジョアンは残忍な目で頼純を見詰めながら、包丁を振り上げた。
「今のお前に何ができる? それとも、すぐさま料理してほしいのか!? 」
すると、作業台から怒声が飛んだ。亭主のフィリップである。
「バカ野郎! そんな親父‥ 固くて、材料にゃなりゃしネーよ! 隣の兄ちゃんも一緒だ! バラして川に捨てるしかねえ! 」
「そんなコタァ、判ってるさ。 ただ、あまりにもうるさいから、喉(のど)だけでも掻(か)き切っておこうかと思ってさ――― 」
「もう‥ そんな事はいいから、早く手伝ってくれ! フランソワ様の料理‥ ローストの準備だ! 」
「はいはい‥ 」
ジョアンは作業台の方に戻っていった。
頼純は傍(かたわ)らを振り返った。
「ゴ‥ ゴルティエ‥ 大丈夫か‥? 」
「‥‥‥ 」
彼は意識はハッキリしているようだが、この地獄のような光景に衝撃を受けていた。大きく目を開いたまま、さばかれていく少年の死体を見詰めている。
「ローストの準備が終わったら‥ 次の材料連れてこい! 急がねーと、注文さばききれネーぞ! 」
「待っとくれよ 」
ジョアンは奥中央にある扉を開けるとその中へ入っていった。
中は牢になっているようで、『助けて! 』『許してください 』『ゴメンなさい 』『神様、神様、神様‥ 』などと懇願する少年達の声が聞こえてくる。十数人の少年達が捕らえられているようだった。
ジョアンは、一人の少年の髪を掴(つか)んで連れてきた。彼の両手は前で縛られている。
「やめて‥ いやだ! 殺さないで! ボクを食べないで! 」
まだ、十歳にもならないであろう少年が、狂ったように泣き叫んでいる。
フィリップはその声を無視して、砥石(といし)を掴(つか)むと大きな肉切り包丁の刃を研(と)ぎ始めた。
叫ぶ少年をジョアンがなだめる。
「安心おし! 痛いのは最初だけさ。 苦しませずに、すぐに死なせてあげるからね 」
「いやだいやだいやだ‥ 食べられるのはいやだ! 」
そんな少年の声を無視して、ジョアンは彼の服の背中を包丁で切り裂くと、素っ裸にした。
そして、暴れる少年をフィリップと二人で作業台に載(の)せ、押さえつけたのだ。
「やめろォ―――オッッ‼ 」
頼純が絶叫を上げた。