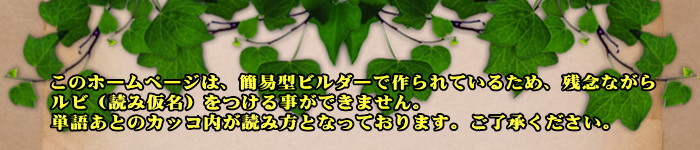
42
1026年 ファレーズ・フルベール邸
それから三日間、『カラス団(コルブー)』の不良達は、様々な場所の様々な人々―――およそ千人ほどに話を聞き、そこから得られた情報は百件にも登った。
集められた目撃情報はすべて頼純に報告され、壁に書かれていく。
だが、その情報がどこまで正確であるかは、はなはだ疑問であった。
なにせ、紙のない時代なのである。
不良達は、聞き込みをした情報を記録する術(すべ)がなかった。
一応、全員に蝋板(ろうばん)は持たせていた。学生が使う蜜蝋(ワックス)を塗った板で、それを尖筆(せんぴつ)で引っ掻いて文字を書き残すのである。
だが残念な事に、彼らは全員文字が書けなかったのだ。
それゆえ、けっして賢くはない『カラス団(コルブー)』達は、聞き込んだ情報をそれぞれの頭に記憶するしかなかった。
数字ならば、一から十くらいまで書ける者も4人に一人ぐらいはいた。 だが、その数字もアラビア数字(0、1、2、3、4、5‥‥イスラーム社会からヨーロッパに伝わったタメ、こう呼ばれるが、実際に作ったのはインドである)ではない。ややこしい、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ‥‥で、0の概念はない)であった。
また、目撃者達が証言する時間も、教会や修道院が鳴らす鐘の音(ね)が基準である。
この時代、社会の『刻(とき)』を管理しているのは教会だったのだ。
教会や修道院では日々、『朝課(ちょうか)』、『賛課(さんか)』、『一時課』、『三時課』、『六時課』、『九時課』、『晩課(ばんか)』、『終課(しゅうか)』という八つの祈祷(きとう)が行われており、そのつど鐘が鳴らされていた。
一般の人々はこの鐘の音(ね)を聞いて、『刻(とき)』を知ったのである。
だが、この鐘は一定の間隔で鳴らされているわけではなかった。
ローマ時代からの習慣に基づき、日の出から日の入りまでの『昼』を12等分し、日の入りから次の日の出までの『夜』を12等分して『刻(とき)』を決めていたのである。
つまり、季節や場所によって『刻(とき)』は違うのだ。
夏は『昼』の『刻(とき)』は長く、夜のそれは短い。反対に、冬には『昼』のそれは短く、夜の『刻(とき)』は長くなるのだ。
また、北へ行けば行くほど、その差は大きくなる。
スカンジナビアの北部などでは、夏はほぼ『夜』がなく、冬はほぼ『昼』がなくなる。
教皇領ローマとノルウェー王国のオスロでは、同じ日時であっても、鐘の鳴る『刻(とき)』がまったく違う事になるのだ。
こうした時刻制度を『不定時法』と呼ぶ。
だが、この『不定時法』であっても、一年中同じ時刻に鳴らされる鐘があった。『六時課』の鐘である。この鐘だけは、太陽が真南にきた時(正午)に鳴らされるからである。
人々は、日の出に鳴らされる『賛課(さんか)』の鐘とともに仕事を開始し、日の入りに鳴らされる『晩課(ばんか)』の鐘で仕事を終え、家路についた。
こうした『不定時法』による時鐘は、機械式時計と連動されるようになる14世紀まで続くのであった。
というわけで、目撃者達の証言も正確ではなく、それを聞き取った『カラス団(コルブー)』の面々の記憶はさらに怪しかったのだ。
それでも、頼純はそれらの目撃情報を、真っ白な壁が真っ黒になるくらいまで書いていった。
初日に女中からの報告を聞き、すっ飛んできたこの家の主(あるじ)フルベールは、真っ青な顔で汚(けが)された壁を見詰めていたが、頼純が顔を出すと、引きつりながらもニッコリとほほえんでその場を立ち去った。
それ以降、彼は一言の文句も言う事はなかった。
頼純はあらかたの情報を書き終えると、今度はそれを横の壁に時間別に並べ直して書いていった。
こうして、行方不明になった少年達が、それぞれ最後に見かけられた時間を割り出していくのだ。
その結果、少年達が最後に見かけられたのは、『九時課』の鐘の後、『晩課(ばんか)』の鐘が鳴る前に集中している事が判った。日没前の夕方頃という事だ。
つまり、この時間帯に少年達を見た者が、彼らの最後の目撃者と言う事になる。
頼純はその証言をした二十人ほどの目撃者一人一人に会いに行く事にした。
翌日は、サミーラとゴルティエ、『カラス団(コルブー)』達を引き連れて、早朝から街へ聞き込みに回った。
最初に行ったのは、パン屋のジュールの店だった。彼の妻・ソフィーが、行方不明になった少年ラウルの最後の目撃者という事になっていた。
「その時、何か見ませんでしたか? なんでもけっこうです 」
頼純の問い掛けに、ソフィーはパンをこねながら宙をぼんやりと見詰め、その時の光景を思い出そうとしていた。
「いえ‥ とくに何も‥‥ ごめんなさい、あまり憶(おぼ)えていなくって‥ 」
「おい‥ 椅子! 」
頼純は、グラン・レイモンから渡された椅子に彼女を坐らせると、『カラス団(コルブー)』達に静かにするよう命じた。
「目をつむって、ゆっくりと深呼吸を5回してください‥ 」
「はい‥ 」
ソフィーは彼の言葉に従って、深呼吸をした。
「次に‥ 最後に見たラウルの姿を思い浮かべてください‥ 」
「はい‥ 」
「では‥ その周囲に何か見えませんか‥? 」
これは催眠術ではない。ただ、気持ちを落ち着かせ、彼女を集中させているだけである。
「ああ‥ 思い出した‥! 」
ソフィーは頭に浮かんだ映像をゆっくりと語り出した。
「あの時は‥ 隣のおばあさんが、猫を抱えてパンを買いに来て‥ その後ろを酒場のポールが卵の入ったカゴを抱(かか)えて走っていきました。 あと、馬車が止まっていたかな‥‥? 酒樽(さかだる)を積んだ馬車よ 」
その言葉をサミーラが蝋板(ろうばん)に書き留めていった。ペルシャ語である。彼女はまだフランス語もラテン語も書く事が出来ないのだ。
「‥‥‥ほかには、ありませんか? 」
頼純の問いに、ソフィーは目を開き、首を横に振った。
「覚えているのは、それくらいね 」
頼純は彼女に丁寧(ていねい)にお礼を言った。
「ありがとう。 お陰でたいへん参考になりました。 」
一行はパン屋を後にし、次なる目撃者モーリスの元へと向かった。
モーリスは大工である。
頼純達が工場を訪(たず)ねると、彼は手斧(ちょうな)で木を削っているところだった。
「ちょっと、お伺(うかが)いしたい事があるのですが‥ 」
頼純が声を掛けると、
「なんでい! こちとら忙しいんだ。 早いとこすませてくんな! 」
彼は返事をしながらも、仕事の手を止めようとはしなかった。
「ちょっと、手を止めて‥ こちらに目を向けていただけますか 」
「やなこったい! 伯爵様からのご命令で、大量の注文をこなさなきゃならネーんだ! ホレ、農民達に配る鍬(くわ)だよ。 その柄(え)を作ってんだ。 急がネーと、オイラが鍛冶屋(かじや)から文句を言われちまうんだぞ 」
モーリスは、たくさんの木くずを頭から被(かぶ)りながら、そう答えた。
傍(かたわ)らでは、弟子達が丸太にハンマーで楔(くさび)を打ち込み、木を裂(さ)いている。
工場だから当たり前なのだが、うるさくてしょうがない
そんなモーリス達の手を止めさせるため、頼純は大きな声を上げた。
「これはファレーズ領主・ロベール伯の命(めい)である! 最優先事項と心得(こころえ)よ! 速(すみ)やかに手を止め、我が問いに答えるのだ! 」
モーリスも弟子達もギョッとした顔で頼純を振り返った。
やっと工場は静寂(せいじゃく)に包まれたのだった。
頼純は先ほどと同様に、モーリスを腰掛けさせると、目をつむらせ、深呼吸をさせてから、静かに尋(たず)ねた。
「アナタはピエールを先週の土曜日に見かけたそうですが‥ その時に何か気づきませんでしたか? 何かを見ませんでしたか? 」
モーリスはしばらくの沈黙の後に、ポツリポツリと言葉を漏らし始めた。
「あの子は、あの井戸の縁(ふち)に腰掛け、うちの仕事場をしばらく覗(のぞ)いていた‥ 」
モーリスが指差す方を振り返ると、店の前にある広場の中央に、共用の井戸が設(もう)けられていた。彼の位置からは10ウナ(約12メートル)はあるだろう。
「それから、大きな男がやって来て‥ そいつと一緒にどっかに行ったよ 」
「他には? 」
「靴屋のエマニエルが、仕入れた革を運んでた気がする 」
「その日、ピエールを見たのはいつ頃でしたか? 」
「そうだな‥ 『晩課(ばんか)』の鐘が鳴った後だったと思う。 鐘の音(ね)で、そろそろ店じまいにするかと顔を上げた時だ 」
「つまり、日没後って事ですね!? だとしたら、かなり暗かったと思いますが‥ あの距離で顔まで見えましたか? 」
「たしか‥ 月が出てた―――? そう、教会の鐘楼(しょうろう)の横に月が出ていて、その月明かりで見えたんだと思う‥ 」
「そうですか‥ わかりました。 ありがとう 」
そう言って、頼純は大工の作業場を後にした。
ゴルティエとプチレイは、頼純を慌てて追い掛けてきた。
「もう終わりですか? もっと聞く事があるんじゃないのですか? 」
「弟・ピエールの貴重な証言なんです。 もっと、ちゃんと質問してください 」
「残念だが、あの大工はピエールを見ていない。 」
「どうしてです? 彼がウソを言ってるとでも‥? 」
「いや‥ 見間違えたんだろうな。 あの忙しさだ。 作業に集中し、俺達が声を掛けても顔を上げないほどの状況だぞ。 周囲の事に注意を払う余裕などなかったはずだ。 」
「けど‥ 」
「さらには‥ 日没後の薄暗い中、10ウナ(約12メートル)も離れた井戸に坐る子供の顔が見えるわけがない 」
「しかし、月が出てたって‥! 」
「いいか‥!? 教会は井戸の背後にある。 その日が満月だったとしても、ピエールの顔は影になって見えなかったはずだ 」
「でも‥ 目がよければ―――」
「あの日は曇りだったんだよ。 教会の記録でも確認した。 だから、月が見えるハズはないんだ! 彼が月を見たと言う事なら、それは違う日と勘違いしてるって事さ 」
二人には返す言葉がなかった。
頼純はさらに付け加えた。
「ちなみに、その日の月は‥ 教会の記録によると、新月だったそうだ! 」
頼純は、昼間『カラス団(コルブー)』達が情報を集めている間、前日に彼らが集めてきた情報の裏を取っていた。
ゴルティエは取って付けたかのような笑顔を作ると、頼純を褒(ほ)め称(たた)えてみせた。
「な‥ なるほど‥ 素晴らしい推理と検証ですね! 」
ウソ臭いゴルティエの態度に、頼純は冷たい視線を返すばかりであった。
頼純達はさらに数人の目撃者らを回り、ファレーズでは最後の証言者となるジョゼフ爺さんの家へと向かった。
町外れに住む彼の家はたいへん小さいので、『カラス団(コルブー)』達は外で待たせ、頼純とサミーラ、ゴルティエとで尋(たず)ねる事にした。
中に入って声を掛けると、裏庭から返事があった。三人がそちらへ回ると、ジョセフは小さな菜園を耕(たがや)していた。
「セザールを見た日の事かい? そうじゃなァ――― 」
切り株に腰を下ろしたジョセフは、立てた木の鍬(くわ)の柄の尖端に両手を乗せた。そして、その上に白い髭(ひげ)に覆(おお)われた顎(あご)を乗せると、静かに目を閉じる。
「あれは、10日ほど前の事じゃった。 ワシが隣村に住む甥(おい)の結婚式から帰ってくると、街の入り口にある大きな岩の上にセザールが坐っておったんじゃ。『九時課』の鐘の後じゃった 」
70歳を超えたジョセフは、シワだらけの顔で語った。
「坊主、なにしとるんか?―――と尋(たず)ねたら、出稼(でかせ)ぎに行った父親の帰りを待っていると、寂(さび)しそうに言うておった 」
「その時、何かを見ましたか? 奇妙に思った事は―――? 」
頼純の問いに、ジョセフ爺さんは
「いや‥ ナーンにも‥! 空の高いところをトンビが舞っておったくらいじゃ。 あとは、樽を積んだ馬車も通ったかのォ‥ 」
その言葉に頼純の動きが止まった。
「ほう‥ それで――― 」
「それだけじゃ‥。 あとはナンも見とらん 」
ジョセフからこれ以上何も聞き出せないと判断した頼純は、お礼を言って家を出た。
ジョセフの家を出ると、ふたたび『カラス団(コルブー)』を引き連れて、次なる目撃者に会うべく、街道へと向かった。
スタスタと早足で歩く頼純に、ゴルティエが声を掛けてきた。
「いや‥ あの爺さんはボケてるって事で有名ですから‥ あんな証言はアテになりませんよ! そもそも、この時期に畑を耕(たがや)すなんておかしいじゃないですか。 こんな冬場に、いったい何の種を蒔(ま)くっていうんです? あれこそが、爺さんがボケている証拠ですよ! 」
追いすがってくるゴルティエを頼純はチラリと振り返った。
「もし、ジョセフ爺さんが人を殺して‥ その死体を埋めようと、穴を掘っているのだとしたら? 」
「え‥? 」
「畑を掘っているからって、それが農作業とは限らないだろう!? 人は誰しも不可思議な行動をとる。 それを、自分の常識や先入観で判断すると、間違った結果しか導き出されないぞ 」
「けど‥ 」
「今日のジョセフ爺さんの話はすべて理屈が通っていた。 だったら、それが真実かどうかは、後で判断すればいい 」
「は‥ はい‥ 」
ゴルティエは苦々しい表情で頷(うなず)いた。
街を抜け、街道を歩き始めると、吹きすさぶ風がかなり寒い。すでに12月半ば、完全に冬である。
頼純がブルッと体を震わせると、サミーラは肩から提(さ)げた物入れから長い毛織物を取り出し、それを首に巻き付けてくれた。お陰で、首から胸元が温かくなり、寒さもずいぶんと和(やわ)らいだ。
サミーラは頼純の首に襟巻きを巻きながら、『カラス団(コルブー)』に判らないようソグド語で話し掛けてきた。
「何か、お考えがあるのですか? 」
「え!? 」
「彼らに何かを教えようとなさっているのでしょう? 」
「そうだな‥ ちょっと考えている事はあるかな‥ 」
薄笑いを浮かべながら、頼純もソグド語で答えた。
「まあ‥ あまり性急に事を進めず、ゆっくりと教えていかれては――― 」
「そうしたいところだが‥ 我々には時間がない。 いつリスボンへむけて、出発するか判らないのだからね 」
「そうでした 」
「それに、彼らは思ったよりもずっと覚えがいい! 大丈夫さ 」
「そうですか。 それはよろしゅうございました♡ 」
北のオービニー村から南のコルデ村まで聞き込みを終え、最後が東のラ・オゲット村の鍛冶屋コンラドだった。
「そうかい‥ また、子供がいなくなっちまったんだ‥‥ 」
彼は仕事の手を止め、作業用の分厚い皮手袋を外しながらつぶやいた。
「それでも‥ 騒がれてるのはほとんど親のいる子供ばかりだ。 孤児(みなしご)達は捜してさえももらえネーからなァ‥ 俺も孤児(みなしご)だったが‥ そりゃ寂(さび)しいモンよ‥! 」
頼純が質問せずとも彼は語り始めた。
「アルベールは火花が好きでな‥ よくここへ来ては、真っ赤に焼けた鉄を俺がハンマーでトンカン叩くところをじっと見ていたよ 」
作業台に尻を乗せたコンラドは、革エプロンについた火玉カスを払いながら孤児アルベールの話を続けた。
「あの日は、『晩課(ばんか)』の鐘が鳴る前までここにいたっけ。 腹が減ってるみたいだったから、弁当の残りをやったら、美味そうに喰ってやがった。 それから、『また明日♡ 』って帰っていったんだ。 あの子は、森の中に一人で住んでるって言ってたかな‥ 」
『カラス団(コルブー)』の中にも孤児出身者が半分ほどいたので、急にしんみりとしてしまった。
頼純は穏やかな声で質問した。
「その時に、何かを見ませんでしたか? 」
コンラドは宙を見詰めて、ゆっくりと答えていった。
「かなり暗くなっていたが‥ 役人がまだ4、5人いたなァ。 なんでも、台帳を作るとかで―――お城のお偉いさんだ 」
頼純はそれに頷いた。
「ティボーのおっさん達だな!? この村に来たのは、その日に間違いない。 他には? 」
「あとは‥ たしか、農夫のブノアとトビーがつるんで酒場に行っていた‥‥ その二人の前を、酒樽(さかだる)を積んだ馬車が横切っていった‥ 」
その言葉に頼純の目が光った。
「え!? 酒樽(さかだる)を積んだ馬車―――? 」
頼純は険しい表情でサミーラを振り返った。
「『酒樽(さかだる)を積んだ馬車』を目撃した人は―――? 」
サミーラは、『カラス団(コルブー)』に持たせていた20枚を超える蝋板(ろうばん)の中から、数枚を取り出し、その問いに答えた。
「パン屋のソフィーさんとジョセフ爺さん‥ これで、3件目です 」
「すべての証言で、目撃された共通の物は――― 」
サミーラは、たどたどしいフランス語ながらも、質問には素早く答えた。
「有効証言17件の内、一番多かったのが『月』で5件‥ 2番目が『鳥』で4件‥ その次がこの『酒樽(さかだる)を積んだ馬車』です 」
頼純は大きく息を吐き出すと、『カラス団(コルブー)』の不良達をゆっくり見渡した。
「この馬車が怪しい! おそらく、犯人はコイツらに違いないぞ! 」
その言葉に、ゴルティエをはじめ、『カラス団(コルブー)』の全員が色めき立った。