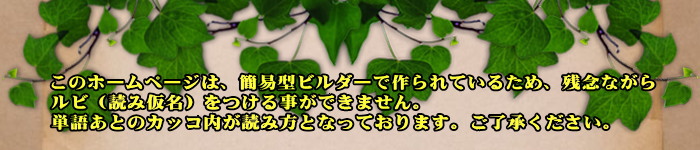
65
1027年 ファレーズ・ティボー邸
シュザンヌから『まだ、死なない』と診断されたエルキュールは、すっかり元気になって、一日おきに頼純を呼びつけるようになっていた。
『カラス団(コルブー)』を探索方(たんさくがた)とするための訓練に、頼純は日々忙しくしていたが、彼もエルキュールからの誘いを断る事はなかった。
頼純は、エルキュールと馬が合うのか、彼といるのが楽しいのだ。
一方、エルキュールも、本当は毎日でも頼純を呼びつけたかったのだが、彼が忙しい事を知って一日おきに我慢(がまん)していたのである。
彼はティボーの邸宅に訪ねてきてくれた頼純と、天気の話や街の噂、音楽の話から女の話まで、様々な他愛もない話題を語り合った。
説教臭い話はなくなり、ただ会話そのものを楽しむようになったのである。
頼純に小烏丸(こがらすまる)を振らせ、その様子を何時間と眺(なが)める事もあった。
昼食をとったあとに、ただ昼寝をするだけの日もあった。
エルキュールの一族は、祖々父の代からノルマンディー公家に仕(つか)えてきた家柄(いえがら)であったが、彼らはみな執事(しつじ)や家令(かれい)といった家政方(かせいがた)の職に就(つ)いてきた。
そんな一族にあって、エルキュールは初めて武人となり、名誉ある騎士(シュヴァリエ)の称号(しょうごう)を与えられたのである。
だが、長男であった彼が剣の道を志(こころざ)した時、彼の父、フィリップは大いに憤慨(ふんがい)した。裏方の仕事に誇りを持っていたフィリップは、表側の戦士になろうとした息子が、一族を裏切ったようで許せなかったのである。
そして、彼は三男であるティボーにその跡(あと)を継(つ)がせ、死ぬまでエルキュールの事を許さなかった。
エルキュールもそんな父に反発したのか、あまたの恋はしたものの、結婚だけはしなかったのである。跡継(あとつ)ぎなど絶対に残してやらないと心に決めていたのだ。
フィリップは4人の息子をもうけたが、次男は4歳で夭逝(ようせい)し、四男も20代で病死していた。その上、エルキュールもティボーもそれぞれの理由で結婚しておらず、子供もいなかったのだ。このままでは、家系が断絶する事は間違いなかった。
独り身のエルキュールにとって、頼純は息子のような、友達のような関係であった。
彼は頼純と一緒に過ごす間、2人が同じ歳に―――いや、少年時代に戻ったかのような、ウキウキとした気持ちになるのであった。だから、毎日が楽しくてしょうがなかった。
こうして気分がよくなっていくと、あれほどひどかったエルキュールのボケもその出現回数は大幅に減少していったのである。
そんな2人がこのところ夢中になっているのが、一輪の手押し車であった。手押し車にエルキュールを乗せ、頼純がそれを押して街中を滑走(かっそう)するという遊びだ。
足の悪いエルキュールのため、頼純は中国で見た手押し車を大工に頼んで作らせたのだ。
意外な事に、この単純かつ重要な運搬(うんぱん)道具が、当時のヨーロッパにはまだ存在していなかったのだ。
手押し車は3世紀の中国―――三国時代に、蜀(しょく)の諸葛亮孔明(しょかつりょうこうめい)が発明した『木牛(もくぎゅう)』がはじまりであると云(い)われている。
逆に言えば、紀元前からあれだけの巨大土木工事を行(おこな)ってきた中国においてでさえも、この簡単な運搬(うんぱん)道具が3世紀まで発明されていなかったという事である。
手押し車で坂道を滑走(かっそう)していく事はけっこうな重労働であったが、エルキュールが大いに喜ぶもので、頼純もついつい頑張ってしまった。
エルキュールは、なだらかな坂道を風を切って滑走(かっそう)する時、心の底から嬉しくてしょうがなかった。まるで空を飛んでいるような気分にさせてもらえるからである。
「テュロルド‥ もっと速度を上げろ。 もっと走るんじゃ! テュロルド、もっともっとじゃ‼ 」
「はいはい! 」
老人の叫びに従って、頼純は必死に走った。
エルキュールがよく叫ぶ『テュロルド』という人物が誰なのか、頼純はまったく知らなかったが、もはやそれを訂正するのも面倒臭かった。
彼にとって、頼純は『テュロルド』なのである。
街中(まちなか)を奇声を上げて走り回る老人と『勇者様』に、人々も最初は驚いていたが、やがてその様子(ようす)を笑顔をもって眺(なが)めるようになっていた。
あの勇者様が、手押し車に乗った老人に大きな声で命じられて、必死に走っている―――その光景は滑稽(こっけい)であり、ほほえましくもあった。
そして、いつの日か人々は、頼純の事を『テュロルドのヨリ様』とか、『テュロルドの勇者様』と呼ぶようになったのである。
そんな或る日、ティボーの屋敷で昼食をとったあと、エルキュールは少し真面目な顔をして
「テュロルドよ‥ 本日は剣について語ろうか 」
と、言いだした。
「は‥ はい‥ 」
久々の説教が始まった。
エルキュール自身の剣の腕前はさほど立派なものではなかった。中の上か、中の中―――ごくごく平均的な剣士でしかなかったのだ。
それは、『年老いて反射神経が鈍くなり、剣を振る力もなくなったから』‥‥とかいう次元の話ではない。元々の資質の問題である。
50年以上にもわたる彼の武人人生で、さしたる戦功(せんこう)を上げられなかった事が、それを如実(にょじつ)に物語っていた。
だが、誰よりも早く山賊の気配(けはい)を察知し、頼純が人を殺せない事も一瞬で見抜いたエルキュールの洞察力(どうさつりょく)は、この歳になっても人並みはずれていると言えよう。
さほど広くはない中庭の隅に椅子が置かれていた。そこに腰を下ろしたエルキュールは静かに語りはじめたのだ。
「お前は様々な事情から、人を殺す事を恐がり、ためらっておるようじゃな。 それはけっして悪い事ではない。 相手が5人までならば―――もしかすると、10人ぐらいでも‥ お前ほどの腕をもってすれば相手を殺す必要はないじゃろう。 手足を切断するだけで充分じゃ。 しかし、先日の山賊に囲まれた時のように、数十人もの敵を前にした時は、その一瞬のためらいが自分の命をも危(あや)うくしてしまう。 戦場ではなおさらの事じゃ 」
「ま‥ まあ、それはそうだけど‥‥ 」
「よく考えてみよ‥ お前が手足を切断した者達の行く末を! お前は相手が死なぬようにと、そのような情けをかけているやもしれんが‥ 大量の血を流した彼らのほとんどは、そのあと死んでしまっておるのじゃ。 さらに、何とか生き延びる事ができたとしても、彼らのその後の人生は悲惨(ひさん)であるに違いない。 なにせ、剣はおろか鍬(くわ)さえも持つ事ができんのじゃからのォ‥。 足を斬られた者は、なおの事じゃ。 そのような者らは、物乞(ものご)いにでもなるしか生きる道は残されておらん。 周囲の人々が助けてくれて、はじめて生きてゆけるのじゃ。 じゃが、元山賊や元盗賊のような輩(やから)に、そのような温かい手が差し伸べられる事はない。 じゃから、そやつらはもう、野垂(のた)れ死ぬしかないのじゃ。 最も惨(みじ)めな死に方となるじゃろう 」
「‥‥‥ 」
「つまり、お前はその場で殺していないだけで、結果的には相手を死に追いやっておる。 自分が殺したと思いたくないだけで、相手の事を考えておるわけではない。 もし本当に、お前が人を殺したくないと考えるのであれば―――お前は剣を捨てよ! 剣士ではなく、農民として生きればよいのだ 」
「‥‥‥ 」
「じゃが、お前には‥ そこまで割り切る勇気も無い。 じゃから中途半端に人を傷つけ、それで『勝った』だの、『自分は強い』だのと申しておるだけ。 それは、じつにさもしい事じゃとは思わんか? 」
すべてがおっしゃる通りで、エルキュールの言葉になにも反論できない頼純は、苦笑いを浮かべるばかりだった。
「いやいや‥ 俺だってそれぐらいの事は判ってるさ‥! 」
だが、エルキュールは追求の手を緩めようとはしなかった。頼純の事が本当に心配だったからである。
「じゃったら、今後も剣士として生きていくのじゃな!? もし、そう思うのならば、自分が『殺人者』であり、人々に『災厄(さいやく)を撒(ま)き散らす存在』である事を自覚して‥ その事に反省と後悔を繰り返しながらも、敵を殺し続ける覚悟が必要となる! それがお前にできようか? 」
「ん~~~ん‥ とても、できるとは思えねェな。 だから、アンタが言うように‥ 中途半端な俺は、敵を殺さなかったせいで、いつの日かその敵に殺されてしまうんだろうよ。 きっとそうに違いない! しかしそれは、己(おのれ)の未熟さであり、愚かさであると思って諦(あきら)めるしかネーんだ。 その覚悟なら、もうとっくにできてるゼ 」
「うむ‥‥ お前がひとりの時であれば、それもよかろう。 しかしそのせいで、お前が守らねばならない君主が殺されたらどういたす? もしかすると、それが一国を滅ぼす原因となるやもしれんのじゃぞ 」
「それなら、大丈夫だい! 俺は誰かに仕官(しかん)するつもりもなければ、忠誠を誓う気もない。 今の仕事だって、金で雇われてるだけだからな 」
「ならば‥ それがお前の愛する者であればどうじゃ!? 妻や子供が死んでしまってもよいのか? 」
「つ‥ 妻や子―――!? 」
それは、頼純が今まで考えてもみなかった事であった。だが、その言葉を聞いた瞬間に、彼の脳裏にはサミーラの顔がよぎっていた。
「よくよく、考えるのじゃ。 敵を『殺さぬ事』は大いにけっこうである。 じゃが、『殺せない事』はお前のみならず、お前が大切に思う者まで死なせてしまう可能性がある。 剣を捨てる事ができないのであれば、人を殺(あや)める意味を考えよ。 そして、その事を噛(か)み締めながら、その業(ごう)を背負っていくしかないのじゃ! 」
「は‥ はい‥‥‥ 」
× × × × ×
イングランド王国ウェセックス領―――ゴドウィン伯爵は、4週間ぶりに自領に建つ城へと戻ってきた。
クヌート王やエマ王妃が住むウィンチェスター城もウェセックス領内にあったが、ここはそれとは別の城である。
あちらは、イングランドの首都ウィンチェスターに古くからある王の居城であり、こちらはウェセックス伯爵の城である。
元々この領地は、七王国(ヘプターキー)のひとつ、ウェセックス王国であり、アルフレッド大王も統治した由緒(ゆいしょ)正しき土地である。
イングランドを征服したクヌート大王でさえも、この土地の歴史に敬意を払い、戦争の報償(ほうしょう)として家臣に譲(ゆず)り渡す事をためらったほどである。
その最も広く、もっとも権威ある土地を、ゴドウィンはクヌート王から下賜(かし)されたのだ。それは、彼がいかにクヌート王から信用されていたか、あるいは、いかにゴドウィンの口が上手かったかの証(あかし)であった。
彼は大王を気遣(きづか)って、首都・ウィンチェスターから少し離れた場所に、彼の城を新しく建てたのである。
城内では、降誕祭(クリスマス)にウルフ伯が殺されたという噂で持ちきりであった。 それはウルフ伯が伯爵夫人であるガイサの実の兄だったからだ。
人々は、その犯人がスウェーデンの傭兵(ハスカール)だったらしいとの噂もすでに知っていた。
3人目の息子トスティを産んだばかりだったガイサは、その心労でかなりやつれていた。
幼い頃から28歳の今日(こんにち)まで、ずっと慕(した)ってきた兄が殺されたのだ。
彫りの深い凛々(りり)しい顔立ちと美しい金髪を持ったウルフは、身長も高く、逞(たくま)しい肉体を兼ね備えていた。さらには、誰よりも賢く、正義を貫き、剣の腕は国内随一(ずいいち)といってもよいほどであった。
独身の頃は、デンマーク宮廷のすべての女性が―――いや、国中の女性が彼に恋い焦(こ)がれたほどである。
ガイサはそのような兄が自慢であり、恋心さえ抱いていたほどであった。
それゆえに、彼女の心中が穏(おだ)やかであろうはずはなかった。
ゴドウィンが家臣達とともに城へ到着した時、喪服(もふく)を着た彼女は黙礼するだけで何も語らなかった。
だが、ゴドウィンが着替えのため寝室に入り、ガイサと二人だけになると、彼女は鋭い眼光で彼を睨(にら)みつけてきた。
「アナタでしょ!? アナタが兄さんを殺したのね? 」
腰から剣をはずしながら、ゴドウィンはしらを切った。
「違うよ。 犯人はスウェーデン人さ。 俺は関係ない。 そんなコトを言ってる奴は誰もいないぞ 」
しかし、ガイサはさらに夫に詰め寄った。
「ワタシには判るの。 アナタが誰が好きで、誰が嫌いなのか‥ ワタシは、何でもお見通しなのよ 」
「‥‥‥ 」
「アナタがワタシをさほど好きでない事も‥ もっと好きな人がいる事も知っているわ 」
ゴドウィンはガイサを振り返ると怒鳴った。
「うるせェな! 少し黙ってろ‼ 」
だが、夫の恫喝(どうかつ)にも、ガイサは一切たじろかなかった
「つまり、認めるのね? 」
開き直ったゴドウィンは、意地悪げな表情でガイサにまくし立てた。
「ああ‥ そうだよ! ウルフを殺したのはこの俺様だ。 大王様の命令でね。 まあ‥ 正直、俺もアイツの事が邪魔だったから、積極的に殺してやったんだけどな! 」
ガイサは涙を一杯に溜(た)めた瞳でゴドウィンを見詰めた。
「‥‥‥ 」
「どうだ、これで満足か? 」
ガイサはヒステリックな声を上げた。
「満足じゃない。 大切な兄を殺されたのよ! 満足なはずがないでしょう‼ 」
「じゃあ、どうするんだ? 実家にでも帰るのか。 それとも、この俺を殺してみるか? お前の好きにするがいい! 」
冷たく突っぱねるゴドウィンを、ガイサは怒りと憎しみのこもった目で睨(にら)んだ。
「‥‥‥ 」
そんな妻を無視するように背を向けると、ゴドウィンは重たい鎖帷子(ホーバーク)を脱ぎはじめた。
やがて、ガイサの震える唇からゆっくりと言葉が漏れ出した。
「く‥ 悔しい‥ 悔しいけど‥ それでもアナタの事が嫌いになれない‥ ああ、情けない‥ アナタを殺してやりたいけど‥ 守ってもやりたいなんて‥‥ 」
「―――お前のそういうところが、俺は好きだよ‥ 」
ゴドウィンは振り返らずにそう言った。
「そんなコト言っても‥ 誤魔化(ごまか)されないわ 」
ポロポロと涙を流しながら、ガイサは泣き始めた。
彼女はどうしていいのか判らなくなっていた。何で、こんな男を好きになってしまったのかも、さっぱり理解できない。
容姿(ようし)はパッとせず、身長も自分とたいして変わらない。剣の腕はからきしで、正直さもなければ、敬虔(けいけん)な信仰心もない。
クヌート王の前ではいつもヘラヘラとした愛想笑いを浮かべ、回りの者が恥ずかしくなるようなおべっかを平気で言うような男である。
兄ウルフとは正反対の男なのだ。
兄の猛反対を押し切ってまで、どうしてそんな男と結婚したのか―――ガイサは自分の決断に納得がいかなかった。
そしてもっとも驚くべき事は、この期(ご)に及(およ)んでもまだこの男の事を自分が愛しているという事であった。
ゴドウィンは、新しいチュニックに袖(そで)を通しながら、ガイサを振り返った。
「じゃあ、別の話をしよう 」
彼はチュニックの胸元の紐(ひも)を結びながら、彼女に近づいていく。
「お前も知っての通り、俺は没落(ぼつらく)貴族の出身だ。 裕福な家庭に育ったお前ら兄妹には判らないようなひどい生活をしてきた。 子供の頃は、喰えない日が何日も続いた事だってある。 かっぱらい、喧嘩(けんか)、恐喝(きょうかつ)‥ たいていの悪事は一通りやったよ。 それも、喰うタメだけじゃなく、娯楽としてやる事さえあったんだ 」
ゴドウィンは、自分が町の不良であった頃の話をよくした。
しかし、その話のほとんどがウソであった。彼の本当の過去は、とても他人には―――たとえ妻であっても、話す事などできなかった。それはそれはおぞましい過去なのである。
黙って見詰め返すガイサの肩を、ゴドウィンは両手で掴(つか)んだ。
「それだけに‥ あんなクソダメのようなところには、もう二度と戻りたくはないし、もっともっと出世したいんだ 」
「しゅ‥ 出世って‥ アナタはとっくに登り詰めたじゃない。 これ以上、どう出世するっていうの? あとは王にでもなるしかないのよ! 」
眉を顰(しか)めて尋(たず)ねるガイサから、ゴドウィンは視線をはずす。そして、それを宙にはわせた。
「‥‥‥ 」
その様子に、ガイサの目が大きく開かれていく。もう涙は完全に止まっていた。
「ま‥ まさか‥ そうなの? アナタは王になろうとしているの? 」
視線を落としたゴドウィンがクスリと笑った。
「残念ながら、それは無理だね。 俺のような出自(しゅつじ)では、王にはけっしてなれない。 だから、お前を『王妃』にしてやる事はできないんだ 」
「そ‥ そんな事は判っているわ。 けど、だったら――― 」
その言葉を遮(さえぎ)って、ゴドウィンはガイサの瞳を覗(のぞ)き込んだ。
「俺は、お前を『王の母』にしてやろうと思っている 」
「え!? 」
あまりの話に、ガイサは一瞬息をする事さえ忘れてしまった。
「俺の代では無理だが、息子達ならできる。 奴らを王にしてやる事ならできるんだ! 」
「そ‥ そんな‥ 大それた事を―――! 」
ゴドウィンはガイサを抱きしめ、その耳元で囁(ささや)いた。
「だから、ウルフ伯の事は我慢しろ。 この計画で最大の邪魔者は、兄上だったのだから 」
ガイサは返す言葉を持たなかった。
ただ、ゴドウィンの腕の中で、彼女はひとつ思い出した事があった。
―――このような途方もない野望を語る時のゴドウィンの顔が、彼女は大好きだったのである。