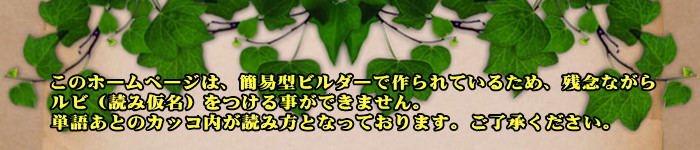
93
1027年 ファレーズ城
藤原頼純(ふじわらのよりずみ)は自宅の中庭で小烏丸(こがらすまる)を無心に振っていた。
すでに1000回近くも振ったであろうか。
季節は夏も盛りを過ぎ、秋風が吹きはじめる頃となっていた。だが、彼の額や胸からはぷつぷつと汗が噴き出している。
彼がこの地へ赴(おもむ)いて、すでに一年近くが過ぎようとしていた。
はじめこそ、毎日のように戦闘漬けの日々であったが、この半年ほどは人に太刀(たち)を向ける事もなくなっていた。
最後は、あの傭兵団(ようへいだん)との戦いである。
頼純の脳裏(のうり)には、あの時の後悔がこびりついていた。
敵を斬り殺せなかったばっかりに、重大な危機を招いてしまった事である。
それは、自分の死のみならず、仲間やこの街全体をも危機にさらそうとしたのだ。
人を殺さねばならない時に殺せない自分は、はたして本当の戦士といえるのだろうか。
もしふたたび、そういう状況に見舞われた時、今度こそ相手を確実にしとめる事ができるのか―――彼には自信がなかった。
そんな思いを抱えながら、この半年間一心に剣を振り続けてきたのである。
それは、仮想の敵をイメージした殺人剣であった。突きを主体としている。
鎖帷子(オベール)を着けた騎士数人と戦う場合、斬りつけるのではなく、突き刺す方が効果的であった。心臓や喉、それほど正確に狙えない場合でも胸や腹を突き刺せば、十分に致命傷を与える事ができる。
もちろん、名刀・小烏丸(こがらすまる)であれば、鉄製の鎖帷子(オベール)であっても難なく斬り裂く事は可能であった。たとえ敵が、分厚い鎧下(ガンベゾン)の上に頑丈な鎖帷子(オベール)をつけていたとしても、この太刀ならばそれらごと、彼の胴体を真っ二つにする事ができるのだ。
しかし、小烏丸(こがらすまる)がどれほどの名刀であろうとも、どれほど強い鋼鉄でできていようとも、鉄の鎖帷子(オベール)を斬り続ければ、やがて斬れなくなっていく。小さな刃こぼれは必ずおきるからだ。それは、刃物の宿命であった。
さらに相手の人数が多くなればなるほど、彼らの長剣(エペ)を体(たい)さばきだけで躱(かわ)す事は不可能になっていく。当然、小烏丸(こがらすまる)の刀身で相手の分厚く重たい長剣(エペ)を受けなければならなくなるだろう。これも刃こぼれの大きな要因となる。
そうなると、刃を研(と)がなければならなくなるのだが、刀身は研(と)げば研(と)ぐほど、細く痩(や)せていく。それを十数年も続ければ、やがて折れやすくなったり、曲がりやすくなったりするだろう。そしてそうなってしまうと、日本の刀鍛冶がいないこのヨーロッパではその修理は困難なのである。
頼純にとって小烏丸はただの武器ではない。
それは彼が日本人である事の証明であり、その誇りや郷愁(きょうしゅう)を具現化(ぐげんか)した物なのだ。
それゆえに、彼は小烏丸を大切にしてきたのである。
敵の長剣(エペ)を受けるにあたっては、他の騎士達のように、盾(たて)を使う事も考えた。
だがむしろ、左手に長剣(エペ)、右手には小烏丸(こがらすまる)という二刀流の方が頼純は戦いやすかった。巨大ワニと戦った時の戦法である。
ただし、強い武者と闘う場合は、2本の手でしっかりと小烏丸(こがらすまる)を掴(つか)んだ方が良いに決まっている。でなければ、彼の剣技は十分に引き出せないからだ。
頼純の悩みは尽きない。
そんな悩みを断ち切るように、彼は空想の敵に向かって小烏丸(こがらすまる)を突き続けるのであった。
「御主人様‥ ご夕飯ですよ 」
そう告げたのは、新妻であるサミーラだった。
振り返った頼純は、それまでの厳(いかめ)しい表情から穏やかな笑みへ変わった。
「だから―――その『御主人様』ってーのは、やめてくれって言っただろう。 昔が思い出されていやなんだよ。 お前は、わたしの召使いでも奴隷でもないんだからさ 」
「はいはい。 では‥ ヨリ様、ご飯ですよ―――これでよろしいでしょうか? 」
「う‥ うん‥ あの‥ ア‥ アナタなんてどうだろう? そういうのも悪くないと思うのだが‥‥ 」
頼純は顔を真っ赤にしながら言ってみた。
だが、サミーラはお腹を手でさすりながらつぶやいた。
「もしかしたら‥ お父上様と呼ばれるかも‥‥♡ 」
「え!? 」
頼純は完全に固まった。
「あした、シュザンヌさんのところへいって、診(み)てもらおうかと‥‥ 」
サミーラは頬(ほお)を赤く染めて告げた。
「あああ‥ そ‥ そうなんだ‥! 」
頼純はどう答えればよいのか判らなかった。本当は飛び上がって喜びたかったのだが‥‥‥。
ともかく、彼は新婚生活を満喫していた。
× × × × ×
翌日、サミーラはシュザンヌのところで診察してもらっていた。
診察台に横たわったサミーラの体から離れると、シュザンヌは木桶(バケツ)に入った水で手を洗いながら告げた。
「うん‥ 妊娠してるわね、たぶん三ヶ月くらいでしょう。 おめでとうございます 」
その言葉に、体を起こしたサミーラは無上の喜びを噛み締めていた。
「よかったァ‥ ありがとうございます 」
女性にとって、愛する人の子供を授(さず)かる事は大いなる喜びである。
だが、愛する人と結婚する事さえ、なかなかままならぬ時代である。ましてや、奴隷の身分であったサミーラにとって、好きな人の子供を妊娠する事など、夢のまた夢だったのだ。それゆえに、彼女の喜びもひとしおなのである
彼女の大きな瞳からは、涙がポロポロとこぼれた。
そして、この事を頼純に報告したら、どれほど彼が喜ぶだろうかと思うと、顔の筋肉もついつい緩んでしまう。
サミーラはしばらくの間、泣き笑いが止まらなかった。
シュザンヌはエルレヴァの頼みもあって、いまだエレーヌの森には帰らず、街で診療を続けていた。
しかし、そうなると他の医者達の目もあり、キリスト教の教えに反する治療行為は行えなかった。異端だの、魔女だのと噂が立ってしまうからである。
彼女は、最新のアラビア医学や、それらを元に代々研鑽(けんさん)し続けてきた画期的医療手法を封印しなければならなかった。
もどかしい思いながらも、シュザンヌは街の人々を安価な代金で治療していたのである。
この診療所の運営資金はロベール伯が提供していた。
さらに彼女は、ロベール伯の意向もあって、軍隊や『カラス団(コルブー)』達にも応急手当の方法を教授し、街の人達には日常の簡単な手当のしかたなどを伝授していた。
それは、『火傷をしたらすぐに水で長時間冷やしましょう』とか、『裂傷で血が出た場合は、傷口を布などで強く抑えましょう』などといった話であったが、その程度の知識でさえも民衆は知らなかった。
シュザンヌの診療所は患者であふれ、彼女はますます森に帰る事ができなくなっていった。
新しい治療法や薬の研究などができない事は不満であったが、鉤鼻(かぎばな)の仮面を付け、腰を折って老婆のフリをしなくてすむ事はありがたかった。
なにより、完治した人々の喜ぶ顔は、彼女がこれまで知らなかった満足感を与えてくれるのだった。
× × × × ×
同じ頃、頼純はロベール伯爵からの呼び出しを受け、『領主の館(メヌア)』に出向いていた。
街全体を囲む外城壁のレンガ化は、まだ1年以上かかると思われたが、『領主の館(メヌア)』の城壁のレンガ化の方は、ほぼ完成しつつあった。
人夫達の活気ある声と工事の音が響く中庭を抜けて、頼純は館の広間へと通された。
玉座で彼を待ち構えていたロベールは、挨拶もそこそこに切り出してきた。
「それで、どうですか新婚生活は? 」
「どうって、聞かれても―――アンタだって、知ってるだろう。 先週だって会ったんだからさ 」
サミーラの妊娠の結果が気がかりでしょうがない頼純は、ロベール伯に素っ気ない返事を返した。この呼び出しさえなければ、自分もシュザンヌの診療所に行けたのに―――と、ややおかんむりだったのだ。
ロベールは少しあらたまった口調で言葉を続けた。
「ま‥ まあ、そうなんですけど‥ 生活費の方は足りているかなと思いまして 」
「ああ、大丈夫だよ! 結婚祝いにアンタから立派な家をもらったし、ロレンツォ殿が払ってくれた給金と報奨金もまだ十分にあるからね 」
「とはいえ、蓄えを切り崩しての生活では、いつまでも続かないでしょう?」
「そん時はそん時さ。 金を稼ぐ方法ならいくらでもある。 用心棒や傭兵‥ 街の人達のモメ事や問題を解決する―――『何でも屋』てー仕事だってあるしな。 『よろず相談承(うけたまわ)ります』ってヤツだ♡ 」
「いやいや‥ そのような下々のお仕事をするくらいなら―――私の家臣になってはもらえませんか‥? 出会った時とは、我々の関係も違っていますし‥‥ そろそろ、もう一度お考え直しいただいてもよろしいのではないかと‥‥‥ 」
「なんだい、今日はその話? アンタの家来になれって―――?」
「そ‥ そうなんです 」
「う~~~ん‥ 」
頼純は腕組みをして考え込んだ。
ロベール伯はすがるような目つきで言葉を続けた。
「ぜひ、アナタを騎士として―――いや、貴族として迎え入れたいのです 」
やがて、ロベールに顔を向けた頼純は、小刻みに首を振った。
「ダメだね、やっぱ無理だろう 」
「そ‥ そんな‥ もうちょっと考えてくださいよ。 すぐに答えを出さなくてもいいんです 」
「‥‥‥ 」
「それに‥ これは、わたしだけの願いではありません。 この街の多くの者がそれを望んでいるのです。 アナタにずっとこの街にいて欲しいんです 」
懸命に訴えかけるロベールに、頼純は真面目な顔で答えた。
「オレだって、アンタの事を嫌っちゃいないし‥ これからも、一緒にいろんな事をやっていきてェとは考えちゃいるさ 」
「は‥ はい‥ 」
「けど、騎士になるてェ相談なら、こりゃ別の話だ。 だって、そのためにゃあ、俺がキリスト教徒にならなきゃならネーじゃねぇか! 」
× × × × ×
民衆のほとんどがキリスト教徒であったヨーロッパ社会において―――個人がどれほど、心から神を信じていたのかは別にしても―――国王は無論の事、貴族や騎士が異教徒である事は絶対に許されなかった。
騎士―――シュヴァリエ(仏)、ナイト(英)、カヴァリエーレ(伊)、リッター(独)と呼ばれる戦士達は、古ゲルマンの従士制(Gefolgschaft(ゲフォルクシャフト))に端(たん)を発している。
従士(ゲフォルクシャフト)とは、各地の有力者と誓約を交わし、その自宅に住み込んで、彼らのために戦闘行為を行う自由男子―――つまり、奴隷ではない戦士―――の事である。
その一方で、有力者は誓約を交わした従士を十分に庇護(ひご)しなければならなかった。
この従士制は、紀元前から存在したと思われ、ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が著した『ガリア戦記(紀元前1世紀)』や、タキトゥスの『ゲルマニア(紀元1世紀)』にもその記述がある。
ローマ領の東に住むゲルマン民族が、中央アジアのフン族に襲撃されて帝国領内に逃げ込む少し前、4世紀初頭からゲルマン社会ではキリスト教(アリウス派)の布教が活発になっていた。
アリウス派は、『イエス・キリストは人間であった』と定義したため、紀元325年のニカイア宗教会議で異端とされ、ローマ帝国領内での布教を禁じられていた。そこで彼らは、その外側に住むゲルマンの人々に布教をはじめたのだ。
アリウス派の伝道師らは、ゲルマンの言葉で書かれた聖書を作り、人々が文字を知らなければ文字を教え、彼らが文字を持たなければ文字を編み出すまでして、必死に布教に努めたのだ。
こうして熱心に布教活動が行われていく過程で、彼らは古ゲルマン社会で成人式に行われていた『武器授与』の儀式も利用した。
それまでは、槍で行われていた儀式を、キリスト教のシンボルである『十字架』と同じ形をした長剣(エペ)で行うよう推奨(すいしょう)したのだ。
さらに、その成人の儀式は従士の叙任の儀式へと変わっていく。
跪(ひざまず)いた戦士の肩を、長剣(エペ)で叩くという儀式である。
その後、フランク王国では鐙(あぶみ)の普及により、馬での戦闘が主流になっていく―――騎士(シュヴァリエ)の誕生である。
従士から騎士へと変わり、宗教も異端であるアリウス派キリスト教から、正統のニカイア派(アタナシオス派)キリスト教に変わっていったが、叙任式の肩打ち(首打ち)は引き継がれていく。

余談であるが、この叙任式の肩打ちは、かなりの力で叩かれていた。
そのため、王や貴族の手元が少し狂うと、騎士の耳はその端が切れる。よく研(と)いだ長剣(エペ)だと、ちょっとかすっただけでもかなりの出血となり、血まみれの叙任式となる事も多かったようだ。
こうしてキリスト教は、ゲルマン社会の様々な行事を取り込み、信徒を増やしていったのである。やがてゲルマン各国は国教としてキリスト教を認め、ヨーロッパのすべての人々がキリスト教徒となっていく。
それから数百年が経ち、いまではキリスト教の神の『許し』がなければ叙任式は行えないし、叙任式が行えなければ騎士にはなれなかった―――そして、その神の『許し』は、キリスト教徒にしか与えられなかったのである。
× × × × ×
強張った表情でロベール伯爵は言った。
「まあ‥ それは形だけでも、教会で洗礼を受けてもらって‥ キリスト教徒になっていただかないと――― 」
しかし、頼純はそれに納得しない。
「そんなのはダメだよ。 オレはキリストさんを信じていネーし‥ ましてや、神様にウソをつくってーわけにはいかねぇだろう。 だから、無理なんだよ 」
「それはそうですけど‥‥ 」
「ただな‥ 俺の子供はキリスト教徒にしようと思っている。 だから、もし子供が男だったら、そん時ゃアンタの家臣にしてやってくれ 」
笑顔で申し出る頼純に、ロベールはついに諦(あきら)めたようだった。
「そうですか‥ 残念ですねェ‥‥‥ 」
それは、しょんぼりとした口調だった。
その時、広間に声が響いた。
「だったら剣術指南役という事で召し抱えられてはいかがですか 」
そう進言したのは、奥の間から登場したティボーであった。
「剣術指南役? 」
訝(いぶか)しげな顔をする頼純とロベールに、玉座の傍らにまで進み出たティボーがしたり顔で説明した。
「そうです。 アナタ様やご子息ギヨーム様に武術を教えるという名目で、賃金をお支払いすればよろしいのです。 ヨリ殿がここに住む理由にもなりまするぞ 」
ロベールの目がふたたび輝きはじめた。
「おお‥ なるほど! ヨリ殿、この方策はいかがでしょうか? 」
頼純はクスリと笑いながらも
「うむ‥ 悪くないと思う。 剣術指南か―――つまり、師匠ってわけだな。 なら、アンタの家来じゃネーから、その命令に服従する必要もない。 うん、そりゃいいよ 」
「そうですね。 では、主従関係ではなく、これからは師弟関係―――いや、友人関係のままでいいですよね? ぜひ、わたくしの剣術指南役となっていただけませんでしょうか? 」
「こちらから、ぜひともお願いしたいね♡ 」
こうして、藤原頼純はロベール伯とその子・ギヨームの剣術指南役となったのだった。