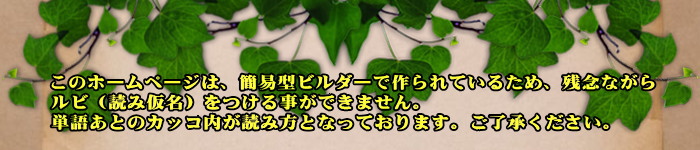
99
1027年 ルーアン城
頼純達がサン・マリクレール修道院の院長室に通されていた頃、公都(こうと)ルーアン城でもひとつの事件が起きていた。
ノルマンディー公国の公都(こうと)であるルーアンは、人口2万人を超える大都市である。
そこには市(いち)がいくつも立ち、あまたの商人が珍しい品物を手に行き交った。街全体が喧噪(けんそう)に満ちているのだ。
その中心にあるルーアン城は、ファレーズ城よりもはるかに大きく、公爵リシャール3世が鎮座(ちんざ)する大広間もまた、ロベール伯爵が住む『領主の館(メヌア)』の広間より、2倍以上もある広々としたものであった。
夜ともなれば夕餉(ゆうげ)をともにする家臣達でにぎやかしいこの部屋であったが、昼間はその広さゆえに、静寂(せいじゃく)をより強く感じさせた。
その広間に立つクレポン伯オズバーン卿は、憂鬱(ゆううつ)な気分だった。
昨夜食べた川エビにあたったらしく、激しい下痢と胸のむかつきに苦しめられていたからである。
吐き気をもよおした時は、天井見上げてゆっくり深呼吸をしなければならない。
このような体調の時は休みを願い出たいところだが、本日はそうもいかなかった。
静まり返った大広間に、朗々(ろうろう)たる声が響く。
「どうも、リシャール大公様‥ ご無沙汰(ぶさた)をしておりました♡ 」
その声の主は、北海帝国(=イングランドおよびデンマーク、ノルウェー同君連合)の重臣ウェセックス伯ゴドウィン卿である。
ノルマンディー公家の家宰(セネシャル)であるオズバーンは、主人リシャール3世のありとあらゆる執務を補佐しなければならない。ましてや、外国の要人が訪れたのである。食あたりぐらいで休むわけにはいかなかった。
リシャール3世は、公爵に就任してまだ2年足らず。内政についてはずいぶんと慣れてきたものの、複雑な外交はまだまだ力不足であった。
おそらくは自分の助言が求められるだろう―――そう思うと、オズバーンは宮殿から退(しりぞ)く決意ができなかった。
愛想笑いを浮かべたゴドウィン伯爵は、リシャール3世が坐る玉座の前で恭(うやうや)しく挨拶(あいさつ)の言葉をのべた。
「公爵様におかれましては、お健(すこ)やかなるご様子。 麗(うるわ)しきご尊顔(そんがん)を拝(はい)し、恐悦至極(きょうえつしごく)に存じあげます♡ 」
だが、リシャール3世は、憮然(ぶぜん)とした表情で頷(うなず)くだけであった。
ふたたび現れたこの胡散臭(うさんくさ)い男に、主人が苛立(いらだ)つ気持ちは判らないでもない。ただ、その気持ちが態度に出過ぎていた。やはり、この場は自分が仕切らなければならないだろう―――オズバーンはそう思った。
玉座の脇に控えていたオズバーンは、主人の代わりに、ゴドウィン伯へ声を掛けた。
「いやいや‥ そう、ご無沙汰(ぶさた)でもありますまい。 前回のご訪問からまだ半年も経っておらぬのですぞ。 にもかかわらず、イングランドからノルマンディーまで、遠路はるばるのご出馬とは‥ あなた様もさぞやお暇(ひま)なお立場にあられるのでしょうな。 まことに、痛み入ります 」
オズバーン卿は、冗談とも皮肉ともつかない挨拶(あいさつ)を告げた。
しかしゴドウィンは、こうした言葉にもへりくだった物言(ものい)いで応対する。
「これはこれは‥ 我が身をご心配いただき、まことに恐れ入ります 」
彼は作り笑いを絶やす事なく、話しを続けた。
「また、たび重なる拝謁(はいえつ)、たいへん恐縮ではございますが‥‥ このたびのご縁談は大切な外交でございます。 婚姻(こんいん)による国と国の結びつきは、条約などよりもはるかに強固なものとなりますから。 ゆえに、このゴドウィン、何度でも足をお運びいたしまする♡ 」
玉座のリシャール3世は、そんなゴドウィンを苦々しく見下ろすばかり。一言も発しようとはしない。
体調の良くないオズバーンだけでなく、リシャール3世もこの接見をおこないたくなかったのだ。
ならば、適当な理由をつけて断ればよいではないか―――と思われるだろうが、そうもいかないのである。
それは、ゴドウィンが大国・北海帝国の使者だという事もあったが、なによりも、彼がイングランドの伯爵だった事が大きい。
リシャール3世は公爵であり、ゴドウィンは伯爵である。
公爵と伯爵ならば、とうぜん公爵の方が位は上だと思われがちだが、当時のイングランド王国とフランス王国では、伯爵という言葉の意味が違っていた(これは、日本語に翻訳する際の問題でもあるのですが‥‥ )。
フランスでは伯爵をCount(コント)(英語ではカウント)という。
これはカロリング朝フランク王国の絶頂期、シャルルマニュー(=カール大帝)が古代ローマ帝国にならって統治を行った事に由来する。
彼は王国を数百の管区にわけ、その行政長官をComes(コメス)としたのだ。
また、その行政長官(コメス)の上位にあたる軍司令官をDux(ドゥクス)と定めた。
その後、フランク王国から西フランク王国へと分かれ、フランス王国となる過程で、軍司令官Dux(ドゥクス)は公爵Duke(デュク=英語ではデューク)へ、行政長官はComes(コメス)がComteとなり、伯爵Count(コント)へと変化していった。
ちなみに、このフランス語Count(コント)が、国や郡、田舎を表す英語Country(カントリー)の語源となる。
ファレーズ伯ロベールやクレポン伯オズバーンは、この伯爵(コント)にあたった。
一方、イングランドでは伯爵をEarl(アール)と呼ぶ。
元々、サクソン王朝時代に、王から地方の行政・司法・軍事等の権限を与えられた貴族をEaldorman(エアルドルマン)と呼んでいた。
だが、1016年にクヌート大王がイングランドを征服すると、このEaldorman(エアルドルマン)をデンマーク語で貴族を表すJarl(ヤール)に寄せて、Earl(アール)という言葉に変えたのだ。
さらに、比較的小規模であったEaldorman(エアルドルマン)の行政単位(=領地)を変更し、旧七王国(ヘプターキ)時代の各王国をEarl(アール)の所領とした。
これにより、Earl(アール)はフランスにおける『大公(グラン・デュク)』、または下級王に匹敵するほどの大領主を意味するようになる。
これから50年後の1066年、ロベール伯爵の息子ギヨーム(=ウィリアム1世)がイングランドを征服(=ノルマン・コンクエスト)すると、こうしたEarl(アール)が持つ広大な領地はフランスの伯爵Count(コント)と同じ程度にまで縮小され、その人数は大幅に増員された。
しかし、呼称の変更はされず、また公爵Duke(デューク)も新設されなかったため、イングランドでの爵位は13世紀になるまでEarl(アール)だけであったと言われている(ちなみに、現代のイギリスでは、自国の伯爵をEarl(アール)、他国の伯爵はCount(カウント)と呼ぶ)。
つまりこの当時、イングランドの伯爵は、フランスの公爵と同じか、それ以上の地位であったという事である。
その上、ゴドウィン伯の領地は、かつてアルフレッド大王が治めたウェセックス王国であった。その由緒正しき土地は、ノルマンディ公爵領よりもはるかに大きく、豊かでもあった。
それゆえ、いくらゴドウィン伯爵が恭(うやうや)しく下手(したて)に出てくるからといって、この成り上がり貴族を軽んじるわけにはいかないのだ(現代にたとえるなら、県知事、州知事のもとに、中堅国家の国王、大統領が訪ねてきたようなものであろうか)。
そこで、リシャール3世もこの接見に、渋々ながら応じざるを得なかったのである。
「して‥ 弟君(おとうとぎみ)ロバート(仏=ロベール)伯爵様とクヌート王の妹君(いもうとぎみ)エストリド様とのご縁談―――いかがでございましょうか? 」
ゴドウィンがリシャールに尋(たず)ねた。
だが、主人が言葉を発する前に、オズバーンが代わって返答する。
「ですから、その縁談はお断りしたはず。 ロベール伯には深く愛する女性がいらっしゃって、2人の間には男子まで誕生しております。 我がノルマンディーでは、この2人を結婚させたいと考えておるのです 」
ゴドウィンは、いちいち口を挟(はさ)んでくる家宰(セネシャル)に顔を向け、鼻を鳴らして笑った。
「それは、先日おっしゃっていた、アルレット殿―――こちらではエルレヴァ殿と呼ばれておりましたか―――ファレーズの街を救った『聖女』と称されておる町娘でございましたな。 しかしながら、こちらは北海帝国クヌート大王様が妹君(いもうとぎみ)、エストリド様でございますぞ。 いくら、『聖女』などと噂されても、しょせん我が妃様(ひめさま)とでは格が違いましょう 」
「そ‥ それは――― 」
「それに、『ファレーズの聖女』殿とのご結婚について、いまだ教皇庁からのお許しは出ていないと聞き及(およ)んでおります。 申し込まれてすでに半年以上。 なのに、なんの音沙汰(おとさた)もないとは‥‥ これは普通ではありますまい。 許可されないという事ではありませぬか? 」
当時のヨーロッパでは、貴族の結婚はキリスト教会の承認が必ず必要であった。
リシャールは、自分と義父・ロベール2世フランス国王、さらには叔父・ロベールルーアン大司教の承認書を添付して、弟・ロベールとエルレヴァの結婚をローマ教皇庁に申請していた。
だがその後、何の返答もない。そこで親しいジョヴァンニ枢機卿(すうききょう)を通じて、手続きの進展を確認したのだが、教皇庁からは『審議中』との解答しか得られなかったのだ。
リシャールやオズバーンは、どこからか圧力が掛かり、この結婚申請がワザと棚上げにされているのではないかと疑っていた。
たとえば、クヌート大王が親しい教皇ヨハネス19世に頼み込んだとか―――。
それでも、リシャールは2人の結婚許可を待ち続けた。
ただしそれは、弟ロベールと町娘をどうしても結婚させたかったからではない。
リシャールはそれほど弟思いだったわけでもないし、そもそも、貴族の縁談は主家(しゅけ)や父兄によって決められるものである。好きな者同士が結婚できるわけではないのだ。
にもかかわらず、リシャールがロベールとエルレヴァを結婚させようとするのは、弟をクヌート王の妹とだけは結婚させたくなかったからである。
リシャールは、クヌート王を嫌っていたのだ。
そして、彼がゴドウィン伯に対して言葉を発しないのも、下手(へた)な事を口にすれば、それを逆手(さかて)にとられ、このイングランドの使者から言葉巧みに、エストリド妃を押しつけられてしまうのではないか―――と、恐れているからなのだろう。
彼はこうした交渉事や駆け引きが不得意な男なのだ。
そして、それが主人の考えならば、自分が何とかしてやるしかない―――オズバーンはそう考えていた。
しかし、この縁談はなかなかの良縁である。大国・北海帝国の大王と義理の兄弟となる結婚話なのだ。これほどの良縁を断る理由など、早々に思いつくはずもなかった。下手な事を言えば戦争にもなりかねない。国と国の縁談とはそういうものなのである。
それでもなんとか抵抗しようと、オズバーンはへ理屈をひねり出した。
「し‥ しかし、エストリド様はもう齢(よわい)30を越えられておられまする。 お子も2人おられる身。 この上、ロベール伯のお子までもうけられると? 」
「ええ! それが、貴族の妃(ひめ)の運命ですからな。 必ずや御子(みこ)をもうけられる事でしょう。 むしろ、経産婦である方が子をもうけやすいとも申します。 我が王妃エマ様が良い例でございましょう。 立派な王子ハーディクヌーズ殿下をお生みになられましたぞ 」
ゴドウィンにあっさりと切り替えされてしまった。予想はしていたが、やはりこの程度の問題提起ではまったく太刀打ちできなかった。
ここはもう、リシャールにはっきり断ってもらうしかない。そうすれば、あとは自分が何とかまとめる事ができる。
そんな事をオズバーンが考えていた矢先、ゴドウィンがリシャールに迫った。
「如何(いかが)でございましょう? ご承諾(しょうだく)いただけますか? 」
その時、やっとリシャールが重い口を開いた。打つ手がないオズバーンの状況を察してくれたのだろう。
「では、正直に申し上げましょう。 わたくしは、イングランドと―――いや、北海帝国とあまりお近づきになりたくないのです。 親戚づきあいなど真っ平(まっぴら)御免(ごめん)こうむりたい! ですから前回、この縁談をお断りしたのです 」
オズバーンの顔が固まった。
うん、確かにはっきりと断ってくれた‥‥‥。
けど、それははっきり過ぎではないでしょうか‥? 率直な言葉ではありますが、外交的にかなりまずいのでは‥‥!? そこまで言っちゃうと、わたしの口添えくらいでは交渉をまとめる事はできないかも‥‥‥。
オズバーンは段々腹が立ってきた。
無言のあなたに変わって、ずっとわたしが相手をしてたんだから、その間に何か良い返答を考えておいてくださいよ。 やっと出た言葉が、よりにもよって『親戚づきあいなど真っ平(まっぴら)御免(ごめん)こうむりたい 』って―――そりゃ言い過ぎでしょう。 もうちょっと婉曲(えんきょく)な表現もあるだろうに‥‥ まったく、この無骨者(ぶこつもの)が!―――オズバーンは心の中でそう罵(ののし)った。それは体調の悪さがなさせた、ささやかなる抵抗であった。
とはいえ、この場を平和裏(へいわり)に乗り切りつつ、縁談は断らなければならない。どうすればいい?―――オズバーンは頭脳を高速回転させ、その打開策を思案した。
その最中(さなか)、ゴドウィンがリシャールに声を掛けてきたのだ。
「ほう‥ 我が国と姻戚(いんせき)となる事がそれほどお嫌ですか? 」
その顔からは笑みが消えていた。そこには、さきほどまでのへりくだった態度は微塵(みじん)もない。
「で‥ それは、どのようなご理由からでしょうか? 」
まずい、これは戦争になる―――オズバーンは一気に吐き気が込み上げてきた。