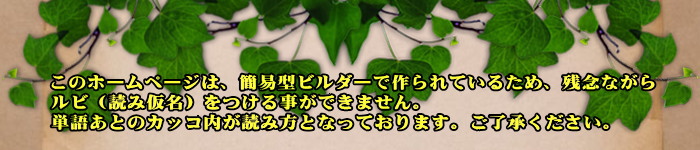
12
1026年 ファレーズ城・広間(1)
馬小屋の軒下(のきした)に腰を下ろす頼純とサミーラを、ジッと見詰める人物がいた―――なめし革職人(ペルティエ)の娘、エルレヴァである。
彼女は、ロベール伯から遣(つか)わされた白馬で、この豪雨の中、領主の館(メヌア)へと招(まね)かれていた。
広間へと通されたエルレヴァは、ずぶ濡(ぬ)れになった頭巾付きの外套(マント)を脱ぐと、伯爵が現れるまでの間、ぼんやりと窓の外を眺(なが)めていた。
そこからは、馬小屋にいる頼純達の姿が見えた。そして、自分の命を救ってくれた二人が好き合っている事にも気づくのである。
「なるほど。 そうだったワケね 」
当時の女性には、刺繍(ししゅう)と噂話(うわさばなし)、あとは恋愛ぐらいしか娯楽はなかった。それだけに、たいていの女性は、男では気づかないような、かすかな恋の香りも、敏感に嗅(か)ぎ取る事ができたのである。
エルレヴァもその例外ではなかった。
頼純とサミーラは、東洋人らしく決して自分の胸中(きょうちゅう)を口にする事はなかった。しかし、彼らのはにかんだ笑顔は、エルレヴァに二人が好意を寄せ合っている事を教えてくれていた。
その時、口論する声が聞こえてきた。
「だって、子供が‥ 赤ちゃんができたんだよ! 」
「だから‥ 何度も申し上げておりますように、ノルマンディー公爵家の血を引く方は、身分卑(いや)しき者とは結婚などできないのです。 教会とて、そのような婚姻(こんいん)を認める事はありません 」
大声を上げながら広間へと入ってきたのはロベールと執事(アンタンダン)のティボーだった。
「そんな事よりも―――『山犬のジャン』が死んでしまったのですぞ。 暗殺の依頼人は不明のままです。 このままでは、また若が狙われるやも―――」
エルレヴァがすでに広間に通されているとは知らなかったロベールは、彼女に気づくと『あッ 』と声を上げた。『結婚は認めない』という話を聞かれてしまったからだ。
かたや、その話をエルレヴァに聞かせるために、ここで待機するよう命じていたティボーは、彼女を一瞥(いちべつ)すると、横柄(おうへい)な口調で言った。
「本日は、お前なんぞにかもうとるヒマはない。 さっさと家に帰るがよい」
召使いに下知(げち)する時と同じ物言いだった。
ティボーはエルレヴァを蔑(さげす)んでいた。それは、彼女が下賤(げせん)の者だからだけではない。妊娠を理由に、伯爵の妻になろうとする心根(こころね)を卑(いや)しいと思っていたからだ。
「じい‥ いくら何でも、そのような言い方はないであろう。 彼女は、未来のファレーズ伯爵夫人になるやも知れぬ方なのだぞ 」
ロベールを振り返ったティボーは、エルレヴァに指を突き付けると、苛(いら)立った声を上げた。
「ご冗談を! この女は、革なめし職人(ペルティエ)の娘でございますぞ。 獣の腐臭(ふしゅう)が体に染(し)み込んだ家の者にございます! そのような者が、伯爵夫人になれましょうや 」
「い‥ いや‥ 」
「貴族とは言わぬまでも、富豪の娘であれば‥ じいとて、ここまで反対はいたしませぬ。 しかし、この女の父・フルベールは身分卑(いや)しきだけでなく、この町の嫌われ者―――近在(きんざい)の者はみな憎んでおる人物です。 それぐらいは、若とてご承知のハズ! 」
ティボーの言う事ももっともであった。
「そ‥ それは、そうだが―――では、我が子は‥ 生まれてくる赤ん坊はどうなるのだ? 」
「結婚ができない以上、庶子(しょし=婚外子)という事になります。 当然、家督(かとく)の相続権は一切与えられませぬ。 まあ‥ 養育費ぐらいなら、払ってやっても誰も文句はいいますまいが――― 」
「よ‥ 養育費だけ‥? 」
とりつく島のないティボーに、ロベールは弱り果てた。
「どうせ、そんな事じゃないかと思っておりましたわ 」
ロベール達のやり取りに、エルレヴァはうんざりしたように声を掛けた。
「執事(アンタンダン)様がおっしゃるように‥ 今日はこれでお暇(いとま)いたしましょう。 お話は、また日を改めておうかがいする事といたします 」
ロベールは、エルレヴァが不快に思っている事を知りながらも、この場のややこしい問題がとりあえず先送りにできると安堵した。
「え? そ‥ そう? そうしてくれると、助かるよ‥。 ありがとう。 また、必ず連絡するから 」
「‥‥‥ 」
「へへへ‥ 」
エルレヴァの冷たい視線をロベールは愛想笑いでかわそうとする。
そんな優柔不断(ゆうじゅうふだん)な態度に、エルレヴァは呆れて言葉が出ない。
「後日、このワシからお前の父に連絡をしよう 」
ティボーは尊大(そんだい)な態度で命じた。
「しかしながら‥ お前の腹の子は、たとえ庶子(しょし)といえど、ロベール様の―――いや、ノルマンディー公爵家の血を引く者である。 あだや疎(おろそ)かにしてはならぬぞ。 よいな! 」
「ええ‥ 大丈夫ですよ。 この子は絶対に堕(お)ろしたりはいたしませんから。 どうぞ、ご安心を―――! 」
皮肉たっぷりの返事をティボーに返したエルレヴァは、床に置いていた外套(マント)を拾い上げながら、今度はロベールに話し掛けた。
「ところで、伯爵様‥ アナタ様はわたくし達を助けてくれたあの武人―――ヨリズミ殿にご興味がおありになるのでは? あれほどお強い方を目(ま)の当たりになさったのなら、おそらくは――― 」
「い‥ いや‥ まあねェ‥ そりゃあ、気にはなるけどさァ‥‥ 」
「だったら‥ あの方を家臣として、召(め)し抱えられればよろしいのに! そうすれば、ずっとお側(そば)に控(ひか)えさせる事もできましょう 」
「え? 」
唐突(とうとつ)なエルレヴァの話に、ロベールは戸惑(とまど)った。エルレヴァはその伯爵の瞳を見据えて確認する。
「いかがです? そうなさりたいのでしょう? 」
ロベールはしばし、息を吸う事も忘れてしまった。
それはハッキリとした願望ではなかったが、頼純と出会って以来、ずっと感じていた事であった。
「け‥ けどォ‥ ヨリ殿はロレンツォ殿の大切な家来だし―――いくらこちらが召(め)し抱えたいって思っても、そう簡単に手放してはくれないだろうから‥‥ 」
そう言いながらも、ロベールの欲望はドンドンと膨(ふく)れ上がっていった。それはまるで、友人の妻に恋するかのように、いけないと判っていても押さえる事のできない望みだった。
「だったら‥ わたくしがいい方法を授(さず)けて差し上げますわ 」
それは、ロベールの心を縛り付けていた鎖を破壊するに、十分な台詞(せりふ)だった。
ロベールはどうしても頼純が欲しくなってしまったのだ。
× × × × ×
ロレンツォ一行がファレーズに着いて6日目に入っていた。二日間続いた雨のせいで、いつもより長い逗留(とうりゅう)であった。だが、ぬかるんでいた街道からようやく水が引き、重い荷馬車でも進めるようになったと物見(ものみ)から報告を受けたのだ。
ロレンツォ達は次の地・カーンへと向かうべく、荷造りを始めていた。
カーンからは、モン・サン・ミッシェルを経て、レンヌへと入り、ナント、ボルドー、さらにはフランス国境であるピレネー山脈を越えて、イベリア(スペイン)のナバラ王国へと至る予定である。
そこから、サラセン人が支配する『コルトバのウマイヤ朝(後(ご)ウマイヤ朝)』へ入国しようとしていた。
むろん、キリスト教会はイスラム圏内への入国を禁じている。
しかし、ロレンツォはインドの旅以来、冒険心が治まらなかった。
ヨーロッパ一の金持ちとなった彼の旅は、もはや商売とは無縁である。それは、諸国(しょこく)の人々と出会い、語らうための漫遊(まんゆう)の旅であり、見知らぬ文物(ぶんぶつ)や風景と出会うための遊山(ゆさん)の旅であった。
そして、彼はさらなる大冒険まで考えていたのである。
そんな彼らの元へ、領主ロベールの召使いが訪(おとず)れた。
「今夕(こんゆう)の送別の夕食会を前に、主(あるじ)ロベールがロレンツォ様、およびヨリ様にお会いしたいと申しております 」
「了解いたしました。 すぐにお目通(めどお)りにうかがいますとお伝えください」
ロレンツォはそう返事を返すと、頼純に目配(めくば)せをした。
「はッ 」
頼純は荷造りの手を止め、立ち上がった。
× × × × ×
ロレンツォと頼純、そしていつものサラセン人通訳が、領主の館(メヌア)の広間へと通されると、ロベール伯爵は玉座から立ち上がり大いに歓迎した。
「ささ‥ どうぞこちらへ。 近くまでお進みくださいませ 」
広間には、執事(アンタンダン)のティボーと騎士(シュヴァリエ)であるレオン兵士長、さらに四人の衛兵と三人の召使いがいた。
ロベールは目一杯の笑顔で二人に話し掛けてきた。
「どうも‥ 出立(しゅったつ)のご準備でお忙しい中、わざわざお呼び立てして申し訳ございません 」
頼純の背後に立った通訳は、どこかの国の言葉で彼の耳元に囁(ささや)きかけた。
ロベールはやや緊張した面持ちで本題を切り出した。
「じつは‥ 先日、わたくしとエルレヴァを助けてくださったヨリ殿とサミーラ殿にお礼がしたいと思いまして――― 」
一拍の間(ま)をとるように大きく息を吸うと
「で‥ 奴隷であるサミーラ殿を、このわたくしにお売りいただきたいのです! 」
と申し出た。
ロレンツォと頼純は一瞬キョトンとなる。
やがて、ロレンツォが固い笑顔で返した。
「いやいやいや‥ せっかくのお申し出ですが、サミーラはすでに買い手がついております。 このヨリが――― 」
ロレンツォの話を最後まで聞かず、ロベールが強引に割り込んできた。
「ならば‥ こちらは、その二倍の料金をお支払いいたしましょう。 奴隷は売り物なのですから‥ 高い料金を提示(ていじ)した方に落札(らくさつ)権があるのでは? 」
いつも笑顔のロレンツォがスッと真顔になった。
「そのような事はございません。 いったん取り決めた契約は、あとでさらに有利な条件の買い手が現れようとも‥ 必ずや履行(りこう)せねばならないのです。 それが商売というモノ! ましてや、今回はヨリがすでに支払いまで済ませております。 どうか、おあきらめください 」
「そうですか‥ ヨリ殿はすでにお支払いされておられましたか。 それは残念! けれど、わたくしとてサミーラ殿を当家の召使いにしようと思っていたワケではないのです 」
「‥‥ 」
いつもの事であるが、ロベールはロレンツォや頼純が不快な顔をしている事に気づいていない。
「わたくしは、サミーラ殿がヨリ殿と結婚なさるのがよろしいかと思いまして‥‥ そのお手伝いをさせていただきたかったのです 」
唐突な言葉に、ロレンツォはキョトンとした顔になった。
「はあ!? ヨリとサミーラが結婚―――? 」
「ええ‥ お気づきになりませんでしたか? 二人は愛し合っていらっしゃるのですよ 」
怒りと恥ずかしさで、顔が真っ赤になっていく頼純。その拳(こぶし)がきつく握り締められていく。
「ククク‥ 」
しかし、彼の口から漏(も)れる唸(うな)り声も、ロベールの耳には届いていなかった。
「わたくしは、ヨリ殿に感謝の印として‥ 奴隷のサミーラ殿を買い取り、贈(おく)り物としたいのです。 ですから、サミーラ殿はどうかわたくしにお譲(ゆず)りください。 ヨリ殿から受け取られた料金は、お返しになればよいでしょう 」
ロベールは、憤怒(ふんぬ)の目で睨(にら)みつけてくる頼純を、得意満面の笑顔で覗(のぞ)き込んだ。
「そして‥ ヨリ殿には、わたくしの家臣となっていただきたい! そうすれば、貴族の身分と領地をお与えいたしましょう♡ 」
その言葉に、一瞬広間が静まり返った。
やがて、『おおお! 』と声が轟(とどろ)いた。レオンをはじめとする兵士達の驚きの声である。いくら命を救ったとはいえ、それは破格の報償(ほうしょう)だからであった。
ロベールはよい人である。
貴族であるというのに、地位をカサにいばったり、人を見下したりしなかった。誰にでも優しく接し、丁寧な言葉遣(つか)いで話す。五代前の先祖は盗賊団だったというのに、彼はフランス宮廷のしきたりがしっかりと身についた良家のお坊ちゃまだった。
だが、言い方を変えれば、いまだに少年のような性格なのだ。
幼い頃に『貴族の習慣だから』と父母から引き離されたロベールは、ティボーにさんざん甘やかされて育てられた。
それゆえ、彼は優柔不断(ゆうじゅうふだん)で、すぐに人を信用し、欲しいモノは手に入れないと気が済まない―――そしてもっとも問題なのが、その場の空気を読めない事であった。それで、兄や父をよく怒らせていた。
「一方、ロレンツォ殿には‥ サミーラ殿の代金とは別に、大樽(たる)一杯に詰めた銀貨を差し上げましょう 」
金(きん)がほとんど産出されないヨーロッパでは、銀本位制(ぎんほんいせい)が主流であった。つまり、金貨は存在せず、取引はつねに銀貨で行われていたのである。
しかも、いまだ物々交換が主流であり、貨幣(かへい)経済自体が発達していないのだ。
そんなヨーロッパにあって、大樽(たる)一杯の銀貨と言えば五十万ドゥニエ(だいたい5億円ぐらい)を越える。
そのとてつもない金額は、ロベールがいかに頼純を欲しているかを現していた。
しかし、ロレンツォはわずかな嘲笑(ちょうしょう)を浮かべただけだった。
「なるほど‥ それはなかなかの報酬(ほうしゅう)ですねェ 」
それが皮肉だと気づかないロベールは、嬉しそうに応える。
「―――でしょう? 」
途端に険しい目つきとなったロレンツォは、見下すように言い放った。
「しかし、ロベール様はまァだ判っていらっしゃらない。 わたくしはヨーロッパ一の金持ちなのですぞ! たかが、樽(たる)一杯の銀貨ぐらいで、命の次に大切な宝を手放すとでもお思いか! 」
「あ! 」
ロベールは、やっとロレンツォ達が怒っている事を理解した。
先ほどとは違った意味で、広間は沈黙してしまった。
その静まり返った中に、サラセン人通訳の小声だけがボソボソと漏(も)れ聞こえてくる。
いつもにこやかなロレンツォだけに、彼の怒りを買った事はロベールにとって大きな衝撃となり、狼狽(うろた)えるばかりであった。
「あ‥ い‥ いや‥ わたくしはそういうつもりではなくて――― 」
傍らに立つティボーが、主人に代わってロレンツォに尋(たず)ねた。彼は、ロベールが恥を掻(か)かされたと思い憮然としている。
「では、いかほどの銀貨を積めば、ロレンツォ殿はご納得されるのですか? 大樽(たる)10個ならばご満足か? 」
その挑戦的な態度に、ロレンツォは冷徹な目を向ける。
「そうですな‥ では、裏のモッド(盛り土の丘)ほども積み上げていただきましょうか。 それほどの銀貨が、このヨーロッパに存在するのであればの話ですが―――♡ 」
ティボーは、そのあまりの金額に口を開けたまま固まってしまった。
涙をうっすらと滲(にじ)ませているロベールに、ロレンツォはちょっとやりすぎたかなと反省した。
「とはいえ‥ わたくしとヨリは対等な関係です。 彼がここに留(とど)まり、貴族になりたいと言うのなら、わたくしにはそれを止める権利はありません。 どのように金を持とうとも‥ 商人には、人を貴族にする事はできぬのですから 」
ロベールは上目遣(うわめづか)いに、恐る恐る尋(たず)ねた。
「で‥ では―――? 」
「どうぞ‥ ヨリにご確認ください。 わたくしは彼の意見に従いましょう 」
微(かす)かな可能性に期待を膨(ふく)らませたロベールが、頼純に目を向けた。
「い‥ いかがです、ヨリ殿? わたくしの家臣となって、このファレーズでサミーラ殿と結婚したり‥ 貴族になったり‥ 子供を作ったり‥ 幸せになったりしてみませんか―――? 」
ロベールの問いを、通訳は少し遅れて頼純の耳元で囁(ささや)く。しかし、頼純はロベールをジッと睨(にら)んだまま何も語らない。
「‥‥‥ 」
ロベールは顔を強張(こわば)らせながらも、もう一度尋(たず)ねてみる。
「いかがでしょう‥? 」
「‥‥‥ 」
だが、やはり頼純は黙ったままである。
その沈黙に不安になったロベールは、今度は通訳に確認する。
「つ‥ 通訳さん‥ わたくしの言葉はちゃんと伝えていただけましたか‥? 」
とその時、聞いたコトもない声が天井に響いた。
「ッたく! 誰がこんなくだらねェ事を考えやがったんだ? 」
声の主は頼純であった。
「そ‥ それは、このわたくしが―――ええ? 」
その異様な事態に気づいたロベールは、ポカンとしたティボーやレオン兵士長、さらにはロレンツォにまで確認する。
「は‥ 話した‥? 話したよねぇ? いま、ヨリ殿がフランス語で話したでしょう? 」
ふて腐れた態度の頼純が、流暢(りゅうちょう)なフランス語でまくし立てた。
「話したよ。 話せますよ、フランス語ぐらい! いつもは話せねェフリをしていただけさ―――このボンクラ野郎!! 」
その怒声に広間の誰もが言葉を失っていた。