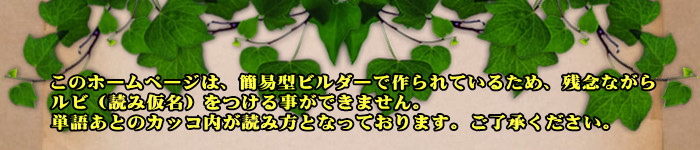
33
1026年 ファレーズ城 礼拝堂
ファレーズ城の祝宴(しゅくえん)もすでに三日目に入っていたが、そのにぎわいが衰(おとろ)える事はなかった。
だが、昼も夜もなく騒ぎ続ける『領主の館(メヌア)』の中で、礼拝堂(シャペラ)だけはただ一カ所静まり返っていた。
内側からかんぬきが掛けられ、誰も入る事が出来ないその内部は、嵐が去った後のように散らかっていた。左右の壁に沿(そ)ってそれぞれ10台ずつ立てられていた燭台(しょくだい)はすべてなぎ倒され、正面の祭壇(さいだん)は破壊されていた。その祭壇(さいだん)の傍らに、壊された十字架と教会の助祭・トマが横たわっている。
ロベール伯爵が生きていたという噂を聞いてから4日間、彼は泣き続けていた。そして、涙も涸(か)れ、疲れ果ててしまったのである。
あれほどまでに完璧な暗殺を企(くわだ)てたというのに、ロベールは意気揚々(いきようよう)とこのファレーズへ戻ってきた。
その事に対する激しい怒りに、トマは当初、地団駄(じだんだ)を踏んで悔(くや)しがり、十字架を振り回して壁に打ちつけ、獣のような声で意味の分からぬ言葉を怒鳴り続けた。礼拝堂からはかなり大きな物音が漏れていたが、伯爵の無事を知った家臣達が館(やかた)で盛大な前祝いをしていたタメ、誰もその音に気づかなかったのである。
やがて、トマの怒りは悔(くや)しさと悲しさに変わり、膝(ひざ)から崩れ落ちると、床に額(ひたい)を何度も何度も打ちつけ、
「なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜだ―――!? 」
と、大きな声で泣き続けたのだった。
彼は食事も取らず、水も飲まず、ひたすら泣き続けた。
三日目の日が沈みかけた頃になって、ついに精も根も(せいもこんも)尽き果てたトマは、急に睡魔(すいま)に襲われ、その場に倒れ込むようにして眠りに落ちてしまった。それは、明らかな現実逃避であった。
夜明け前に目を覚(さ)ました彼は、横たわったままピクリともせず、昼過ぎのこの時間になるまで、ただ壁の一点を呆(ほう)けたように見詰め続けていたのだ。
祝宴(しゅくえん)にはロベールの『恋人』として、エルレヴァが正式に招待されたらしい。
子供を身籠(みご)もった事も人々に知れ渡り、彼女がロベールの内縁(ないえん)の妻となる可能性は高くなってきた。
それだけは阻止(そし)しなければならない。
たとえ何人殺そうとも、けっしてエルレヴァに子供は産まさせない―――彼は固く心に誓っていた。
なぜならばトマは、エルレヴァに恋をしていたからである。
エルレヴァに恋をしているのは、トマの中にいる『小心者のジロア』の人格であった。『邪悪で狡賢(ずるがしこ)いトマ』の人格は、そんな恋などにはなんの興味も示さなかった。ただ、トマはいつもジロアの味方なのである。彼を守るためになら、どんな事でもした。
ジロアがこのファレーズへ赴任(ふにん)してきたのは、八年ほど前、彼が22歳の時である。その頃の彼は、邪悪なるトマの影響力が強く、反キリストの考えにのめり込んでいた。
そんな彼が、教会のミサでまだ少女であったエルレヴァと出会ったのだ。
15歳の彼女は、その頃からすでに充分に美しかった。そして、そのようにキラキラと美しく光り輝くモノを見たのは、ジロアにとって初めての出来事だったのだ。
金箔(きんぱく)が幾重(いくえ)にも貼(は)られた聖母子像の板絵や宝石がちりばめられた聖杯(せいはい)よりも、彼女の方がはるかに美しいと思った。
週に一度ではあったが、ミサで彼女の顔を見る事がトマにとっての極上の時間となった。
「助祭様、こんにちは♡ 」
そう声を掛けられた時には、天にも昇るような気持ちになった。
ジロアにとって、まさにこれが初恋だったのである。
彼は十数年ぶりに心の安(やす)らぎを得る事が出来たのだ。
ささくれ立っていたジロアの心も、やがて穏(おだ)やかになっていった。
当時の鏡はあまり質がよくなく、また高価であったために、誰もが自分自身の顔を見る機会はなかなかなかった。しかし、それでもジロアは、自分が醜(みにく)い事を十分に理解していた。
世間の女達は、彼の顔を見るとたいてい視線をそらした。彼女達からは、たとえ挨拶(あいさつ)ですら声を掛けられた事など一度もない。男でさえも、『なぜあのように醜(みにく)い者を助祭にするのか』と司祭に詰め寄るほどである。
その事をよく知っていたジロアは、他人から好感を持たれようとは思っていなかったし、自分も誰かを好きになるコトはないと思っていた。
前任のラウル司教は住民らの苦情に配慮(はいりょ)し、ジロアを人目につく教会から、館(やかた)内の礼拝堂(シャペラ)の管理人としたのだった。
それでも彼は、事あるごとに礼拝堂(シャペラ)を抜け出しては教会の仕事を手伝おうとした。そうすれば、何かの機会にエルレヴァに会えるかもしれないと思ったからである。
もちろん、神に仕(つか)える者が結婚する事は許されない。
そのような事は百も承知であったが、ジロアは高ぶる恋心を押さえる事が出来なかったのである。
それは一年に数回、横をすれ違う程度の出会いであった。
声を掛けられたのは、後にも先にもあの時一度だけである。
だが、トマはそれでもかまわなかった。
ただエルレヴァを遠くから眺(なが)めているだけで、幸せな気持ちになれたのだ。
しかし、一年ほど前から―――エルレヴァがロベール伯爵と付き合っているのではないか―――という噂がたちはじめた。
噂の元は、ロベールの警護隊であった。
その噂をはじめて耳にした時、ジロアはまったく信じなかった。
だが、その後も彼は様々な方法を使って、ロベールとエルレヴァの関係を調べ続けた。そして、それが事実である事を確信したのだった。
ジロアは、嫉妬(しっと)で気が狂いそうになった。
日に日にその嫉妬(しっと)の炎は大きく燃えさかり、ジロアの精神は完全に崩壊しかけていた。
その崩壊を防ぐために、『邪悪なるトマ』がふたたび現れたのだった。
トマは、ロベールを暗殺する事を決意した。
ジロアが壊(こわ)れてしまわないように、彼女に近づく者はすべて殺してやる―――トマはひさびさの自分の出番にほくそ笑んだのだった。
ぼんやりと壁を見詰めていたトマの顔が、しだいに邪悪な表情に変わっていった。
「まずはアイツだ! あのヨリとかいう異教徒のせいでわたしの完璧な暗殺は毎回失敗している! アイツを殺さなければ、ロベールを殺す事など出来ない 」
トマは最近とみに、『小心者のジロア』と『邪悪なるトマ』との境がなくなってきていた。
× × × × ×
ワニの頭は切断されてから一週間以上が立っていた。
血や水分は初めの二日ほどでほとんど流れ出し、冬間近の低い気温と乾燥した空気が腐敗(ふはい)を途中で停止させ、ミイラ化に向かっていた。
骨が大きかったため、全体の重量はさほど変わらなかったが、臭(にお)いが治まっただけでもずいぶんと違っていた。
三日三晩続いた祝宴(しゅくえん)もついに終わり、人々にすこし冷静さが戻ってきた頃、ノルマンディー大公リシャール3世よりの使者が来訪し、
『ロベール伯爵は、ドラゴン退治の証拠品とともに、ルーアンへ登城(とじょう)するように! 』との命(めい)が下った。
頼純はどうしようかと散々悩んだが、けっきょくルーアンへ行く事にした。
ロベールや周囲の者達からぜひ同行してくれと頼まれていたし、元はといえば頼純の悪口が原因で始まった事である。
そして、あの厳(いか)めしいノルマンディー大公が、そんなに悪い奴ではない事も判っていた。
さらには、その大公に『こんな巨大なワニを倒してやったぜ! どうだ、凄(すげ)ェだろう 』と自慢してやりたい気持ちもあったのかもしれない。
頼純は傭兵仲間のピエトロとロメオに、モン・サン・ミッシェルで待機する仲間達と合流するように指示を出し、自分はルーアンへ向かう旅支度をはじめたのだった。
翌日、ロベール伯爵と頼純は、ドラゴン退治に同行した二十三人の兵士を従(したが)えてノルマンディーの公都(こうと)ルーアンへと出発した。
一行は再び街道の人々に祝福されながら、4日間の道のりを進んだ。
『ドラゴン退治』の噂はすでに各地に広まっており、ロベール達の事はノルマンディーはおろか、フランス中の人々が知っていた。
頼純は『竜殺し(ドラゴンスレイヤー)』と異名(いみょう)を取り、彼とともに戦ったロベール伯爵も一躍有名戦士となっていた。
彼らは、一台の荷馬車に『ドラゴンの頭』を乗せ、もう一台の荷馬車には『ドラゴンの皮』を乗せて運んだ。『ドラゴンの皮』は、エルレヴァの父、革なめし職人(ペルティエ)のフルベールによって改めて処理され、腐りにくくなっていた。
さらには、旅の食料や道具などを乗せる荷馬車がもう3台ついて、計5台の馬車を牽(ひ)いていたのだが、祝福する人々から送られた供物(くもつ)を乗せるために、あと2台の馬車が必要となるほどだった。
ロベール一行のあとには、二千人ほどの野次馬が続き、人の塊(かたまり)が街道を移動しているようだった。
ロベールの周囲には、ドラゴン退治の話を聞きたがる四、五百人の民衆が常(つね)に詰め寄せていた。
その顔ぶれは、移動するたびにドンドンと入れ替わり、そのつど、彼は何度も同じ話を最初から語らなければならなかった。
また、その声も最後尾まではなかなか届かなかったのである。
そこで、ロベールは十人ほどの吟遊詩人(ジョグラール)を雇(やと)い、彼の話を代わってさせる事にした。
しかし人々は、美しい言葉で朗々(ろうろう)と語る吟遊詩人(ジョグラール)達よりも、朴訥(ぼくとつ)な語り口調(くちょう)のロベールの話を聞きたがった。
心優しきロベールは、苦笑いを浮かべながら、繰り返し繰り返しドラゴン退治の話を語って聞かせた。
そんなロベールを見て、頼純はより一層彼に好感を持ったのである。
やがて、一行は公都(こうと)ルーアンへと到着したのだった。
セーヌ川の北側沿いの丘に広がったルーアンの街は、人口二万人を大きく超える巨大都市であった。
フランスの首都パリが五万人、ヨーロッパ最大の都市ヴェネチアでさえ十万人ほどの時代である。二万人を越えれば、十分に大都市であった。
街と城を取り囲む塀は、ファレーズと同様に木製であったが、四重に施(ほどこ)されていた。すべての道幅は広く、建物も整然と建てられている。
ルーアンは、ローマ教会が古くから『大司教区』として定めており、その教会も大聖堂である。
五千軒近い家々から、富める者、貧しき者、老いも若きも、男も女も、あらゆる立場の人々が総出で、ロベール一行を出迎えた。
人々は、『ドラゴンの頭』を見ては腰を抜かし、続いてロベール達の勇気を讃(たた)え、彼らを祝福するために頭上に花びらを撒(ま)いた。
ルーアン城に到着すると、中庭で出迎えたリシャールの近習(きんじゅう)の騎士達も、荷馬車に積まれたドラゴンの頭の大きさに驚いた。
噂で、それが巨大である事は何度も聞いており、ある程度の心構えはしていたハズだったが、現物を見てみるとその迫力に肝(きも)を潰(つぶ)してしまったのである。
動揺(どうよう)が治(おさ)まると、彼らは荷馬車から丁重(ていちょう)に『ドラゴンの首』を降ろし、輿(こし)に載(の)せ替(か)えて宮廷の広間へと運んでいったのである。
ロベール伯も、父リシャール2世が亡くなる昨年までこの城に住んでいたため、中の勝手は分かっていた。
広間はファレーズ城の4倍ほどの広さがある。
そこに、二百人ほどの事務方や家政方の家臣、騎士や貴族、そしてその妻らが集まっていた。
そして、広間の中央奥、数段高くなった玉座(ぎょくざ)には、リシャール大公が尊大(そんだい)な態度で座っていた。
彼は人々の前でけっして笑顔を見せようとはしなかった。
それは威厳(いげん)を保(たも)つための素振(そぶ)りなのであろうが、まだ29歳だというのに、年寄り臭く、若さを感じさせなかった。
リシャールはたとえ何が持ち込まれようとも、けっして驚くまいと心に決めていた。
たが、運ばれてきた巨大な『ドラゴンの頭』を見た瞬間、思わず『ウッ‥! 』と声を上げ、玉座(ぎょくざ)から腰がすこし浮いてしまった。
集まった家臣達は一斉に、『お―――う‥! 』と驚嘆(きょうたん)の声を上げた。
気の弱い貴婦人などは、そのあまりにも禍々(まがまが)しい顔にショックを受け、気絶しそうになっている。
「兄上―――いえ、大公様‥ ご命令どおり、ドラゴンを退治して参(まい)りました 」
『ドラゴンの頭』に続いて、広間へと入ってきたロベールが改めて挨拶(あいさつ)をすると、リシャール3世は口の端(は)に微(かす)かに微笑(えみ)を浮かべた。
「ご苦労であった。 よくぞ、ドラゴンを退治した。 褒(ほ)めてつかわそう! 」
リシャール3世には珍しく、一同の前で弟ロベールを讃(たた)えた。
ロベールは恭(うやうや)しく頭(こうべ)を垂(た)れた。
「お褒(ほ)めの言葉を頂戴(ちょうだい)し、まことに恐悦至極(きょうえつしごく)にございます 」
リシャールは喜びの感情を抑(おさ)え、無表情で語った。
「本来ならば、主人であるこのわたしに背(そむ)いた罰(ばつ)としての任務である。 だが、同行したジョルジュ伯の報告によれば、まことに天晴(あっぱ)れな働きだったと聞く。 よって、望みの褒美(ほうび)をとらせよう。 欲しいモノがあれば、なんなりと申すがよい 」
「ありがとうございます。 しかしながら、今は欲しい物がございません。 褒美(ほうび)を頂戴(ちょうだい)するのは、いましばらく先に伸ばしてはいただけませんでしょうか? 」
「よいだろう。 好きにするがよい 」
せっかく褒美(ほうび)をやると言ったのに、その言葉を無下(むげ)にされ、リシャールはちょっとむくれた。
その時、家宰(セネシャル)であるオズバーン伯爵が高らかに声を上げたのだ。
「それでは、祝宴(しゅくえん)である。 大公様の御前(ごぜん)ではあるが、大いに飲み、大いに歌え。 大いに食べ、大いに笑うのじゃ! 」
広間には、何十ものテーブルが運ばれ、その上に大量の料理が並べられていった。
それから五日間にわたって、ルーアンの街はドンチャン騒ぎの祝宴(しゅくえん)となったのだった。