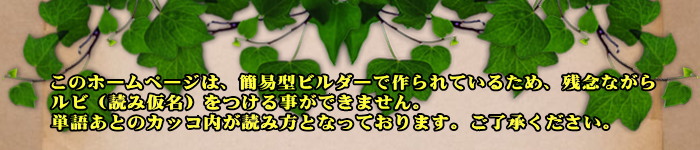
106
1027年 ファレーズの街(4)
助祭トマは、泣き止(や)んだギヨームを寝台の上で着替えさせていた。
赤ん坊のすぐ横には、彼の母親も静かな寝息を立てている。
意外にも、トマはギヨームの着替えを手際よくこなしていた。
彼はかつて、カーンの修道院に寄宿していた。
その醜(みにく)い容姿(ようし)から、なかなか受け入れてもらえなかったトマが、なんとか潜(もぐ)り込んだ3番目の修道院であった。
そして、そこには孤児院(こじいん)も併設(へいせつ)されていたのだ。
彼は17歳から21歳までの4年間、自分と同じように、親から見捨てられた赤ん坊や幼子(おさなご)の世話をしていた。
イタリアから始まった貧しき者達への救済―――修道院による病院や孤児院(こじいん)の運営は、ノルマンディー公領内でも試験的に始められていた。
× × × × ×
ヨーロッパ初の孤児専門施設は、ルネサンス期の1445年、イタリア・フィレンツェに建てられたサンタ・マリア・デリ・インノチェンティ捨児養育院(すてごよういくいん)と言われている。
だが、その原型は、11世紀にはすでに芽吹いていた。
そもそも、孤児院(こじいん)の源流は病院にある。
そして、その病院の原初を遡(さかのぼ)ると、ヨーロッパ社会においては、やはりキリスト教へとたどり着くのだ。
古代、ギリシャ社会やローマ社会にも、早くから病院や療養所が設(もう)けられていた。
しかしそれは、戦争で傷ついた兵士を回復させるための施設、あるいは、傷が深く普通の生活が送れなくなった元兵士の面倒を見るための施設であった。
では、兵士でなかった者がケガをしたり、病気になったりしたらどうしていたのか。
貴族なら医者を自宅に呼び付け、一般市民なら医者の家を訪(たず)ねた。
そして、貧しき者、弱き者達は野垂(のた)れ死にするしかなかったのだ。
ただし、当時のローマの医者達は、医学よりも祈祷(きとう)を専門にしていたようである。 どのような金持ちであっても、病気にかかればたいていは死ぬのだ。
やがて、ローマが共和国から帝国となり、皇帝が2代目ティベリウスとなった頃、帝国領土の東のはずれに一人の医者が現れた。
彼は各地を周り、神の話を人々に語りながら、貧しき者達の病(やまい)を治していった。
―――彼の名は、イエス・キリスト。
彼の死後、その言葉を信じた人々は、彼の教えを広め、弱き者達を救おうとした。
ローマ帝国はその言葉の強さを恐れ、彼らを激しく弾圧(だんあつ)していった。
それでも、彼らはくじける事なく、キリストの教えを広め続けた。
信仰は野火のように、静かに、しかし確実にローマ帝国内に広がっていく。
百年、二百年、そして三百年近く、それは続いた。
その成果あって、ローマ帝国内の多くの人々はキリストの教えを信じ、貴族達までもがその言葉に従(したが)うようになったのである。
313年、ローマ皇帝コンスタンティヌス1世は、ミラノ勅令(ちょくれい)を発布(はっぷ)し、キリスト教を帝国の国教(国が定めた、市民が信じるべき宗教)としたのである。
迫害を受け続けたキリスト教徒達は、やっと自由に集会を行う事ができるようになり、集会場である教会が次々と建てられていった。
そして、その信徒達が、キリストの教えを実践(じっせん)できる場所、個人の信仰をより深めれる場所―――修道院もまた、林立(りんりつ)したのであった。
そのキリストの教えとは、『彼らの神を信じる事』と『弱者の救済』であった。
それゆえ、病人、貧困者、宿無し者、外国人、ハンセン病患者、老人、そして孤児や捨て子などの弱者を救済するための施設が、修道院内に作られたのである。
記録にある最初の救護施設は、372年、現在のトルコのカッバドキアに司教バリジウスが建てたコミュニティである。 368年に発生した飢饉(ききん)の難民を救済するための施設であった。
その後、390年にはローマの貴族の娘であり、敬虔(けいけん)なキリスト教徒であったファビオラが病院を設立している。
こうした病院や療養所は、医学の発展とともに、東ローマ帝国やイスラム圏を中心に発展し、やがて中世のヨーロッパ社会へと広がっていった。
このキリスト教会による『慈善(じぜん)』が、病人だけでなく、1人では生きていけない老人や子供達をも救っていくのである。
× × × × ×
トマは修道院での奉仕のお陰で、乳児(にゅうじ)の扱(あつか)いにも慣れていたのだ。
トマはギヨームの産着(うぶぎ)をスルスルと脱がせていった。
× × × × ×
当時、赤ん坊はリネンの柔らかい布でくるまれ、その上からベルトを交差するように掛けられ、手足が動かないように固定されていた。
イタリアではとくに、包帯状のリネンをミイラのようにグルグルと巻き付け、他の地域よりもさらにきつく固定されていた。
これは『おくるみ(英、仏=スワドル)』と言い、紀元前2000年以上前から世界各地で―――いや、現在でも多くの地域で使用されている産着(うぶぎ)である。
四肢(しし)を伸ばした状態で赤ん坊を固定し、手足に歪(ゆが)みが出ないよう矯正(きょうせい)していた。

イタリア方式のきつめに巻かれた『おくるみ』が、絵画や書籍に多く残っていたため、それはミイラやミノムシのようなイメージであるが、他のヨーロッパ諸国ではもう少し緩(ゆる)めに巻かれていたようである。
もちろん、当時の布はたいへん高価であり、赤ちゃんの産着(うぶぎ)でさえ財産目録に記録されるほどである。
しかしながら、さすがは伯爵様のご長男。 ギヨームはふんだんに産着(うぶぎ)を与えられていた。
× × × × ×
日没直後に『領主の館(メヌア)』の礼拝堂(シャペラ)を離れたトマは、ブノアを連れて、母屋(おもや)の2階にある伯爵の寝室に隠れていた。
母屋(おもや)にはまだ意識のある警護兵、親衛隊もいたが、順調にバタバタと意識を失い続けている。
ティロルドのヨリ達は礼拝堂(シャペラ)へ向かったようだが、自分がいない事を確認したら、すぐにここへ戻ってくるだろう。
しかし、彼らが血眼(ちまなこ)になって探している自分が、まさか彼らのすぐそばに―――それも、伯爵の寝室にいようとは思いもしまい。
トマはそう考えた。
そもそも、トマがこの事件を起こしたのは、ロベール伯爵を殺害し、エルレヴァとギヨームを誘拐するためであった。
そこで、町のすべての井戸に毒薬をまき、全住民を眠らせたのだ。 無人の中、事を易々(やすやす)と遂(と)げれるようにである。
ところが、ティロルドのヨリ達が予想外に早く戻ったせいで、計画は中途半端に頓挫(とんざ)してしまった。
もはや、ロベールの殺害はほぼ不可能であろう。
さらに、彼らは山賊襲撃事件やドラゴン退治の際の毒物混入事件などの真犯人が、自分である事にも気づいているようだ。
だったら、エルレヴァとギヨームをさらって、この街からとっとと脱出するしかない。
ウンチまみれの産着(うぶぎ)を取り替えたトマは、ギヨームを抱き上げた。
ギヨームは気持ちがいいのか、ニコニコとしている。
そんな赤ん坊を、トマは冷酷(れいこく)な微笑(えみ)で見下ろしていた。
トマが、邪魔で鬱陶(うっとう)しいギヨームまでをも誘拐しようとするには、それなりの理由があった。
エルレヴァ1人を連れ去っても、彼女は息子ギヨームを恋しがり、その心はいつまでもファレーズに残るであろう。
そうなると、自分がどんなに彼女を大切に扱(あつか)おうとも、親切にしようとも、彼女の心が自分に向く事はない。
逆に、ギヨームとともに連れ出せば、エルレヴァは激しい抵抗をしないはずであった。
そのまま、薄暗い洞窟(どうくつ)の中で、3人だけで1、2年ほど暮らすのだ。
そして、頃合いを見てギヨームを殺害する。 薬を飲ませて、病死に見せればいい。
ギヨームの死に、エルレヴァは大いに嘆(なげ)き悲しむであろう。
日々、涙に暮(く)れるに違いない。
そんな彼女に、自分は一心に誠意を尽くすふりをするのだ。 2人だけの洞窟で、ともに悲しみ、慰(なぐさ)め、励(はげ)まし続ける。
そうすれば、エルレヴァもやがて自分に心を寄せはじめると思われた。 たとえ、己(おのれ)を誘拐した男であっても、醜(みにく)い男であってもだ―――彼はそう考えていたのだ。
× × × × ×
暗い広間の中は、停滞感(ていたいかん)に包まれていた。
頼純達は、ロベール伯爵が倒れた後、彼を床に寝かせると、広間に倒れている兵士や使用人らの様子を確認していった。
折り重なって呼吸困難になっていないか、頭部や胸部を激しくぶつけていないか、出血はしていないかなどを確認し、危険を感じる者にはそれなりの処置をした。
だが、その先をどうすべきか、打つ手が思いつかなかったのだ。
現在、頼純達がしなければならない事は二つあった。
ひとつはロベール伯爵の警護であり、もうひとつは助祭トマの捜索(そうさく)である。
ロベール伯の警護は、頼純とグラン・レイの2人がいれば十分だと思われた。
たとえ、10人、20人に襲われようとも、敵は頼純1人で十分対応できる。
その間に、グラン・レイがロベール伯を背負(せお)い、安全な場所まで移動すればよいのだ。
となれば、ドニ、ニコラ、ラウルの3人は、トマ探索(たんさく)の任務にあたってもよいわけである。
だが、頼純達は、トマがどこにいるのか、見当もつかなかった。
たった三人だけで、真っ暗闇(まっくらやみ)の街を闇雲(やみくも)にさまよってみても、トマが見つかろうはずもない。
さらには、これだけ大量の病人を放(ほう)って、犯人かどうかも判らないトマを追うべきなのか―――そんな事よりも、倒れた人々を死なないように最低限の処置をし、リシャール公爵による救援を待つべきなのか―――難しい判断であった。
長い長い沈黙を破って、グラン・レイが口を開いた。
「なぁなぁ‥ 俺達ゃ、どうして眠り病にかからネーんだろう? 」
「さ‥ さあ‥? 」
『カラス団(コルブー)』達は首を傾(かし)げた。
「俺達と、ゴルティエやロベール伯爵様とは何が違う? 街の人達とどこが違うんだよ? 」
「え~~~と‥ 日頃から、訓練してる‥ とか? 」
「若くて‥ 体力がある‥‥ から? 」
「そんなの、ゴルティエの兄貴だって同じだろうが! 」
「あ、そっか‥! 」
こうした『カラス団(コルブー)』達の問答は、どう行動すべきか悩んでいた頼純にとって、少々腹立たしいものであった。
確かに、事件の原因を探る事は、『探索方(たんさくがた)』としては重要である。
そして、こんな状況の中でも取り乱す事なく、それをおこなえる彼らは、大した度胸の持ち主なのであろう。
しかしながら、妻であるサミーラが倒れた現在、頼純の心は千々(ちぢ)に乱れていた。
先ほどは、強がりを言ってしまったが、時とともに不安はどんどんと膨張(ぼうちょう)していく。
今にも叫んで、家に帰りたかった。
だが、日頃から『カラス団(コルブー)』達に、「常に冷静であれ」、「使命を何より優先させろ」と訓示(くんじ)をたれている彼にとって、それは許される事ではない。
それゆえ、己(おのれ)の気持ちを抑(おさ)え込み、冷静なフリをしていたのだ。
そして、こうした心の乱れが、これからどうすべきかの決断さえも鈍らせているような気がした。
そんな中で、グラン・レイ達のやり取りは、あまりにも呑気(のんき)に聞こえ、頼純の苛立(いらだ)ちをつのらせるのであった。
一方、目の前のグラン・レイ、ニコラ、ドニ、ラウル達だって、大切な人々―――親や兄弟、友人、そして『カラス団(コルブー)』の仲間達までもこの病(やまい)に倒れていた。
ファレーズのすべての人々が昏睡(こんすい)し、街の至る所にその姿が転がっているのだ。
そしてこの病(やまい)は、こうして眠りについたまま、やがて死に至るかもしれないのだ。 自分達が眠り病に罹(かか)る可能性だって十分にある。
まだ、何も判っていなかった。
にもかかわらず、彼らはさほど動揺(どうよう)していなかった。
倒れた者達であふれかえる不気味なこの大広間で、平然と議論を交わせるほど落ち着いている。
それは、日頃の訓練の賜物(たまもの)ともいえたが、彼らは基本的に人の生き死にに関して鈍感なのであろう。
判りやすく言えば、『バカ』なのだ。
× × × × ×
トマがエルレヴァとギヨームをつれて、この街から脱出するのは、そう簡単な事ではなかった。
当初の計画では、館(やかた)の通用口横に停めた馬車まで、エルレヴァを引きずって運び、そのあとギヨームを抱いて馬車に乗せるはずであった。
体重の軽い女性といえども、意識のない人間をそこまで移動させる事は、かなりの重労働である。 相当な腕力とそれなりの時間が必要とされる。
大きな物音や気配(けはい)、赤ん坊の泣き声も発せられるに違いなかった。
だが、街の全員が眠っている状況ならば、そうした事も気にする必要はないのだ。
トマは休み休み、時間を掛けてエルレヴァとギヨームを連れ出そうと考えていた。
ところが、現実は計画と違い、眠っていない数名の者―――ティロルドのヨリ達がいた。
しかも、彼らはよりにもよって、すぐ下の広間に居座っているのだ。
勘の鋭いあの男がいる屋敷の中で、眠った成人女性をコッソリと運び出す事は、なかなかに難(むずか)しい事であった。
さらに、脱出用の馬車も、館(やかた)の通用口横には停められていない。
眠っていない馬が見つかれば、ティロルド達はすぐにその異変に気づくからだった。
そこで、馬車は昼間の内に、西の端(はし)にある新しい教会の裏手に停めていた。
しかし、階下の通用口まででさえ危(あや)ぶまれるのに、そんな遠くまで、完全に気を失ったエルレヴァを運ぼうなど、力なきトマにとって限りなく不可能な事であった。
そこで、彼は怪力の男に手伝わせる事にしたのである。
傍(かたわ)らにボーと突っ立つ『カラス団(コルブー)』の男だ。
この若造が力持ちにはとても見えなかったが、トマには怪力にする術(すべ)があった。
そしてこの男なら、ティロルド達に見つかったとしても、すぐにはバレないであろう。
トマはブノアに囁(ささや)きかけた。
「俺が3、2、1と声を掛けたら、お前はとんでもない力持ちになっている。 街一番の怪力だ。 岩でも牛でも、どんな物でも軽々と持ち上げる事ができる。 いいな? 3‥ 2‥ 1! 」
ブノアの目が大きく見開かれた。
「さあ‥ 伯爵夫人を抱きかかえるんだ 」
ブノアはエルレヴァを軽々と肩に担(かつ)いだ。 トマは、スヤスヤと眠っているギヨームを腕に抱いた。
そして、二人は静かに部屋を出たのである。
× × × × ×
「そうか! 分かった! 分かりましたよ! 」
ニコラが素っ頓狂(すっとんきょう)な声を上げた。
「今、眠り病にかかっていないボクらは、全員がリジュー村へ行った者達です! 」
「え!? 」
「まあ‥ 確かにそうだけど‥ 」
ドニがムッとした声で尋(たず)ねる。
「だからなんだよ? 俺達がリジュー村に行って、あそこで何かあったのか? まさか、おいしいワインを飲んだからてんじゃネーだろうな? 」
グラン・レイモンドがドニを指差した。
「それだよ! あのサンマリクレール修道院のワインも、トマが作った薬が入ってたんだろう? それが解毒剤だったんだ! 」
「え? げ‥ 解毒剤? 何の解毒剤です? 」
「そ‥ それは‥ トマが作った毒の――― ほら、あのォ‥ なんだ‥‥」
グラン・レイは勢いを失速させ、口ごもった。
ラウルが混乱した顔を向ける。
「えっと‥ それって、おかしくないですか? あのォ――― 俺達が先に解毒剤を飲んで―――あれ、違う‥ リジューのフェビアン家での大宴会は、俺達に解毒剤を飲ませるために――― じゃないですよねェ‥ あれ、俺、何を言おうとしたんだっけ‥? 」
ニコラがつぶやいた。
「そもそも‥ 街の人達は、毒をどうやって飲んだんだろう? 」
『カラス団(コルブー)』達の議論を聞きながら、頼純は気づいた。
彼自身もかつてはこの青年らと同じ種類の人間だったのだ。
人の生き死にに関して鈍感な、『バカ』であった。
ただ、いまの頼純はそんな鈍感さを疎(うと)む側の人間になってしまったのだ。
自分の命よりもずっと大切なもの―――愛する妻やそのお腹に宿った我が子に、心を弱くしてしまったのだろう。
ああ、やはりエルキュール爺(じい)さんの言ってた通りだった―――頼純は焦燥感(しょうそうかん)の中で、そのような事をぼんやりと考えていた。
またまた、ニコラが大きな声を上げた。
「違う、井戸だ! この街の井戸水を飲んだ人達が、眠ってしまったんですよ! 」
「けど、俺達だって井戸水は飲んでるぜ。 一昨日(おととい)帰ってきてから、何杯も井戸水を飲んだ 」
「おそらく‥ 一昨日(おととい)以前の水を飲んだ者か‥ あるいは、水を飲んだ量が一定量を超(こ)えた者! 」
「なるほど。 そして、その毒は体の大きさに比例して眠り病を発生させる。 だから、犬猫から罹(かか)り、次に子供。 やがて、大人の女や老人が倒れ、最後に大人の男といった順番になったんだ! 」
「そっか‥‥ 」
「なるほど‥ 」
「それで、赤ん坊は眠り病にかかっていない! 赤ちゃんはお母さんのおっぱいを飲んでいるから 」
「あ! 何匹かの野良犬や野良猫が眠ってないのも、奴らは水たまりの水を飲んでいるからだ 」
「と‥ 鳥もだ! 鳥も飛んでる! 人から水を与えられてるにわとりは寝てて、カラスは飛んでます! 」
仮説ながら、原因を特定した『カラス団(コルブー)』達は、それが正しいのか答え合わせを求めるように頼純を振り返った。
それまでずっと黙っていた頼純は、頷(うなず)くとようやく声を上げた。
弱い自分と対照的に、成長した弟子達を感心していた。
「ともかく‥ 俺達はこれ以上井戸水を飲むのはやめよう。 腹を壊すかもしれないが、川の水を飲むんだ 」
「はい! 」
『カラス団(コルブー)』達は、目を輝かせてそれに応(こた)えた。
彼らは、未熟な自分達の考えを、勇者様が否定しなかった事に感動していたのだ。
その時、裏口付近で物音がした。
赤ん坊の泣き声もした。
「―――? 」
一同の動きが止まる。
そして、しばし考え込んだ。
それから、グラン・レイが叫んだ。
「しまった! ギヨーム様だ! ギヨーム様の声だ! 」
ここにいたって、やっと頼純も気づいたのである。
「トマがギヨーム様を連れ出そうとしているに違いない! 捕まえろ! 奴を捕縛(ほばく)するんだ 」
頼純は太刀(たち)を掴(つか)むと走り出した。
「グラン・レイとドニは、ここで伯爵を守れ! ニコラとラウルは、俺に着いてこい! 」
「はい! 」
頼純は当初の予定――自分がロベール伯を警護するという計画を無視して、トマを追い掛けていた。
トマを捕まえ、解毒の方法を聞き出すためであった。
彼は、その解毒剤を一刻も早くサミーラに飲ませたかったのだ。