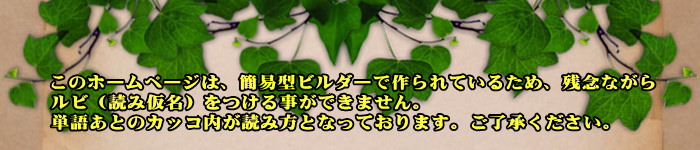
53
1026年 イングランド王国ウィンチェスター城
12月24日、デンマーク王国・ロスキレ宮殿では、北海帝国クヌート大王主催の晩餐会(ばんさんかい)が開かれていた。主イエス・キリストの降誕祭(こうたんさい)である。
降誕祭(こうたんさい)=クリスマスは、イエス・キリストの誕生日を祝う日ではない。
イエス・キリストの誕生日は、かつて何度も大論争となったが、いまだにハッキリと判らないのだ。それゆえに、クリスマスは、主イエスがこの世に誕生してくれた事に対し、感謝する日となったのである。
ちなみに、『Christmas(クリスマス)』とは、『CHRIST(キリスト)』と『Mass(ミサ)』を組み合わせた合成英語で『キリストのミサ』という意味である。フランスでは『Noel(ノエル)』、デンマークでは『Jul(ユール)』と各国によって呼び方も違う。また、『イブ』は、夜や晩を表す『evening(イブニング)』と同義の古語『even(イブン)』が変化したものである。
では、その『前夜祭(イブ)』とはなんであろうか。
これはキリスト教会の教会暦で、『その日』とは、前日の日没(晩課)から始まり、当日の日没に終わると定められていたからである。つまり、12月25日は、24日の日没から始まり、25日の日没までとなるのだ。
そこで、24日の日没後にその日の最初のミサを行い、その直後の晩餐(サパー)で主イエスの降誕(こうたん)に感謝するという習わしができたのである。
楽しい食事会も一段落し、クヌートは義弟でありデンマーク摂政(せっしょう)のウルフ伯(アール)とチェスを始めた。
二人は幼い頃からのチェス仲間でもあった。
クヌートはこれまでの長い長い戦争と、その戦火の合間に何十回となく交えた二人のチェスを思い出し、深い郷愁(きょうしゅう)を感じていた。
だが、その一方でウルフ伯(アール)に対する疑念は膨(ふく)らみ、クヌートの心は淀(よど)んだ思いで一杯になっていた。
× × × × ×
話は1カ月ほど前に遡(さかのぼ)る。
イングランド北部のノーサンブリア領を任せていた伯爵(アール)―――エイリーク・ハーコナルソンが突如死去した。
彼はクヌートの父・スヴェン1世の代から仕(つか)えてくれた忠臣(ちゅうしん)である。
クヌートの初陣(ういじん)には副官となって、戦争というモノを一から教えてくれた師匠でもあった。
さらに2年後のイングランド再侵略の際には、その出陣の隙(すき)をつかれて、彼の祖国であり領地でもあったノルウェーをオーラヴ・ハーコナルソンに奪われてしまう。それでも彼は、文句のひとつも言うわけでなく、イングランドでの戦闘に専念してくれたのだ。
クヌートにとってエイリーク・ハーコナルソンは大恩人なのである。
また、彼の息子であるハーコン・エイリクソン伯(アール)は、現在もクヌート大王の副官として要職を務めてくれている。
そんな老臣エイリーク・ハーコナルソン伯(アール)が死んだのである。
クヌートがその葬儀に参列しないわけにはいかなかった。
彼はそのタメだけに、片道10日以上かかる船旅で、わざわざデンマークからイングランドまで戻ってきたのだ。
葬儀も無事終了し、クヌートは三日後に居城であるウィンチェスター城からデンマークに出立(しゅったつ)する手はずになっていた。
そんな彼のもとにゴドウィン伯(アール)が訪れたのだ。そしてあの密談を持ちかけられたのである。
「お‥ お前はこの私に、ウルフ伯(アール)を殺せと言うのか‥? 」
「ノルマンディーとの政略結婚と‥ 邪魔者の排除―――これは一石二鳥の策だとは思われませんか? ぜひ、そうなさいませ♡ 」
ゴドウィンは甘い言葉でクヌートをそそのかした。
その日は、まるで熱に浮かされたように、クヌートはそうするしかないと信じ込んでしまった。
だが、翌朝になると、幼い頃からの親友であり、妹の夫でもあるウルフ伯(アール)を殺すなど、とても無理だと思った。 そんな事が出来ようはずはなかった。
クヌートが心変わりするのではないかと案じたゴドウィンは、再び城を訪れた。これで3日続けての登城(とじょう)となる。
そんなゴドウィンに、クヌートは苦渋(くじゅう)の表情で語った。
「お前のいいたい事はよく判っておる。 しかし、何の非もないウルフを‥ 最も近しい家臣であるウルフを、自分の都合や不信感で殺したとあっては道理が通らん。 他の家臣達も、今後このわたしを信頼してはくれなくなるだろう 」
案(あん)の定(じょう)、クヌートは昨日の決意を翻(ひるがえ)していた。ゴドウィンは、嫌な予感に登城(とじょう)した自分を、心の中で褒(ほ)めてやった。
「つまり‥ 殺すための大義名分が必要だとおっしゃるのですね? 」
ゴドウィンは煮え切らないクヌートに、少々尖(とが)った声を返した。
「いやいや‥ そういう意味ではない‥! 殺さなくとも方法はあると――― 」
そんなクヌートを、ゴドウィンは皮肉っぽく笑った。
「殺す大義名分なんぞ、いくらでもございますよ! 」
「だから‥ そうではなくて――― 」
ゴドウィンはクヌートの言葉を遮(さえぎ)るようにして話を続けた。その目には怨(うら)みがましい思いが込められていた。
「わたくしは、ウルフ伯(アール)がデンマーク摂政(せっしょう)をお辞めになった時、大王様に何度も申し上げたハズですぞ―――これは謀反(むほん)でございますと! しかし、大王様はそれをお信じにならず、ウルフ伯(アール)になんのおとがめもなさいませんでした 」
「あ‥ あれは‥ お前が、ウルフを快(こころよ)く思っていない事は知っておったし‥ それで、あやつを陥(おとしい)れようとしているのだと思って――― 」
「大王様がわたくしごときを、いかに思われましょうともかまいませぬが―――それこそが大義名分でございます 」
「え? 」
ピンとこないクヌートに、ゴドウィンは迫った。
「よいですか!? あの方は、大王様になんのご相談もなさらず、その職務を勝手に放棄(ほうき)されたのですぞ! これは立派な反逆罪。 本来ならば、十分死刑に値(あた)いたします 」
「―――あ‥! 」
「そもそも‥ ウルフ伯(アール)があの時、摂政(せっしょう)を引退されたのはなぜだとお考えですか? 」
「そ‥ それは、我が息子・ハーディクヌーズを次なる国王としてデンマーク国民に認めさせるために――― 」
普段は家臣達から『雷王(らいおう)』と恐れられるクヌートも、本日は少々押され気味であった。
「なぜ、ウルフ伯(アール)が摂政(せっしょう)をお辞めになると、デンマーク国民はハーディクヌーズ様を次の王と認めるのでしょうか? そんなわけがないでしょう。 それはウルフ殿の一方的な言い訳でございます 」
「ま‥ まあ‥ 」
「そうやって、国民や貴族会議を脅して、ハーディクヌーズ様が次の国王だと無理やり認めさせてみても‥ 彼らは心の中でどう思っているでしょうか? ああ‥ やはり、我々はウルフ伯(アール)がいなければ何もできない―――そう痛感するに違いありません。 ウルフ伯(アール)の存在感がより強まるダケなのです 」
「‥‥‥ 」
クヌートは思わず黙り込んでしまった。親友を信じたいという気持ちもあったが、ゴドウィンの言葉には説得力があった。
「もし、あの時‥ 大王様があのように素早くご出陣なさり、事態の収拾をなさらなければ‥ 無政府状態となったデンマーク国内はさらに混乱を極めていたでしょう。 それをノルウェー・スウェーデン連合は待っていたのではありませんか? その機に乗じて本格的に攻め込まれていたら、指揮官のいないデンマーク王国は簡単に陥落(かんらく)していたはずです 」

ゴドウィンは今日、クヌートの顔を最初に見た時、すでに『ピン』ときていた。
いくら言葉巧(たく)みに騙(だま)そうとしても、クヌートはウルフ伯(アール)を処罰できないと悟ったのだ。ウルフ伯(アール)は彼のたった一人の友達だからである。
ならば、その二人の友情を断ち切ればよい―――ゴドウィンは作戦を変更する事にした。正攻法でウルフ伯(アール)の裏切りを訴え、二人の信頼にヒビをいれようと考えたのだ。
「そしてもし‥ ノルウェー・スウェーデン連合がデンマークを占領したのなら―――その時、誰をその統治者にすると思われますか? 」
「‥‥‥ 」
「奴らとて、大王様が天才的に戦(いくさ)上手な事は承知しているはずです。 ノルウェー達が一番恐れていたのは、まさにクヌート大王様とイングランド軍なのです。 その大王様に対抗するためには、短期間でデンマーク国民の人心をまとめ、自分達と三カ国連合を組み、大王様の率(ひき)いるイングランド軍と互角に戦える人物をデンマーク国王に据(す)えねばなりません。 だとすれば、その適任者は誰でしょうか? 」
クヌートの震える唇から言葉が漏れた。
「ウ‥ ウルフ‥ 」
ゴドウィンは立てた人差し指を何度も振った。
「そうです! それはウルフ伯(アール)しかいないのです! ならば、ノルウェー・スウェーデン連合がはじめからその旨(むね)をウルフ伯(アール)に打診し、計略を組んでいたとは考えられませんか? 」
「ま‥ まさか‥ そのような――― 」
「その一方で‥ ウルフ伯(アール)にとってこの計略は、なんの損失もない博打(ばくち)なのですぞ。 たとえ失敗したとしても、大王様からのおとがめはなく‥ 成功すればデンマーク国王になれるのです。 ならば、誰でもその賭けにはのるでしょう。 たとえ親友を裏切ってでも‥‥ 」
「う‥ 裏切った―――? ウルフ伯(アール)がこのわたしを裏切ったというのか‥!? 」
ゴドウィンはクヌートの目を見据えて言い切った。
「そうです! ウルフ伯(アール)は大王様に対して謀反(むほん)を起こされたのです 」
クヌートは、あり得ないとばかりに首を振る。
「そんな事はない! あの男に限って、わたしを裏切るなどという事は絶対にない‼ 」
クヌートはキッパリと否定した。しかし、その顔は少々強張っている。
彼もゴドウィンの言葉に半信半疑なのだ。
だがそれは、その言葉を半分信じたという事でもある。ウルフ伯(アール)は無条件に許される存在ではなく、非があれば処罰される対象となったのだ。
「まあ‥ 大王様がわたくしの言葉を信じられないとおっしゃるのなら‥ それはそれでけっこうでございます。 たとえ、乗っている軍船が沈もうと、頭上に槍(やり)の雨が降ろうと、わたくしは大王様のご命令に従うだけですから‥‥ 」
ゴドウィン伯(アール)は素っ気(そっけ)なくクヌートの気持ちを突っぱねてから、もう一度引き寄せるように言葉を掛けた。
「しかしながら‥ もしウルフ伯(アール)に些少(さしょう)でもお疑いを感じられましたら、それを確認する方法はございます 」
「か‥ 確認する方法―――? 」
「ウルフ伯(アール)ご自身に、直接聞いてみるのです 」
クヌートはその言葉を鼻で笑った。
「バカバカしい。 お前らしくもない戯言(たわごと)じゃ。 仮に、ウルフが謀反(むほん)を企(くわだ)てていたとしても‥ わたしに尋(たず)ねられて、それを正直に白状するワケがなかろう!? 」
「その時に、こうお尋(たず)ねください―――お前は、何のために摂政(せっしょう)を辞めたのかと‥? 」
「それは‥ 事件後すぐに、ウルフに詰問(きつもん)ずみの事じゃ。 いまさら、問うても意味はあるまい 」
「ここでは、ウルフ殿が何と答えるかは重要ではありません。 大王様のその問い掛けに、あの方がすぐに答えられるかどうかを見るのです 」
「は!? 」
「言葉を発するまでに一拍以上の『間』が空けば、その答えはおそらく嘘でしょう! 一瞬ドキリとしたウルフ殿が、言い訳を思い出そうとして『間』が空くのです。 もし、大王様に対し、二心(ふたごころ)がなければ、淀(よど)みなく答える事ができるはずです 」
「ま‥ まあ‥ それは、そうかもしれんが‥‥ 」
もちろん、これはゴドウィンの詭弁(きべん)に過ぎない。
人は誰でも、自分の失敗に言及(げんきゅう)されれば、言葉に詰まるものである。とくにウルフ伯(アール)のような、愚直(ぐちょく)と言ってもよいほどの律儀者(りちぎもの)は、なおさらに窮(きゅう)する。
その事が判った上で、ゴドウィンはクヌートを欺(あざむ)いたのである。
彼にとって、クヌートがずっと『ウルフ伯(アール)から裏切られた』と信じ続ける必要もなかった。しばしの間―――ウルフ伯(アール)が血に塗(まみ)れるその瞬間まで、そう思ってくれていたらよいのだ。
これからの数日間で、クヌートはしだいに疑心暗鬼(ぎしんあんき)に陥(おちい)っていく。
そして、心に着いた『疑い』の黒い染みは、広がる事はあっても、消える事はけっしてないのだ。
ゴドウィンは今度こそ、クヌートをガッチリ罠(わな)にはめてやったと確信していた。
× × × × ×
「クヌート王‥ クヌート王―――! 」
その言葉にクヌートは我に返った。
目の前にはにこやかに微笑(ほほえ)むウルフ伯(アール)がいた。彼は友との久々のチェスが嬉(うれ)しいのだ。
「アナタの番ですよ♡ 」
「あ‥ ああ‥ 」
ウルフ伯(アール)に促(うなが)されて、クヌートはチェス盤の中央にいた『象(アルフィル)』を斜め前に2マス移動させた。
その一手にウルフがほくそ笑んだ。
「その手でよろしいのですか‥!? では、チェック! 」
あと5手で自分が詰む―――ウルフ伯(アール)はそうよんでいた。
ウルフ伯(アール)が『将軍(フェルズ)』を摘(つ)まみ上げた時、クヌートが声を掛けた。
「お前は、あの時なぜ‥ 摂政(せっしょう)を辞任したんだ‥‥? 」
クヌートの声は少し震(ふる)えていた。そして、ウルフの手が止まった。
「え? 」