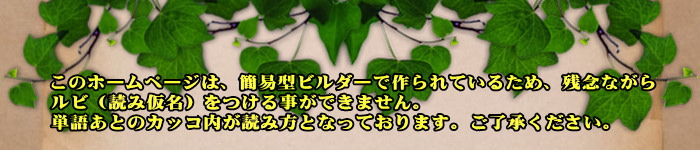
第89話
1027年 ファレーズ郊外
「いやぁ~~~あ‥ 今日はまた、いい天気になったねェ‥ 」
「ほんとですねェ‥ 」
頼純とロベール伯爵は、初夏のさわやかな風が吹き抜けていくファレーズの丘から、眼下に広がる耕地を見下ろしていた。
麦畑では、春蒔(ま)き小麦や大麦の種蒔(たねま)きも終わり、休閑地(きゅうかんち)では油菜(あぶらな)の黄色い花が一面に咲き乱れている。
遠くには、つい先日まで白い花を満開にさせていた修道院のリンゴ畑が青々と広がっていた。10月に収穫されるこのリンゴは、すべてリンゴ酒(シードル)の材料にされる。
この当時、ヨーロッパでの種蒔(たねま)きは、『ばらまき法』が一般的であった。
農地は、犂(すき)によって硬い土地を掘り返し、そこから出てきた土の塊を鎚(つち)で叩き潰し、ハローという道具でその表土を柔らかく平らにしていく。大変な手間暇(てまひま)をかけて造られているのだ。

農具ハローと種まく人・11世紀頃(バイユーのタピストリーより)

農具ハローと種まく人・14世紀頃( Luttrell Psalterより )
こうして耕(たがや)された農地に、丁寧(ていねい)に指で穴を穿(うが)ち、そこに数粒の種籾(たねもみ)を入れて、土を被(かぶ)せていく―――のではない。
腰の袋からつかみ出した種籾(もみ)を、放り投げるようにして、ただ地面にばら撒(ま)くのである。文字通り、畑の上に種籾(もみ)をばら撒(ま)くだけであった。
当然、籾(もみ)は地表に乗っているだけ、地中には埋まっていない。
となれば、鳩やカラスなど様々な鳥が集まってきて、それらをついばんでしまう。こうして、ほとんどの種籾(たねもみ)はなくなってしまうのだ。そして、わずかに残った種籾(もみ)だけが発芽を許されるのである。
それゆえに、種蒔(たねま)きは、『一粒は鳩のため、一粒はカラスのため、一粒はしなびてしまうため、そして一粒は生育のため』と謳(うた)われていた。
中世における麦の収穫率が、わずか2倍(1粒の種籾(たねもみ)から2粒の籾(もみ)しかとれないという事)と極端に悪かったのも、このような非効率的な種蒔(たねま)きがその要因のひとつだったのかもしれない。
しかも、この愚かな種蒔(たねま)き方法は、このあと800年以上も続く事になるのだ。

『種まく人』1850年( ジャン=フランソワ・ミレー画 )
傭兵騎士団(ゼルドナァ)『シュヴェールト』によるファレーズ城襲撃から5ヶ月が経っていた。
住民達の生活もずいぶんと落ち着き、真っ黒に焼け落ちた街の復興も進んでいた。
そんな人々の生活を視察するため、ロベール伯爵と頼純は馬で出かけたのである。
「そろそろ秋蒔(ま)き小麦の収穫期となります。 農民達も忙しくなるでしょうから、復興作業もいったん中断でしょうか‥? 」
ロベールの問い掛けに、頼純が答えた。
「ああ‥ けど、アンタが大量に配った大鎌があるからねェ‥ 麦刈りもずいぶんと楽になるだろう。 すぐに、作業に復帰できるさ 」
「だと、よいのですが‥‥ 」
ロベール伯爵が農民にもたらしたのは大鎌だけではない。
彼らのほぼ全員が鉄の鍬(くわ)を所有しているのだ。
これは、彼らにとって一番高価な財産だった。自分の命と家族の命の次に大切な農具である。
だからあの襲撃の際も、ほとんどの農民がそれだけは忘れずに持ち出していたのだ。
さらにロベール伯爵は、高価な重量有輪犂(じゅうりょうゆうりんすき)を何台も購入し、それを牽(ひ)く何十頭もの馬や牛とともに、農民達に貸し出しをしていた。

重量有輪犂・14世紀頃( Macclesfield Psalterより )
これら最新鋭の農機具によって、農作業の効率は昨年と比べ極端に上がっていたのである。
お陰で農民達には余暇(よか)が増え、その時間はファレーズ再建にあてられた。
その再建工事は無償の賦役(ふえき)労働ではない。働いた日数に応じて伯爵から手間賃が支払われたのだ。
貴重な現金収入に、人々はこぞって工事に参加していた。
「そろそろ街へ引き上げネーか? 」
「そうですね‥ 」
軽く汗ばみながらも農地の視察を終えたロベールと頼純は、『領主の館(メヌア)』へ戻るべく馬の手綱(たづな)を返した。
やがて目の前には、作り直されたファレーズの街が広がっていく。
『領主の館(メヌア)』以外のほとんどの建物が燃え尽きてしまったファレーズだったが、いま新たなる街に生まれ変わりつつあった。
真っ黒に焼け落ちた城下、城外からは瓦礫(がれき)がすべて撤去(てっきょ)され、そこに新しい家々が建っているのだ。
さらに、街作りのための工事関係者が大量に流入し、ファレーズは活気に満ちていた。
城外の下町に入ると、
「こんにちは、伯爵様! 」
「ごきげんよう、ティロルド殿‥ 」
「伯爵様、ヨリ様‥ 今日はよいお天気ですね♡ 」
「あ‥ 伯爵様だ! ティロルド様だ! わーいわーい♡ 」
と、老若男女、幼い子供達まですべての住民から、2人は声を掛けられる。
ちなみに『ティロルド』とは、執事(アンタンダン)ティボーの兄、老騎士エルキュールが、頼純に付けたあだ名である。そのあだ名が街の人々にもすっかり定着していたのだ。
ただし、それがどういう意味なのか―――付けた本人もようとして判らなかった。
「以前の生活に戻れて、みんな生き生きとしてますね 」
「おいおい‥ 以前の生活ってコタァねーだろう。 貴族から商人、手工業者、自由農民ときて貧者に至るまで、すべての家が新築になったんだぜ。 鍋(なべ)、釜(かま)、桶(おけ)も全部新品だ。 みんな、以前よりずっと楽しいに決まってる 」
そんな頼純の言葉に、ロベールは
「それもこれも、ヨリ殿の助言のお陰です 」
と礼を言った。
だが、頼純はロベールの功績を素直に褒(ほ)めてやる。
「いやいやいやいや‥ すべては、お前さんの政治的決断の賜物(たまもの)さ。 特に、真っ先に鍛冶屋(かじや)を再建した事はすばらしい判断だった 」
伯爵はちょっと照れながらも、嬉(うれ)しそうだった。
あの大火災の直後、まだ煙が立ち上る中で、ロベールが一番最初に手をつけたのが、4軒の鍛冶屋(かじや)の復旧だった。
寒風吹き荒(すさ)ぶ中、可能な人手を総動員して、鍛冶屋(かじや)の作業場を再建したのだ。それから、鍛冶職人達はフル稼働で製品を作り続けた。
新たなる街を造るには、大量の木材が必要となる。
それを切り出すためには、何十本もの斧(おの)が必要であった。
切り出された木材は、丸太や板に加工せねばならず、のこぎりもたくさん必要となってくる。
そして、それらを使って家を建てるには、莫大な量の釘(くぎ)も必要となるのだ。
さらに、新しく建った家で人々が生活するには、ナイフや鍋(なべ)、釜(かま)、それらを火に掛ける五徳なども必要になる。
ともかく、ありとあらゆる物を鍛冶屋(かじや)は造り出さなければならなかった。
ファレーズの4軒の鍛冶屋(かじや)は、親方を中心にかなり効率のよい作業態勢をとっていたし、焼け残った物の再利用も行われたが、それでも500軒近い世帯の生活道具をすべて生産するには少々無理があった。
そのため、近在の鍛冶屋(かじや)やルーアン、パリの鍛冶屋(かじや)にまで買い付けにいかなければならない事もたびたびあったほどである。
家屋の建設も同様であった。
集められるだけの大工職人が投入された。また、力仕事や単純作業では一般の住民も多く参加した。
彼らはまず、貴族や金持ち達の屋敷の建設に従事したが、すぐにその半分以上の職人が、ファレーズ住民の大半を占める貧しい者達の住宅建築に取り掛かったのだ。
しかし、貧しい者達ではその建築費をとても賄(まかな)えないため、これらの家屋はロベール伯爵が資金を出して建造する事となった。住民らは完成した家を、家賃を払って借りるという形にしたのだ。
それでも、最貧の者達はその家賃が払えず、さほど広くもない1軒家に、2家族、3家族で暮らさざるを得なかった。
それは窮屈(きゅうくつ)な生活であったが、かつてのすきま風が吹き抜ける掘っ立て小屋や雨漏りのする馬小屋のような住居より、はるかに快適であった。
そしてこれは、画期的な施策(しさく)だったのだ。
領主様が、下々(しもじも)の民に住まいを提供するなど、見た事も聞いた事もない話であったからだ。
この政策は、公都ルーアンはもちろん、首都パリでも宮廷の噂話になるほどであった。ただし、その噂話はけっして好意的なものではない。ロベール伯爵を『変わり者』として呆(あき)れていたのだ。
だが、彼らはロベールがおこなった公営住宅の本質が判っていなかった。
そこまでしないと、多くの貧者達は家無しとなって街から出て行ってしまう。流民となってしまうのだ。
人口が少なく、流動性もあまりないヨーロッパにおいて、住民の流出は本人達にとっても街にとっても損害が大きかった。
人口が減れば、農工業の生産力は低下し、一方でそれら生産物の購買力も低下する。つまり、領地内の経済規模が縮小してしまうのだ。そうなれば当然税収も減少してしまうだろう。
こうした人口減少を防ぐため、頼純がロベールに進言して行われた策であった。
頼純はこれまでの長い長い旅で、火事のみならず、戦争や天災によって消滅してしまった街や村の話をたくさん聞き、実際にその廃墟も数多く見てきたからだった。
人口の減少は、火事や戦争よりもずっと確実に街を破壊するのだ。
頼純ら2人が街の奥へ進んでいくと、先ほどからずっと聞こえていた『ドン、ドン、ドン、ドン』という地響きがさらに大きくなっていく。
城壁内に入れられた土が、何百人もの人夫によって突き固められていく音であった。
住民の家々もほぼ完成したので、街はいま新しい城塞(じょうさい)作りに着手していた。
「だいぶ城壁もできてきましたが‥ 完成まで、あとどのくらいでしょうか? 」
「あせっちゃいけねーよ! 工事はいま半分ってとこだから、外城壁の年内完成は無理だな。 来年の頭くらいになるだろう。 そこから『領主の館(メヌア)』の城壁の工事に入るから―――全体の工事は再来年(さらいねん)の今頃まで掛かるんじゃネーのか? 」
「あ‥ あと2年も掛かるんですか? もう‥ 待ちきれないなァ‥‥ 」
「まあまあ‥ お楽しみはあとにとっておいた方がいいんじゃネーのかい♡」
ロベールが楽しみにしているのは、これまで丸太だった城壁を石造りに作り替える事であった。
頼純と出会ってから、ずっとロベールが乞(こ)い願っていた『石造りの城』の建造を始めたのだ。
まずは、最も重要な城壁から始められた。
とはいえ、それは本当の意味での『石造り』ではない。
採石場から巨大な岩を切り出し、それをノミなどで四角く整形し、この街まで運搬し、それを人力の起重機(クレーン)で積み上げていく本格的な石造りは、莫大な人手と資金が必要となる。
街全体を新造せねばならないファレーズでは、さすがにそこまでの費用(コスト)は掛けられなかった。
さらに、その建造を担う専門家もいなかった。
そこで、まずはその基となる試作品を作り、そこから様々な問題点を見つけ、新たな技術を開発し、それらを蓄積していく事となった。
今回は焼きレンガを多用する事とした。
焼きレンガなら、何十万個と必要になるが、土と水をこねて木型にはめ、天日干しするところまでなら女子供、老人にでもできる。そうすれば、彼女達に金を払う事ができる。
これを高温の窯(かま)で焼き上げていくのだ。
ロベールは、都市再建という巨大公共工事によって、様々な人々が報酬(ほうしゅう)を得れるようにしたのだ。
頼純は中国・宋で捕囚(ほしゅう)となった時、配役(はいえき)(=強制労働)として首都開封(かいふう)の城壁修理を命じられていた。
その経験から、彼が指導した築城法は、『版築(はんちく)』という方法であった。
『版築(はんちく)』は、城壁の形に組んだ板枠の中に土を入れ、それを杵(きね)に似たやや太い棒で平らに、硬く突き固めていく方法である。
板枠の高さを徐々に上げていく事で、より高い土壁を造るのだ。
今回の外城壁の工事では、もとからあった丸太の城壁を利用して板枠を組んでいく事にした。
それが完成すると、周囲の板枠をはずし、カチカチの土壁の側面と上部にレンガを積み重ねて補強していくのだ。
この方法は、秦(しん)の時代からずっと続けられてきた築城法であり、万里の長城もこの方法で作られている(ただし、現在写真などでよく見られる万里の長城は、明の永楽帝の時代に作り直されたものである)。
宋では、レンガを積み重ねていく時、その接着にもち米の糊(のり)を添加(てんか)したモルタルを使っていた。しかし、ヨーロッパに米はないため、石灰モルタルのみで接着する事にした。
石灰モルタルは、水と砂と石灰を混ぜ合わせたものである。
もちろん、これらの有償土木工事を行うためには、巨額の資金が必要となる。
そこでロベール伯は、ファレーズで年2回の『市(マルシェ)』を開く事とし、その『市(マルシェ)』の今後10年間の開催権を金持ちに販売したのである。
ファレーズの街は、ドラゴン退治や傭兵(ようへい)騎士団殲滅(せんめつ)などでフランス国内でもたいそう有名になっていた。そんなファレーズで『市(マルシェ)』を開けば、見物がてら大勢の人々がやって来るだろうと踏んだのだ。
大規模な『市(マルシェ)』ともなれば、そこから上がる売上も莫大な金額となる。
この開催権を買った者は、その出資比率に応じて出店料や売上税など、多額の配当を受け取る事ができた。
この投資話に、ファレーズの金持ち―――革なめし職人のフルベールや毛織物商のオリヴィエなどはすぐに乗ってきた。それはたんに金儲けというだけでなく、街の復興に協賛(きょうさん)するという慈善(じぜん)的な意味あいもあった。
一方、彼ら以外のフランス中の豪商や貴族、教会などは、これが多額の利益を生む利権だと知り、競(きそ)って買い求めた。
お陰で、新しい街を造るための巨額な資金も、簡単に集める事ができたのである。
ロベール伯自身は、大金が簡単に手に入る『市(マルシェ)』に、さほどの思い入れがなかった。
彼の興味は、住民の8割以上を占める農家の生産性を上げ、彼らを豊かにする事であった。そして、そこから税金が徴収できればよいと考えていた。
贅沢(ぜいたく)さえしなければ、財政はそれで十分に賄(まかな)えるはずだった。
頼純とロベール伯爵は新たに整備された城下を抜け、『領主の館(メヌア)』へと戻ってきた。
2人は、間もなく取り壊される城壁の回廊(かいろう)へとのぼり、あらためて新たなるファレーズの街とその田園風景に目をやった。
「わが領地ながら、このファレーズはなんと美しいのでしょうか‥! 」
「ああ‥ 春のおぼろげな風情もよいが、初夏はさらによい。 目に映るすべてのものが、色濃く艶(つや)がある。 風の音や虫の声にも趣(おもむき)があって美しい 」
ロベールはキョトンとした顔で頼純を振り返った。
「ふしぎな表現ですね。 風や虫の音などが美しいとは―――わたしは気にした事もありませんでした。 それは東の国々の文化なのでしょうか‥? 」
そして、ふたたび風景に目を戻すとクスリと笑った。
「でも、なんとなくわかります。 いい表現ですね。 たしかに、色濃くて、艶がある‥‥ 」
二人はしばらく景色を眺(なが)めていた。
その時、頼純がポツリとつぶやいた。
「この美しい風景を見るのも、これが最後なんだろうな‥‥ 」
その言葉にロベールが敏感に反応した。
「え!? それはどういう意味ですか? 」
頼純は『しまった』とばかりに慌てて言い繕(つくろ)った。
「あ‥ いや‥ それは、ホラ‥ ロレンツォ殿もそろそろお戻りになる頃だし―――そうなったら、また行商の旅が始まるだろうからさ‥ しばらくは、ここへ来る事もネーのかなァって意味で――― 」
ロベール伯は頼純をジッと見詰めて言った。
「ヨリ殿は、またこのファレーズに戻ってこられるんですよね? そうお約束なさいましたよね!? 」
「う‥ うん‥ おそらく‥ たぶん、戻ってくると思う‥‥ 」
「本当ですか? ヨリ殿がいないと、この街の建設は進まないんですヨ! 」
「わかってる! わかってますって―――! 」
ウソをついてしまった頼純は、後ろめたさからか、固い笑いを浮かべた。
頼純はロレンツォ達とイベリア(=スペイン)に入り、そこから船に乗って日本へ帰るのである。もう、二度とこのファレーズに戻る事はなかった。
だが、彼の笑顔が強張ってしまったのは、ウソをついたからだけではなかったかもしれない。
―――別れるのがつらくなってしまったのだ。
頼純は、ロベールやファレーズの街が好きになっていた。もうしばらく、この地を離れたくないと思っていた。
それは、17歳から一所(ひとところ)に定住する事なくずっと旅を続けてきた頼純にとって、初めての執着であった。それだけに、彼自身もその感情をよく理解できなかったのである。
その時、大きな声が『領主の館(メヌア)』に鳴り響いた。
「ヨリ殿‥ ヨリ殿は、どちらにおいでじゃ? 」
その声は、館の跳ね橋を渡るピエトロのものであった。
彼は頼純を見つけると、息せき切って回廊(かいろう)の階段をのぼり、頼純の前へ進み出た。
「ロレンツォ様が‥ ロレンツォ様がお戻りになられました! 」
「はあ!? 」
Quand on parle du loup,on en voit la queue.(狼の噂話をすると、その尻尾が見える)
―――噂をすれば影である。