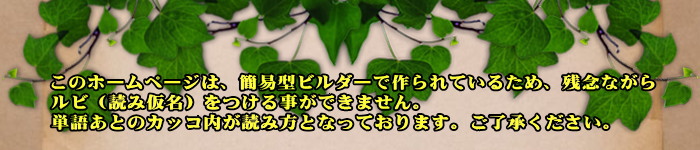
1
1026年 ファレーズの街
太古の昔から分厚い森林塊(しんりんかい)によって包まれてきたガリア(西ヨーロッパ)の地。
ローマ帝国の侵入以来、約千年の月日を掛けてずいぶんと切り開かれてはきたものの、まだまだその大半は巨木に覆われていた。
そんなガリアの北方、広大な森林地帯を抜けると、突如(とつじょ)緩(ゆる)やかに波打つ丘陵(きゅうりょう)地帯が出現する。
フランス王国ノルマンディー公爵領の街・ファレーズである。
正午を告げる教会の鐘(かね)が、町を囲む小麦畑に響き渡る。畑はすでに収穫を終えており、残った麦藁(むぎわら)があちこちに積み上げられていた。
その時、一団の騎馬が地鳴りを上げ、ファレーズの街へと続く一本道を駆け抜け、城門の中へと吸い込まれていった。
丘の上に立つファレーズの町は、ノルマンディーのどの町もがそうであるように、高い壁に囲まれている。城塞(じょうさい)である。

しかしその城壁は、近くの森から切り出されてきた背の高い丸太を町の周囲に何千本と立てただけのモノであり、近隣領との小競り合いや盗賊団の襲撃、野生動物の侵入などから街を守る程度の『囲い』に過ぎなかった。
その『囲い』の内側には、貴族達や僧侶、医者、裕福な商人などの富裕層、そしてその使用人と兵士を含めた約千人ほどが住んでおり、外側には農民や小商いの商人、加工業者など、貧しい人々二千人ほどが居(きょ)をかまえていた。
そのファレーズの町民達の驚きを尻目に、ぬかるんだ城内を一気に駆け抜けた三〇騎ほどの騎馬団は、街の中心部・板塀(いたべい)に囲まれた領主の館(メヌア)へと吸い込まれていった。
中庭で荒々しく馬から下りた騎士(シュヴァリエ)達は、駆け寄ってきた兵士達に手綱(たづな)を預け、しばしの休息をとる。
しかし、六人の武者だけは、分厚い茅葺(かやぶ)き屋根と丁寧(ていねい)に漆喰(しっくい)が塗られた壁を持つ館(やかた)の中へとまっすぐ向かっていった。
館(やかた)の中は、教会のように一階の大部分が吹き抜けの大広間となっており、奥には領主の椅子が鎮座(ちんざ)している。この広間は、領主が人々と出会う『接見の間(ま)』であり、領民(りょうみん)達を裁く『裁判所』であった。また、政治を行う『執務室』でもあれば、家臣や客達と食事をする『食堂』でもあった。
つまり、騎士達が来客ならば、この場で身を正し、領主の登場を待つのが礼儀であった。
しかし武装した六人の男達は、広間の分厚いドアを乱暴に開けるやいなや、ズカズカと広間の中を歩き回っている。
騎士達は、分厚いキルティングの鎧下(ガンベゾン)の上に、膝丈の鎖帷子(オベール=チェインメイル)を着用し、頭には鼻当て付きの兜(カスク)、そして腰には長剣(エペ)をぶら下げていた。
「ロベール! 」
広間に響き渡る大声でこの館の主を呼ぶ男が、彼らのリーダーである事はすぐに判る。
しかしそれは、彼が他の者達と違い、頭に兜(カスク)ではなく宝冠(コロネット)を載(の)せていたからでも、彼だけが鎖帷子(オべール)の上に長いマントを羽織(はお)っているからでも、ましてや、その留め金が幾つもの宝石で作られたフィブラ(ブローチ)だったからでもない。
男が他の者より遙かに尊大で、威圧的であったからである。その声に高い知性と人を引きつけてやまないカリスマ性を見出すからであった。
彼はリシャール3世。フランス王国北部を治める大領主、ノルマンディ公国の五代目大公(グランデュク)であった。
「ロベールはどこじゃ? ロベールは居らぬのか? 」
その声に、隣の部屋のドアが開き、僧侶が現れる。しかし彼は、来訪者がリシャール公爵御一行だと知るや、聖書を抱えたまま棒立ちとなってしまう。
「あ‥ た‥ 大公様! 」
彼はトマと呼ばれる、この街の教会で助祭(じょさい)を務める僧侶であった。
助祭とは、教会で司祭の仕事を補助する者の役職であり、教皇(きょうこう)、大司教、司教、司祭、助祭という教会のヒエラルキーの中にあって、最も低い地位であった。
トマは痩(や)せこけた青白い顔に目ばかりがギョロギョロと大きく、前歯は二本欠けていた。細い体にダルマティカと呼ばれる粗末な法服(ほうふく)をまとい、その姿はまさに『貧相』という言葉を体現するかのようであった。さらに、頭頂部を円形に剃髪(ていはつ)する聖職者特有の髪型・トンスーラが、その貧弱さに拍車を掛けていた。
「あ‥ あの‥ や‥ 館には、いま誰もいらっしゃらないのですが‥ 」
彼は小動物のようなおどおどとした態度でリシャール3世を窺(うかが)った。
そんな助祭をリシャールはジロリと一瞥(いちべつ)する。しかし、立派な髭(ひげ)を蓄(たくわ)えたその口が動く事はなかった。
リシャール3世は、いまだ29歳でありながら、ガッチリとした体躯とその威厳から、30代後半にさえ見えた。そんな大公様から睨まれたのである。トマがますます萎縮(いしゅく)するのは当然の事であった。
リシャールはこの館で何度か見かけたこの助祭が不快だった。ドブネズミのようなこの男を見る度にイライラとさせられるのである。
フランス国王は無論の事、ローマ教皇に対してでさえ意見を述べる事を許されたノルマンディ大公である。彼からしてみれば、地方教会の助祭など取るに足らない存在でしかない。
二人の立場は、文字通りライオンとネズミほども違っているのである。本来なら、そこにいる事すら気に留(と)める必要はなかった。
にもかかわらず、リシャールはこの城を訪れると、いつもこの助祭に気づいてしまう。それは、けっして大きな不快感ではないのだが、屍肉(しにく)に涌(わ)いたウジ虫を見た時のような、胸のむかつきを感じてしまうのだった。
そして、そんな小者(こもの)を必要以上に意識する、おのれ自身に対しても腹が立っていたのかもしれない。
リシャール公は胸中を悟られまいと、トマをあからさまに無視した。
「弟君の、ロベール伯爵はどちらへおいでじゃ? 」
お供の騎士の中でも、最年長となるアンリが見かねて、立ち尽(つ)くす助祭に声を掛ける。
その問いにも、緊張したトマは頭(こうべ)を垂れたままボソボソと答えるばかり。
「は‥ はい‥ あの‥ 伯爵様は本日、馬で森まで遠出をされたとか‥ 執事(アンタンダン)様なら、床屋へ瀉血(しゃけつ)に行かれただけですので、もうお戻りになられるかと思いますが‥‥ 」
弟の不在に、リシャール公はますます不機嫌になる。
「チッ‥ また、奴はおらぬのか! 」
そんな大公を尻目に、肉付きのいい騎士・シャルルが声を上げる。
「なんと‥ ロベール様は森まで遠出とな? お一人ではつまらんじゃろうに 」
背の高い騎士・フェルディナンがシャルルに呆れ顔を返す。
「いやいやいやいや‥ お主は何を申しておるか。弟君がお一人のワケなかろうが」
騎士達の中では比較的小柄なジョルジュが、その言葉に大いに賛同する。
「そうそう。 ロベール殿もお年頃じゃ。 馬駆(うまが)けと称して、どこぞの姫と逢(あ)い引きされておるに違いない 」
そんなやりとりを聞いていた助祭トマに変化が現れる。それは本当に他愛もない世間話であったにもかかわらず、先ほどまで泣きそうなくらいにビクビクしていた彼の顔から脅えが消え、思い詰めたように床の一点を凝視している。
「さすれば、カーンか、アルジャンタンあたりの姫君か? 」
「いや‥ クレシー伯の姫君も怪しかろう 」
「おお、それはよい。 あの姫君は、近年たいそう美人になったと評判じゃ。 ファレーズの伯爵妃殿下として申し分ないぞ 」
「だが‥ あの姫は、たしかガイ殿が籠絡(ろうらく)したハズ 」
大公の前であるというのに、彼らは恐れを知らないのか、あるいはよほど信頼し合った主従(しゅじゅう)関係なのか、はたまた大した呑気者(のんきもの)達なのか、騎士達のロマンス話はいつまでも続く。
しかし、お供である五人の騎士の内、たった一人その語らいに加わらぬ若武者がいた。彼は一人黙ってあたりを観察している。
クレポンの伯爵、オズバーン卿(きょう)である。
彼は弱冠22歳でありながら、大国・ノルマンディ公爵家の家宰(セネシャル)も務めていた。
家宰(セネシャル)とは、宮廷内での王家・公家(こうけ)の家政を司(つかさど)る執事であるが、領地の管理から騎士団の長までを兼ねるため,実質的には行政の最高職―――家老・大臣であった。
若輩(じゃくはい)ながらも、彼はその職にふさわしく、高い知性と冷徹さ、そして固い忠誠心を持ち合わせていた。 そのため、リシャール3世からも大いに信認されていたのである。

「ち‥ 違います! 」
騎士達の語らいを遮(さえぎ)る声が広間に響いた。
声の主は助祭トマであった。一同が注目する中、彼は幾分(いくぶん)かの脅えと抑えきれない怒りが入り混じった目で、恐れ多くもリシャール大公に進言したのである。
「ロ‥ ロベール様が‥ 伯爵様が、現在お付き合いなさっていらっしゃる方は、この町の革なめし職人(ペルティエ)の娘‥エルレヴァにございます! 」
あまりの言葉に、その場の全員が一瞬息を呑(の)んだ。
やがて騎士達は、信じられないといった顔で言葉を吐き出す。
「い‥ いや‥ そんな‥ 」
「革なめし職人の娘って――― 」
「あ‥ あり得ないでしょ‥! 」
しかし、トマは信じてもらおうと、必死に一同に訴えかける。
「本当でございます! 本当に、なめし革職人フルベールが娘―――エルレヴァとお付き合いなさっているのです! 」
リシャール3世が、怒りにギョロリと剥いた目でオズバーンを振り返った。
「聞いたか? いまこの小者(こもの)は、ロベールが下々の者と―――身分卑(いや)しき者どもと、親しく通じ合っておると訴え出たのじゃぞ! それがどういう意味か、お主にも判るであろう? 」
オズバーンは困ったように薄笑いを返す事しかできなかった。
「いやまあ‥ こういった色恋沙汰(いろこいざた)では、その真偽(しんぎ)のほどをきちんと確認いたしませんと――― 」
「ほう‥ では、そなたはこの者が嘘をついたと申すのか? 」
眼光鋭くオズバーンを睨み据(にらみす)えるリシャール3世。
「もし、嘘をついたのであれば、これは貴族に対する重大なる冒涜(ぼうとく)である ! 即刻、この者の首を刎(は)ねるがよい! 」
その言葉に、トマはヒッと小さい悲鳴をあげながら、咄嗟(とっさ)に首へと両手をあててしまった。
抱えていた聖書が床に落ち、バサリと音をたてた。
× × × × ×
抜けるような秋空の下には、ファレーズの街をぐるりと取り囲む丘陵地帯が広がっている。なだらかにうねる広大な麦畑から眺めると、城下で焚(た)かれた幾条(いくじょう)もの煙が空に立ちのぼる様を見る事ができた。
すでに刈り入れが終わった畑には、積み藁(つみわら)があちらこちらに作られていた。
積み藁とは、刈り取った麦を束にして、円柱形に積み上げていったモノで、上部には雨よけ用の藁束(わらたば)が屋根状に葺(ふ)いてある。
収穫した大量の麦は、一度にすべてを脱穀(だっこく)する事ができないため、残った麦は畑に残すしかなかった。だが、それらをそのまま放置するワケにもいかない。大切な麦穂が風で飛ばされたり、雨で発芽してしまうからである。また、麦穂は乾燥させると、籾(もみ)が落としやすくなる。そこで、いにしえからそれらは積み藁にして管理されていたのであった。
形といい大きさといい、小屋かと見まがうような積み藁が田園に何百と広がる光景は、まるで新しい村が誕生したかのようである。
丘陵の中央には、畑へ水を引き込むための小川が流れており、その水力を利用して粉を挽(ひ)く水車小屋も建てられていた。
水車小屋は、牛糞(ぎゅうふん)や藁などを混ぜた土壁に茅葺(かやぶ)き屋根を乗せただけの粗末な建物である。そこから、川のせせらぎとともに、ゴロゴロと石臼(いしうす)が回る音も響いてくる。
水車小屋の薄暗い室内には、藁がこんもりと積み上げられていた。
その藁の上に裸で寝そべる青年がいる。彼は天井に向かって右手をまっすぐに伸ばすと、明かり取りの高窓から差し込む日の光に、手のひらをかざして眺(なが)めている。
「そもそも、兄さんは‥ このボクがいつまでたっても子供だって――ガキだって、バカにしているんだ。 領内のまつりごとをほったらかして、夢みたいな事ばかり考えてるって‥‥ 」
彼は不満げな顔で、光に透ける自分の手の甲をジッと見詰めている。この青年が、ファレーズの領主であるロベール伯爵(コント)であった。
あれこれと不満を口にする彼は、その年齢――26歳よりも遙かに幼く思われた。
それは、くるくるとよく回る大きな目や、金色に輝くカールした髪などのせいではなく、むしろ彼の話し方や考え方がそう見せるのであろう。
「けど‥ ボクがナニか領内の改革をしようとしても、兄さんや執事(じい)は、『また、そんな馬鹿なコトを言って』って‥ いっつも、まったくボクを相手にしてくれないんだよ! そんなのってないだろ!? だから、ボクは――― 」
その傍らで、ロベールに背を向けて座った女が、裸の上に白麻のシェーンス(足首まである丈の長いシュミーズ)を被(かぶ)る。その腰は細く、尻は豊かに張り出していた。
「あの‥ ワタクシ、赤ちゃんができたようでございます 」
彼女はロベールの言葉を遮(さえぎ)ってさらりと告げた。
一瞬、固まるロベール。
が、すぐさまに何を言われたのかを理解し、『えっ』と体を起こした。
やや固い微笑(えみ)を浮かべて、ロベールを振り返った女は、息が止まるほどに美しい。
澄みきった湖のような青い瞳と長い睫毛(まつげ)、形のよいぷっくりとした唇はリンゴのように赤々とし、歯並びも驚くほど整っていた。そして、長く滑(なめ)らかな栗毛(ブリュネット)の髪は丹念に三つ編みにされている。
彼女は、ファレーズ城下に住む革なめし職人(ペルティエ)フルベールの娘、エルレ ヴァだった。彼女はロベールの右手を取ると、そのお腹にそっとあてがった。
「このお腹の中に、伯爵様の御子様(みこさま)がおられるのです 」
ロベールはあまりの混乱に、言葉がうまく出ない。
「い‥ いや‥ ホ‥ ホントに、ボクの‥? 」
ロベールの疑念が、二人の間にしばしの静寂(せいじゃく)をもたらした。
小屋の中には、ただただ石臼(いしうす)の音が響くばかりである―――。
「ち‥ 違う! 違うって! そういう意味で言ったんじゃないよ 」
気まずい空気に、ロベールは必死になって誤解を解こうとする。
「あ‥ 赤ちゃんが‥ 赤ちゃんが、ボクの子だって事は判ってる! 信じてるさ。 そこは疑ってないですよ! ただ、いまのボクに赤ちゃんっていうのはマズくないかなぁって思ってさ。 やっぱり、マズいでしょう、この場合‥ 」
しかし、エルレヴァは何も答えず、ジッとロベールを見詰めている。
その視線に堪(たえ)えられなくなったロベールは、あらぬ方向に顔を向けると真実味のない言葉を並び立てる。心の内は、かなり動揺(どうよう)しているようである。
「あ‥ あれ? えっとォ‥ やっぱり、マズくはないかァ。 うん! そうだネ、マズくない。 マズくないよ! 兄さんだって、きっと判ってくれると思うし‥‥ そう信じようよ、ね? ね? ね? 」
エルレヴァは一転、切なげな表情を作ると必死にロベールに訴える。
「なりませぬか? 身分卑(いや)しきこの身では、ロベール様の御子様(みこさま)など身籠(みご)もってはなりませぬか? 産んではならぬのでしょうか? 」
ロベールはブルブルと首を横に振って、大仰(おおぎょう)にそれを否定した。
「いやいやいやいや‥ そんなコトはない! そんなコトはないけどさァ‥」
エルレヴァは目を細めると、ロベールの瞳の奥を覗き込む。
「『けどさァ』―――? 『けどさァ』って、いったいどういう意味でございます? 」
彼女の問い詰めるかのような口調に、ロベールも少々ムキになる。
「だ‥ だから‥ 産みたきゃ、産めばいいじゃないか! 赤ちゃんは産んでいいですよ。 産みましょうよ。 そうすれば、文句はないんでしょう? 」
エルレヴァは、げんなりしたかのように大きな溜息をつくと
「―――いえ‥ もう、けっこうでございます! 」
と言い放つや、再びロベールに背を向け、着替えを続ける。
「御子様の御命(おいのち)‥ エレーヌの森奥深くに住むという、子堕ろし婆(こおろしばあ)のシュザンヌに委(ゆだ)ねますゆえ―――どうか、伯爵様はご安心くださいませ! 」
「こ‥ 子堕ろしって‥‥ 」
ロベールはエルレヴァのきつい物言いに唖然としてしまう。
朱色の毛織りのチュニックを、シェーンスの上に重ね着するエルレヴァは、明らかに怒っている。くるぶし丈のチュニックは、胸元と裾に金糸(きんし)の刺繍(ししゅう)が丁寧に施(ほどこ)されており、彼女がかなり裕福な家庭の娘であろう事がわかる。
「‥ウソつき 」
小声で彼女が吐き捨てた言葉に、ロベールはますます苛立ち、
「ったく‥ もう! 」
と髪をかきむしった。
これはロベールにとって、非常にまずい事態であった。
貴族であり、大公の公位継承権第一位であるロベールは、平民であるエルレヴァと結婚する事は絶対に許されない。そして、結婚ができないとなれば、生まれてくる子供は庶子(しょし)となり、貴族としての権利をいっさい受ける事ができなくなるのだ。
しかし、そのような事をこのエルレヴァが受け入れるハズもない。
結婚ができない事ぐらいは承知しているだろうが、お腹の子供は将来伯爵に―――うまくいけばノルマンディー大公にさえ、なれるやもしれぬと期待しているに違いなかった。
エルレヴァはけっして意地汚い女ではなかったが、そのへんの損得はしっかりと算段(さんだん)する女であった。
この事が公(おおやけ)になれば、兄であるリシャール3世からどれだけ怒鳴られるのか、エルレヴァからどれだけ責められるのか、その事を考えると憂鬱(ゆううつ)な気持ちで一杯になった。
ロベールは、どうしてこんな事態に陥ってしまったのか―――つらつらと思い出していた。
それは今春の事であった。
温かい日差しに誘われて、野駆(のが)けを思い立ったロベールは城外へと馬を走らせた。
風を切って走る心地よさに酔い痴(よいし)れていると、前方から若い女性達の楽しげな声が聞こえてきた。
ロベールは咄嗟(とっさ)に手綱(たづな)を引いた。
黄色い声は、街道脇の川から聞こえてきていた。そこには数人の少女達が、膝(ひざ)まで水につかって洗濯物をしていたのである。
水を掛け合ってふざけ合う彼女達は、みなキラキラと輝き、本当に美しかった。しかし、その中にあっても群を抜いて美しい女性がいた。
世界中の宝石を集めても、彼女の目映(まばゆ)さにはかなうまいと思えた。
それがエルレヴァだったのだ。
ロベールはいつの間にか馬から降りると、そのまま水の中へジャブジャブと進み、エルレヴァの前の水面(みずも)に跪く(ひざまずく)と自己紹介をしていた。
彼は自分が何をしているのか、何を言っているのか判らなくなっていた。
なぜなら、ロベールはすでに恋に落ちていたからである。
そんな二人の出会いを思い出し、改めて目の前で服を着る彼女を眺(なが)めてみる。そこにはあの時と少しも変わらぬ―――いや、さらに美しさを増したエルレヴァがいた。
ああ、悔しいけれど、彼女のこの美しさは何物にも替え難(かえがた)い。
そして、時折みせる勝ち気な一面―――領主であるこのボクに対してでさえ上から見下すような態度をとるところも、また彼女の魅力なのだ。
どんなに腹が立とうとも、ボクは彼女と別れる事など絶対にできない―――ロベールはそう確信した。そして、そうなれば答えはひとつしかなかった。
ロベールは腹をくくった。
「赤ちゃんをありがとう! 」
「えッ? 」
エルレヴァが驚いたように振り返った。
ロベールは穏やかな表情で言葉を続けた。
「今日はこの素晴らしい報告を素直に喜ぼうじゃないか。そして、ボクらの未来については明日から考える事にしよう。必ずや、君が納得のいく答えを出してみせるからさ 」
「ロ‥ ロベール様‥ 」
やっと安心したのか、エルレヴァはうっすらと涙ぐんでいる。
ロベールは、右手の指先で素早く十字を切ると、神に祈りを捧げた。
「主よ‥ あなた様の素晴らしき御業(みわざ)に、心より感謝いたします―――アーメン♡ 」

× × × × ×
領主の館の中庭では、リシャール3世と五人の騎士(シュヴァリエ)、さらには彼らの家臣も含めて、総勢三十一人が馬にまたがり、まさに出立(しゅったつ)しようとしていた。
高い塀で囲まれた館の周囲には、深い壕(ほり)が掘ってあり、城門に渡された跳(は)ね橋で城内に出入りができるようになっていた。
城門まで馬を進めたリシャール大公は不機嫌な顔で、門の脇に立つトマに命じる。
「我らは、このままカーンへの巡幸(じゅんこう)(国王・領主による領地内の視察)を続ける。 しかしながら、十日後には再びこの地へと戻るがゆえ、その時までに下賤(げせん)の女とは必ず別れておくようにと―――ロベールに、よォく申し伝えよ! よいな‼ 」
信心深げに聖書を両手で抱きかかえたトマは、リシャールに恭(うやうや)しく頭を下げる。
「ハハァ──ア! 肝(きも)に銘(めい)じて、お伝え申し上げます 」
トマが深々と頭を下げたタメ、馬上のリシャールからは見えなかったが、彼の顔は不気味なまでに無表情であった。
× × × × ×
大きな土煙を上げてリシャール公爵一行が向かった方向とは反対側に、ロベール達のいる水車小屋は建っていた。
その水車小屋周辺に目を凝(こ)らすと、あたりに護衛の兵士達がいる事に気づく。
いくら逢い引きとはいえ、主君の外出を警護せぬワケにもいかず、八人の兵士がひっそりと護衛についていた。彼らは、小屋からの声が届かない十分な距離をとって侍(じ)していた。
積み藁にもたれ掛かって立つ者、立て膝をついてしゃがみ込んだ者、腕を組み空を仰ぐ者と、それぞれが好みの体勢で時間を潰していた。
いつもの事である。兵士らに緊張感はなかった。
彼らの装備も、短めの鎖帷子(オベール)だったり、キルティングの鎧下(ガンベゾン)だけだったりと軽装で、兜(カスク)まで被る者は一人もいなかった。武器もおのおのが、刃渡り2クデ(1クデ=1キュビット=約45センチ。2クデは約90センチ)ほどの長剣(エペ)を腰にぶら下げるのみ。槍(ラーンス)や弓(アーク)を持つ者はいなかった。
そんな衛兵達を、少し離れた積み藁の陰から窺う男がいる。
男は、あちこちが破れた薄汚いチュニック姿。その垢だらけの細い手には、抜き身の剣が握られていた。
さらにその背後を、斧を手にした別の男が、身を低くして積み藁から積み藁へと移動していく。
川の土手にも数名の男が伏せて、小屋の方を覗いている。
衛兵達は、武器を手にした二十人ほどの男達に、遠巻きながらも完全に取り囲まれていたのであった。
