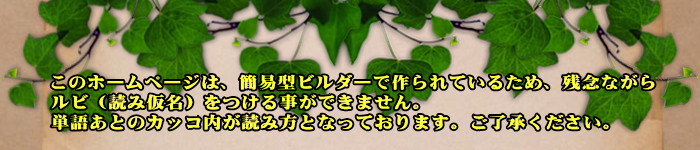
90
1027年 ファレーズ・領主の館
「どうも、ご無沙汰(ぶさた)しております! お元気にしておられましたか?」
広間に通されたロレンツォは、儀礼的な挨拶(あいさつ)もそこそこに、玉座(ぎょくざ)で迎(むか)えたロベールに、なれなれしい口調で話し掛けてきた。
「え‥ ええ‥ まあ‥ 」
「いやいや‥ お噂はいろいろとお聞きしておりますよ。 ドラゴン退治とか、傭兵(ようへい)騎士団の襲撃とか‥ わたくしがおらぬ間に、ずいぶんとご活躍だったみたいですね? 」
ロレンツォは一方的に話をした。やや躁気味(そうぎみ)の様子である。
「は‥ はい‥ しかし、ヨリ殿やそのお仲間達に助けられましたから―――」
いつもと様子が違うロレンツォに、ロベール伯爵は少々戸惑っていた。
「そうでしょう、そうでしょうとも! でも、ご安心ください。 わたくしは、彼らに寝床と酒食(しゅしょく)までご提供くださったロベール様から、その料金を頂戴(ちょうだい)しようなどとは考えておりませんぞ。 今回の傭兵(ようへい)使用料は、無料という事にさせていただきます♡ 」
「そ‥ それは‥ ありがとうごさいます 」
ロレンツォが発する妙な空気に押されて、ロベールは言葉が出なかった。
玉座(ぎょくざ)の傍(かたわ)らには執事(アンタンダン)のティボーも控えていたが、彼も口を開かなかった。いつもならば、このような態度の者には、『無礼者!』と一喝(いっかつ)するはずの彼が、今日は苦笑いするだけだったのだ。
ロレンツォは胸に手をあてると、軽く腰を折り、恭(うやうや)しく告げた。
「伯爵様とも積もる話はございますが‥ まずはともあれ、ヨリズミら我が警備隊にお会わせください。 伯爵様とのお話は夕食の時にでも‥‥ では、失礼いたします 」
言うが早いか、ロレンツォはそのまま退席したのであった。
衛兵によって開かれた扉がふたたび閉じられ、バタンという音が響く。
広間はしばしの静寂(せいじゃく)に包まれた。
やがて、ロベールは大きな溜め息をつくと、隣に立つティボーに話し掛けた。
「じい‥ やはりヨリ殿は、ロレンツォ殿といっしょに旅立たれてしまわれるのだろうか? 」
ロベールは不安そうだった。先ほど城壁で語った頼純の口ぶりから、彼がもう二度と帰ってこないような気がしていたからである。
それに対し、ティボーは率直な言葉を返した。
「やはり、そうなるでしょう‥。 ヨリ殿は、大商人ロレンツォ殿の警備隊長なのですからな―――数日内には、隊商(カラバンヌ)の旅に出発なさる事かと存じ上げます 」
これまでのティボーなら、ロベールを傷つけぬように、根拠のない慰めの言葉を言っていただろう。だが、近頃の彼は違っていた。
また、ロベール自身が強く大きく成長したため、そのような気遣いをする必要もなくなっていたのだ。
ロベールは渋い顔をして考え込んだ。
「そうなんだよねェ‥ けど、あの方が本当にいなくなるなんて―――考えてなかったなァ。 ずっとこの地にいてくれるような気がしてたんだ。 でも、あの人は旅人だもんねェ‥‥ 」
「はい‥ 7ヶ月もの間、このファレーズでともに暮らし、苦楽を分かち合ってこられた若とヨリ殿ですから‥ そのお別れは、さぞやお辛(つろ)うございましょう。 お察し申し上げます 」
執事(アンタンダン)の言葉に、ロベールは寂しそうに笑った。
「フフフ‥ わたしにとって、あの方は初めての友人だったからね‥ ヨリ殿がいなくなるって考えると、なんだか切ない気持ちになってしまうよ‥ 」
ティボーもしんみりとした口調でつぶやいた。
「そうですね。 じいとて、はじめこそは‥ 異教徒という事もあってヨリ殿を毛嫌いしておりましたが‥ いつの間にやら、あの方の人柄(ひとがら)に引き込まれておりました。 とくに、死ぬとばかり思っていた兄エルキュールが、あれほどまでに元気になれたのも、ひとえにヨリ殿のお陰。 大いに感謝しております 」
頼純の出現によって、ロベールが、この街が、いや自分自身さえも大きく変わった気がしていた。
たかが半年ほどの間に、何もかもがこれほどまでに変わってしまうとは―――頼純の不思議な力にティボーは驚いていた。
そして、彼自身も頼純との別離を寂しく思っていたのだ。
× × × × ×
館(やかた)を出たロレンツォは、頼純らが泊まる兵員宿舎に向かった。
「久しぶりだな。 みんな、大変な目にあったらしいが、無事だったか? 」
宿舎の椅子に腰掛けると、ロレンツォは目の前に立つ自分の警備隊達に満面の笑(え)みで話し掛けた。
「もちろんです! 」
一同は声を揃(そろ)えて応(こた)える。
そんな中、頼純が心配そうに尋ねた。
「お母上様のお加減はいかがでございますか? 」
「う‥ うん‥ もう、すっかり良くなった。 当分は、大丈夫だろう‥ 」
「それはよかった 」
「一安心ですね♡ 」
久しぶりの主人との再会に、頼純とサミーラ、さらに5人のイタリア人傭兵(ようへい)―――ピエトロ、フィリッポ、ジャコモ、ジョヴァンニ、ロメオ達も興奮気味である。彼らの間には、雇い主と傭兵(ようへい)という関係を越えた、深い結びつきがあった。冒険仲間という絆(きずな)である。
「では‥ いよいよ出発ですね? 」
「モン・サン・ミッシェルに逗留(とうりゅう)するアンドレア達も、さぞかし待ちくたびれている事でしょう 」
隊商(カーラバンヌ)の本隊である14人とイタリア人傭兵(ようへい)アンドレアは、商品や銀貨とともに、モン・サン・ミッシェル修道院に匿(かくま)われていた。
モン・サン・ミッシェルは、『大天使聖(セント)ミカエルの山(モン)』と言う意味である。修道院は海中から突如突き出した小山の上に建っていた。ここならば、泥棒や強盗も簡単には襲ってこないだろう。

1900年のモン・サン=ミッシェル修道院 (日本語版Wikipediaより)
11世紀から12世紀のモン・サン=ミッシェル修道院 (アメリカ版Wikipediaより)

モンサンミッシェルのウィリアム1世とハロルド (バイユーのタピストリー・アメリカ版Wikipediaより)
ちなみに、この修道院を建てたのはロベール伯爵の祖父リシャール1世ノルマンディー公爵である。
彼らはふたたびここに集結し、ヨーロッパの最西端―――イベリア半島のリスボンを目指すのだ。そして、そこから船に乗って、日本(ワクワク)、中国(スイーン)へ向かう航海が始まる。
「いよいよ、黄金の島『ワクワク』に向かうのかァ‥ 」
「うん! 楽しみだなあ♡ 」
頼純は皆の勘違いを正そうとした。
「いやいや‥ 日本はそんなトコじゃないって! 道端に黄金なんか転がってないんだから。 何度も言っただろう 」
だが、誰もその言葉を信じてくれなかった。
「またまた、そうやって、俺達を驚かそうと思ってるんでしょ? 」
「それとも、独り占めしたいんですか? そうはいきませんよ♡ 」
一同はドッと笑った。楽しくてしょうがないのである。
当時、日本は黄金の島『ワクワク』として、イスラム商人達の間でも有名であった。その島は、『スイーン』の東方にあり、すべての物が黄金でできていると信じられていたのだ。『ワクワク』は『倭国(わこく)』がなまったものである。
ちなみに中国は、紀元前221年に中国全土を統一した『秦(しん)』が、インドで『シーナ』と呼ばれ、それが中東に入ると『スイーン』へと変化した。 やがて、『シーナ』はヨーロッパに入り、フランス語で『Chine=シーヌ』、英語で『China=チャイナ』と呼ばれるようになる。
「で‥ 出立(しゅったつ)はいつにいたしましょう? 明日ですか、明後日ですか? 」
目を輝かせて尋(たず)ねるジョヴァンニに、ロレンツォの口が重くなった。
「うむ‥ それなんだがな――― 」
一同の目がロレンツォに注がれた。
だが、ロレンツォは胸元で十字を切ると、両手の指を組み合わせ彼らに詫(わ)びた。
「すまん! 中国(スイーン)への冒険旅行は中止にさせてくれ 」
「え!? 」
ロレンツォ以外の全員が、一瞬息をする事も忘れてしまった。
何を言われたのかわからなかったのだ。それほどに、彼の発言は予期せぬものであった。
ロレンツォは笑顔を強張(こわば)らせながら説明した。
「いや、お恥ずかしい話だが‥ ヴェネツィアに戻って病気の母と穏(おだ)やかに暮らすうちに、それまで燃え盛っていた冒険への情熱がドンドンと薄れていってな――― 」
「は‥ はあ‥ 」
「そんなこんなしている間に、とある女性と出会って‥ 恋に落ちて―――20歳も年下の女性なんだが、結婚までしちゃって‥‥ それで、いい歳して子供までできてしまいました。 すみません。 今年の秋にはパパになります。 だからもう、冒険旅行はちょっと無理! へへへ‥ 」
ポカーンとした一同を前に、ロレンツォはヘラヘラとした愛想笑いを浮かべていた。
そんなロレンツォに頼純が呆れ顔でつっ込む。
「『へへへ』じゃないでしょう、『へへへ』じゃ。 この半年間、みんな待っていたんですよ 」
それをきっかけに、フィリッポ達も一斉に文句を言い始めた。
「そうですよ。 いまさら冒険旅行をやめるってーのはないでしょう! 」
「目標を失っちまって‥ 俺達はこれからどうしたらいいんですか?」
「いやいやいや‥ そんなのあり得ないって! これは人生を賭けた約束事なんですゼ 」
「それを急に『なし』にしてくれだなんて――― 」
「本当にゴメン! 」
ロレンツォはひたすら謝るしかなかった。
「もし、みんながどうしても中国(スイーン)に行きたいっていうんなら、みんなは旅出ってもらってもかまわないんだ。 西航路の資金はわたしが全額出すし、さまざまな手配もすべて必ずやっておくから。 あと、一生食うに困らないくらいの報奨金(ほうしょうきん)も出しましょう。 それで勘弁してくれ! 」
全員が『う~~~ん‥ 』と唸(うな)り声を上げると、そのまま黙り込んでしまった。頭が混乱し、何を考えてよいのかさえ分からなくなっていたのだ。
ロレンツォが伯爵の前で様子がおかしかったのも、仲間にこの重大な発表をしなければならないという重圧から、テンパっていた事が原因だろう。
長い沈黙の後、最初に口火を切ったのはピエトロだった。
「お‥ おい、どうする‥? 俺達だけで中国(スイーン)に行くか? 」
フィリッポが弱々しく首を横に振った。
「いやいや、行かないでしょう。 ロレンツォの大将が行かないんじゃ、行く意味ネーし―――! 」
他の者達もそれに賛同した。
「う‥ うん‥ そうだよなあ‥! 」
「俺‥ なんだか、急に冒険心が冷めてきちゃった 」
「あ‥ 俺もだ。 どうしちゃったんだろう。 」
「そもそも‥ なんで、中国(スイーン)に行こうなんて考えたのかさっぱり判らない 」
みんなにかけられていた魔法は、すっかり解けてしまった。
それも当然である。冷静になって考えれば、この旅がいかに危険きわまりない無謀な冒険なのか、すぐに判るはずである。
すべては、ひとときの情熱(パッション)がかけた魔法だった。
しかし、その魔法が解けてくれたお陰で、『中国(スイーン)』と思い込んだアメリカ大陸を、彼らが延々(えんえん)さまよい続けるという難からも、逃(のが)れる事ができたのであった。
ロレンツォは頼純に視線を向けた。
「ヨリズミよ‥ お前は日本(ワクワク)に帰りたいんじゃないのか? 」
頼純は眉を顰(しか)めて答えた。
「急な事なんで、即答はできませんが―――どうしても、日本に帰りたいってー思いはありませんねェ‥‥ もっと、冒険はしたいですけどォ‥‥ 」
そう答えながら、頼純はホッとしていた。
ただ、旅が中止になった事で、なぜ自分が安堵(あんど)しているのかまでは彼も気づいていなかった。
「サミーラはどうなんだ? 」
こんどは、ずっと黙っていたサミーラに問い掛けた。
「わ‥ わたしは、ヨリ様のいるところなら、どこでも‥‥ 」
彼女は、消え入るような声で恥ずかしそうに答えた。
ロレンツォの顔がパッと輝く。
「ヨシッ! だったら、みんなヴェネツィアに戻ってくれ。 そして、これからもわたしの下(もと)で働いてもらいたい 」
その言葉が終わるか終わらないかの内に、
「う~~~ん‥ だったら、俺はもうしばらくここにいようかなァ‥ うん、このままファレーズにいたいかな 」
腕組みをし、難しい表情で考え込んでいた頼純が、自分の希望を口にした。
「いやいや‥ そんなコト言わずに、わたしのとこへ帰ってきてくれ。 ヨリズミ、頼むよォ‥ 」
「まあ‥ 先に約束を破ったのは、ロレンツォ様ですからねェ‥ 」
「そ‥ そんなァ‥ 」
悲しそうな顔をするロレンツォを、頼純はニンマリとした笑(え)みで覗(のぞ)き込んだ。
「それに、ロベール伯爵はすごく興味深い(おもしろい)人なんですよ。 これこそ、『奇貨(きか)、居(お)くべし』ですね 」
「ん!? なんだ、それは? 」
ロレンツォをはじめ、ピエトロ達もキョトンとしていた。
頼純はその場の全員がわかるように、この故事の説明をした。
―――いまから1300年ほども昔、はるか東にある中国では、7つの大国が200年近くに渡って戦争を繰り返していました。
その大国のひとつ、『韓(かん)』の都、陽翟(ようてき)に住む呂不韋(りょふい)という大商人が、ある時、別の大国『趙(ちょう)』の都・邯鄲(かんたん)へ商用で出掛けたのです。
にぎわう街の中で、彼はたいそう品があるのにみすぼらしい格好(なり)をした青年を見かけました。
呂不韋(りょふい)は商売相手に「あの青年は誰ですか?」と尋(たず)ねました。
するとその商人は、「あの方は『秦(しん)』の王子で、この国に人質として送られた子楚(しそ)様です」と答えたそうです。
呂不韋(りょふい)は即座に、「奇貨(きか)、居(お)くべし(これは良いものを発見した。是非とも手に入れておくべきだ)」と決断しました。
この王子を後押しして秦(しん)の国王にすれば、自分にも途方もない見返りがあると考えたのです。
しかし、子楚(しそ)には20人もの兄弟がおり、敵国趙(ちょう)へ人質に出されるような重要視されていない王子では、跡継ぎ候補になるなど不可能に近い事でした。
それでも呂不韋(りょふい)はこの王子にすべてを賭けると決めたのです。
彼は全財産をつぎ込み、東奔西走(とうほんせいそう)して、『秦(しん)』の宮中に様々な人脈を作っていきました。
その甲斐あってか、王子・子楚(しそ)はやがて大国『秦(しん)』の皇太子となり、ついには国王の座をも手に入れたのです。
呂不韋(りょふい)は思惑通り、『秦(しん)』の相国(しょうこく)(宰相(さいしょう)の事)にまで登り詰めました。彼は一世一代の博打(ばくち)に勝ったのです
その後、子楚(しそ)―――のちの荘襄王(そうじょうおう)の息子『政』が国王につくと、7つの大国を打ち破り、中国全土を手中に収めました。
この『政』が、あの有名な『始皇帝』なのです―――
一通り頼純の話を聞いたロレンツォは尋(たず)ねた。
「つまり‥ わたしがその呂不韋(りょふい)で、ロベール殿が子楚(しそ)王子って事かね? ロベール殿に大金をつぎ込んで、彼をノルマンディーの公爵につかせ、わたしはその家令(セネチョル)となって権勢を振るう。 そして、間もなく産まれてくる彼の子供をフランス国王にでもせよと――― 」
たしかに、子楚(しそ)とロベール伯爵の状況は驚くほど似ている。子楚(しそ)の子『政』の実母は元芸妓(げいぎ)であり、身分卑しき階級の出身であったところまで同じであった。
ただ、この二人の身分卑しき母には決定的な違いがあった。
一人は愚かで淫蕩(いんとう)であり、もう一人は聡明(そうめい)で礼儀正しく、様々な事をわきまえていたのだ。
「いえ‥ というよりも、ロベール伯爵はそうなってもおかしくない人物だと言いたかっただけです。 ですから、ぜひ彼の後援をしていただきたいと――― 」
いくら状況が似ているとはいえ、頼純はなぜそのような故事を持ち出したのか、自分でもよく判らなかった。誰に何を伝えたいのかさえも‥‥‥。
一方、ロレンツォは理解したようだった。
「なるほど! 『パトロン』―――それも、見返りを求めたり、下心を持ったりしない、純粋な応援者になれと言うのだな? 」
「はい、そうです―――いや、違う‥ 違います! 」
頼純はやっと自分が何を言いたいのか―――何がしたいのか、おぼろげに判ってきた。
「そうじゃなくて‥ えっと‥ わたしがなりたい‥? そう、ロレンツォ様じゃなくて、わたしが伯爵を応援したいんです 」
頼純はこのファレーズにもっと居たかった。ロベール伯爵ともっといろんな事を語り合いたかったのだ。
ロレンツォの肩が震えだし、やがて『クククク‥』と笑い声が漏れ始めた。
「まったく‥ お前って奴は、ホンッッットに変な奴だな! 出会った時からずっと変だったけど、いまだに変だ。 けどそのお陰で、この数年間、ドキドキワクワクの連続でタップリと楽しませてもらったよ 」
「は‥ はあ‥ 」
「しかし、そうした冒険の楽しさを、わたしは放棄(ほうき)すると決断したんだ。 だったら、お前とも距離を置かねばならないだろう‥ 」
「‥‥‥ 」
「わかった。 お前の好きにするがいい。 ロベール伯のそばにいるというのも、おもしろい事かもしれんな。 わたしも応援させてもらうよ 」
「はい! 」
頼純は子供のように元気よく返事をした。
だが、彼とて呂不韋(りょふい)になろうとしているのではない。誰も呂不韋(りょふい)になってはならないのだ。
なぜなら、宰相となって大国『秦(しん)』を思うがままに操(あやつ)っていた呂不韋(りょふい)は、しだいに『政』―――のちの『始皇帝』に疎(うと)まれていったからである。
そして、『政』の実母である皇太后とその愛人が謀反(むほん)を起こした時、彼もその企(くわだ)てに加担していたのではないかと疑われ、流刑を命じられてしまう。最高位から最下位への転落を大いに悲嘆(ひたん)した呂不韋(りょふい)は、流刑地へ送られる途中、毒をあおって死んだという。
一説には、呂不韋(りょふい)こそが始皇帝『政』の実父で、その事が世間に露見(ろけん)する事を恐れた『政』によって殺されたとも言われている。
後年、広大な中国を制覇(せいは)するほどの超大国『秦(しん)』において、最高の権力を手にした呂不韋(りょふい)だったが、その最後はあまりにも惨(みじ)めな死であったのだ。
「という事は‥ お前はしばらく、このファレーズに留まるわけだ? 」
「はい、そうなります! 」
「だったら、サミーラと結婚したらどうだい? 」
唐突にロレンツォが切り出してきた。
「は‥ はい‥!? 」
そう言ったきり、頼純は固まってしまった。
サミーラは頬(ほお)を真っ赤に染めて俯(うつむ)いている。
他の5人の傭兵(ようへい)は、『オ~~~オ♡ 』という歓声とともに、拍手をした。
ロレンツォは自分の名案に満足していた。
「うん、それがいい! お前達はキリスト教徒じゃないから、司祭に代わってわたしが二人の媒酌(ばいしゃく)をしよう 」
「け‥ け‥ 結婚―――? こ‥ この俺が―――? 」
頼純の口からは、そんな言葉しか出てこなかった。