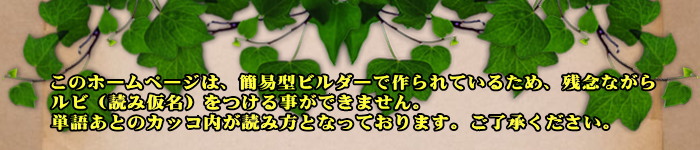
54
1026年 デンマーク王国ロスキレ宮殿
チェス盤から顔を上げたウルフ伯(アール)は、クヌート大王を不思議そうに見詰めた。
「な‥ なぜですって‥‥? 」
突然の質問に驚いたのか、ウルフ伯(アール)はすぐには答えなかった。
クヌート王は、これを『ウルフ伯が言い淀(よど)んだ』と感じていた。
やはり、ウルフは裏切っていたのか‥‥‥。 だが、もう少し‥ もう少しだけ待つから、早く答えを返してくれ。 どんな答えでもいいから、早く、早く―――クヌートは心の中で一心に願った。
しかし、ウルフ伯(アール)は笑顔を引きつらせたダケで、その質問に質問で返した。
「それは、前回の取り調べでも申し上げたではないですか。 なのにまだ、わたしの事をお疑いですか? 」
「‥‥‥ 」
クヌートは何も語らず、ただジッとウルフの目を凝視(ぎょうし)している。
ウルフ伯(アール)は、そんなクヌートから視線をはずすと、忌々(いまいま)しげに鼻を鳴らした。
「なるほど、そうか‥! ゴドウィン伯(アール)ですね? あやつが、アナタにくだらない事を吹き込んだのでしょう。 あのような者の言葉を信じて、このわたしを疑うなんて――― 」
その時、クヌートがチェス盤をひっくり返し、怒鳴った。
「よいから、早々に返答をせい! 」
チェス盤と駒が床に落ち、けたたましい音を立てた。
その大きな音と声に、広間にいた全員が二人を振り返った。
信じてもらえぬ苛立(いらだ)ちにウルフ伯(アール)は少し語気を荒くした。
「ならば、もう一度お答えしましょう! あのままでは、貴族会議によってわたしがこの国の王にさせられていたからです! 」
「‥‥‥ 」
「教会からもかなりの圧力が掛けられ‥ エストリドや息子達が誘拐されるという噂まで立っていました。 けれど、わたしはアナタを裏切る事は出来ない! ですから、結果的には失敗だったかもしれませんが――― 」
「もうよい! 」
クヌートは怒声とともに立ち上がった。そしてウルフ伯(アール)に背を向け、扉へと向かったのだった。
「だ‥ 大王様‥! クヌート王―――! 」
ウルフがクヌートの背に掛けた声は、語尾がしだいに濁(にご)っていった。
「―――クヌート様‥‥‥ 」
ウルフはもう一度親友の名を呼んでみた。それは寂(さび)しそうな呟(つぶや)きだった。幼い頃から大の仲良しだった親友が、今は自分の言葉も届かない存在になってしまった―――そう思うと切なく、悲しかったのだ。
衛兵が扉を開こうとした時、クヌートの元へゴドウィンが横から駆け寄ってきた。
「大王様‥ いかがでございましたか‥? 」
しばしの沈黙の後、クヌートは正面を向いたままムスッとした声でゴドウィンに命じた。
「――――――決行しろ! 」
ゴドウィンはニンマリとほくそ笑んだ。
「はい。 仰せの通り、ウルフ伯(アール)を処罰いたしまする‥ 」
結果は判りきっていた。クヌートとウルフの友情は、クヌートが質問した時点ですでに崩壊していたのだ‥‥‥
× × × × ×
ロスキレの街にクリスマスの朝が訪れた。
朝といっても、日照時間の短い冬場では、かなり遅い時刻に日が昇る(現在の午前9時ぐらい。ちなみに日没は午後3時半前後である)。
街は積もった雪で真っ白になっていたが、空は雲ひとつなく、青々と晴れ渡っていた。
雪に朝日が反射してキラキラと目映(まばゆ)い中、聖トリニティー教会は降誕祭(こうたんさい)のミサに参加する人々でにぎわっていた。
ハーラル1世青歯王が建てた聖トリニティー教会は、樽板(スターブ)式と呼ばれる木造建築の小さな教会である。
太い支柱と梁(はり)、さらには分厚い立て板の外壁によって全体が支えられる構造で、その外観があたかも樽のように見えるのだ。

スターヴ式教会参考例 ノルウェー ボルグンド教会
ゴドウィンは、その入り口を見渡せる巨木の陰に潜(ひそ)んでいた。
周囲の木立(こだち)には武装した10人以上の兵士が身を潜(ひそ)めている。彼らは『ハスカール』とよばれる傭兵(ようへい)で、正規軍とは違う服装をしていた。
教会から10ロッド(約50メートル)ほど離れた位置に隠れる彼らは、油断する事なく、ジッと入り口周辺の監視をしている。
本日、ウルフ伯(アール)は、キリスト降誕祭(こうたんさい)のミサにデンマーク国王執政(しっせい)として出席する予定になっていた。
そのウルフ伯(アール)を襲撃するタメに、彼らは長い時間張り込んでいたのである。
外気は氷点下をはるかに下回っていた。
だが、ゴドウィンはその冷気の中でずっと待機しているにもかかわらず、まったく震(ふる)えていなかった。
湧(わ)き上がるウルフへの殺意が体をほてらせているからである。
× × × × ×
ゴドウィンは妻の兄であるウルフ伯(アール)が大嫌いであった。
ゴドウィンは、征服者デンマーク人軍団の中にあって、数少ないイングランド人家臣である。それは、外様(とざま)中の外様であった。
かつての仲間であったイングランド人達からは『裏切り者』とさんざん罵(ののし)られたが、新たに仲間となったデンマーク人達も、けっして彼を信用してはくれなかった。一度裏切った者は、また裏切るに違いないと思われたからである。裏切り者が相手先で重用(ちょうよう)される事などあり得ないのだ。
それでもゴドウィンはのし上がろうとした。
そのためには、クヌート王は無論の事、すべてのデンマーク貴族に媚(こ)びへつらい、贈り物を届け、愛想笑いを絶やす事なく接さねばならなかった。そうやって頭を下げ続け、なんとか仕事をもらうのだ。
もらった仕事は、確実にこなすだけでなく、相手の期待以上の結果を出さなければならない。裏切り者が出世するタメには、目を見張るような機転と、血を吐くような努力が必要だった。
戦場では真っ先に飛び出し、たくさんの首を上げた。女・子供から赤ん坊にいたるまで、村人全員を皆殺しにした事など何度もあった。
投降した捕虜を平気で殺し、残忍な手口で拷問しては、彼らから重要な情報を聞き出した。
そうする事でデンマーク人達に感心され、喜ばれ、そして恐れられたのだ。
こうして、クヌート王から重責を任(まか)されるまでに這(は)い上がってきたゴドウィンであった。
しかし、ウルフ伯(アール)だけは、彼のお世辞(せじ)やおべんちゃらに一度も笑顔を見せる事はなかった。いつも、不快げな目でゴドウィンを見ていたのである。
それはまるで、道端に落ちている糞(クソ)を見るような目つきであった。
たしかにウルフ伯(アール)は、彼とは違いスカンジナビアの超エリート家系の血を引き、いつデンマークやスウェーデンの国王になってもおかしくない人物である。
のし上がるために周囲の人々を踏みつけ、そのせいで大いに嫌われているゴドウィンとは対照的に、ウルフ伯(アール)はデンマーク貴族のみならず、多くの国民から好感を持って受け入れられていた。
さらに、ゴドウィンが妻ガイサと結婚しようとした時も、その兄であるウルフ伯(アール)は、『我が家名(かめい)が欲しいだけなのであろう』と、猛反対をした―――まあ、それは事実なのだが‥‥
ただ、ゴドウィン伯(アール)がウルフ伯(アール)を嫌う本当の理由はそれ以外にあった。
ウルフは、ゴドウィンが恋い焦(こ)がれてやまないエストリド妃と結婚していたからである。
とはいえ、彼がはじめてエストリドと出会った時には、二人はすでに結婚していた。だが、たとえ他人の妻であろうとも、奪いたくなるほどに彼女は美しかったのだ。
もちろん、ゴドウィンがどんなに出世しようとも、彼の家系ではクヌート大王の妹君を妻に迎える事など到底(とうてい)不可能である。それくらいは、彼も十分に判っていた。しかし、そうであるからこそ、彼の恋心はますます燃え上がったのである。
そして、そんなエストリドを妻に持つウルフ伯(アール)がうらやましく、妬(ねた)ましかったのだ。
―――ああ‥ 今宵(こよい)、二人はどのような会話をするのだろうか‥‥二人はベッドの中でどう睦(むつ)み合うのだろうか―――そう考えただけで、ゴドウィンは大いなる興奮に心臓が高鳴り、息は荒くなった。
その狂おしいまでの妬(ねた)ましさは日に日に募(つの)っていき、邪悪な思いもどんどんと大きく膨(ふく)らんでいった。
そしてついに、ゴドウィンはすべてをブチ壊してやろうという思いに至(いた)った。どうせエストリド妃が自分の物にならぬのなら、二人を破滅させてやろうと考えたのだ。
幼い頃から愛し合っていたウルフ伯(アール)とエストリド姫の仲を永遠に引き裂き、最も苦しい思いをさせてやると、固く心に誓っていた。
ゴドウィン伯(アール)は、ノルウェー・スウェーデン連合の侵攻に乗じて、裏でこっそりデンマーク貴族らを焚(た)きつけ、不安にし、さらには買収までして、ウルフを国王にすべく運動した。
それによってウルフ伯(アール)がデンマーク国王となれば、クヌート王がイングランドの大軍を使って討(う)ってくれるだろう。たとえ、そこまでいかなくても、クヌート王に反逆の疑義(ぎぎ)を植え付ける事はできる。
ところが、まさかの展開となった。
ウルフ伯(アール)がみずから摂政(せっしょう)の座を下りてくれたのだ。ゴドウィンにとってこんな好都合はなかった。
これでウルフ伯(アール)を、完全なる『反逆者』に仕立て上げる事ができるからである。
彼のすべての名誉を剥(は)ぎ取る事ができるのだ。
その知らせをウィンチェスター城で聞いたゴドウィンは、廊下(ろうか)で思わず小躍(こおど)りしたほどであった。
‥‥‥やっと殺せる。あの忌々(いまいま)しいクソ野郎をやっと殺せる―――そう思うと、冷たい外気の中でもゴドウィンの頬(ほお)はついつい緩(ゆる)んでしまうのであった。
× × × × ×
ウルフ伯(アール)は、妻であるエストリドと二人の息子―――スヴェンとビヨルンを連れて、聖トリニティー教会のミサに徒歩で向かった。摂政(せっしょう)として王宮に住む彼らにとって、教会は目と鼻の先に建っている。それゆえに、衛兵も4人しか連れて行かなかったのだ。
教会に着くと、ウルフ伯(アール)の家族4人はその中に入り、衛兵達は正面入り口を警護した。
広くはない教会の中には、すでに多くの信者らが詰めかけていた。国王摂政(せっしょう)であるウルフ伯(アール)とその家族が到着すると、彼らは最前列まで道を開けた。
当時の教会に椅子はない。それぞれが思い思いの場所に、勝手に坐ったり、立ったりしてよいのである。だが、降誕祭(こうたんさい)のミサであるこの日は、全員が十字架の置かれた祭壇に向かって、膝立ちをしていた。
ウルフ伯(アール)もその場に跪(ひざまず)くと、十字架を見詰め、手を合わせた。そして、ミサが終わったら、もう一度クヌート王に会いに行き、きちんと謝ろうと考えていた。
司教が祭壇(さいだん)に向かって祈祷(きとう)を始めた。
信者らは両手の指を組み合わせ、頭(こうべ)を垂れて、司教の滔滔(とうとう)たる声に聞き入っていた。
その祈祷(きとう)の声が外にまで聞こえてくる。
それはウルフ伯(アール)が着座した事を意味していた。
「いけ! 」
ゴドウィンが声を上げる。
その掛け声に、弾(はじ)かれたように10人の傭兵(ハスカール)達が、教会の入り口へと殺到した。
傭兵(ようへい)達は油断した4人の衛兵に一気に近づくと、引き抜いた剣で彼らを串刺しにする。
衛兵達は声を上げる事も出来ず、その場で絶命した。
暗殺者達は扉を開くと中へと飛び込む。
「ウルフ伯(アール)、ご覚悟を―――‼ 」
血まみれの剣を携(たずさ)えた男達が大声でなだれ込んできたため、教会内は大混乱となった。
悲鳴とともに一般の信者達は逃げ惑(まど)い、左右の扉へと向かう。
その時、その扉が外側から開かれた。人々は雪崩(なだれ)を打って外へと逃げ出したのだった。
だが、その人混みの中にウルフはいない。彼は、家族が人の流れに巻き込まれないようにかばいながら、剣を抜き、身構えていた。
あらかじめ、信者の中には4人の傭兵(ようへい)が紛(まぎ)れ込んでおり、彼らはウルフが外に逃げないように事前に見張っていたのである。
ウルフ一家は全部で14人の暗殺者に囲まれた事になる。絶体絶命だった。
教会内には、ウルフ一家と逃げきれなかった司教しか残っていない。
そこへ、左右の扉から男達が侵入してきた。
「ウルフ伯(アール)、ご無事ですか? 」
「お助け申し上げます 」
そう言う彼らは、デンマーク軍正規兵の鎧兜(よろいかぶと)をつけていた。10人はいる。
「おお‥ 助かったぞ! まずは家族を! 」
ウルフ一家を取り囲む傭兵(ようへい)達に正規軍が斬り掛かる。大きな金属音を響かせて斬り合いが始まった。
「エストリド様‥ コチラです‥! 」
包囲の輪の中に飛び込んだ正規兵二名が、エストリドと二人の息子を扉へと誘導する。
ウルフの剣もなかなかの腕前だったが、凄腕(すごうで)の傭兵(ようへい)を三人も相手にしたのでは、彼らを倒すどころか、逃げるスキさえ与えてもらえなかった。
だが、エストリドと息子達、さらには司教までも外へ脱出した事を確認すると、ウルフ伯(アール)は大いに安心した。
「さあ‥ これからが勝負だ! 思う存分相手になってやるから、覚悟しろ! 」
敵は14人、コチラは9人だったが、まったく勝ち目がないわけではない。騒ぎを聞きつけた援軍もまもなく到着するだろう。
そんな計算をしていた時、ウルフの右脇腹に鋭い痛みが走った。
痛みの箇所に目をやると、剣が深々と刺さっている。背後を守ってくれていた正規兵の剣であった。彼らもまた傭兵(ハスカール)だったのだ。
「ウルフ様こそご覚悟を♡ 」
「き‥ 貴様ァァァァァア‼ お前らもグルかァァア‥‥!」
ウルフは、血が大量にあふれ出る傷口を右手で押さえながら、左手で剣を振り回した。
だが22人の傭兵(ようへい)達はさっと後ろに飛び退き、遠回しにウルフを囲んだ。
左右の扉は完全に閉まっている。
ウルフはどうすればよいのかまったく見当もつかなかった。
もしかしたら、自分は今日死ぬのかもしれない―――漫然(まんぜん)とそのような事を考えていた。
そこへ、どこからともなくゴドウィンがあらわれた。
彼はニヤニヤと嬉(うれ)しそうな顔で、ウルフを覗(のぞ)き込む。
「どうも、兄上‥ いや、摂政(せっしょう)様‥ おかげんはいかがですかな? 」
「や‥ やはり、貴様だったのか‥! こ‥ これは‥ ク‥ クヌート様のご命令なのか‥? 」
「ええ! もちろん、大王様のご命令ですよ。 親友であるアナタを殺せと、クヌート大王様が命じられたのです。 残念でしたね♡ 」
「そ‥ そうか‥ 」
ウルフ伯(アール)の口からは血が滴(したた)っていた。食道を逆流してきた血が口にあふれているのだ。
「だったら、貴様だけでも道連れにしてくれるわッ! 」
ウルフは持てる力を振り絞って、ゴドウィンに斬り掛かった。
だが、その剣は傭兵(ようへい)の一人によって弾(はじ)かれた。
ウルフが剣を構え直そうとした瞬間、その左腕が別の傭兵(ようへい)によって切り落とされる。
「ガッ! 」
腕の切断面から大きな血飛沫(ちしぶき)が上がるが、ウルフ伯(アール)には絶叫を上げる気力も残っていなかった。
腹から流れ出した大量の血はウルフの力を奪っていたが、その事よりも親友に信じてもらえなかった事の方が彼の気力を失わせていた。
目の前が暗くなっていく。ああ、これが死というものなのか―――ウルフはそんなコトをぼんやりと考えていた。
そこへ五人の傭兵(ようへい)が一斉に剣を突き立てた。
「ウギッ‥! 」
5本の剣で胴体を前後左右に貫かれたウルフは、床に崩れ落ちる前に絶命していた。
床で息絶えたウルフをゴドウィンは見下ろした。
「お前はこれで終わりだ! しかし、お前の家族はこれからが地獄の苦しみを味わう事になる。 そのあり様をあの世からとくと眺めるがいい♡ 」
ゴドウィンは嬉(うれ)しそうに微笑(ほほえ)んだ。それはまさに、『悪魔』の笑顔であった。