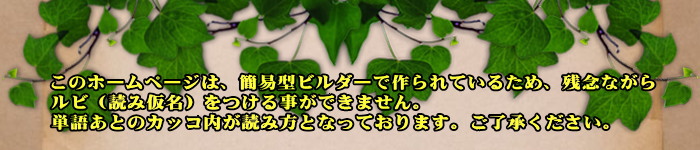
64
1027年 ファレーズ城(2)
「そもそも、罪人の詮議(せんぎ)にあたり‥ その者の名を尋(たず)ねぬなど、ありようハズがない! それはこの男が何かを隠しておるからだ! そうに違いない‼ 」
ルノーは怒りに充ち満ちた口調で頼純に詰め寄った。
だが、頼純は頼純で、そんなルノーを鼻で笑う。
「ハン! 冗談じゃネーや! そっちこそ、オヤジが本当は何者なのか、知ってたのか? たとえ親子だってなァ‥ 裏で何やってたかなんて、そうそう判るもんじゃネーんだぞ! 」
「ニャ‥ ニャニォ―――オ‼ 」
ついに怒りが頂点に達したルノーは、勢いよく立ち上がると、頼純の胸倉を掴(つか)んだ。
「ちょっと‥ ルノー殿もそう興奮なさらずに‥ お互い、証拠はナニもないのですから――― 」
ロベールは睨(にら)み合う二人の間に割って入ったが、ルノーの頼純に向けられた怒りは治まらなかった。
「たとえ父に何かがあったとしても‥ 貴様のような下郎(げろう)ごときに、伯爵である父を殺す権利などないのだぞ! 『勇者』だか、なんだか知らないが、その事を思い知らせてやる 」
売り言葉に買い言葉で、頼純とルノーの諍(いさか)いはますます激しくなっていく。
「ほう‥ だったら、どうすんだよ? 」
「フランス国王ロベール2世陛下にお願いして、再調査をしていただく。 そしてもし、父殺害の証拠が出てきたら、その時は貴様を火炙(ひあぶ)りにしてくれるわ! 覚悟しておけ‼ 」
ルノーは憎々しげな顔をロベールにも向けた。
「ロベール殿‥ アナタも同罪だ! このような無法行為を黙認していたのだからな。 さらには、リシャール大公殿の責任までも追及してやろう! 絶対にただではすまさぬぞ‼ 」
状況が判っていない上にしつこいルノーに、ロベールは大きな溜息(ためいき)をつく。そして、彼の目を見詰めて尋(たず)ねたのだ。
「じゃあ‥ その調査で、もしお父上があそこにいたと立証されたらどうするおつもりですか‥? 」
「だから、その時はこやつを火炙(ひあぶ)りに――― 」
「オットー・ギヨーム伯爵が、あの店にいたという事が確定すれば‥ お父上は悪魔崇拝(すうはい)の人喰い野郎って事になりますが‥‥それでもよろしいのですね? 」
ルノーはヒステリックな声でそれを否定した。
「何度も申しておるだろう‼ 父はそのような人物では――― 」
「残念ながら‥ あの店が人肉料理しか提供してなかった事は間違いありません! それは簡単に証明できるのです 」
「―――!? 」
「まずは‥ 誘拐されながらも、生き残った16人の少年の供述(きょうじゅつ)です! 彼らは仲間が殺され、調理される様子をすべて牢の中から見ておりました。 第二に、店内で客達と一緒にいた娼婦(しょうふ)達。 この女らもすぐに見つける事が出来るでしょう。 彼女達は、特殊な容貌(ようぼう)をしているそうですから。 そして、第三にトレノ村の村人達の証言です。 その後の調査によると、彼らはあの食堂がどういう場所なのか、知っていたようですから‥ 」
「ググ‥ 」
「となると、立場がひじょうに悪くなられるのは、むしろルノー殿ではありますまいか? もし、お父上が悪魔崇拝(すうはい)者であったと断ぜられれば、ローマ教会はフランス国王陛下に圧力を掛け、ブルゴーニュ伯の爵位(しゃくい)や領地を剥奪(はくだつ)するに違いありません。 それのみならず、すべての財産が没収される可能性だってあるのですぞ。 下手をすれば、一族にも悪魔信仰の疑いありとして、全員が火炙(ひあぶ)りとされるやもしれません 」
「き‥ 貴公はこの私を脅すつもりか? 」
「さきに、我々を脅迫されたのはルノー殿の方でしょう? 我々は絶対に間違った事などしておりません。 確実に正義を果たしたのです。 主イエス様に誓って、我々には一点の曇(くも)りもございませんぞ! 」
ロベールははっきりと言い切った。
「ギギギギ‥ 」
ルノーは悔しさのあまり、奥歯を折れんばかりに噛(か)み締(し)めた。その軋(きし)みが微(かす)かに響く。
ロベールはルノーを冷徹な目で睨(にら)み据(す)えた。
「よろしいですか!? 何度でも申し上げますが‥ お父上、オットー・ギヨーム伯爵はカーンで消息(しょうそく)不明となられたのです。 それ以上の事はありません! そうお考えください 」
その眼光には、つい2、3ヶ月前までのロベール伯爵からは想像もつかない迫力が込められていた。かつての彼ならば、「どうしよう‥ どうしよう‥」と右往左往(うおうさおう)するばかりであっただろう。
このように肝(きも)が据(す)わったのは、頼純と出会って3ヶ月ながら、ともに幾多(いくた)の死地を乗り越えてきた賜物(たまもの)であると思われた。
「わたくし共も、この件をけっして口外いたしません。 先ほど広間で話を聞いておった者達にも、厳しい箝口令(かんこうれい)をしきますゆえ‥ アナタ様はご安心なさって、ブルゴーニュ伯領の後継者とおなりくださいませ 」
頼純は胸倉を掴(つか)むルノーの手をはずした。
力なく俯(うつむ)いたルノーは、しばらく鼻息を荒くして、テーブルの一点を睨(にら)みつけていた。
それから、彼はゆっくりと言葉を吐き出したのだった。
「よ‥ よかろう‥‥ 」
顔を上げたルノーの目には、憎悪の炎がありありと浮かんでいた。
「ただし‥ この恨み―――父を殺され、侮辱(ぶじょく)され、家名まで汚(けが)された恨みは、けっして忘れはせぬぞ! いつの日か、必ず思い知らせてやる! 覚悟しておれ‼ 」
「そうですか‥‥ それは誠に残念です! わたくしは、義理の兄弟として、これからもアナタと仲良くしていきたかったのですが――― 」
言葉とは裏腹に、ロベールには一歩も引く様子がなかった。
× × × × ×
デンマーク王国・ロスキレ宮殿にも新年は訪(おとず)れていた。
しかし、宮廷も国民も、とてもその事を祝う気分にはなれなかった。 摂政(せっしょう)であり、多くの国民から愛されていたウルフ伯が殺害されたからである。
伯爵を襲った一行は、スウェーデン王国から差し向けられた刺客(しかく)であるとの噂が拡がり、多くのデンマーク国民は、戦争も辞さないと、大いに憤(いきどお)っていた。
もちろんそれは、イングランド王国ウェセックス伯であるゴドウィン卿が流したデマゴギーであった。
新年初日である降誕祭(クリスマス)にウルフ伯が殺されて、すでに10日が過ぎていた。
宮殿の大広間に置かれた玉座では、クヌート大王が家令(スチュワード)から租税徴収の報告を受けていた。
彼は肘掛けに乗せた右腕で頬杖(ほおづえ)をついている。その顔はぼんやりとし、気力がまったく感じられない。
「大王様‥ という事でよろしいでしょうか‥? 」
自分の話を王が聞いていないと思った家令(スチュワード)が、クヌートの顔を覗(のぞ)き込んだ。
クヌートは家令(スチュワード)に目を向ける事なく、面倒くさそうに手を払った。
「それでよい。 よきに計(はか)らえ‥! それよりも、しばらく一人にしてくれないか 」
「はは! 」
家令(スチュワード)は羊皮紙の台帳を閉じると、恭(うやうや)しく礼をし、その場をあとにした。
大広間にはクヌート一人がぽつんと残されていた。
ウルフ伯(アール)死亡の報告は、その日の正午にはクヌートの元へと届けられていた。ゴドウィン伯(アール)直々の報告である。
彼が『大王様の命(めい)により、逆臣(ぎゃくしん)ウルフ伯を討(う)ち取って参(まい)りました』と告げた時、クヌートは改めて―――そうだ、わたしの命令でウルフは死んだのだ。わたしがウルフを殺したのだ―――と、実感した。
その時は平静を装(よそお)い、そのままゴドウィン伯(アール)を退出させたのだが、扉がバタンと閉まった瞬間に、彼の目の前は真っ暗になってしまった。
そしてその日以来、彼はずっと暗闇の中にいたのだ。
なんという事をしてしまったんだろう―――彼は親友を殺してしまった事を深く深く後悔していた。
ウルフへの処分は、公職から追放し、牢にでも閉じ込めておけば十分だったのだ。なのに、ゴドウィンの口車に乗って親友を処刑してしまった。
ウルフは、幼い頃からいつもクヌートと同じ方向を眺(なが)め、その命を賭けて自分とともに歩(あゆ)んでくれた大切な友人であったのに‥‥‥。
今さらどのように嘆(なげ)いても取り返しはつかないのだが、大いなる後悔が彼の心臓を鷲掴(わしずか)みにし、口から溢(あふ)れる慟哭(どうこく)は治まらなかった。
クヌートは戦上手(いくさじょうず)な良き指揮官であったが、王としては凡庸(ぼんよう)か、それ以下であったと思われる。
たとえば―――
父スヴェン1世と二代に渡って、死ぬような思いでやっと築き上げた北海帝国を、あっさりと三人の幼い息子達に分割統治させようとしていた。それは、とても賢者の考えとは思えない。本来ならば、成長した三人の息子の中で一番優秀な者一人に帝国のすべてを譲るべきなのだ。
アレクサンドロス帝国や古代ローマ帝国、カロリング朝フランク王国など古(いにしえ)の巨大国家も、分割統治した事でその強大な力を弱めてしまい、滅びるか、あるいは別の国になってしまった。
しかしクヌートは、三人の息子の母達、『ノルマンディーのエマ』と『ノーサンプトンのエルギフ』との板挟みにあって、息子一人一人にそれぞれの国を与えてしまったのである。
帝国建設のため死んでいった多くの家臣達を裏切る事よりも、二人の女の喧嘩の方が怖かったのだ。
だが、クヌートに賢王としての資質を見いだせない最大の理由は、彼に人を見る目がなかったという事であろう。
そのなによりの証拠が、ゴドウィンのような奸臣(かんしん)を重用(ちょうよう)した事である。
彼の政治的判断は、このゴドウィンによって徐々に間違った方向へと導かれていくのだ。
そんなゴドウィン卿の重しとなって、クヌートのために彼の台頭を押さえつけてくれていたウルフ伯も今はもういない。
この先、彼の凋落(ちょうらく)は目に見えていた。
この年―――1027年こそが、クヌートにとって頂点の年であり、その後、北海帝国はゆっくりと崩壊へ向かっていく。
クヌートが、ウルフ伯の死を大いに後悔したのは、彼自身が帝国の『終わりの始まり』を予見していたからかもしれなかった。