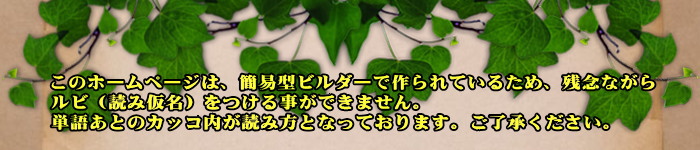
27
1026年 アンデーヌの森(2)
森へ入って二日目の夜は、ロベール一行も昨夜のような失敗はしなかった。
直接地面に寝るような事はせず、4、5人の班に分かれ、焚(た)き火を囲むようにして『寝床』を作ったのだ。
頼純は『寝床』を作りながら、昼間きこりのアランから聞いた言葉を思い出していた。
「そりゃあ、土ん上に直接寝たら、誰だって風邪(かぜ)ひくだよ。 そがあなモン、町ん中じゃろうと、野っ原じゃろうと、こったら季節なら一緒だべェ。 ましてや森ん中じゃあ、そりゃもう自殺するようなモンじゃ! そがあな事は、常識だっちゅうの 」
彼自身は、昨晩もちゃんと『寝床』を作って、その上で寝たという。
言われてみれば彼の言う通りであった。
頼純とて長い歳月(としつき)、途方もない距離を旅してきた旅人である。野宿だとて、何百遍(ぺん)とやってきたのだ。その野宿で、一番やってはいけない事が、火の不始末と地面に直接寝る事である。地面から這(は)い上がってくる冷気は、体を芯から冷やすからであった。
それは、旅をする者の常識なのだ。
にもかかわらず、頼純はそのような重大な事を失念(しつねん)していた。
何かがおかしいと思った。少々注意力が散漫(さんまん)になっている。
そう考える一方で、兵士達が地面に直接寝る場面を目の当たりにしながら、その事について何の助言もしてくれなかったアランもアランだと思った。
「だったら‥ 地面に直接寝ちゃダメだって、どうして注意してくれなかったんだよ? そうすれば、みんなだってこんなふうに体調を崩す事もなかっただろうに 」
そう尋ねると、
「そったらコト言ったって、誰もオラに聞かなかったっぺ。 んだから、言わなかっただけだ。 お偉いさんによけいなコトば言って‥ ほんでもって間違(まちげ)えでもした日にゃあ、オラ達ゃ殺されちまうからよォ。 言えねェ、言えねェ、もう言えねェや‥ 」
アンリは当然のように答えた。
頼純は、腹が立つような、立たないような、理解できるような、できないような、モヤモヤした気分で胸が一杯になった。
ただ、アンリはまぬけで、不親切、小心者なのだ。そしてその反面、賢くもあり、親切であった。その矛盾こそが庶民(しょみん)というモノなのだ。
頼純はまたもや、『自分の注意力の欠如(けつじょ)』という重大な事実から目を背(そむ)け、呑気(のんき)にきこりに関する考察などを行っていた。
そのアンリが、簡単な『寝床』の作り方を教えてくれたのだった。
まず各自が、見渡す限りに生(は)えているスギやモミなどの針葉樹から、その枝を10本ほど切り取る。つづいて、その枝が平たくなるように小枝を払い、それを地面に並べていくのだ。その上に先ほど払った小枝を重ね、さらに大量の乾いた落ち葉を敷き詰めれば、簡易『寝床』の完成である。
じつに単純だが、これだけでも地面から上がってくる冷気をかなり防ぐ事ができた。
また、寝る前に鎖帷子(オベール)を焚(た)き火でよく温めておくと、毛布にくるまった後、暖かさがぜんぜん違うのだ。
こうして、この夜はみなグッスリと眠ることができたのであった。
『アンデーヌの森』に進入して、三日目の朝がきた。
木々の隙間から差し込む朝日に目を覚(さ)ましたロベールは、寝ぼけ眼(まなこ)で周囲を見回した。
兵達はほぼ全員が起きていて、朝食の準備を始めている。
「皆、大丈夫か? 昨日のように、息苦しい者はいないか? 」
体を起こすと、ロベールは彼らに尋(たず)ねた。
「大丈夫です! 」
一同は笑顔で振り返った。
すでに起きて、火熾(おこ)しをしていた頼純が、もう一度彼らに詳しく聞いた。
「節々が痛い者、熱がある者、腹痛がする者―――何か体に異変がある者はいないか? 」
「いませ―――んッ! 」
「昨夜はたっぷりと寝ましたんで、本日はバッチリです! 」
「食欲もモリモリですよ♡ 」
そう答えると、全員が元気そうに笑った。
その笑顔に、頼純とロベールは大いに安心したのだった。
その日の朝食は、二日ぶりに鍋で焼いたパンと、干し肉の入った塩スープだったが、全員が食欲旺盛(おうせい)であった。
頼純は、倒木(とうぼく)の前の焚(た)き火に当たって食事をしていた。
焚(た)き火は、岩や倒木(とうぼく)を背にするように配置した方がよい。風を避けるという事もあるが、焚(た)き火の熱が岩や倒木(とうぼく)に反射して温かいからだ。
頼純がちぎったパンを口に放り込もうとした時、その視線の中にジョルジュ伯の姿がある事に気づいた。
「そういえば、アイツ‥ 昨日はまったく話し掛けてこなかったな‥ 」
いつもなれなれしくしてくるジョルジュ伯の事を、『鬱陶(うっとう)しい野郎』だと思っていた頼純だったが、まったく声を掛けられないとちょっと寂(さび)しい気もした。
頼純は立ち上がると、パンを囓(かじ)りながらジョルジュ伯の方へと近づいていった。
ジョルジュは焚(た)き火の前に坐り、木の椀の中の塩スープをすすっていた。
「オイ‥ 昨日はどうした? ぜんぜん話し掛けてこなかったじゃネーか。 具合でも悪いのか? まさか、お前も息が上がったとか? 」
初めて声を掛けてきた頼純に、ジョルジュ伯は照れ笑いで返した。
「え!? いやいやいや、別にィ‥ 昨日は道が狭(せま)かったじゃん! それに、息が苦しそうな兵隊ちゃんを抱えてやってたからね‥ そんで、アンタに声を掛けるヒマがなかったダケさ 」
「そうか。 なら、いんだけどな 」
「アレェ‥? もしかして、それって寂(さび)しかったとか? ツーことは、俺の事が好きになってきたってコトじゃん。 だったら、友達になろうよ。 友達、友達ィ♡ 」
「バァ~~~カ‥ ンなんじゃネーよ! 誰がテメーみてーな野郎と友達なんかになるモンかい! 」
そう悪態をつきながらも、頼純はちょっと安心した。
朝食が終わると、一同はさっそく出発の準備に取りかかった。
頼純も太刀を腰に縛り、大きめの布袋に木の椀やコップ、火打ち石、そして食料などを詰め込んでいった。
そこへロベールが不安げな表情で現れた。
「本日の進軍をどう思われます? 大丈夫でしょうか? 」
「うん‥ みんなの様子を見てると、大丈夫だと思うんだけどなァ‥ 」
頼純はちょっと自信なげに答えたが、ロベールはその言葉で確信を持ったようだった。
「ですよネ!? うん‥ 大丈夫だ‥! 」
「まあ‥ 頑張しかないか‥! 」
頼純はそう返した。

ほどなくして、ロベール一行は『アンデーヌの森』縦断に出発した。
だが、2マイル(3キロメートルほど)も前進すると、一人二人と息を荒くする者が出て、昼近くには隊の三分の一ほどがへたばってしまった。その中には傭兵(ようへい)仲間のロメオもいた。
しかたがないので、まだ余力のある者が疲れている者を助けながら、休み休み前進する事にした。そのタメ、行軍速度はかなり遅くなってしまったのである。
それでも彼らは、夕方近くまで前進を続けた。
お陰で、ロベール一行はけっこうな距離、森の奥へと入ってしまったのだ。もはや、後戻りは困難な状況となっていた。
それは事態の悪化と言える。多くの病人を抱え、森の中で立ち往生してしまう可能性があるからである。
朝、すぐに出発をせずに、もう少し様子を見ていればよかったのではないか―――いや、たとえ出発しても、呼吸困難者が出た段階で行軍を止めるべきだったのだ。
頼純やロベールはその程度の、当たり前の判断さえできなくなっていた。
「ん!? 」
最初に、その異変に気づいたのは頼純であった。
「なあ? なんだか、このあたり温かくネーか? ほら‥ 風はあるのに、ほわっとするような‥‥ 」
「そ‥ そうですか‥? 」
ロベールはその時点ではまだ判らなかった。
しかし、さらに半マイル(750メートル)も前進すると、全員が頼純の言っている事を理解した。歩いている内に汗ばんできたからだ。
それは、冬も近いこの季節に異常な事であった。
この森に入ってからおかしな事ばかり続いているのだが、頼純は今回の件もさほど気にしていなかった。むしろ、この異変はありがたいとさえ考えていたのだ。寒いよりはずっとマシであったからだ。
日が落ちかける頃には周囲から木々の香りは消え、硫黄(いおう)の微(かす)かな臭いも漂(ただよ)ってきた。
皆もずいぶんと疲れているようである。
少しばかり開(ひら)けた野原があったので、明日の事は明日考えようという事になり、その日はその場所で野営する事にした。一行は昨夜のように寝床を作ると、固くなったパンを食べて寝たのだった。
その日の夜中、頼純は呻(うめ)く声で目を覚ました。
誰かが闇の中でもがき苦しんでいる。
「ど‥ どうした? 大丈夫か? 」
しかし、それは一人や二人の声ではなかった。
頼純は急いで松明(たいまつ)に火を灯(とも)すと、あたりを覗(うかが)った。
呻(うめ)いているのは、兵士達であった。みな腹を押さえ、体を『く』の字に折ってもがき苦しんでいた。その中にはピエトロやロメオもいる。
「おい‥ 大丈夫か? しっかりしろ! 何があった? 」
「ウウウ‥ く‥ 苦しい‥ 」
「は‥ 腹が‥ 腹が痛い‥ 」
あのお調子者のジョルジュ伯さえも、苦しげに呻(うめ)いているのだ。
ほぼ全員が腹を押さえ、激痛に悶(もだ)えている。
「誰か、元気な者はいるか? 異常のない者はいないのか? 」
「は‥ はい‥ 」
頼純が声を掛けると、暗闇の中で恐る恐る手を上げる者がいた。
ロベール伯爵である。
その場で、腹痛に悶絶(もんぜつ)していなかったのは、頼純とロベールだけしかいなかった。
4日目、夜が明けても兵士達の容態(ようだい)はよくならなかった。むしろ悪化していた。
「ウウウ‥ は‥ 吐きそうだ‥ 」
「痛い痛い痛い痛い‥ は‥ 腹が‥ 腹が痛いよォ‥ 」
激しい腹痛だけでなく、ひどい下痢(げり)にも彼らは苦しみ続けた。
「あ‥ ダメ、漏れる‥ 」
兵士達は尻を押さえて木立(こだち)の中に駆け込むと、『ブビビビ‥』と下痢(げり)便を排出する。
悶(もだ)え苦しんで排便に向かう―――これを繰り返していると、やがて体力もなくなり、人目のない場所にまでたどり着けない者も出てくる。
「ああ‥ ああああ‥ 」
そしてついに、力尽きた者が横たわったまま、ブレー(ズボン)の中に漏らし始めた。
彼らの糞尿(ふんにょう)で、周囲にはかなりの悪臭が漂(ただよ)っていた。
だが、大した医術の知識もない頼純やロベールには、どうする事もできなかった。頼純は持っていただけの腹痛の丸薬を彼らに与えたが、なんの効果もなかった。
今はただ、兵士達に水を飲ませる事ぐらいしか、二人にできる事はなかったのだ。
ロベールは不安に満ち、頼純は苛立ちで一杯だった。
「どうしよう? 全員が食あたりだなんて‥ ナニが悪かったんでしょうか? パンか干し肉か‥ あるいは水が――― 」
「原因なんてどうでもいい! 今は俺達が、どうすべきかが問題なんだ 」
「そんなコト言ったって‥ まずは、腹痛の原因が分からないと、その対処もできないでしょう! 」
「この原因なんて、素人の俺達に判るワケねェだろう! これは食あたりなんかじゃない。 だから、俺達が彼らにしてやれる事はないんだ 」
「け‥ けど‥ 」
頼純は普段の冷静さを完全に失っていた。
「下痢がひどい悪疫(あくえき)(伝染病)なら、俺も『宋』で見た事がある。 もし、彼らがその病気なら、半分以上の者が死ぬ! 」
「え!? 」
「たとえ、その悪疫(あくえき)でなかったとしても‥ このままじゃ、まもなく死人が出る事は間違いない。 おそらく、何人も死ぬだろう! 」
「‥‥‥ 」
ロベールは言葉を失った。
「いや‥ この俺達だって、いつ彼らと同じようになったっておかしくないんだ。 それに、たとえ俺達が生き残れたとしても、二人じゃこの森から脱出する事はできない! つまり、全員が死ぬって事になる 」
「そ‥ そんな‥ 」
その時、ロベールは何かを思い出し、ハッと息を呑んだ。
「そうだ! 道標(みちしるべ)がある。 ホラ‥ きこりが来る途中に木の枝に着けてくれた‥ 白い糸の目印! あれをたどっていけば‥‥ 」
その言葉に、頼純は額(ひたい)にピシャリと手を当て、大きな嘆息(たんそく)を漏らした。
「あちゃ~~~あ‥ そうだった! なんで、そんな大事な事を忘れていたんだろう。 今日の俺は、どうかしちまってるゼ‥! 」
ロベールは真剣な顔で頼純に申し出た。
「彼らにしてやる事がないのなら‥ わたし達が、救援を呼びにいくしかないでしょう 」
頼純は渋い顔で考え込む。
「うむ‥ だが、行って戻ってくるのには、どんなに急いでも5日以上はかかるぞ。 」
「彼らは、そんなに持ちませんか? 」
「ああ‥ ちょっと無理だと思う‥! だが、今はその方法しかないだろう。 ただし、彼らを放(ほう)って、二人で脱出するワケにもいくまい。 問題は、アンタが行くか、俺が行くかだ 」
「は‥ はい‥ 」
「とは言え、ひとりで森を戻るのは非常に危険だ。 道に迷わなくても、崖から落ちたり、熊や狼に襲われる事だってある。 けれど、糸をたどってなんとか三日間歩き続ければ、人里までたどり着くコトもできるだろう。 一方、ここに残れば、五日以上も救援を待っている間に死んでしまう可能性が高い 」
「‥‥‥ 」
「どうする? 」
ロベールはしばし考えていたが、
「―――彼らはワタシの家来です! ワタシが救援を呼びに行きます 」
頼純は静かに頷(うなず)いた。
「判った! じゃあ、そうしてくれ。 コイツらの面倒は俺がみる。 幸い寒くはないが、もう水もなくなりかけている。 どうにかして、それを手に入れなければ‥ 」
「‥‥ええ‥ そうですね‥! 」
ロベールは数日分の食料と野営の道具を大きな袋に入れて、背中に背負(しょ)った。
大きく深呼吸すると、彼は意を決した表情で頼純を振り返った。
「では‥ いきます! 」
「ああ‥ 頼んだぞ! 」
「はい! 」
そう言って、ロベールは出発した。
頼純は合掌(がっしょう)して、その後ろ姿を見送ったのだった。
その後、頼純は兵士達になけなしの水を与えていった。
「ホラッ‥ 水を飲むんだ! 」
ジョルジュ伯を抱きかかえると、頼純は水筒をその口にあてがった。
「あ‥ ありがと‥ ゴメンね、ゴメンね‥ うんこ漏らし野郎で‥ ゴメンね! 」
「バァ~~~カ‥ いいから、さっさと飲め! 」
ジョルジュ伯はパサパサになった口の中を潤(うるお)すように、ゆっくりと水を飲んだ。その目の輝きから、頼純はジョルジュがもうしばらくは死なないと確信した。
兵士全員に水を与えると、すべての水筒が空になった。
頼純は、水を探しに周辺を探索(たんさく)する事にした。それで、水源が見つからなければ、あとは自分も含めて全員が死ぬしかないのだ。
頼純は持てるだけの水筒をすべて肩からぶら下げ、兵士の剣を借りて、森の中へと入っていった。
彼は10歩(約6メートル)進むごとに、木の幹(みき)に剣を叩き付け、傷をつけていった。道標(みちしるべ)である。
きこりのアンリが、なぜこの簡単な方法を使わず、わざわざ輪にした白糸を枝に引っかけて道標(みちしるべ)にしたのか―――それには理由(わけ)があった。
木々の修復力は大したもので、刃物で着けられた傷などは、初めは白く見えていてもすぐに酸化して黒ずみ、表皮(ひょうひ)と変わらない色になってしまう。一週間もすると、パッと見ただけでは判らなくなってしまうのである。
さらに、樹木は彼らにとって大切な商品であった。その表面に、傷をつけるという事はやはりタブーなのであろう。
頼純はその方法で印を残しながら、四方向に1000歩(約620メートル)ずつ進んで水の在りかを調べてみた。だが、その程度ではせせらぎの音さえ聞こえてはこなかった。
半日以上掛けて、飲み水の手掛かりはまったくないのである。それは、非常にまずい状況であった。
クタクタになって戻ってきた頼純は、倒木(とうぼく)の上に腰を下ろし一息ついた。
ふと視線を送った先の兵士が動いていない。
嫌な予感を感じながらも、頼純は一番奥に横たわっていたその兵士に近づいた。彼は目を見開いたまま、呼吸が止まっていた。死んでいるのだ。
「ついに始まったか‥ 」
一人目の死者に頼純は絶望し、その場に崩れ落ちた。