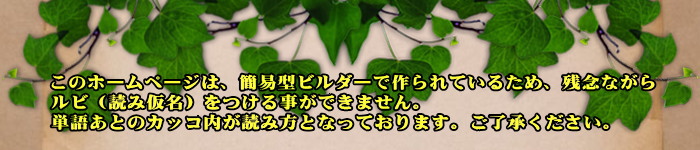
100
1027年 ルーアン城(2)
リシャールは平静を装(よそお)っていたが、心の中ではいささか動揺していた。
自分の発言で、ゴドウィンの顔色が明らかに変わったからである。
しかし、たとえ彼に変化がなかったとしても、リシャールは自分がマズい発言をした事は理解していた。
ただ、リシャールにはそのようにしか言えなかったのだ。
彼はデンマーク人が嫌いであった。
それは、日頃から『クヌートやその父・スヴェン1世は信用できない 』と、家臣らを前に明言するほどであった。
リシャールが5歳の年に隣国で始まった『イングランド・デンマーク戦争』は、彼が19歳になるまで断続的に続いた。
娯楽のない時代というだけでなく、叔母が嫁いだ国の戦争である。リシャール少年が、これに興味を持たないはずがなかった。もちろん、彼が応援していたのはイングランド王国である。
だが、この戦争の中で、クヌート・スヴェン親子は、停戦の約束を幾度となく破っては、イングランドに攻め込んだ。そして、そのたびにディーンゲルドという法外な立ち退き料を要求するのだ。
それは、大量の人命を奪い、国土を荒廃させたのみならず、経済までも徐々に弱体化させていくやり方であった。
そして、最後の最後は、謀略を使ってイングランド全土を掠(かす)め取ったのである。リシャールはそのやり方が気に入らなかった。
彼はクヌート親子を『姑息(こそく)な嘘つき』だと考えていた。
しかし、それ以上に気に入らなかったのがイングランド側の対応であった。リシャールは彼らにほとほと呆れていたのだ。
口にこそ出さなかったが、いとこであるエドアール、アルフレド兄弟の父・エセルレッド2世イングランド王、そしてその息子エドモンド剛勇王を、リシャールは軽蔑(けいべつ)さえしていたのである。
エセルレッド王は、イングランド国内に住むデンマーク人への民族浄化(=セントブライスデーの虐殺)という愚行(ぐこう)を犯した。そして、この虐殺に激怒したデンマーク国軍が攻め込んできた事から、この戦争は始まったのである。いわば、エセルレッド王が発端(ほったん)を作ったのだ。
にもかかわらず、王はデンマーク人とろくに戦いもせず、形勢不利と知るや、イングランド国民や将兵を残したまま、妻の実家であるこのノルマンディーに逃げ込んできた。
リシャールからすれば、彼はとんでもない『卑怯者』であった。
そんな中、王不在のイングランド国軍を支え、父・エセルレッド2世の死後は国王として懸命に戦っていたのがエドモンド剛勇王であった。
リシャールは、隣国の戦果を聞くたびに、この新王の事を応援していた。だがそんな彼も、最後は己の保身のため詐欺まがいの約束を信じ、契約書に署名してしまう。そして、その直後に暗殺され、国を奪われてしまうのだ。
そんなエドモンドを、リシャールは『愚か者』だと考えていた。
さらには、イングランドの最高諮問(しもん)機関である『賢人会議(ウィティナジモット)』までもが、こうした卑怯な手を使ったデンマーク王子クヌートを、自分達の国王として認めてしまうのだ。
彼らは賢いふりをしながら、国を売り渡した『腰抜け』だと見なしていた。
また、敵国の王と結婚し、子までもうけた叔母(おば)エンマ王妃も嫌っていた。
『ノルマンディーの宝石』とまで謳(うた)われた、美しく、気高(けだか)かったあこがれの叔母(おば)が、命惜しさにデンマーク人に汚(けが)されてしまったのだ。
リシャールはそれらすべてが口惜(くちお)しく、腹立たしく、幻滅していたのである。
もちろん彼とて、それらが青臭い理屈だという事は十分理解していた。
『国盗り』とは、そういうものだという事も承知している。
しかしながら、多感な10代を通して、この大戦の成り行きをずっと見守ってきた彼としては、その時に与えられた強烈な印象が、十年経った今も変わる事はなかったのである。
ノルマンディー公国も、デンマーク王国と同じく、ヴァイキングが建てた国である。
だが、我らが始祖ロロ様は、フランス王を武力でトコトン追い詰め、しかし一旦条約を結んだならばそれを遵守(じゅんしゅ)し、国王に永遠の忠誠を誓った。
王や戦士は、卑怯(ひきょう)な戦略はおこなわず、死力を尽(つ)くして敵と正々堂々と戦い、だが一旦約束を交(か)わしたならば、それがたとえ自分にとって不利な取り決めであろうとも命を懸(か)けて守る―――そういうものだと、リシャールは考えていた。
そしてそれは、始祖様から現在の自分にいたるまで、脈々(みゃくみゃく)と受け継がれてきた『ノルマン魂』だと信じていたのだ。
もちろん、それは彼の身びいきな思いに過ぎない。
ロロの始祖伝説も、強盗団が自分達の正当性を主張するために、美談(びだん)にしたて上げたおとぎ話である。ロロとて、卑怯な騙し討ち(だましうち)や残虐な殺戮(さつりく)も数多くおこなっていただろう。正々堂々と戦った事など、ほとんどなかったはずである。
それでも、リシャールのロロへの思い込みは強く、それゆえイングランド、デンマーク両国に対する不信感がよりつのっていったのだ。
さらに、リシャール3世は30歳、クヌート王は32歳と、二人は同じ世代であった。
しかし、大国イングランドを筆頭に、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの一部を率(ひき)いるクヌートに比べると、フランス王国の一領主に過ぎないリシャールは、ずいぶんと格下になってしまう。
また、若き武人として、戦闘の経験もクヌートの方が桁外れに場数を踏んでいた。
それゆえ、心の奥底でクヌートに対する嫉妬心や劣等感も感じていたに違いない。
そうした思いは、巡り巡(めぐりめぐ)って―――このような『覇(は)』をもって建国された北海帝国は、そう長く続かないであろう―――という『先入観』を作り上げていく。
彼らはその貪欲(どんよく)さゆえ、やがて継承者争いや内乱を引き起こし、民衆の武装蜂起(ほうき)や周辺国の侵略など、その国内外が混乱するに違いない―――とリシャールは推測していた。昨年、クヌート王の妹エストリドの夫が暗殺されたのも、その前兆であろう。
だからこそ、そんなエストリドと弟ロベールが結婚すれば、こうした諍(いさか)いにノルマンディー公国が巻き込まれる可能性もある。 兄としてのみならず、君主としても、そのような事態は絶対に避けたかったのだ。
とはいえ、ゴドウィンからの『我が国を嫌うのは、どのようなご理由からか? 』との質問に、自分の本心―――イングランドに対する数々の侮辱(ぶじょく)的思いを口にすれば、両国は必ずや戦争になるだろう。
傍(かたわ)らのオズバーンもそれを心配して、自分に目配せしているようだ。
―――だが、それぐらいは自分だって判っている。
リシャールは考え抜いた末、先ほどの言葉を発したのだ。そして、その理由もちゃんと用意してあった。
「それは‥‥ エンマ叔母(おば)と故エセルレッド2世王との間にできた息子達―――エドアールとアルフレドの命を、いまだにクヌート王が狙っているからです。 彼らは、これまでも何度となくデンマークの刺客に襲われましたが、その暗殺命令はいまだ解除されていないと聞きおよんでおります。 彼らはすでに立派な修道士となり、イングランドの王位継承をきっぱり放棄(ほうき)したというのにです 」
「‥‥‥‥ 」
「彼らはわたしのいとこです。 この宮殿で、ともに青春時代を過ごした家族なのです。 その大切な家族を殺そうとする一族と、どうして親しくする事などできましょうや。 ですから、我々はクヌート王や北海帝国が好きになれませんし、この縁談もお断りさせていただきたいのです 」
リシャールは、自分の言い訳に満足していた。
これならば事を荒立てずに、この男を追い返す事ができる―――そう信じていた。
だが、隣のオズバーンは微妙な表情をしている。
何か落ち度があったのだろうか―――リシャールの心にわずかな不安が生じた。
その時、ゴドウィンが告げた。
「いやいや‥ それは誤解でございます。 我が国は、いまさらエドワード様、アルフレッド様のお命を頂戴しようなどと、ゆめゆめ思ってもおりません。 なんなら、書面にてお二人を暗殺しないと確約いたしましょうか!? 」
リシャールの言葉に脅威を感じなかったのか、ゴドウィンはまたいつもの愛想笑いに戻っていた。
しょ‥ 書面‥? そうかァ‥ そう返してきたかァ―――
けれど、その書面に書かれているのは、どうせいつもの、何の効力も持たない詐欺まがいの約束だろう。わたしは、そんなものに騙(だま)されはしないぞ―――リシャールは心の中で身構えた。
ゴドウィンは続ける。
「我が北海帝国は、狭いドーバー海峡を隔ててお向かいにあるノルマンディー公国と、ただただ仲良くなりたいだけなのです♡ 」
そこへリシャールを助けるべく、オズバーン伯が口を挟(はさ)んできた。
「確約と申されても‥ それは簡単な事ではありませんぞ。 外交は互いの信頼関係があってこそのもの。 残念ながら、我が公国は、北海帝国をそうした友好的な国とはまだ考えてはいないのです 」
「‥‥‥‥ 」
ここは強引に拒絶するしかない。オズバーンは厳(いか)めしい顔で突っぱねた。
「ですから、いくらそのような約束事をしてみたところで、それが本当に実行されるかどうか、我々には判りません。 ならば、それを検証しなければならないでしょう。 まずは、エドアールご兄弟の暗殺禁止を公文書にした上で、数年間様子を見させてください 」
「す‥ 数年間―――?」
「それで、ご兄弟に異変がなければ、このご縁談も検討する事といたしましょう。 また、信頼できる友好国として、親睦(しんぼく)も深めてまいりたいと考えております 」
ふたたび、ゴドウィン伯から笑顔が消えた。
「つまり、それは‥ ロベール殿とエストリド様を絶対に結婚させないという意味ですかな? どうしても、この縁談は断ると―――? 」
「いえ、そう言う意味ではありません。 ただし、ゴドウィン殿がそうおとりになられるのはご自由です。 ともかく、これが我が大公のご結論なのです 」
「ムムムムム‥ 」
ゴドウィンが唸(うな)り声を漏らした。
オズバーンはさらに、にべもない態度で
「伯爵殿のせっかくのご訪問でしたが‥ あいにくと、本日は重要な接見が立て込んでおりまして‥ ゴドウィン殿とはここまでとさせていただきます 」
「‥‥‥ちょっとお待ちください。 この事は――― 」
ゴドウィンがさらに食い下がろうとした時、
「あ‥ あのォ‥ お話中、まことに申し訳ございません 」
広間の入り口から声が掛かった。侍医のジョセフである。
「おお‥ いかがした? 」
リシャールが声を掛けると、年老いた医師は胸を押さえ、恭(うやうや)しく頭(こうべ)を垂れながらも、客を気遣って言葉を濁(にご)した。
「い‥ いや‥ ホントによろしいのでしょうか‥ 」
オズバーン伯は、ジョセフが遠慮している事に気づいた。
「構わぬ。 こちらのお客様はもうお帰りじゃ! 用があるのなら申すがよい」
ジョセフは恐る恐る口を開いた。
「お客様と接見中である事は存じ上げておりましたが‥ 公妃様がどうしてもとおっしゃいますもので‥‥ 」
そこへ、3人の侍女に手を引かれた公妃アデルがゆっくりと登場した。
「公爵様‥ リシャール様‥ お喜びください。 御子(みこ)を、アナタ様の御子(みこ)を授(さず)かりました 」
アデルの告白に、リシャールは思わず息を呑んだ。
「な‥ なんと! それはまことか? 」
頭(こうべ)を垂れたままのジョセフがそれに答えた。
「はい! わたくし、医師を30年続けておりますが、これは間違いなくご懐妊(かいにん)でございます 」
「おお‥ 何という事だ。 でかした! でかしたぞ、アデル! 」
ゴドウィンや家臣らの前であるにもかかわらず、リシャールは感情をあらわにして大いに喜んだ。
「リシャール様‥ おめでとうございます 」
オズバーン卿が歓喜の声をあげると、玉座の前に立つゴドウィンも祝辞を述(の)べた。
「公爵殿‥ おめでとうございます。 北海帝国を代表し、このたびの慶賀(けいが)、心よりお祝い申し上げます 」
リシャールの脳裏(のうり)に一瞬いやな予感がよぎったが、せっかく祝ってくれるゴドウィンを無視もできず、彼は返礼した。
「あ‥ ありがとう 」
ゴドウィンは不気味な笑顔でリシャールを覗(のぞ)き込んできた。
「わたくしが謁見(えっけん)に拝しておる時に、このような吉報がもたらされたというのも何かのご縁でございましょう。 ここはひとつ、北海帝国で盛大なる祝宴を設(もう)けさせてください 」
「は‥ はい? 」
なにか、まずい方向に話が流れそうだと直感したリシャールはその申し出を断った。
「いやいや‥ そのようなご配慮は無用です。 どうか、お気になさらずに‥‥ 」
しかし、ゴドウィンはリシャールの言葉など無視して、話をどんどん進めていく。
「アデル様は当分御身(おんみ)を大切になさらねばならないでしょうから、場所はこのお城を使わせていただきたい。 ならば、ご安心でしょう。 開催の資金とその準備はすべて北海帝国で責任を持ちまする。 大量のお祝い品とともに、我が国の要人もたくさん送り込んで、盛大なる祝宴を執(と)りおこないましょう 」
そのあまりに強引なゴドウィンの態度に、リシャールは少々きつい口調で断った。
「ですから‥ お気持ちだけ、頂戴いたしまする! 」
だが、ゴドウィンはさらに続ける。
「北海帝国の主賓(しゅひん)は―――エマ王妃でいかがでございましょう? 10年ぶりの里帰りという事ですな♡ 」
「え!? 」
その場にいた全員が言葉を失った。
やがて、そのあり得ない話に目を丸くしたオズバーンが話し掛けた。
「エ‥ エンマ様を? イングランド王妃をノルマンディーに送り込むとおっしゃるのか? 」
ゴドウィンはしたり顔で頷(うなず)いた。
「さようでございます。 エマ様のお母上―――グンノール太公太后(たいこうたいごう)様もかなりのご高齢。 これが最後のお目通りとなるやもしれません。 となれば、これが我が国最大の贈り物といえましょう 」
「‥‥‥‥ 」
それは、御子(みこ)懐妊以上の重大発表であった。
国王・貴族の婚姻は、相手国に人質を送り込むという意味もある。その人質を実家に帰してしまったら、二度と戻ってこないかも知れない。ましてや、エンマにはこの地に匿(かくま)われている3人の子供がいるのだ。これは、イングランド側としてはかなり危険な賭けといえた。
ゴドウィンはそれほど重大な案件を、いともたやすくリシャールらに確約したのだ。つまり彼は、王に相談する事なく、重要な国政を決定する権限を持っているという事になる。
それでも、リシャールはこの男が信用できなかった。
「しかし‥ 」
ゴドウィンは笑顔でさらにたたみ掛けた。
「先ほどから申し上げているように‥ 我々に他意はありません。 我が国はただただノルマンディ公国と親しくなりたいだけなのです 」
執拗(しつよう)にノルマンディーに接近しようとするこの男に、オズバーンが疑問をぶつけた。
「なぜ、そこまで我が国と親しくなりたいのですか? 少し、おかしくないですか? 」
「どこに不思議(ふしぎ)がありましょうや。 当たり前の事でございます 」
ゴドウィンは淡々とした口調で答えた。
「我が北海帝国は、10年前に統一されたばかり。 まだ、各国にはたくさんの不穏分子(ふおんぶんし)を抱えておりますし、本国デンマーク王国の背後には、強大なローマ帝国(=神聖ローマ帝国。現在のドイツ、オーストリア等)が控(ひか)えております。 この上、わずかな海峡を挟んで対峙(たいじ)するノルマンディ公国まで敵に回したくはないと考えるは必定(ひつじょう)! 」
今度はリシャールがそれに反論した。
「敵に回すなど‥ 我が公国よりも、貴国の方がはるかに強大ではないですか。 そもそも、このノルマンディーがイングランドの敵となる理由がない 」
口元こそ緩(ゆる)んでいるものの、ゴドウィンは強い目力で見返してきた。
「本当にそうお考えですか? このノルマンディーには、イングランド王国の王位継承者が2人もいらっしゃるのですよ。 あなた方が彼らを担(かつ)ぎ上げて、イングランドに攻め入(い)る可能性だってある。 その時、2人のサクソン人王子の味方をしようとするイングランドの有力者は、まだまだたくさんいるのです 」
「‥‥‥‥ 」
リシャールは、ゴドウィンの言葉になにも返さなかったが、やはりこの男は嘘つきだと確信した。
さきほど、エドアール兄弟を殺さないなどと語りながら、やはり兄弟をイングランドの継承権者と認め、それを脅威に感じているではないか。
ゴドウィンも口を滑らせた事に気づいたのか、話題を変えようとする。
「ともかくです! 両国が友好国となり、軍事のみならず、貿易・商業を促進し、互いが経済的発展をする事がわたくしの希望なのです 」
すがるような笑顔でゴドウィンが頼み込んだ。
「お願いいたします。 少しはこちらの顔も立ててくださいよ 」
「‥‥‥‥ 」
リシャールは返事を一瞬躊躇(ちゅうちょ)した。
すると、ゴドウィンの態度が瞬(またた)く間に変わった。その顔からへりくだった様子がすべて消え、恫喝(どうかつ)する口調となったのだ。
「ここにいたり‥ よもや、祝宴の申し出さえもお断りなさるおつもりではありますまいな。 エストリド様とロベール様との婚姻を拒絶され、ご子息誕生のお祝いまで断ると申されるか。 それは、我が国の誠意すべてを拒絶するという意味! すなわち、我が国との国交を断ち、戦争に向かうという事ですぞ 」
「い‥ いや‥ 」
リシャールは追い詰められてしまった。
「判りました。 では、祝宴の方は、よろしくお願いいたします 」
ロベールの縁談はいざしらず、御子懐妊(みこかいにん)の祝宴くらいならさほど問題はなかろうと、リシャールは考えたのだ。
エンマ叔母が里帰りすれば、グンノールお祖母様(ばあさま)もさぞやお喜びの事だろうし‥‥‥
一方、ゴドウィンはふたたび穏やかな表情に戻ると
「ありがとうございます。 ならば、エストリド様、ロベール様のご縁談話は、しばらく保留とさせていただき‥‥ わたくしは、御子(みこ)様ご懐妊の祝賀の宴(うたげ)に専念する事といたしましょう。 祝宴は1ヶ月後―――それでよろしゅうございますな。 かならずや、両国の架け橋となる素晴らしい祝宴にしてみせましょうぞ 」
リシャールは不承不承(ふしょうぶしょう)、謝辞(しゃじ)を述べるしかなかった。
「ゴドウィン殿のご厚情(こうじょう)‥ このリシャール、心より感謝いたします‥! 」