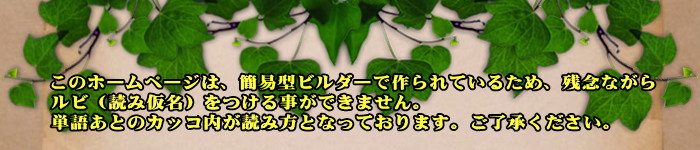
103
ファレーズの街(1)
ファレーズの街並みが茜色(あかねいろ)に染まりはじめた。 やがて、教会の鐘も晩課(ばんか)を告(つ)げるであろう。
その頃、元革なめし職人であったフルベールの館の一室に、『カラス団(コルブー)』達が招集されていた。
彼らは石畳の床に車座になっている。
「え!? 助祭のトマ? 」
ゴルティエが訝(いぶか)しげに聞き返した。
ニコラは頷(うなず)くと、話を続けた。
「ヨリ様の話では、『山犬のジャン』による伯爵様襲撃事件と、『ドラゴン退治』での伯爵様ご一行への毒物投与事件は、どちらもトマ助祭が絡(から)んでいるのではないかと―――! 」
頼純、グラン・レイと分かれてファレーズに先着した4人は、街に残っっていたゴルティエら6人に、サン・マリクレール修道院での出来事などを説明していた。
「え!? トマ助祭って、誰? 」
プチ・レイが尋(たず)ねた。
その問いにドニが答える。
「ホレッ、あの人ですよ‥ 『領主の館(メヌア)』の礼拝堂(シャペラ)にいる―――貧相な顔をした陰気くさい人! 」
自分達だって顔を忘れていたくせに、遠征組の面々は知ってて当然とばかりに、居残り組にトマの容姿を教えた。
「そーそー! ネズミみたいな顔をした――― 」
「いつも、オドオドしてて‥ ホラ、いるじゃないですか! 」
「あ~~~あ‥ いた、いた! 」
「―――あの人ねェ‥‥ 」
居残り組達もやっとトマの顔を思い出したようだ。
「けど‥ 俺達は、『領主の館(メヌア)』の中庭で訓練をしてるから、時々見かける事もあるけど‥ 街の人達は誰も、あの人の事なんか知らないんじゃない? 」
日々、探索方(たんさくがた)(=刑事のような仕事)の訓練をしているゴルティエ達にとって、人の顔を覚える事は当然の能力であった。その彼らが、すぐに思い出せないほど、トマの印象は薄かったのである。
「あ、そうだ! 俺がこないだ教会に行った時、あの人の事が話に出てたよ 」
リュカがそう言うと、仲間達が一斉に茶化(ちゃか)した。
「はあ? お前が教会に行ったって? 」
「らしくねェなァ‥ 」
リュカは、ちょっと照れ臭そうに言い訳をした。
「いや‥ 俺んち、婆ひとり、子ひとりの家族だろう!? そのばあちゃんが、教会につれてけってうるせーんだよ。 もうすぐ、お迎えがくるから、神様にお祈りをして、告解(こっかい)をしなきゃならないんだって。 で、ばあちゃん、足が悪いから、そのお供さ 」
「本当は、蜂蜜でもなめにいってたんじゃネーのか? 」
「バァ~~~カ‥ ありゃ、5歳までの限定ご褒美(ほうび)だぞ 」
「だって、リュカの頭ん中はそれぐらいの年齢だろう♡ 」
「ギャハハハハハ‥ 」
「おい! こりゃ、遊びじゃネーんだぞ! 」
ゴルティエが硬い声を上げた。
緊張感のない、仲間内の空気となっていた室内が、ピリリと引き締まる。
「で‥ お前は教会で何を聞いたんだ? 」
ゴルティエの問いに、リュカは真顔になって語った。
「あ‥ はい‥ ばあちゃんが司祭様に、『最近、おかわりはありませんか?』って聞いたんですよ。 まあ、世間話なんですけど。 そしたら、司祭様‥ 『変わったと言えば、礼拝堂(シャペラ)のトマ助祭がおかしくなっちゃった事くらいですかね 』なんて言ってたんです 」
ドニやマルクが眉を顰(ひそ)めた。
「なんだ、そりゃ? どういう意味? 」
「取って付けたような返事ツーか‥ 普通、そんな個人の話なんかしネーだろう 」
リュカは一同に説明した。
「ですよねェ‥ 俺も最近はそういう訓練受けてっから‥ 今までなら聞き流してたような会話にも敏感になっちゃって‥‥ それで、司祭様に尋(たず)ねたんですよ 」
「そしたら? 」
「なんでも、別人みたいになっちゃったんですって。 いつも、ビクビクと脅えてた助祭様が、今は堂々としているというか‥ むしろ、尊大な感じになっちゃったらしいんです! 司教様はいつも、その事がすごく心配らしくて‥ それで、ついポロリと――― 」
一瞬、『カラス団(コルブー)』が沈黙した。
しばし考え込んでいたゴルティエが、ポツリとつぶやく。
「―――やっぱり、トマ助祭は怪しいな。 さっそく、調べてみた方がいいか‥‥ 」
「けど、もう日も沈むし‥‥ まだ、ヨリ様だってお戻りじゃないからさ‥‥ すべては、明日っからって事でいいんじゃない? 」
そう提案したプチ・レイに、ニコラが反対した。
「ダメです! ヨリ様はトマ助祭の居場所だけは、すぐに確認しておくようにとおっしゃってました! ただし、助祭はすごく頭がいいので、近づきすぎると見破られるそうです。 ですから、距離を取って見張るようにと―――! 」
ゴルティエが頷(うなず)いた。
「なるほど‥ それもそうだ。 じゃあ、まずは俺とラウルで張り込もう。 お前達は、ヨリ殿が戻ってこられたらコッチに連絡してくれ 」
立ち上がろうとした一同に、ニコラがさらに付け加えた。
「あのォ、それと‥ トマ助祭は、自分が疑われてると知ったら、井戸に毒を入れる可能性もあると思うんです。 ですから、その時はすぐに、トマが近づいた井戸すべてを閉鎖すべきだと思うんですが‥‥ 」
「ど‥ 毒? 」
遠征組が初めて聞いた時と同じように、居残り組も『毒』という言葉に大いに動揺(どうよう)した。
それに応(こた)えるかのように、ゴルティエは厳(きび)しい表情で一同を見渡す。
「よし、徹底して慎重にいくぞ。 絶対バレないように、尾行するんだ! 」
「了解! 」
かすかな不安を感じながらも、『カラス団(コルブー)』達は力強く声を上げた。
× × × × ×
夜半にエレーヌの森から戻ってきた頼純とグラン・レイは、フルベールの屋敷に立ち寄った。ゴルティエは、張り込みをプチ・レイと交代し、すでに戻ってきていた。彼らは、事態の詳細(しょうさい)といくつかの確認をすませた。
それからすぐに、『領主の館(メヌア)』へと向かったのだった。
すでにベッドに入っていたロベール伯爵を起こすと、頼純は事の次第を説明した。犯人と思われる者が、すぐ近くに―――同じ敷地内に建つ礼拝堂(シャペラ)にいるのである。 助祭トマの事を知らせないわけにはいかなかった。
「そうですか、あの男が‥‥? 」
「『山犬のジャン』が殺された時、わたしはロレンツォ様の通訳だったフランチェスコや警備隊のピエトロ、フィリッポを通じて、ジャンを担当した拷問官や警備兵に事細かな尋問(じんもん)をしたんです。 確かにその時、トマの名前も出てました。 なのに、わたしはそれを見落としていた‥‥ 」
頼純が口惜しそうに語った。
「それは、いたしかたのない事でしょう。 あの時、あなたは旅人でしたから。 異国のこのような事件にそう関心もなかったでしょうし‥‥ ましてや、教会の者が怪しいなどとは誰も考えませんよ 」
「それで‥ 伯爵は、トマ助祭から恨まれるような事―――何か、心当たりはないですか? それは、アナタの何気ない言動かもしれませんけど‥‥ 」
「いえ‥ おそらく、それはないと思います。 そもそも、わたくしはあの方と話した事がないのですから 」
「え!? 話した事がない? 」
「ええ‥ 礼拝堂(シャペラ)はすぐ隣なので、彼もこの館に頻繁(ひんぱん)に出入りしているようですが‥ わたしが彼と直接話した事はありません。 礼拝の儀式は、すべてエイマール司教がおこなってくれますしね 」
「‥‥‥ 」
「まあ‥ それでも、何度かこちらから話し掛けた事はあるのですよ。 けど、彼は無言で恭(うやうや)しく頭(こうべ)を垂れるばかりでした 」
「なるほど‥ やはり、動機はわからないか‥‥? 」
困ったように顔を曇らせた頼純に、ロベールが尋(たず)ねた。
「で‥ 彼が犯人かどうかは、どうすれば確定するのでしょうか? 」
「『山犬のジャン』に、アナタの暗殺を依頼した犯人は、いつも分厚い本を持ち歩いていたそうです。 その中は真っ黒になるくらい何かが書き込まれていたというのです。 その分厚い本とは、おそらくトマ助祭がいつも抱えている聖書ではないかと‥‥‥ ですから、その中を見る事ができれば、はっきりすると思います 」
「なるほど‥ その確認ができれば、捕縛(ほばく)という事になるわけですね。 わかりました。 明日にでも、わたしが声を掛けてみましょう 」
「それから‥ 今夜は、エルルインら親衛隊にお側(そば)を警護させますので‥ どうか、ご安心ください 」
「ありがとう 」
× × × × ×
静かな、静かな夜だった。
いや、それは異様といえるほどの静寂(せいじゃく)であった。だが、誰もその異様さに気づいてはいなかった。
頼純はとりあえず自宅に戻った。
事態が大きく動くのは明日以降である。
トマへの張り込みは、『カラス団(コルブー)』だけでも十分であろうと考えていた。
彼らはしっかり訓練を積んでいたし、それだけの能力があると確信していた。
だから、それまでは食事と睡眠を取っておいた方がよいと考えたのである。
頼純はパンと野菜スープを食べながら、サミーラの大きくなったお腹(なか)を眺(なが)めていた。
『ああ‥ 自分にもついに、守らなければならない存在ができてしまったな‥‥ 』などと、ぼんやり考えていた。
すると、笑顔のサミーラが話し掛けてくる。
「ごめんなさい。 急なお戻りだったから、こんな物しかなくって 」
「かまわないよ。 それよりも赤ちゃんの具合はどう? 」
2人の会話は、かつてのようなソグド語ではなく、フランス語でなされていた。 もう、サミーラになまりはなく、発音も完璧であった。
彼女はこの土地になじむべく、大きく変化していたのだ。
近所の人々と積極的に会話し、ノルマンディー料理もならっていた。
まだ、キリスト教に改宗はしていなかったが、すでにイスラムへの信仰は薄れていた。
これまでタブーとされてきた豚肉食も何度か挑戦している。
外出時、ヒジャブで顔を隠す事は変わっていなかったが、それが街の女性達との大きな違いにはならなかった。
この時代、キリスト教徒の女性も、みな頭部を布で覆(おお)っていたからである。 髪を見せる事は、『男を惑(まど)わせる、はしたない事 』とされていた。
「どんどん大きくなってくれるのはうれしいけど‥ お腹の中で暴れ回って困っちゃう。 きっと、元気な男の子ですよ 」
そう答えたサミーラの笑顔に、頼純は大いなる幸せを感じていた。
そして、2人を守るためにも、明日の捕り物は重要であると考えていた。
× × × × ×
そのまま時は過ぎ、天空が瑠璃色(るりいろ)に変化していく。新しい1日の始まりである。だが、その日雄鶏(おんどり)が朝を告げる事はなかった。
礼拝堂(シャペラ)内の小部屋で寝起きしている助祭トマは、まだ薄暗いうちからエイマール司教のおわすファレーズ教会へと向かった。 日々の日課である礼拝のためである。
『領主の館(メヌア)』の中庭に出た彼は、何やらいつもと違う空気を感じた。
館(やかた)周辺を警備する親衛隊に、なんとなく違和感を感じたのだ。 それは、ほんの些細(ささい)な事であった。
たとえば音―――ガチャガチャという音が耳に残る。そこで目を凝(こ)らしてみると、いつもなら鎧下(ガンベゾン)しかつけていない彼らが、今朝は鎖帷子(オベール)を着用しているのだ。 その鎖帷子が長剣(エペ)とぶつかって音を立てている。
トマは何事であろうかと訝(いぶか)った。
それでも彼は、そのまま城門を抜け、ファレーズ教会へと歩いて行く。
朝靄(あさもや)けむる早朝の街は、いつもと同様に人気(ひとけ)がない。
すると、彼の後ろから、ヒタヒタと2人分の足音が聞こえてきた―――何気なく背後をうかがうと、2人は『カラス団(コルブー)』のようである。
その尾行はなかなかのものであった。 普段なら、まったく気づかなかったに違いない。
だが、さきほどの親衛隊の様子が、トマの神経を敏感にしていた。
トマは瞬時に、自分が疑われている事を悟った。
ロベール伯爵の警護を固めたという事は、自分が伯爵襲撃を企(くわだ)てた事がバレたからであろう。
彼は一瞬、緊張した。
だが、すぐに落ち着きを取り戻す。
これは、予想していた事なのだ。
かつてのオドオドしたジロアは、いまや完全に邪悪なるトマに乗っ取られてしまった。 ジロアはトマに殺されたのだ。
そして、トマの態度が急変した事を、教会関係者全員が知っていた。 すでに、街の噂(うわさ)にもなりはじめている。
それが、彼にとってひじょうに不利な状況を生み出す事も判っていた。
それでもトマは、それを誤魔化そうとはしなかった。
かつてのジロアの真似をして、オドオドしてみせれば、みなも勘違いだったと納得しただろう。
だが、彼はそうしたくはなかった。 どんな時でも、堂々と邪悪でありたかったのだ。
それは、『トマ』が偽(いつわ)りの人格であるがゆえ、自分の存在を必要以上に主張したかったのかもしれない。
ともかく、彼は自分を変えなかった。
だから、近いうちに、自分の正体がばれるであろう事も覚悟していた。
―――ただ、彼はすでに手を打っていた。
そして、そろそろその成果が現れ始める頃であった。
トマはそれを確認するため、礼拝と称(しょう)して街に向かっていたのだ。
× × × × ×
その朝、鍛冶屋(かじや)の妻・アンヌは5歳の息子・ジョルジュに声を掛けた。起こすのはもう3回目である。 だが、息子はいっこうにベッドから出てこない。
夫・レオンは、すでに作業場の炉に火を入れ、仕事の準備をしていた。
アンヌも早く息子に食事を与え、夫の手伝いをしたかったのだ。
業(ごう)を煮やしたアンヌは、ジョルジュを無理やりでも起こそうとベッドに向かった。
「いい加減にしなさい。 早く起きるの! 」
だが、ジョルジュは微動(びどう)だにしない。
「もう! お母さんだって忙しいのよ! 早く起きなさいってば! 」
そう言いながら息子の肩を揺さぶった。その時、彼女はジョルジュの異変に気づいた。
息はしているものの、死んだようにグッタリとしているのだ。
彼女はけたたましい悲鳴を上げた。
「どうした? 」
仕事場にいたレオンが駆け寄ってきた。
レオンは動かない息子の様子を確認した。
熱もないし、苦しんでもいない。 ただ、グッスリと眠っているだけなのだ。
しかし、明らかにジョルジュの容体は尋常(じんじょう)でなかった。
2人は医者に診せるべく、息子を抱えて表に飛び出した。
医者はたいそう高額だったが、2人にはどうしたらよいのか判断がつかなかったからである。
すると、通りのあちらこちらに、彼らと同じように幼い子供を抱えた親達がうろうろしている。
レオンはパン屋のジュールを見かけ、声を掛けた。
「お‥ お前のところも―――エマヌエルもか? 」
「ああ‥ どれだけ声を掛けても、ぜんぜん動かないんだ 」
何人もの子供が同様の症状であった。
その時、誰かが叫んだ。
「これって、疫病(えきびょう)じゃネーのか? 俺達にも病気がうつるんじゃないの? 」
その声が、街を大混乱へと導いていったのだった。