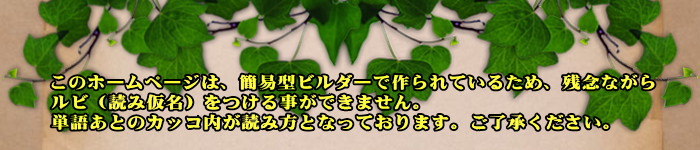
24
1006年 アルベルタン修道院
深夜ともなり、ファレーズ城内の明かりはすっかり消えていた。
昼間、あれほどまでに熱気に充ち満ちていた中庭には、もはや熱のかけらも残ってはいなかった。ただただ、冷たい秋風だけが吹き抜けていくばかりである。その温度差が、よけいにもの悲しさを感じさせた。
そんな中、ただひとつ微(かす)かな光を漏らす場所があった。
礼拝堂(シャペラ)である。
暗闇の中、祭壇(さいだん)に灯(とも)した一本のロウソクが、弱々しい光を外にまで漏らしているのだ。
その祭壇(さいだん)に向かって、助祭のトマは一身に祈りを捧(ささ)げていた。
彼のその姿を見れば、誰もが熱心な助祭様だ―――と感心するに違いなかった。
だが、彼がブツブツと呟(つぶや)くのは、ロベールに対する呪いの言葉であった。
「どうして、アイツは死ななかったんだ! あの時、自殺すればよかったのに‥ 死んでくれればよかったのに‥ ああ‥ なぜ死なない!? 死ね死ね死ね! 」
その表情はおぞましく、醜(みにく)かった。
「山賊のジャンの時も生き延(の)び、今日もあと一歩のところで死ななかった。 クソ! どうしてだ、なんで死んでくれない! 」
彼は教会の助祭でありながら、神もキリストも信じていなかった。
「悪魔(サトン)様‥ どうか、あの者の命が尽(つ)きますように! あの男が結婚する事などありませんように! 私があの男を殺す時、どうかその偉大なるお力をお貸しくださいませ! 」
トマは反キリスト主義の悪魔崇拝者であった。
そのトマという名さえ、彼の本当の名前ではない。彼が生まれた時につけられた名前はジロアといった。
ジロアは30年ほど前、ルーアン近郊のアルベルタン領の寒村で生まれた。
母の腹から9ヶ月で産み落とされ、その時の大量出血によって彼女は死亡した。
ジロアという名は、母が出産前から決めていた名前で、彼女の祖父の名前だった。
父は妻を死に追いやったジロアにまったく興味を示さず、彼はほぼ育児放棄の状態で育てられる。
発育不全で産まれ、満足に乳や食事も与えられなかったジロアであったが、彼はなんとか生き延びていた。
だが、たった一人の肉親であったその父も、彼が4歳の時に死んでしまう。
酒ばかり飲んでいた父は、冬の寒い朝、酒場の前で凍死しているところを発見されたのだ。
引き取り手のない幼子(おさなご)ジロアは村の世話人の手で、修道院へと連れて行かれた。『奉献の子(オブラートウス)』と言われる制度である。
彼は教会に―――神に捧(ささ)げられたのだ。
僧侶(そうりょ)となれば、厳(きび)しい戒律(かいりつ)に縛られた生活を強(し)いられるが、質素ながらも食事は毎日とる事ができた。貧しき者達では、日に一度の食事さえままならない時代である。
まだ4歳であるというのに、ジロアは極度の栄養失調から痩せこけ、身長も一般的な児童のそれにぜんぜんとどいていなかった。
彼を見る者が一瞬眉を顰(しか)めてしまうのは、ジロアが汚い身なりで、猛烈な悪臭を放っていたからではない。その容姿が、ひどく醜(みにく)かったからである。
さらに言葉がほとんどしゃべれなかった。会話という行為をした事がないからである。彼は誰かに抱かれた記憶さえなかった。
人の温(ぬく)もりや優しさを与えられた事がないのである。
そのタメ、肉体も知能もかなりの発育不全であった。
修道院には、ジロアとはまったく別の理由で入門する『奉献の子(オブラートウス)』達がいた。彼らの多くは、貴族の次男、三男や、富豪の子弟達などであった。
彼らはジロアを、汚い子犬にするように、棒で叩き、水を掛け、イジメ、罵(ののし)り、からかった。神に仕える身だとはいえ、彼らはまだまだ子供なのだ。
だが、大人の修道士達も彼を無視し、あるいは下男のようにこき使った。
何も分からず、右往左往する4歳のジロアを、人々は嘲(あざけ)り、怒鳴るのだ。
しかしある時、そんなジロアに救世主が現れた―――修道院長のギベールである。
彼は、いつもジロアをかばい、優しくしてくれた。
ジロアを風呂に入れ、食事を与え、言葉を教えてくれた。
いつも抱っこしてくれた。
四十を過ぎ、でっぷりと太った彼の膝の上で、ジロアは文字を覚え、聖書を読んでもらったのだ。
ジロアは生まれて初めて『幸せ』というモノを感じる事ができたのである。
だが、彼が8歳、9歳になるとギベールは彼にイタズラを始めた。
最初はちょっとイヤだと思う程度であったが、そのイタズラは徐々にエスカレートしていった。
性的虐待の始まりである。
× × × × ×
11世紀のキリスト教社会には『私有教会制』というものが存在していた。
これは、国王や貴族・領主達が自(みずか)らの領地内に教会を建て、そこで祭事(さいじ)を行う司祭をも、自分達が指名する制度であった。
彼らが指名するのはたいていの場合、彼らの遺産を相続する事ができない者―――国王や貴族の次男坊、三男坊であった。
彼らは、ローマキリスト教会とは関係なく、勝手に教会運営者である司祭となる事ができるのだ。大した修行を積む事もなく、人々から崇拝(すうはい)される地位を手に入れる事ができるのである。
メリットはそれだけではない。
教会は、貴族同様に教区内に荘園(しょうえん)を所有していた。
また教区(きょうく)内に住む全ての者から、その所得の十分の一を教会税として受け取れるなど、様々な税の徴収権も持っていた。
つまり、莫大な収入を得る事ができるのである。
そして彼らは、厳格なキリスト教の教えに縛られず、好きなように自分達の教区で振る舞う事ができた。
戦争を好み、狩りをし、美食に溺(おぼ)れ、女好きの聖職者達である。
こうした、司教や司祭を任命する権利を『叙任権(じょにんけん)』という。
この『叙任権(じょにんけん)』を国王や貴族が勝手に行使する事に、ローマキリスト教会は大いに頭を痛めていた。
これら世俗(せぞく)司祭は、ローマキリスト教会の統制の外にいるからである。
キリスト教会は、教皇(きょうこう)、大司教、司教、司祭、助祭といったピラミッド形式の位階(いかい)を持つ強固な組織である。
だが彼ら世俗(せぞく)司祭は、そのキリスト教会の頂点に立つ教皇(きょうこう)の言葉ではなく、彼らを任じた国王や貴族の言葉に従うのだ。
しかも、これら世俗(せぞく)司祭の権力が大きくなると、その地域の司教の選出に対しても発言力を持つようになっていく。
さらに『私有教会』の司祭達は、国王や貴族にとって都合のいい教皇(きょうこう)を選ぼうと画策さえしたのである。
これでは『神の家』である教会が、人間である国王達の下につく事になってしまう。
これを危惧(きぐ)したローマキリスト教会は、司教区の統一を乱す『私有教会制』廃絶(はいぜつ)と『叙任権(じょにんけん)』奪還(だっかん)のタメ、国王や貴族と対立し、やがて『叙任権(じょにんけん)闘争』へと向かっていくのだった。
そしてこの五十年後に、あの『カノッサの屈辱(くつじょく)』事件は起きるのである。
× × × × ×
アルベルタンの修道院もこういった『私有修道院』のひとつであり、ギベール院長はアルベルタン伯ギスカール2世の次男であった。
この修道院には美しい少年達が数多くいたにもかかわらず、ギベールはジロアをわざわざ選んだ。それが彼の趣味だったからである。
やがて院長はジロアを鞭(むち)で打ち、サディスティックな行為を始める。
醜(みにく)い小悪魔め、成敗(せいばい)してくれる!―――そう叫びながら、彼は絶頂に達した。
哀(あわ)れなジロアは、とても口には出せないような虐待(ぎゃくたい)を受け、その激しい痛みと深い悲しみは、彼を底なしの闇へと引きずり込んでいった。
わずか10歳のジロアは、毎日毎日犯され続けるのである。
周りの者達はそんなギベールの行為を知りつつも、誰もジロアを助けてはくれなかった。
その狭い世界では院長こそが頂点であり、ギベールを咎(とが)める上部組織などなかったからであった。
身の毛もよだつような巨大な恐怖が、ジロアを無限に襲い続けた。
彼はネズミのように、いつもビクビク、オドオドとしていた。この時の恐怖が現在のジロアの人格を形成したのだ。
その恐怖は、しだいにジロアの心の底まで蝕(むしば)んでいった。
そして或(あ)る日、彼の精神は完全に崩壊するのである。
ジロアとはまったく別の人格が出現したのだ。
彼はジロアの代わりに恐怖の時間をすごしてくれ、ジロアはその間の苦痛の記憶が全くなかった。
一方、ギベール院長はその変化を大いに喜んだ。新たなる人格は、彼の性的虐待を積極的に受け入れたからである。
その人格が、普段のジロアとはあまりにもかけ離れていたため、行為が終わったベッドの中で、ギベールは彼をトマと名付けた。
トマとは、ラテン語で『双子のもう一方』という意味である。
ギベール院長があまりにも彼をトマ、トマと呼ぶので、修道院の人々もジロアをトマと呼ぶようになる。
だが、トマと呼ばれた人格は、大胆で残忍、かつすばらしく賢かった。
彼は本当に『小さな悪魔』となったのである。
やがて、修道院は大火事となる。
完全に焼け落ちた修道院の跡地から、真っ黒焦げになったギベール院長の死体が発見された。その口の中には、切り取られた彼自身の陰部が押し込んであった。
調査に当たっていたギベールの兄・ダミアン1世も、その火事が殺人放火である事はすぐに気づくのだが、その犯人を見つけ出す事はできなかった。
いつもオドオドとした14歳のジロアが、よもや殺人犯であろうとは誰も思わなかったからである。
聖書はジロアに譲(ゆず)るというギベールの遺言書が残っていたため、その高価な書は彼の手に渡った。
なぜ、突然殺された修道院長の遺言書が残っていたのか‥ なぜ、聖書は修道院とともに燃えなかったのか―――その謎に目を向ける者は一人としていなかった。
ジロアの中のトマは、『この世は悪に充ち満ちており、そのような世界を作った神もまた、悪に違いない』と信じ込んでいた。
そして、修道士であるにもかかわらず、悪魔崇拝者となるのである。
ジロアはその後、各地の修道院を転々としたが、その中のとある図書館で運命的な禁書と出会う。それはイスラムの医学書であったが、古今東西の様々な毒の製法が記(しる)されていた。
トマは必死にそれを読み、ギベールの聖書の隙間に書き写していった。
やがて、ギベールの聖書には毒薬の事だけではなく、悪魔の言葉までが書き並べられていく。その禍々(まがまが)しい言葉は細(こま)かな字で、聖書の文字と文字の間にビッシリと書き込まれていった。
羊皮紙の上に美しい文字と絵が手書きされた『神の書』は、おぞましい悪魔の書と変わり果てたのである。
それゆえに、トマであるジロアは、その聖書を誰にも見られないよう、いつも抱えて歩いているのであった。
× × × × ×
ロベール伯爵は、兄リシャール公爵の命令に背(そむ)くわけにもいかず、ドラゴン退治のための戦仕度(いくさじたく)をしていた。
ロベールがあまりにも不安がる上、こうなった責任の一端は自分にもあるような気がする頼純は、仕方なくその任務に付き合う事にした。
だが、彼の体力は極限にまで低下していたので、四日の猶予(ゆうよ)をもらったのだ。
その間、彼は眠り続けた。たまに目が覚めると、排泄をし、水替わりの牛乳を飲み、軽い筋肉のストレッチなどをしたが、それ以外はベッドでひたすら爆睡(ばくすい)した。
一方、ロベール達は武器や武具、食料や水を用意していた。
アンデーヌの森の入り口は、ファレーズから2日半ほどの距離にあったが、そこから深い深い森へと進入していくのである。
となると、旅路は十日から2週間近くになるであろう。
その旅には、兵士を30人ほど連れて行く予定だった。
その場合、たとえ途中の村で補給したとしても、食料や水は大量に必要となる。
それらを揃(そろ)えるだけでも、四日では足りないくらいであった。
四日目の朝、目を覚ました頼純はゆっくりと全身の筋肉を動かしてみた。どこにも痛みはない。巨兵兄弟との戦いでできた擦(す)り傷や挫傷(ざしょう)も完治していた。
サミーラは蜂蜜がたっぷりのったパンと、豚肉の塩漬けを焼いたモノ、野菜がたっぷり入ったポタージュスープなど、栄養価の高い食事を出してくれた。
頼純はそれらをむさぼるように食べた。サミーラは、そのあまりのがっつきぶりに呆れるほどであった。
モン・サン・ミッシェルからの帰途で捕まってから、頼純はほとんど何も食べていなかったのである。空腹は限界にまで達していた。
彼は、一日中食べて、再び眠った。
五日目の朝に目を覚ますと、頼純の体調は完璧な状態に戻っていた。
太刀を軽く振ってみる。エノー兄弟達との対決時より、倍ほどの速度で振る事ができた。
「ヨシッ! 」
頼純は満足げに頷くと、旅支度(じたく)を始めた。
傭兵仲間のピエトロとロメオもついてくるという。
サミーラを含めた残りの者達は、モン・サン・ミッシェル近くの村に宿泊する本隊へと戻らせる事にしていた。
今回のリシャール3世の逮捕劇と、これからのドラゴン退治については、ヴェネチアのロレンツォに使いをやって報告させていた。
頼純が中庭に出ると、晴れ渡った空の下、すでに兵士達は整列している。
食料やテントなどを積んだ馬車が5台、ロベール達が乗る馬が四頭いた。
「ヨリ殿‥ 」
ロベールが心配そうな顔で近づいてきた。
「うむ‥! 」
頼純は彼を安心させるかのように、大きく頷(うなず)く。
そこへティボーが呑気(のんき)な顔をしてやって来た。
「若‥ 大丈夫です! 『アンデーヌの森』に入ったら、入り口付近で二、三日、ジッと動かずにお過ごしなさい。 そうして、帰ってくればよいのです―――『ドラゴンは見つからなかった』ってね。 あとは、じぃが兄上にうまく取りなして差し上げますから 」
「け‥ けどォ‥ 」
頼純は苛(いら)立った顔でティボーを振り返る。
「ッたく! テメーって野郎は、ホンットにどうしようもねェバカだな! これから勇(いさ)んで冒険に出ようてー時に‥ その出鼻をくじきやがって!」
その物言いにムッとするティボー。
「ナ‥ ナニを申すか、この無礼者が――― 」
頼純は険しい顔をティボーの耳元に近づけ、囁(ささや)いた。
「おい‥ おっさん! 俺はなァ‥ 俺があの兄弟に勝った時、テメーが俺を殺せって、城中の兵士に命令した事―――忘れちゃいネーからな。 俺ってけっこう根に持つタイプなんだよ‥ その首、洗って待っとけよ♡ 」
「ひッ! 」
ティボーは脅えた顔で首をすくめた。
そこへ号令を掛ける者がいた。
「それでは、全員‥ 出発進行ォ―――オ! 」
それは、お調子者のジョルジュ伯であった。
その登場に、頼純はまず驚き、すぐにげんなりとした。
「ま‥ また、オメーがついてくんの? まったく関係ねェだろう!? 」
しかし、そんな事はお構いなしに、隊列は進み始めた。
馬に乗ったロベールは、不安げに『領主の館』を振り返りながら、ファレーズ城を出発するのだった。