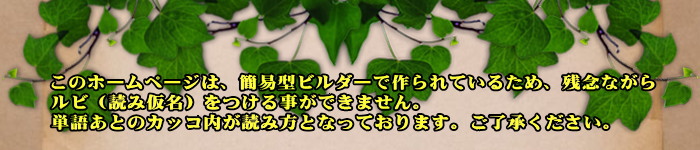
28
1026年 アンデーヌの森(3)
しばしの間、頼純は死んだ兵士の傍(かたわ)らにしゃがみ込み、ジッとしていた。
やがて、力なく立ち上がると、彼は死亡した兵士の両手首を掴(つか)み、みんなから少し離れたところへそれを引きずっていく。
死者が出た事で、他の兵士達が不安や混乱を起こさないようにと思ったからであった。
しかし、その死体をこの森に埋めるべきか、そのままにしておくべきかの判断はつかなかった。遺体を家族に返してやる事は無理だろうが、こんな森の奥深くに埋葬(まいそう)してもよいモノか―――。
第一、埋葬(まいそう)するタメには、深さ3ピエ(=約90センチ)以上の穴を掘らなければならない。浅いと、すぐに森の動物たちに掘り返され、喰われてしまうからだ。だが、ペェレ(=シャベル)さえない状況で、そんな深い穴を掘る事など不可能であろう。
たとえ、ペェレ(=シャベル)があったとしても、それほどの穴を掘るとなると、半日ちかくかかる作業である。さらには、これからどれだけの死者が出るのかさえ判らないのだ。
頼純にそんな重労働をこなす気力はもはや残っていなかった。
彼はなすすべもなく、ただただ仲間達の苦しむ声をぼんやりと聞いていた。
頼純は様々な決断が出来なくなっている。
次第に森は、闇に包まれていった。
頼純が意味もなく考え事をしていると、森の奥からロベールが息を切らせて戻ってきた。
彼は本日の昼近くに出発したばかりである。あと5、6日は戻ってくるハズがなかった。
「どうした? 道に迷ったのか? 」
声を掛けた頼純に、ロベールは絶望の表情を返してきた。
「それが‥ 1マイル(=約1.5キロ)ほど戻ったところから、目印の白糸がなくなっていました。 必死に探しましたが、まったく見つかりません。 誰かがはずしていったとしか思えないのです 」
「バ‥ バカな‥! 」
彼らは戻る道までも失ってしまったのだ。
頼純とロベールは、あたりが真っ暗になるまで途方(とほう)に暮れていた。
それから松明(たいまつ)を灯(とも)し、二人は一人一人の兵士の手を握って、声を掛けていった。もはや、励(はげ)ますぐらいしかしてやれる事がなかったのだ。
みな一様(いちよう)に喉(のど)の渇(かわ)きを訴えたが、彼らには水がない事を説明するしかなかった。
そうやって夜が明けた。森へ入って5日目の朝である。
明け方にさらに三人が死んでいた。その一人は木こりのアランであった。
「何もできない‥ 」
頼純とロベールは大いなる徒労(とろう)感に打ちひしがれていた。
これから、さらに死者が続出する事が予想された。しかし二人に出来る事は何もない。ただ、彼らの死を見守るだけであった。
その時、近くで数本の枯れ枝が折れる音がした。
熊でも出たのかと振り返った二人は、木の陰に半身を隠して、自分達をジッと見詰める老婆を発見した。
腰の曲がった彼女は、頭巾(ずきん)付きの外套(がいとう)をはおっていた。
左手に持ったかごには、摘(つ)んだと思われる草が一杯に入っている。
深くかぶった頭巾のせいでその顔はよく見えなかったが、曲がっている大きな鼻が印象的であった。
老婆は頼純達が気づく前から、彼らの様子を観察しているようだった。
その不気味な様子に、頼純は思わず太刀を抜き、誰何(すいか)した。
「そこにおるのは誰だ! 名を名乗れ! 」
木の陰から身を曝(さら)した老婆は、右手で杖をつきながら、二人の方へと近づいてくる。
「ワシは、エレーヌの森のシュザンヌと申す者‥ 」
その答えにロベールは驚いた。
「え!? エレーヌの森って―――もしや、アナタは『子堕(こお)ろし婆(ばあ)のシュザンヌ』殿では? 」
「ああ‥ そう呼ぶ者もおるのォ‥ 」
彼女はしわがれた声で答えた。
ロベールはその名をエルレヴァから聞いたことがあった。
「しかし、エレーヌの森に住むあなたが、なぜアンデーヌの森に‥? 」
「この森には変わった薬草が色々と生えておるのでのォ‥ それらを摘(つ)みに来ただけじゃ。 お前達こそ、このような危険な場所でナニをしておる 」
「い‥ いや‥ それは‥ 」
「フンッ‥ そのなりからして、おおかたドラゴン退治にでも来たバカ貴族であろう。 さほどに名声が欲しいのか? 愚か者めが‥! 」
「‥‥‥ 」
ロベールは何も言い返せなかった。
「まあ、ワシには関係ない事じゃがのォ‥ 」
シュザンヌはそう言いながら、地面に横たわった兵士達の容体を見ていた。脈を取ったり、まぶたを開いたり、口を開いて舌の色などをみている。
頼純は太刀を鞘(さや)に戻しながら彼女に尋(たず)ねた。
「アンタは医者なのか? 」
「ひゃひゃひゃ‥ そのようなご立派なモノではないが‥ 病を治(なお)す方法なら少し知っておる 」
頼純とロベールの目に希望の光が差した。
彼女ならば、この絶望的な状況を何とかしてくれるかもしれない。少なくとも、自分達よりも専門の人間が現れたのだ。彼らが期待するのも無理はなかった。
老婆は、兵士達が漏らした下痢便(げりべん)を観察し、その臭いをかぎ、吐瀉物(としゃぶつ)を指で触って、その中身を確認しているようであった。
そして、しばし考え込むと、ひとつの結論を口にした。
「うむ‥ これは、毒じゃ! みな、毒を盛られておる‥ 」
「え!? 」
「ど‥ 毒‥? 」
シュザンヌは今度は頼純達の方に近づき、彼らのまぶたや舌、脈や呼吸を確認する。
「なるほど‥ お前らも毒に犯されておるぞ! ただし、お前らは一種類―――死に直結する毒ではないが‥ 倒れておる者達は二種類の毒が効(き)いておる。 ひとつは、おそらくトリカブトの毒じゃろう! 」
「ト‥ トリカブトって‥‥? 」
頼純は愕然(がくぜん)とした。
トリカブトと言えば、剣や矢尻に塗って使えば、たちどころに死に至るという猛毒である。。
「じゃあ‥ 我々の毒は? 」
シュザンヌは頭巾に覆(おお)われた頭をわずかに振ると、
「それは、調べてみんと判らん。 いや‥ 正直言って、判るかどうかさえ疑問じゃ。 これは、今までに見た事もない不思議な毒‥ 」
「ふ‥ 不思議な‥‥ 」
「―――毒? 」
気を取り直した彼女は、頼純達に指示を出す
「ともかく‥ まずはこの者達に水を大量に飲ませなさい! 水は、この方向に真っ直ぐ進むと、小さな泉がある。 そこには、温かい湯が湧(わ)いておるから、その湯を汲(く)んで飲ませるのじゃ 」
「あ‥ は‥ はい‥! 」
頼純とロベールは、老婆が指差す方向を確認した。
「ワシは薬草を探してくる。 しばし、待つがよい 」
そう言い残して、シュザンヌは再び森の奥へと消えていった。その立ち去る速さは、とても老人のモノとは思えなかった。

頼純は弓を手にすると、シュザンヌ婆さんから指示された方向へと構えた。
弦(つる)を大きく引き絞り、一気に矢を放つ。
鋭く飛び出していった矢は、巨木の高い位置に突き刺さった。
持てるだけの水筒を肩からぶら下げた頼純は、さらに弓と二十本ほどの矢を背負(しょ)い、兵士の剣を二本借りて樹海へと入っていった。
それぞれの手に握った剣を振りながら、歩くのに邪魔になる下生えの草や低木、ツルを切り、木に道標(みちしるべ)を残しながら、矢の刺さった木に向かって進んでいった。
矢が刺さった木のところまで来ると、ふたたび同じ方向に向かって、弓矢を放ち、木に目印をつけるのだ。そしてその矢に向かって、同様に前進するのである。こうすれば、方向を見失う事はないハズであった。
これを十数回繰り返した頃、水の流れる音がかすかに聞こえてきた。野営地から1/2マイル(約750メートル)ほどの場所であった。
近づいてみると、岩の裂け目から湯気(ゆげ)が立ち、大量のお湯が湧(わ)き上がっている―――温泉であった。
流れ出たお湯は岩の窪(くぼ)みにたまり、小さな泉を作っている。
「そうか、温泉か! だから、このあたりは温かかったんだ。 しかしこんなモン、あの婆さんに教えてもらわなきゃ、絶対に判らなかったぞ 」
頼純は持って来たすべての水筒に温泉の湯を入れ、ふたたびロベールの元へと戻っていった。水筒はずっしりと重かったが、それでも帰りはあっという間だった。
帰り着く頃には、お湯もだいぶ冷めていた。
頼純とロベールはそれを木の椀に移してさらに冷まし、手分けして兵士達に飲ませていった。
そして、水筒の半数がカラになると、兵達をロベールに任(まか)せ、頼純は再びカラの水筒と余っていた水筒を肩に掛け、お湯を汲(く)みに行くのだ。
二人はその作業を昼過ぎになるまで繰り返した。
だがその間にも、二人の兵士が亡くなってしまった。
六人目の遺体を他の遺体が並ぶ場所まで移動させていると、シュザンヌ婆さんが戻ってきた。
彼女は直ぐさま、大鍋(おおなべ)にお湯をなみなみと沸(わ)かし、その中へ大量の薬草らしき物と木の根のような物を投げ込んだ。そして、それらをそのまましばらく煮詰めたのだ。
待つ間、シュザンヌは袋から取り出した粘土のようなモノをこね始めた。
「これがトリカブトの毒ならば、解毒(げどく)の方法はない! 」
「え!? 」
「ただ、この毒はトリカブト本来の毒だけではないようじゃ。 そこに、唯一の突破口があるやもしれん! 」
「それは、どういう意味だ? 」
頼純が彼女に説明を求めた。
「トリカブトは、吐き気や呼吸困難から心の臓を止めてしまう猛毒。じゃが、あっと言う間に死にいたらせる速効性が持ち味じゃ。 しかも、トリカブトで下痢の症状は出ない。 つまり、この毒はただのトリカブトではないという事になる! 」
彼女は説明をしながらも、煮詰めた大鍋を、布を掛けた別の大鍋にあけ、中の薬草の煮汁を漉(こ)していった。
「何日も掛けてジワジワと死に導(みちび)かれるよう‥ 他の毒物と混ぜ合わせ、複雑な調合・抽出を繰り返して、その薬効(やっこう)を特化させたのじゃろう。 この毒を作った者は、まさに天才! 邪悪なる薬剤師(アプチケェ)じゃ! 」
「‥‥‥ 」
シュザンヌはその漉(こ)した煮汁を、先ほどこねた粘土のようなモノの中に混ぜ合わせていく。
「しかしながら、その分トリカブト本来の毒性は弱まっておる。 心の臓が動きを止める前に、毒で汚(けが)れた血を清める事さえ出来れば、きっと彼らも助かるに違いない! 」
大鍋の中で何度も何度も折り返しながら、丹念(たんねん)に粘土へ煮汁を練(ね)り込んでいくシュザンヌ。
均等に混ぜ合わさったら、今度はそれを小さくちぎり、丸めて60粒の丸薬を作った。
「さあ‥ これを一粒ずつ飲ませてやりなさい! 」
「は‥ はい! 」
いつの間にか、日は落ちていた。
シュザンヌ、ロベール、頼純の三人は松明(たいまつ)を頼りに、できあがったばかりの丸薬を兵士達に飲ませていった。
やがて、薬を飲んだ者達は、そのまま気を失ったように眠りについた。
「みんな、苦しまなくなった。 痛みが治(おさ)まったんだ。 」
「ていうか‥ みんなピクリともしねェぞ! まさか、死んだんじゃ‥? 」
「大丈夫! いまは、眠っておるだけじゃ 」
頼純は数人の兵士の胸に耳を当ててみた。
「本当だ! みな、心の臓は動いてる。 息も穏(おだ)やかで、安定してるぞ 」
「あとは、夜中にもう一粒ずつ飲ませなさい 」
ロベール伯は嬉しそうな顔でシュザンヌに尋(たず)ねた。
「これで、全員が助かるのですね? 」
だが、シュザンヌはゆっくりと首を横に振った。その表情は頭巾(ずきん)に隠れ、ほとんど判らない。
「いや‥ その効果のほどはワシにも判らん。 半分生き残れるかどうか―――あとは、彼らの運と神のご加護(かご)しだいじゃろう。 じゃが、明日の夕刻まで生き延びる事ができれば、死ぬ可能性はほとんどないと思ってよい 」
ロベールはその生存率に唖然(あぜん)となった。
「は‥ 半分‥!? 」
「‥‥‥ 」
「それでも、完全に血液が浄化するまでに三日はかかろう。 その間は、足腰が萎(な)え、立ち上がる事すらできないハズじゃ 」
「つまり、三日間はこの場に留(とど)まって、コイツらの面倒をみなきゃならねェってワケかい!? 」
「やります。 頑張ります! 」
「あと、水に塩‥ さらに蜂蜜があれば、それを溶かして飲ませてやりなさい 」
シュザンヌは立ち上がると、
「それから、パンは食べてはならぬ。 もう一つの毒は小麦粉の中に入っていたと思われるからじゃ。 おそらくは、ベラドンナの毒―――集中力がなくなり、判断や決断に間違いが生じていたハズ! 」
「え!? 」
「じゃあ‥ あれは―――! 」
二人が驚いている間に、シュザンヌは森の中に消えていった。
「怪物は近くにおる。 気をつけるのじゃ 」
遠くで声が響いていた。だが、二人にはその意味が理解できなかった。
「まったく‥ とんだドラゴン退治だったぜ! 」
兵士達に二粒目の丸薬を飲ませ終わった頼純とロベールは、焚(た)き火を囲んで語り合った。
「まさか‥ これって兄が仕組んだ罠(わな)って事はないですよね? ボクを試すタメの――― 」
「え!? 」
「兄はボクが酒を飲めない事を知っています。 だから、毒を飲まないと判っていた‥! 森の真ん中でボクをひとりぼっちにさせて、その状況でボクがどうするかを観察しているのでは‥? 」
「それはねェな! 」
頼純はキッパリと否定した。
「これだけの兵士を殺してまで、アンタを試す意味はねェだろう。 アンタの兄貴だってそこまで残酷ではないハズ! そもそも、アンタが生きて帰ってきた後に、そんな真相を知ったら、アンタは部下を殺した兄を憎むはずだ。 ひょっとしたら、復讐のために兵を挙(あ)げるかもしれない。 さらに、その反乱に同調する諸侯(しょこう)が現(あらわ)れれば、ノルマンディーは内乱となる。 それは統治者として、もっともあってはならない事態だ 」
「では、いったい誰がこんな事を? 」
「まずは、酒を送った村の村長‥ 次に酒を届けたあの農夫を問い質(ただ)さなければ。 もっとも、彼らに伯爵を敵に回すほどの度胸があるとは思えないけどネ。 きっと、その後ろに黒幕がいるハズだ。 そいつはたぶん、山賊襲撃事件で山犬のジャンを雇(やと)った者と同じ人物だろう 」
「なるほど‥ 」
そんなコトを話している内に夜が明けた。
ウトウトとしていた頼純は、目映(まばゆ)い朝日で目を覚ました。
ロベールも同様のようであった。
幸いにも、薬を飲んだ兵達は全員が生きていた。
「じゃあ‥ 俺はもう一度お湯を汲(く)んでくるよ。 このままじゃ、水がすぐに足りなくなるだろうし‥ 」
頼純は両手に剣を掴(つか)み、立ち上がった。
それは何気(なにげ)ない行動である。
源泉(げんせん)までのルートは、何度も通ったタメにすでに貫通していた。もはや、二本の剣を持っていく必要などなかったのだ。
ただ、これまで二本の剣を持って何度も湯を汲(く)みに行ったから、今回もそうしたにすぎなかった。
その時、背後で大きな咆吼(ほうこう)がした。
頼純とロベールが振り返ると、そこには巨大なドラゴンがいるのだ。
それは信じられない光景だった。
「ド‥ ドラゴンだ‥! 」
「ホ‥ ホントにいやがったのか!? 」
地響きを立てながら近づいてきたドラゴンは、その巨大な口で一番端に横たわっていた兵士に喰(く)らいついた。
その口は5ピエ(=約1.5メートル)はあると思われた。
バキボキと骨が砕ける嫌な音が森に響いた。