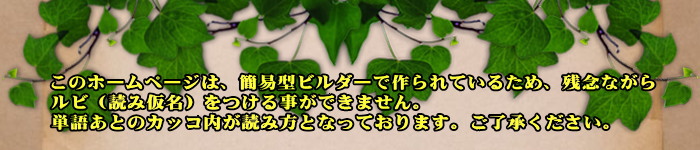
68
1016年 イングランド・ロンドン(2)
「な‥ 何を言うか、この無礼者! どこの馬の骨とも判らぬお前ごとき‥ 死刑にするのは造作(ぞうさ)もない事! 」
エマ王太后(おうたいごう)は、ヒステリックな声でゴドウィンを怒鳴った。
ゴドウィンはわざと彼女を怒らせ、その言葉の端々(はしばし)から彼女の発するとげとげしさの原因を見抜いていた。
「アナタ様は、エドマンド剛勇(ごうゆう)王様の継母(けいぼ)様。 王妃であられるエディス様ならいざしらず‥ アナタ様に、そのようなお力があるとは到底(とうてい)思えません 」
「何を申すか! エディス殿は王妃などではない。 前王であらせられたエセルレッド様は、彼女との結婚をお認めにはならなかったのじゃぞ 」
「いいえ、あの方はれっきとした王妃様でいらっしゃいます。 その事は、ローマ教会も『国政審議会(ウィティナゲモット)』もお認めになられておる事。 アナタ様だけが―――いや、お亡くなりになられたエセルレッド前王様とアナタ様のお二人だけが、お認めになられておらぬだけです 」
前王のエセルレッド2世とその三男である現王エドマンド2世は、つい先日まで険悪な関係にあった。
1013年にデンマーク国王スヴェン1世が4度目の侵攻をしてきた時、父エセルレッド王は、新しい妻エマとその子供達―――ゴーダ、エドワード、そしてアルフレッドの三人だけをつれてノルマンディーへと脱出した。
最初の妻である『ノーサンブリアのエルギフ』の子供達は、全員ウィンチェスター城に置き去りにされたのである。この事をエドマンド王は恨(うら)んでいた。
22歳であった彼は、病弱な兄アゼルスタンを城に残し、幼い弟や妹達を連れて、ウィンチェスターから逃げ出さなければならなかった。デンマーク軍がすぐそこまで迫っているというのに、自分達を守ってくれる兵士はほとんどなく、心細い思いで森の中をさまよい続け、村々を逃げ回ったのだ。
だが、エドマンドが父を嫌ったのはそれだけではなかった。エセルレッド王の弱腰な外交政策にもまったく納得がいかなかったのである。
それ以前も、スヴェン1世率(ひき)いるデンマーク国軍が攻めてくるたびに、エセルレッド王はたいして戦いもせず、敵と協定を結び、『ディーンゲルド』と呼ばれる立ち退き料を支払ってきた。しかし、その協定はすぐにデンマーク側から一方的に破られ、また攻め込まれるという事態を繰り返してきたのだ。
そんな父をエドマンド王子は腰抜けだと思っていた。王たる資格がないとさえ考えていたのだ。
さらには、ノルマンディーから戻ってきた父がイングランド王に復位(ふくい)した後も、20歳を過ぎたばかりのクヌート王子に攻め込まれ、連戦連敗を喫していた。
首都ウィンチェスターは陥落(かんらく)し、ロンドンに逃げ出す始末(しまつ)である。
そんな父に見切りをつけたエドマンド王子は、自分が立ち上がってデンマーク軍と戦う事にしたのだ。
だが、父王(ふおう)エセルレッド2世は、自分は戦おうとしないくせに、彼が軍を動かす事に難色(なんしょく)を示した。自分を守る兵士が減るからである。
さらに、彼の恋人であった『イーストアングリアのエディス』との結婚にも反対し、彼女を無理矢理修道院に押し込んだのであった。
そこで親子は大喧嘩となった。それは修復不能の争(あらそ)いであった。
けっきょく、王宮を飛び出したエドマンド王子は、兵を募(つの)り父王(ふおう)に反旗(はんき)を翻(ひるがえ)したのだった。さらに、恋人のエディスを修道院から救い出して、結婚までした。
だが、ともに反乱を起こした盟友であり、義理の弟でもあったウートレッド伯爵がデンマーク側に寝返ると、エドマンド王子の情勢は一気に悪化した。
彼は仕方なく、父エセルレッド王に頭を下げ、ともにデンマーク軍と戦うしかなくなったのである。それはエドマンド王子にとって屈辱(くつじょく)でしかなかった。
ところが、その直後にエセルレッド王が急死したのだ。
彼がなぜ死んだのか、病死だったのか、暗殺だったのかは判っていない。ただ、この時点でエセルレッド2世に最も死んで欲しかった人物は、デンマークの王子よりもエドマンド王子であったに違いない。
エドマンド王子は直(ただ)ちに、エドマンド2世としてイングランド王に即位したのであった。
ゴドウィンは薄ら笑いを浮かべてエマに語った。
「エドマンド王様は、継母(ままはは)であらせられるアナタ様から一切の権限をお奪いになったはずです。 ですから、アナタ様がわたくしを死刑にする事はできないと思うのです 」
エセルレッド前王が亡くなって、まだひと月ほどしか経(た)っていなかったが、彼女は夫の死を悲しむよりも、それによってこれまで得ていた絶大な権力を失ってしまった事に恐怖を感じている──ゴドウィンはそう確信していた。
「な‥ なにを、こしゃくな! 」
エマは椅子から立ち上がって怒鳴ったが、ゴドウィンは彼女の怒りなど平気の平左(へいざ)で、さらに不躾(ぶしつけ)な質問―――というよりも、『挑発』を試(こころ)みた。
「アナタ様は怖くないのですか‥ 自分に何の力もない事が? アナタ様はもはや修道院に入り、尼(あま)さんにでもなるしかないのですよ♡ 」
「あああ‥ 」
本来なら、「無礼者め‼ 」と一喝するような問いであったが、前王妃は心臓を鷲掴みにされたかのように言葉が出なかった。
ゴドウィンは『きこりの息子』であったにもかかわらず、イングランド王国とデンマーク王国との関係や、イングランド宮廷の内情などにかなり精通していた。それらはロンドンへ来てから勉強したのである。
書籍がない時代、様々な知識・情報を得る手立ては人からの口づて―――噂話しかなかった。
様々な人々と話をし、解説をしてもらい、人によって内容がずれる部分はみずから修正し、理解を深めていった。
それは政治だけの事ではない。社会経済から歴史、軍事情勢や戦略戦術、上流階級のしきたりから様々なスキャンダル、さらには裏社会の仕組みにいたるまで、ありとあらゆる事に関する知識を吸収していった。それはまるで海綿(かいめん)が水を吸うがごときであった。
何度も言うが、ゴドウィンの知能は極めて高かったのである。
言葉を失ってしまったエマにゴドウィンは得意げな笑顔を向けた。
「しかし、わたくしは‥ アナタ様をお救いする方法を―――アナタ様が権力の座に返り咲く方法を知っております 」
「なに!? それはまことか? 」
はじめて出会った男の、命乞いとも思える言葉にも、敏感に反応してしまうほど、その時のエマは切羽(せっぱ)詰まっていた。
ゴドウィンから人払いを頼まれ、広間には彼とエマ前王妃だけが残った。
ゴドウィンは流れるようにウソをつく事ができる。たとえ盲点(もうてん)を突かれ、相手から反論されようとも、直ぐさまにそれに対するウソを突き返す事ができるのだ。それはまさに天才的な才能であった。
「復権の第一の方法としては‥ アナタ様とエセルレッド前王様との御子様(みこさま)―――エドワード王子様かアルフレッド王子様がこのイングランドの国王となられる事!―――これがもっとも簡単な方法です。 さすれば、アナタ様は幼き王の摂政(せっしょう)としてふたたび玉座に返り咲き、あらゆる権力を取り戻す事ができましょう‥! 」
「う‥ うむ‥ 」
「ただしそのためには、エドマンド現国王様がお亡くなりになるという事が前提条件となります‥‥ 」
「そ‥ それは‥ エドマンド王を殺すという事か‥? 」
王殺しを平気で口にするゴドウィンにエマは一瞬たじろいだ。
だが、ゴドウィンはそれには答えず、宙を見詰めながら、さらに恐ろしい言葉を吐き出した。
「とはいえ‥ 現在はエドマンド王のご活躍で、何とか敵の猛攻も防いでおりますが‥ 我が国はすでに国土の8割近くを失っておるのです。 今後形勢が逆転する事はまずありますまい。ましてや、王様がお亡くなりにでもなれば、軍は総崩れとなり、我がイングランド王国はまたたく間に陥落(かんらく)してしまうでしょう 」
「‥‥‥ああ‥‥ 」
エマの顔は恐怖に引き吊っていた。
「つまり、エドマンド王が亡くなろうと亡くなるまいと‥ このイングランドは、まもなくデンマーク人達に征服されてしまうんです! うん‥ 間違いなくそうなりますよ。 そうなれば、王太后(おうたいごう)様も含め、エセルレッド前王様の縁者―――いや、ウェセックス家につながる者は一人残らず殺される事でしょう‥‥ こりゃあ、権力がどうのこうのと言ってる場合じゃなくなりますぞ。 生きるか死ぬかの瀬戸際(せとぎわ)だ♡ 」
「そ‥ そんなァ‥ 」
ゴドウィンは悪魔のような笑顔で、脅(おび)えたエマ王妃の顔を覗(のぞ)き込んだ。
「ならばいかがでしょう‥ いっその事、イングランドを征服した後のクヌート王子と結婚されてみては? さすればアナタ様は再び王妃として、これまで以上の権力を手に入れる事ができると思いますが‥‥ 」
ゴドウィンの非常識な提案に、エマは憤然(ふんぜん)と抗議した。
「な‥ なにを申すか! このわらわに、敵の―――残虐非道なバイキングの妃(きさき)になれと申すのか? 」
しかし、ゴドウィンは呆れたように笑った。
「いやいやいやいや‥ アナタ様のご先祖様であられる初代ノルマンディー公もバイキングではございませぬか。 さらに、現在のイングランド・ウェセックス王家とて、もとはユトランドから渡ってきたバイキングですぞ。 そのような事をお気になさるな 」
ウェセックス朝などのイングランド王室は、5世紀前後にブリテン島の原住民であったブリトン人(ケルト民族)を追い出して、そこに住み着いたアングル人やサクソン人達である。彼らは元々はユトランド半島の南側に住んでいたゲルマン民族で、その北側に住んでいたディーン人とは文化や言語などに大きな隔(へだ)たりはなかった。
つまり、イングランド王国とデンマーク王国は、民族的な違いがさほど大きくはなかったのである。
一方、フランス北部に移住したノルマン人達も、元はユトランドに近いスカンジナビアに住むゲルマン民族であったが、彼らは100年ほど前からフランスの文化と言語を取り入れたため、イングランド人とは相容(あいい)れない部分が多かったのだ。
ゴドウィンはさきほどから終始笑顔であった。それは彼が、この国の頂点にいる貴族を目の前にしても、その権力に脅(おび)える事なく、この機会を大いに楽しんでいたからである。一方、その『頂点の貴族』である前王妃エマが不安そうにしているのは、不気味な若い男に心の内を読まれ、いいように翻弄(ほんろう)されているからであった。
「し‥ しかし、亡き夫が戦っていた敵国の王子と結婚すれば、わたしは我が国民からなんと陰口を叩かれるものか――― 」
「大丈夫ですって! 歴史を遡(さかのぼ)れば、そのような王妃様はいくらでもいらっしゃいます。 それに、アナタ様は元々ノルマンディーの公女様でございましょう。 ならば、このイングランドにさほどの忠誠心もありますまい 」
「‥‥‥‥ 」
エマはゴドウィンの提案に一瞬思いを巡(めぐ)らせた。しかし、すぐにその考えを否定したのだった。
「やっぱり、無理! だって、わたしは31歳だもの‥‥ そんな中年のわたしが、21歳の若き王子に見初(みそ)められる事なんてあり得ませんって! ダメダメ、絶対に無理ですわ! 」
エマの口調はすっかり変わっていた。もはや、臣民(しんみん)に対する横柄(おうへい)な言葉遣いではなかった。
ゴドウィンは自信たっぷりに言い放った。
「ご安心ください! アナタ様のそのお美しさならば、必ずやクヌート王子を籠絡(ろうらく)できます。 わたくしが言うのもなんですが‥ 女性は若ければよいというものではありません。 その御年(おんとし)になられて、妖艶(ようえん)さまで加わり、ますますお美しくなられておりますぞ。 微力ながら、このわたくしめもお手伝いいたしますので‥‥ 」
「し‥ しかし‥‥ 」
「わたくしは、死刑を取り消していただきたくて、アナタ様を騙(だま)そうとしているワケではございません。 死んでしまった愛する妻マーガレットの親友であらせられるアナタ様を案じて‥‥ アナタ様が生き残るための唯一の方法をご注進(ちゅうしん)申し上げているのでございます♡ 」
「‥‥‥‥ 」
「大丈夫です。 クヌート王子は、必ずアナタ様をお気に召されます。 いや、この私が絶対にそうさせてみせますから! 」
これらすべての言葉は、あらかじめ用意されていたものではない。この場で瞬時に思いついたゴドウィンの『でまかせ』であった。ただ、彼自身もよくできた筋書きだと心の中で感心するほどであった。
ゴドウィンの甘言(かんげん)にのせられ、すっかり心が傾(かたむ)いたエマは、それでもまだためらいがあるのか、少し顔を曇らせて考え込んでいた。
当然である。むしろ彼女の心がゴドウィンの言葉に傾いている方がおかしいのだ。
今日、会ったばかりの得体の知れぬ男の言葉を信じて、どう考えても常軌(じょうき)を逸(いっ)した結婚を推(お)し進めようというのである。冷静な状況であれば、とても目の前の男を信用できようはずはなかった。
だが、エマはゴドウィンの執拗(しつよう)な説得に、ついにそれを了解してしまったのである。『敵国の総指揮官であり、10歳も年下のクヌート王子との結婚』という無謀な計略を、目の前の男に託(たく)したのだった。
催眠術にでも掛かったかのように、彼女はゴドウィンの言いなりとなっていた。先ほどまでのゴドウィンに対する苛立(いらだ)ちや怒りは、もはやどこにもなかった。
「ただし、そのためには3ヶ月のご猶予(ゆうよ)をちょうだいしたい。 そして、アナタ様に、2通の手紙を書いていただきたいのです。 さらに、この御結婚が成功したあかつきには、わたくしをアナタ様の側近としてお召し抱えください 」
「い‥ いいでしょう‥ アナタの希望はすべて叶(かな)えます 」
ゴドウィンは、エマ王太后(おうたいごう)よりの親書2通を懐(ふところ)に、意気揚々(いきようよう)と宮廷を後にしたのだった。
手紙は2通とも同じ文面、
「この手紙を持ちたる者の話をお聞きください 」
と書き添(そ)えられているだけであった。
デンマーク軍から二重三重に包囲されていたロンドンを、ゴドウィンは何とか抜け出す事ができた。彼はその足で、エセックス領の古都イプスイッチへと向かったのである。
そこには、マーシア領エアドリク伯爵を殲滅(せんめつ)せんと、オーウェル川を遡上(そじょう)しようとしていたデンマークの主力軍が陣を張っていた。
ゴドウィンは、警備の兵に前王妃エマからの手紙をクヌート王子に届けるよう願い出た。
ほどなくして、ゴドウィンはクヌート王子と会う事ができたのである。
クヌート王子は、大きな天幕(テント)の中にしつらえられた椅子に腰掛けていた。
彼はまだあどけなさの残る青年であった。この22歳の若者が、何十人もの歴戦の将軍らを従(したが)え、何万というデンマーク軍を動かして、このイングランドを火の海にしているのだ。
「デンマーク王国皇太子、クヌート殿下に申し上げます 」
クヌートの玉座の前に、立て膝(ひざ)をついて頭(こうべ)を垂れるゴドウィンは、
「殿下にあらせられましては、イングランドの大半を征服なさり‥ この国の王座により近づかれました事、心よりお喜び申し上げます 」
「ああ‥ くるしゅうない! して、エセルレッドの妻がこのわたしに何のようなのだ? 」
「イングランドの戦況を鑑(かんが)み‥ 前王妃エマ様は、クヌート殿下の軍門に下るご用意がありとのおうせでございます。 」
「ほう‥ つまり、あの女はイングランドにもう見切りをつけたという事か? 」
「エマ様は、現王との関係がうまくいっていない事もありますが‥ 何よりも聡明(そうめい)であらせられ、この国がもう長くないという事をご承知なのです。 そこで、この国の新しき王クヌート殿下に恭順(きょうじゅん)の意を示そうとお考えなのです。 」
「なるほど‥ このわたしに命乞いをしたいという事じゃな―――? 」
ゴドウィンは上目づかいで、考えるフリをした。
「う~~~ん‥ それは、ちょっと意味が違いますかねェ‥ 」
「むむ‥ それはどういう事じゃ? 先を続けよ 」
「クヌート殿下率(ひき)いるデンマーク王国軍は、これまで圧倒的な戦果を上げられてきました。 しかしながらこのところ、ロンドンでのエドマンド王の抵抗も並々ならず‥ デンマーク軍もあと一歩のところで苦戦しているとのお噂も聞き及(およ)びました 」
「なんの‥ 詮(せん)無き事じゃ。 あと半年もあれば、この国は我が手中に落ちる。 ここは腰を落ち着けて戦うまでよ 」
「おっしゃる通りでございます。 エドマンド王との戦い、必ずや殿下の勝利となられましょう。 しかしながら、そこで勝ったからと言って、イングランド王国がこのまま殿下の手に転がり込むわけではございませんぞ 」
「なにィ‥!? 」
「クヌート殿下は、デンマークの方でございます。 イングランドにとっては『征服王』。 ウェセックス王家の血を引く者達が生き残る限り、まだまだ抵抗の火種は残ります。 完全にこの国を征服するためには、さらにあと5年はかかるのではないでしょうか 」
「うむ‥ なるほど‥! 」
「しかし‥ その間、治安を維持し、残党狩りをするためには、デンマークの軍勢をずっとこの地で養わねばならないのです。 その費用は莫大なものとなりましょう 」
「あ~~~あ‥! 」
クヌートは、思わず声を上げてしまった。イングランドの攻略ばかりに気をとられ、占領後の経費にまでは思いが及(およ)ばなかったからである。たしかに、この男の言う通りであった。
ゴドウィンはこの若き指揮官に対して、淀(よど)む事なく『でまかせ』を語り続けた。自分でも、よくこんなに『でまかせ』がポンポン出るものだと感心していた。
「しかし、わたくしには‥ 今年中に全イングランドを占領し、その上でイングランド国民がアナタ様にひれ伏す方法を持っております。 アナタ様を『征服者』としない方法があるのです。 この方法を持ってすれば、占領経費は激減するに違いありません 」
「ほう‥ ならば、その方法とやらを申してみよ 」
クヌートは身を乗り出して、ゴドウィンの話を聞こうとした。だが、もしいい加減な事を言えば、即刻(そっこく)首を刎(は)ねるつもりだった。
「ただし、成功いたしますれば‥ 王太后(おうたいごう)エマ陛下のお命の保証と、このわたくしめを殿下の小者としてお雇いくださる事をお約束くださいませ 」
「いいだろう。 ワタシがお前の方策に納得できたなら、お前を雇い入れてやろう 」
ゴドウィンは人払いを頼み、クヌートにその方法を打ち明けた。
その話を聞いたクヌートは、しばらく考えていたが、やがてコクリと頷(うなず)いた。
ゴドウィンは足取りも軽く、ふたたびデンマークの陣を出ていったのであった。