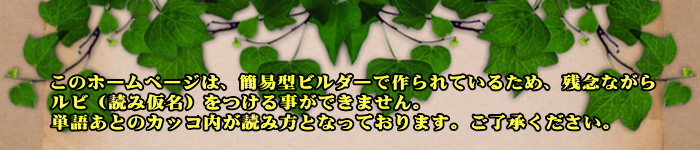
9
1026年 ファレーズ城・広間
「カリンガナガラの倉庫には、山のように積みあげられた莫大(ばくだい)な胡椒(こしょう)が眠っていました 」
ロレンツォが語る冒険譚(ぼうけんたん)に、ロベールは無論の事、執事(アンタンダン)のティボーから館内の警備兵、さらにはロレンツォの傭兵(ようへい)にいたるまで、広間にいる誰もが固唾(かたず)を呑(の)んで聞き入っていた。唯一、頼純だけが退屈そうにしている。
「インドは‥ ガズナ国の侵略と、長く続く国内の小国家間での紛争によって‥ 大いに混乱していました。 そのタメ、危険を冒(おか)してまで胡椒を買い付けに来る者はいなかったのです 」
淡々と語るロレンツォに、ロベールは玉座(ぎょくざ)から身を乗り出して尋(たず)ねる。
「というコトは‥ 他のサラセン(イスラム)商人達もまだ―――? 」
ロレンツォは満面の笑顔をつくって、ゆっくりと頷(うなず)いた。
「はい‥ 私が出発する時、ガズナ国の戦火を1年だとよんでいたファーティマ(エジプト)やブワイフ(イラン及びイラク)のサラセン商人達も、いまだインドの胡椒を買えていなかったのです 」
「おお‥ やはり、そうであったか 」
ロベールはうれしそうに目を輝かせた。
彼らのやり取りを聞いているのかいないのか、頼純は腕組みをすると広間の中をジロジロと眺(なが)めている。
さらにロレンツォの話は続く。
「これは大儲けができると判断した私は、有金すべてをはたいて胡椒を買い付けました。 しかも、いつもの五分の一の値段で―――♡ 」
「え!? ご‥ 五分の一ィ? 」
ロレンツォは、得意げに語った。
「そうなんです。 インド商人達は大量の在庫を抱えて困っていました。 ですから、思い切り買い叩いてやったのです 」
「おお‥! 」
ロベールだけでなく、その場の全員が驚きの声を上げた。
イタリア人らしく、大きく手を動かして語られるロレンツォの話に、広間のすべての人が引き込まれていたのだ。
各地を回って商売をするロレンツォ達商人は、行った先々で必ず諸国の様子を尋(たず)ねられる。それは―――ある時は、敵国の情報収集のためであったり‥ またある時は、ヒマをもてあました貴族の娯楽であったりした。それゆえ、長く商売を続けていると、いやでも話し上手になる。また、話し上手でなければ売上も上がらないのだ。
「こうして得た大量の胡椒を、私は30艘(そう)の大型ダウ船(三角帆をつけた小型帆船。風上に向かっても進めたヨット)に山積みにして、カリンガナガラの港を出航したのです 」
「ちょ‥ ちょっと、待って! 」
ロレンツォの話に矛盾を感じたロベールは、怪訝(けげん)な表情になっていた。
「たしか‥ 海路は海賊だらけでとても危険だったのではないのですか? なのに、わざわざ船を使って帰ったと‥? 」
ロレンツォは大きく頷(うなず)くと、話の山場を迎えようとしていた。
「そうなのです。 お陰で、我々は途中六回も海賊と遭遇(そうぐう)いたしました」
「ろ‥ 六回って――― それで、どうなったんです? 」
目の前に五体満足なロレンツォが立っているのだから、彼が死んだり傷ついたりしていない事は判っている。だが、『ならばどうやって?』―――が聞きたくてたまらないロベールは、さらに身を乗り出し質問を浴びせる。
その時、家臣の一人が近づいてくると、執事のティボーに耳打ちをした。ティボーはそれに頷(うなず)き、ロベールに声を掛ける。
「若‥ そろそろ夕餉(ゆうげ)の時刻でございます。 お話の続きは、ロレンツォ殿の歓迎会にて、お聞きになってはいかがでしょうか? 」
ティボーの言葉に、ロベールは引きつった顔で振り返る。
「ちょ‥ ちょっと、待ってよ! いま、一番いいところなんだ。 そこまで聞いてからでもいいだろう 」
話の続きが聞きたくてしょうがないロベールを、ティボーはいかめしい顔で諭(さと)した。
「若‥ ワガママをおっしゃってはなりませぬ。 家臣達も腹を空(す)かせて待っておりますゆえ 」
しつこいティボーに、ロベールは大きな声を上げる。
「だから、あとちょっとだって言ってるだろう!! 」
それはまさに、母と子の喧嘩のようであった。
その場の空気を読んだロレンツォが、ロベールに申し出る。
「まあまあ‥ そう慌(あわ)てなくとも、おもしろき話は逃げてはゆきませぬ。 それに、我々も立ったままは少々疲れましたので‥ ここは、ゆるりと腰を下ろし、酒を酌(く)み交わしながら‥ 続きをお話しすることといたしましょう 」
ロベールは不承不承(ふしょうぶしょう)ながら、
「―――判った‥ 」
と、ロレンツォの意見に従った。
× × × × ×
それまで玉座(ぎょくざ)しか置かれていなかった大広間には、中央の囲炉裏(いろり)を挟んでテーブルが二列に並べられていた。
白い布が掛けられたテーブルには、六十人ほどの家臣達が向かい合って腰掛け、肉を喰(く)らい、ビールやリンゴ酒を飲んでいる。
あちこちにたくさんの燭台(しょくだい)が立てられた広間の中央部分は、昼よりもむしろ明るいくらいであった。
二つある囲炉裏(いろり)のうち、一つ目には大きな豚の丸焼きが掛けられ、料理人達によって回転させられている。
二つ目のそれには、スープの大鍋が掛けられ、中で野菜と肉のポタージュがグツグツと音を立てていた。ポタージュは、半分ほどに減っている。すでに、大きな木のスプーンで木の椀(エキュエル)に取り分けられ、家臣達に配られていたからである。
豚からは時折脂(あぶら)が滴(したた)り、それが囲炉裏(いろり)の火に落ちると、もうもうとした煙が立ち込める。そのたびに、人々は涙を浮かべて目をこすった。
本日は、伯爵の無事の生還を祝う宴(うたげ)と、お客様の歓迎会という事であったが、飲めや歌えの大騒ぎをしているのはそのせいではない。このような夕食会は毎晩行われているのである。
ただし本日は特別に、キジのローストと蒸したマスも添(そ)えられていた。
玉座(ぎょくざ)が乗っていた台は広い台と取り替えられ、その上に長いテーブルが置かれていた。
テーブルには三つの席が設けられている。中央に坐るのはこの館の主人であるロベール伯爵、その右には主賓(しゅひん)であるロレンツォが坐っていた。ただ家臣達が不思議に思ったのは、ロベールの左側に奇妙な格好をした小男が座っていることであった―――頼純である。
その背後にはサラセン人風の格好をした男が立っており、時折、頼純に耳打ちをしている。おそらく、通訳なのであろう。
それにしても、いくら伯爵を救った者とはいえ、異邦人(いほうじん)が上座に座るなど異例の事であった。
小男はなにやら、二本の細い棒を器用に使って、料理をつまんでは口へと運んでいる。その様は、奇妙で滑稽(こっけい)にさえみえた。家臣達は頼純の方をうかがいながら、コソコソと話し、嘲笑(あざわら)った。
しかし、彼らの事を馬鹿にしているのは頼純も同様であった。
家臣達は自前のナイフで大皿に乗った肉や魚を切り、手づかみでそれを口に運ぶ。その様は見苦しく、汚らしかった。手はいつもベタベタしており、彼らはその汚れた指先や口元をテーブルクロスや、自分の服で拭(ぬぐ)う。とうぜん、それらはシミだらけになるのだ。
だったら、自分達のように箸(はし)を使えばいいのに―――頼純はいつもそう思っていた。
ロレンツォの本拠地・ヴェネツィアには、ビザンティン(東ローマ)から入ってきた『フォーク』というモノを使う貴婦人達がまれにいた。せめて、あの『フォーク』でも使えば、このように汚らしく食べる習慣もなくなるだろうにと―――。
さらに、料理を乗せる大皿はあったが、それを取り分ける小皿はなかった。料理は大皿から、テーブルに並べられた平たい黒パンの上に手づかみでのせられる。黒パンはまずく、食べられない。食べるタメの白いパンは別にあり、黒パンは皿代わりにするためだけに焼かれたモノであった。だったら、なぜ小皿を作らないのか―――頼純はヨーロッパに入って以来、ずっと疑問に感じていた。
会食が始まってすぐに、隣席のロベールも物珍しそうに頼純の箸(はし)を眺(なが)めていたが、ロレンツォとしばらく話しをすると、納得したかのようにフンフンと頷(うなず)いていた。どうやらロレンツォは、『ヨリは手が汚れる事を嫌うのだ』―――と説明したようだった。
食事を終え、デザートから食後酒へと移ると、ロベールは隣に坐ったロレンツォにさきほどの話の続きをせがんだ。
「それで‥ 六度も海賊に襲われて、どうなったんです? もういいかげんで話してくださいよ。 ロレンツォ殿が死ななかった事だけは判ってますけど――― 」
酔いも手伝ってか、やや絡(から)み気味である。
ロレンツォは穏やかな微笑(えみ)で振り返ると、ゆっくりとした口調でそれに答えた。
「はい‥ 私は死にませんでした。 それも、すべてはヨリのお陰なのです。 彼が海を知り尽くしていてくれたから、私は助かったのです 」
「う‥ 海を‥ 知り尽くしていた―――? 」
「ええ‥ 私はヨリの進言にしたがって、海路を選んだのです 」
ロレンツォは、前に少し身を傾けると、ロベール越しに同じテーブルにつく頼純をうかがった。それは、彼の姿を通して、一年前の冒険を思い出そうとしているかのようだった。
「海賊との初めての遭遇(そうぐう)はセレンディープ島(セイロン島)の海峡でした。 ヨリは海賊の船影をいち早く発見し、相手に見つかることなく我が船団を回避させたのです。 また、カリカットの沖200マイルのあたりで賊と鉢合わせした時には、風向きと敵の操船(そうせん)技術をよみきり、その真横をギリギリですり抜けました 」
ターバンを巻いた通訳は、頼純の耳元でしきりに何かを囁(ささや)いていた。 しかし、それを聞いていないのか、頼純は素知らぬ顔で、箸(はし)でつまんだキジのロースト肉を口に放り込むと、グイッとリンゴ酒を煽(あお)った。
ロレンツォは話を続ける。
「もちろん、毎回そううまく逃げられるワケではありません。 とうぜん、海賊どもと刃(やいば)を交わして、戦わなければならない場面も何度かありました。 そんな時、ヨリはたった一人で―――各船には、カリンガナガラで雇(やと)ったインド人の護衛がそれぞれ数名乗っておりましたが―――彼らの力を借りる事なく、たった一人で敵を撃退させていったのです 」
「は~~~あ‥ 凄い‥‥ 」
あたかも、大天使ミッシェルのような神々(こうごう)しい活躍を頭に思い描くロベールは、思わず大きな溜息(ためいき)を漏らしていた。
「ロープを巧みに操(あやつ)って船から船へと飛び移ると、彼の刀が一閃(いっせん)二閃(にせん)と瞬(またた)くのです。 そのたびに海賊の手足が宙を舞い、賊達は次々とインド洋に落下していきました。 その強さといったら、サタンも裸足で逃げ出すほどです 」
「ええ‥ 同じ光景を、私も本日見せていただきました 」
「いいえ‥ ヨリは陸上よりも、揺(ゆ)れる船上の方がはるかに上手く闘う事ができるのです 」
ロベールは信じられないといったふうに、眉を顰(しか)めてつぶやいた。
「え‥? あ‥ あれよりもさらに強いのですか―――? 」
ロレンツォは、ヨーロッパに戻ってから何度も語ってきた頼純の功績を、吟遊(ぎんゆう)詩人のような大きな身振り手振りで滔滔(とうとう)と讃(たた)えた。
「すべてが、ヨリの力によって救われたのです。 彼は海戦に自信があればこそ、我々に海路を選ばせました。 どうせ危険であるのなら、二年半も掛かる陸路より、わずか5ヶ月で到着する海路の方がよいと―――そう考えたからでした 」
「‥‥‥‥ 」
もはや、ロベールは唸(うな)り声を上げるばかり。発する言葉がなかった。
にぎやかだった広間も、いつの間にか静まり返っていた。一同が、ロレンツォの語る頼純の活躍に耳を傾けていたからである。
広間に、ロレンツォの声が響く。
「そしてついに、私の胡椒(こしょう)はヴェネツィアへと到着しました。 ヨーロッパでは2年以上も、正規のルートでの胡椒は入荷しておりません。 海賊達が強奪した胡椒は、サラセン商人を通していくらか売りさばかれてはおりましたが、その量はわずか―――そして各国の王や諸公(しょこう)達は、その少ない胡椒を奪い合って買っていたのです。 胡椒の値はかつての20倍にまで高騰(こうとう)していました。 私はすぐさまその値段ですべての胡椒を売り払ったのです 」
ロベールは唖然とした表情で言葉を吐き出した。
「ご‥ 五分の一の値段で買って、20倍で売ったというコトは―――ひゃ‥ 百倍の利益‥‥ ですか!? 」
「いいえ‥! 私は従来、仕入れ値の2倍の価格で胡椒を売っておりましたから、同じ量でも利益は39と5分の4倍―――約40倍となりました。 お陰で、私はヴェネツィア一の大金持ちとなれたのです 」
その言葉に、静かだった広間がざわめく。家臣達が次々と感嘆(かんたん)の声を上げたのだ。
「ヴェ‥ ヴェネツィアで一番って―――!? 」
「それは、ヨーロッパで一番って事じゃないか! 」
「ああ‥ フランス国王はもちろん、我らがノルマンディ公爵様よりもさらに金持ちって事だぞ 」
だが、ロレンツォはその事に得意になるのではなく、彼の本当の自慢話を始めた。
「しかしながら‥ 金などいくら持とうとも、たいした価値はありません。 私の本当の財産はこのヨリズミなのでございますから。 彼はヨーロッパ中の財物(ざいぶつ)をかき集めようとも、換(か)えがたき宝といえましょう 」
一瞬静まり返った広間に、ロベール伯爵の声がこだました。
「皆の者、聞いたか! 」
立ち上がったロベールは、胸を押さえて感動を一同に告げる。
「ナンの見返りも求めず、行き倒れの者を救ったロレンツォ殿も素晴らしいが―――命の恩人であるロレンツォ殿へ、心からの礼を尽くし、命を賭(と)して働くヨリ殿こそ最高の家臣と言えよう これこそが騎士道精神なのだ! シャルルマニュー大帝の十二勇将(パラディン)もさにあらん。 実に素晴らしき関係ぞ 」
ロベールはロレンツォを振り返ると、
「うらやましい。 このような家臣に恵まれたロレンツォ殿が本当にうらやましいです 」
と、褒(ほ)め称(たた)えた。
ロレンツォは胸元で十字を切ると、両手を組み合わせ、祈りのポーズをとった。
「ありがとうございます。 ヨリズミと巡り会わせてくださった神の思(おぼ)し召しに、心より感謝しております 」
その場の全員が立ち上がり、ロレンツォと頼純に対する賞賛(しょうさん)の拍手を送った。
「ああ‥ ホントに、うらやましいィ‥ 」
割れんばかりの拍手の中、ロベールがつぶやいたその一言に、ロレンツォは何やら物欲しげな意味合いを感じ、
『ハハハハ』
と乾いた笑いでごまかすしかなかった。
拍手のもう一人の対象である頼純は、その意味を通訳から伝えられながらもそれに応えるわけでもなく、ただゆっくり周囲に視線をはわせ、建物の構造や調度品の質、家臣達の様子などをジッと観察していた。
× × × × ×
再び、ドンチャン騒ぎが始まった館とは対照的に、中庭をはさんだ礼拝堂(シャペラ)は静まり返っていた。
礼拝堂の内部は、椅子などは置かれておらずガランとしている。壁の両側に立てられた二十数本の燭台(しょくだい)は、数本しか灯(とも)されておらず、中は不気味なまでに暗い。
一番奥には祭壇が設けられ、その上には十字架が乗せられていた。両脇に置かれた燭台(しょくだい)の灯火(ともしび)が、十字架をぼんやりと照らし出している。
燭台(しょくだい)の蝋燭(ろうそく)はさらに、祭壇の前にぬかずく一人の男の姿も浮かび上がらせていた。
この礼拝堂の管理人・助祭(じょさい)のトマである。
彼はローマ教会の象徴である十字架に向かって一心に祈りを捧げていた。
両手の指を固く組み合わせ、何やらブツブツと唱えると、素早く胸元で十字をきる―――トマはそんな事をもう8時間以上も繰り返していた。
飲み食いを一切せずに、長時間固い床にひざまずき、ひたすら祈りを捧げ続ける事は、たいへんな苦行(くぎょう)である。まるで、己を罰しているかのようだった。
やがて、祈りを終えたトマはフラフラになりながら立ち上がった。
しかしその顔からは、苦行を達成した満足感や神に対する真摯(しんし)な思いなどは、微塵(みじん)も感じられない。むしろ、その目には狂気が宿っているかのようだった。
萎(な)えた足の感覚が戻ってくるのを待っているのか、立ったまましばらく十字架を見つめていたトマは、ふいに踵(きびす)を返すと、出入り口へと真っ直ぐに向かった。その足取りには、痺(しび)れや痛みはまったく残っていない。
というよりも、それは何かに取り憑(つ)かれたかのように、いつものトマの歩みとはまったく違っていた。一歩一歩に力強さを感じられたからである。
普段なら、人に見つからぬよう背中を丸め、人混みを避けてコソコソと移動していくのが、トマの歩き方であった。
しかし、いまは堂々としているのである。
本日、ノルマンディー大公のお相手をし、脅えた小動物のような振る舞いで大公を怒らせてしまった‥‥あのトマの姿ではなかった。
トマは礼拝堂のドアを開き、表へと出た。