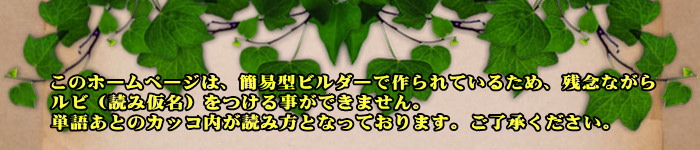
46
1026年 トレノ村・ひなげし食堂(2)
「やめろォ―――オッッ‼」
だが、フィリップは絶叫を上げる頼純をチラッと見ただけで、再び少年の首を見詰めながら、肉切り包丁を研(と)いでいた。
このままでは、少年は殺され、食べられてしまう。目の前で、そのような残虐非道(ざんぎゃくひどう)な蛮行(ばんこう)を許すわけには絶対にいかない。
頼純は、気が狂いそうな混乱の中で、現状を打破(だは)すべく行動にでた。
必死に体と腕を捻(ひね)り、頼純をぶら下げている鉄製フックをなんとか右手で掴(つか)む事に成功した。
そのまま、右腕の力だけで体をグイッと持ち上げる。だが、これだけでは体が少し持ち上がる程度で、両手首を縛る縄にガッチリと食い込んだフックをはずす事はできない。
さらに手首を捻って、今度は左手でフックのさらに上の部分を握るのだ。縄が右手首に食い込み、左手首もちぎれそうなほどに痛い。
「ギギギギギ―――ッッ‼ 」
脂汗(あぶらあせ)まみれになりながらも、頼純は何とか左手でフックの上の部分を掴(つか)む事ができた。
フックから右手をはずし、今度は左腕だけで懸垂(けんすい)をする。さらに体が少し持ち上がった。
これで縄を引っかけていたフックからはずれる事ができたのだ。
しかし、このまま左手をはなしてしまったのでは、また元の状態に戻ってしまう。
作業台ではフィリップが、少年めがけて包丁振り上げていた。もう時間はない。
「ふんッ! 」
頼純は左手でフックを握ったまま、腰を折って下半身を数回振り、勢いをつけた。わずかではあったが、頼純の体が振り子のように揺(ゆ)れた。その一番振り切った時に、彼は左手を放したのである。
ドスンという音とともに、頼純はなんとか3ピエ(約90センチ)ほど前方の床に落ちる事ができた。
しかし、その音にフィリップとジョアンが背後を振り返る。
「あ‥ 」
「クソッ! 」
一方、背中から落ちた頼純は呼吸困難を起こしていた。
「ア゛‥ ア゛ア゛‥ ア゛ア゛ア゛‥ ア゛ア゛‥ 」
息が吸えない。
作業台を凝視(ぎょうし)していたゴルティエは、『あの少年はもうダメだ、殺される』と諦(あきら)めていたのだが、そんな彼のすぐ横で、頼純が床に転げ落ちたのである。
彼は大きく目を見張った。そのけっして諦(あきら)めない強い精神力に驚いていたのだ。
そして、猿ぐつわの口で始めて叫んだ。
「はぁやふ(早く)‥ ふぁふへへ(助けて)! はぁのふぉをふぁふへへ(あの子を助けて)‼ 」
だが、背中を床に着けたまま身動きが取れない頼純の元へ、肉切り包丁を握り締めたフィリップが近づいてくる。その顔は殺意に満ちていた。
「さっきから、うるせえ奴だ! もう我慢ならねェ‥ ブッ殺してやる‥!」
床に転がった頼純は、両手両足がまだ縄でしっかりと縛られている。たとえ『戦いの達人(たつじん)』である頼純であろうとも、包丁持ったフィリップに対抗できるとは思えなかった。
「死ね! 」
フィリップは頼純の腹を狙い、包丁を突き立ててきた。
「そ‥ そうはいくかい! 」
呼吸が回復した頼純は、そのフリップを狙いすました両足で蹴り飛ばす。
「ぐあッ! 」
腹を思い切り蹴られたフィリップが、後方によろめいた。
頼純も反動で後ろへとずり上がる。
腹を押さえながら、苦悶(くもん)の表情を浮かべていたフィリップだったが、すぐに体勢を立て直し、包丁を振りかぶって頼純へ突進してきた。
「この野郎ォォォォォオ‼ 」
怒気で顔を真っ赤にして駆け寄るフィリップ。その左膝めがけ、再び頼純の両足蹴りが叩き込まれた。
「ガッ! 」
頼純の蹴りは、曲げた膝を真っ直ぐに伸ばすという程度のものであったが、フィリップが前進してくる力と彼の体重の相乗効果によって、かなりの破壊力となったはずである。
「ギャ―――ア‼ 」
激しい激痛に見舞われたフィリップは、その場に崩れ落ち、膝を押さえて身もだえしていた。
彼の左膝関節は脱臼したようである。
今度は、夫の絶叫に慌てたジョアンが走り寄ってきた。
彼女は頼純に向かって包丁をめったやたらと振り回す。
「エイエイエイエイ‥ 」
頼純の蹴りを恐れたジョアンは、もたげた彼の足を切りつけた。
彼女の包丁はサクサクと頼純の足に食い込んだ。ジョアンは確かな手応えを感じていた。
だが、頼純の顔に目をやると平気な様子である。
「え!? 」
さらに彼の足を見ると、傷一つ負っておらず、血一滴流れていない。ただ、頼純の足首を縛っていた縄がボロボロになっているダケだった―――そう、彼女の包丁が切っていたのはその縄だったのだ。
「あ! 」
頼純からすれば、ジョアンの包丁による攻撃など、ゆっくりとした動きにしか見えない。そして、その軌跡に合わせて、足を微妙に動かし、足首を縛った縄の中央でその刃先を受け止める事はさほど難しくはなかった。
ズタズタになった足首の縄は、頼純が両足に力を込めると、あっさり解(ほど)けたのである。
足が自由になると、頼純は宙を蹴って立ち上がった。
その光景にジョアンは悲鳴を上げて飛び退(の)くのだった。
いくら両手が縛られていようともこの状態になれば、素人二人を倒す事など造作(ぞうさ)もない。
そんな頼純を見ていたゴルティエは、ただただ感心するばかりであった。
「ふごい(凄い)‥ ふぁふが(さすが)、ほいはまら(ヨリさんだ)! 」
フィリップは激しく痛む左膝を引きずりながら、何とか立ち上がっていた。顔は涙と汗でビショビショになっている。
「こ‥ この‥ 野郎ォォ‥ 」
頼純はそのフィリップの腕を掴(つか)むと、彼の後ろで立ちすくんでいるジョアンめがけて振り回した。
二人はぶつかり、床に転がる。
「ひィ―――い! 」
ジョアンが叫び声を上げた。彼女はフィリップが握っていた包丁で腕を深く切ってしまったようだ。
形勢は完全に逆転していた。
床で体を起こした二人は、頼純の方を見詰めながら後ずさる。
「た‥ 助けてくれ‥ 」
「お願いです‥ 殺さないで‥ 」
頼純はそんな二人の元へゆっくりと近づいてゆく。
「子供達がそう頼んだ時、お前らはその願いを叶えてやったのか? 」
頼純は落ちていた包丁を拾うと、刃先を手首にあて、その両手を固めていた縄を切断した。
その時、フィリップとジョアンが立ち上がり、奥の右側の扉へと飛び込んだのだ。フィリップの膝は、相当なダメージを受けているはずである。にもかかわらず、素早い動きであった。
「コラッ、待て! 」
二人を追おうとした頼純は、壁に小烏丸(こがらすまる)が立て掛けられているのを発見する。
太刀を掴(つか)み、右の扉へ向かおうとすると、
「ふぉ(ヨ)‥ ほいはん(ヨリさん)! 」
猿ぐつわを咬(か)まされているゴルティエが声を掛けてきた。
「ああ、ゴメン! 」
頼純は彼に駆け寄ると、抜いた太刀でゴルティエの手首の縄を切断してやった。
そのまま落下したゴルティエは、床にドサリと尻餅をつく。
「痛(い)てッッッ! 」
尾てい骨に走る痛みに顔を歪めながら、猿ぐつわをはずすゴルティエに、頼純は声を掛けた。
「正面ドアの奥にいる子供達を頼む。 俺はあの夫婦を追う 」
「は‥ はい! 」
そう言い残して、頼純は夫婦が逃げた扉へと飛び込んだのだった。
× × × × ×
『食人』の風習は人類史上、普遍(ふへん)的に存在していた。
壊滅的な飢饉(ききん)や戦争による略奪によって、食料が完全に枯渇(こかつ)した場合―――人は人を食う。
籠城戦(ろうじょうせん)などで、城塞(じょうさい)都市が丸ごと食料の供給を断たれると、中の人々は猫も犬も虫も、木から雑草にいたるまで、ありとあらゆる有機物を食い尽くしていく。そして、極度の飢えに理性を失ってしまった時、共食いが始まるのだ。
だが、こうした極限状態での『食人』ならまだ致し方ないとしても、そうでない状況―――食料があるにもかかわらず、好んで人肉を喰(く)らう輩(やから)もいた。
『安いから』、『無料だから』、『美味しいから』、『病気が治るから』、『魔的な能力を得られるから』などが、その理由であった。
広大な国土の中で、異民族による侵略や悪天候による飢饉(ききん)などが多発したせいもあろうが、中国には『食人』の記録が多く残っている。
ただ、ここではその詳細は記さない。あまりにも、おぞましく不快な資料だからである。
ただ、繰り返される戦火の中で、征服した兵士達がその都市の住民を食い尽くしてしまう事が幾度(いくど)もあったという。そしてそれは、食料に不自由しないハズの将軍達でさえも例外ではなかった。
また、市場には人肉屋があり、値段は豚肉よりも安かったという記録も残っている。
特に、戦乱は人を狂わせる。
戦争は常に悲惨であり、人の精神を破壊していくのだ。
たとえば、兵士は敵を『人』として見ない。
敵を『人』として見てしまえば、彼の人生やその家族、自分の人生やその家族、宗教や道徳などに思いを巡(めぐ)らせてしまう。そうなると、敵を憐(あわ)れみ、殺せなくなってしまうからである。
だから、兵士は『魂のある人間』を、『倒すべき、ただの物体』として見るように訓練されるのだ。
そう感じられるようになれば、敵を殺す事に罪悪感を感じなくて済む。苦しまなくてもよいのだ。その行為を楽しむ事さえできる。
ただ、敵という『物体』を、動かなくなるまで破壊し続けるのだ。
こうしたいびつな精神状態が長期間続き、さらに極度の飢餓(きが)がくわわれば、「腹が減ってしょうがないのだから、『物体』を喰(く)って何が悪い」という理屈になっていく。
そして一端、禁忌(タブー)が破られてしまうと、その後は平時においても、その垣根は低くなってしまうのだ。
頭のネジがふっ飛び、その行為の異常性に気づかなくなってしまうのである。
この『食人(カニバリズム)』は、ヨーロッパでも例外ではなかった。
とくに、この当時のキリスト教社会は大いに揺れ、人心は不安定だった。
なぜなら、人々は間もなく『最後の審判』が行われると信じていたからである。
主イエス・キリストが再臨(さいりん)し、『最後の審判』が行われるのは、彼の死(復活)から千年後であると言われ続けてきた。
その年が紀元1033年なのである。
その日まで、あと7年しかない。あと7年でこの世界はすべて終わり、『神の国』が誕生するのだ。
その時、生者のみならず死者までもが生き返り、『神の国』に入れるか、入れないかの選別を受けるのだ。
それゆえに、己(おの)が人生を顧(かえり)みて、自分は『神の国』へは絶対に入れないと悟った者は、自暴自棄(じぼうじき)になっても当然であろう。
7年後には『地獄』へ落とされ、『永遠の業火(ごうか)』に焼き尽くされるのだから―――。
こうして、紀元1000年をすぎたあたりから、反キリスト、悪魔崇拝の者達が急増していった。
彼らは神や主キリストを卑(いや)しめるため、あらゆる禁忌(タブー)を破った。その一つに『食人(カニバリズム)』も含まれていたのだ。
彼らは好んで人肉を喰(く)らい、悪魔に近づこうとした。
この食堂の客達も、大半がそのような者であった。
× × × × ×
頼純が飛び込んだ扉の奥は、すぐに下り階段になっていた。
転げ落ちそうになるところを、なんとか踏み止(とど)まり、素早く階段を下りていった。
何か仕掛けがあるのか、扉はまた勝手に閉まってしまった。
階下へ下り立ったところは、先ほどの真っ暗な空間だった。
暗闇の中に、食堂の夫婦が足を引きずりながら、走る音がこだました。
頼純がその方向に目をやると、奥の扉が開き、かすかな月明かりが差し込んだと思ったら、すぐに扉はしまってしまった。
「あとは頼んだぞ―――! 」
フィリップが最後にそう叫んだような気がした。
次の瞬間、背後に空を切る音が聞こえた。
さっきの棍棒(こんぼう)だ―――そう思った頼純は咄嗟(とっさ)に床に伏せた。
頭上を棍棒(こんぼう)らしきモノが横にビュンッと通りすぎていく。
初手の攻撃をかわせたと、一瞬安堵(あんど)した刹那(せつな)、その頭めがけて棍棒(こんぼう)が振り下ろされた。
風切り音を頼りに、床を転がってその攻撃を躱(かわ)す頼純。
だが、棍棒(こんぼう)は何度も何度も頼純に襲いかかった。その狙いは正確無比である。頼純でさえも、それを躱(かわ)すのが精一杯であった。
いや、むしろ躱(かわ)している頼純が凄かった。
完全な闇の中である。敵がどこにいるのか、いつ攻撃してくるのかまったく判らない状態なのだ。何人いるのかさえ判らない。
頼純は、敵の気配とその微かな風切り音で、強烈な連続攻撃をすべて躱(かわ)しているのだ。
だが、頼純も相手がどうやって、自分の位置を把握しているのか理解できなかった。
「クソッ! 」
ドコンドコンと床に叩き付けられる棍棒(こんぼう)を躱(かわ)しながら、頼純はどうにか立ち上がり、太刀を正眼に構えた。
その太刀が横に弾かれる。
しかしそのお陰で、相手のおおよその位置が判った。
頼純はその方向へ太刀を振り下ろす。
「エイッ‼ 」
だが、そこには誰もいない。
小烏丸は敵がいるはずの空間を切った。
『しまった! 』そう思った瞬間、頼純の右肩に太い棍棒(こんぼう)が叩き付けられる。
「グアッ! 」
肩の骨が砕けたかと思うほどの激痛が全身を貫く。
頼純は崩れ落ちそうになった。
今度はその左側頭部に、横に払われた棍棒(こんぼう)が襲いかかる。
その風切り音に向かって、頼純は左手で握った太刀を払った。
カツッという音を立て、小烏丸はその棍棒(こんぼう)を半分ほどに切り落としたようだった。
『やった! 』
頼純は歓喜(かんき)した。
だが、次の瞬間、今度は彼の右横腹に激痛が走る。
反対側からもう1本の棍棒(こんぼう)が襲いかかったのだ。
「カカカカカ‥ 」
ついに崩れ落ちた頼純は、呼吸ができないほどに悶(もだ)え苦しんだ。
そして覚悟したのだった。
次の攻撃は脳天を襲ってくるはずだ。だが、彼にはもう、その攻撃を躱(かわ)せそうにはなかった。
「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)、南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)‥ 」
頼純は死を覚悟し、念仏を唱(とな)えた。
その時、フィリップとジョアンが逃げ込んだ、船着き場へと通じる扉が開いた。
「ヨ‥ ヨリ様―――? 」
振り返った頼純の目に、松明の火が飛び込んできた―――サミーラである。
そしてその光で、頼純の目の前に立つ敵の姿が浮かび上がった。
大男が一人、頼純の頭頂部めがけて、棍棒(こんぼう)を振り上げている。
だが、彼もサミーラの声に驚き、攻撃を一瞬躊躇(ちゅうちょ)していた。