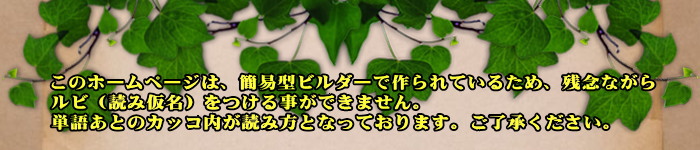
94
1027年 ファレーズ教会
「といったワケで‥ 」
祭壇(さいだん)前に立ったエイマール司教は、礼拝堂の人々をゆっくりと見回した。新しく建てられたファレーズ教会には、この街のキリスト教徒を導く21人の聖職者達が集められていた。
「新しい修道院建設について、ルーアンのロベール大司教様にこの手紙を届けてもらいたいのだが―――」
司教は、人々の一番後ろにいたトマを指差した。
「トマ助祭‥ この仕事は、あなたにお願いする事にいたしましょう 」
その場の全員が、一斉に背後を振り返った。大司教区であるルーアンへ手紙を届けるというのは、たいへん名誉な仕事だった。彼らは、このような大役を、トマのような小者が任された事に大いに驚いていたのだ。
しかし、そのトマは
「そのご命令―――お断りいたします 」
と、拒絶したのだ。
礼拝堂の全員がさらに驚かされた。
いつも、ビクビクおどおどして、誰の言う事にも逆らった事がなかったトマ助祭が、この地の最高責任者であるエイマール司教様に逆らったからである。
今日、ここに集められた者達は、ファレーズの街に新しく建った4つの教会(イグリーズ)に勤める司教、司祭、助祭らである。
ファレーズはノルマンディー公国内でも中堅の都市であった。
あの『傭兵団の襲撃事件』で一端人口は減ったものの、離散する者はほとんどおらず、そこへ城壁建設の人夫や彼らを相手にする商人などが大量に流入したため、現在の人口は去年の1.4倍近くにまで増加していた。
そして、彼らキリスト教徒は、毎週日曜日に必ず教会に行かなければならなかった。
そうなると、教会が足りなくなる―――というよりも、そもそも以前からミサの収容人数が圧倒的に足りなかったのだ。
そこで、ロベール伯はエイマール司教の具申(ぐしん)に従い、新たに3軒の教会を建てたのである。そこに勤(つと)める聖職者達も、かつての7人から21人へと大幅に増加したのだった。
そして今回、さらに修道院までも作るべく、ルーアンの大司教にその陳情をする事となった。ロベール伯爵とエイマール司教との連名での嘆願書(たんがんしょ)であった。
それを届けるという大役は、通常ならば助祭などに任せられるものではない。
ましてやトマなど、助祭の中でも一番下の立場にあった。彼は教会ではなく、『領主の館(メヌア)』の中にある礼拝堂(シャペラ)に勤めているのだ。礼拝堂の維持管理―――その仕事のほとんどが内部の掃除だったが―――をしているに過ぎない。下男とたいして変わらないのである。
そんな小者に、このような重要な書類の配送を任せるなど誰も考えられなかったのである。
かような大抜擢であるにもかかわらず、トマは不満をスラスラと口にしたのだ。
「だって、建てられる修道院はクリュニー修道会のものなんですよ。 あそこは、世俗司教の存在を完全否定している集団です。 王や貴族、豪族などのバカ息子達が、領地目当てに親の権力を使って教会の司教や司祭、修道院長に就任する風潮を、『絶対にあってはならない事』と言い切っている修道会です」
「‥‥‥ 」
「一方、ロベール大司教は‥ ノルマンディー大公リシャール1世の息子ってダケでルーアン大司教という高い地位を得た人じゃないですか。 聖職者がしてはならない結婚だってしている。 そんな大司教に、『アナタのような存在を完全に否定しようとしている者達の修道院を建てたいのですが‥‥』って申し出るんですか? そんなモノ、相手にされるワケがない! 」
× × × × ×
トマが言うように、クリュニー修道院は、ベネディクト修道会が唱(とな)えた「清貧」「従順」「貞潔(童貞)」「定住」の誓いを、さらに厳格に推し進め、様々な世俗権力からの自主独立と、教会内の不正腐敗を糾弾していた。
だが、1027年の時点で、世俗司祭らを含むローマ教会とクリュニー修道会は対立していたわけではない。
ただ、彼らの理念はヨーロッパ―――特にフランス、イタリア、スペインなどで徐々に広まっていき、やがて聖職叙任権(じょにんけん)闘争―――『カノッサの屈辱』へとつながっていくのだ。
1076年、神聖ローマ帝国(現在のドイツ・オーストリアなど)皇帝ハインリヒ4世は、ローマ教皇グレゴリウス7世からの再三の注意にも耳を傾けず、ミラノ大司教やフェルモの司教、スポレートの司教などを次々と任命していったため、業(ごう)を煮(に)やしたグレゴリウス7世から破門された。
神の加護がなくなったハインリッヒ4世は、神聖ローマ帝国内での権威を失い、諸侯から皇帝退任を求められる事になる。
これに慌てた皇帝ハインリッヒ4世は翌年の1077年、教皇に謝罪を申し出た。だが、グレゴリウス7世はこれを拒否。そのため、皇帝は窮地に追い詰められてしまう。
そこで皇帝ハインリッヒ4世は、教皇グレゴリウス7世が訪(おとず)れていたカノッサ城にみずから赴(おもむ)き、面会を申し出たがこれも拒否される。
もはや、体面など気にしていられなくなったハインリッヒ4世は、皇帝の証しである剣や鎖帷子、兜などをすべて脱ぎ去り、裸足の修道着姿となって、雪降るカノッサ城の門前で3日間、教皇に謝り続けたのである。
この恥も外聞もない皇帝の謝罪を哀れに思ったグレゴリウス7世はこれを受け入れる事にした。この事件を『カノッサの屈辱』という。
この事件は、長く続いた『聖職叙任権(じょにんけん)闘争』の一端に過ぎないが、転換点となった事は間違いない。
ローマ教皇から破門され、キリスト教徒でなくなると、国王でさえもその地位を脅(おびや)かされるという事を証明したからである。
その後、1122年の『ヴォルムス協約』によって、司祭、司教の任命権は教皇にあるという事が確定されると、ローマ教皇とローマカトリック教会は絶頂期へ突入していくのだ。
また、クリュニー修道会は、1096年から始まる『第一回十字軍』にも多大なる影響を与える存在であった。
× × × × ×
トマは小馬鹿にしたように鼻を鳴らすと、エイマール司教に告げた。
「そんな修道院の建設なんて、絶対反対されるに決まってるじゃないですか! 」
だが、その意見に他の司祭達が反論した。
「いやいや‥ そうなるとは限らないでしょう 」
「そうですよ。 そのルーアンにでさえ、すでにクリュニー会系の修道院はもう建っている。 それを認可されたのはロベール大司教様ですよ 」
「ロベール大司教様はそのような心の狭いお方ではない 」
「トマ殿はナニも判っていない。 アナタのおっしゃる事は大袈裟すぎるんですよ 」
一斉に浴びせられた自分への非難に、トマは今度はふて腐れた態度となった。
「ああ、そうですか。 どうせ、私は愚(おろ)か者で、大袈裟(おおげさ)なんでしょうよ。 いままでだって、誰一人としてわたしの意見なんか聞いてくれた事はありませんでしたしね 」
「いや‥ それはお前が、集会の間ずっと俯(うつむ)いて、誰にもナニも話さなかったからだろう 」
フランシス司祭がムッとした顔で言い返した。
そんなフランシスをトマは無視して、さらに語った。
「どっちにしたって‥ わたしがルーアンに行って何の得があるのでしょう? わたくしのような助祭ふぜいでは、ロベール大司教にお目通りがかなうわけでもありませんし‥ 待たされるだけさんざん待たされたあげく、大司教の秘書―――いや、小間使い程度の司祭に、わけのわからない文句をさんざん言われ、『ご苦労様』のひと言も、お駄賃のひとつもなく、教会を追い出されるだけです 」
「いや‥ 得って―――? 」
「それが我々の仕事だし‥‥ 」
「修行でもあるんじゃないか? 」
全員が唖然(あぜん)とした。聖職者がその業務に損得を持ち込むなどあり得ないからだった。
「だったら‥ 私のような下っ端ではなく、どなたかもっとお偉い方にお任せになった方がよいと思いますよ。 ともかく‥ あたしゃ、こんな仕事、真っ平ごめんです! 」
トマの口ぶりは、その場の全員に憎しみを向けていた。
そんな中、それまで沈黙を守っていたエイマール司教が、穏やかな口調でトマに話し掛けた。
「そうですか。 アナタのご意見は拝聴(はいちょう)いたしました。 でも、これはこの教会区にとって、どうしてもやらねばならない事なのです。 」
それから司教は視線を移動させ、一番若い助祭に声を掛けたのだ。
「では、オリビエ助祭にお願いいたしましょう 」
「は‥ はい‥ 」
オリビエはちょっと顔を引き攣(つ)らせていた。
司教はふたたびトマに顔を向けると、さらに付け加えた。
「わたしは、こういう細かな顔合わせでルーアン大司教区の方々とも交流を深め、トマ殿の顔と名前を覚えてもらおうと思ったのです。 そうする事で、あなたの司祭への道も開(ひら)けていくと考えました 」
そんなエイマール司教の優しい言葉を、トマは睨み付けるようにして笑った。
「わたしのこの醜(みにく)い顔なら、誰であろうとも一度見たら忘れませんよ。 そして、不快な印象しか残らない。 そんな接見など何度やってもわたしの出世にはつながりません! 」
礼拝堂は静まり返った。
言葉を続けるトマは怒りに満ちていた。
「そもそも、わたしが司祭になれるとでもお思いですか? 醜いわたしの説教を聞くために、誰が教会まで来るというのです? 笑わせちゃいけませんよ」
雄弁で攻撃的、憎しみに充ち満ちたトマの発言は、以前とはかけ離れていた。そのあまりの違いに、その場の全員が言葉を失ってしまった。
やがて、エイマール司教が恐る恐る声を掛けた。
「―――し‥ 失礼な事を申し上げますが‥ あなたは本当にトマ助祭ですか‥‥? 」
かつておどおどしていたジロアの人格はそこに微塵(みじん)もなかった。
邪悪な人格トマは、元々の人格―――気弱なジロアを完全に乗っ取ってしまっていたのだ。
カモフラージュのためこのような集まりにも出席しているが、宗教の事や日々のお勤めの事など考える事はない。彼の脳裏には、どうやってエルレヴァを誘拐するかとか、どうやって街の人々を苦しめてやるかしかなかったのだ。
そう、もう一人の人格・ジロアが好きなだけで、自分はまったく興味のない女―――エルレヴァの誘拐であった。
× × × × ×
晴れ渡った秋の午後。気温はまださほど低くはないが、ファレーズの丘を抜けていく風は冷ややかに感じられる。
そんな風が舞い込むファレーズ城の広間では、執事(アンタンダン)のティボーと徴税官(ちょうぜいかん)が、羊皮紙で作られた分厚い租税(そぜい)台帳を見せながら、ロベール伯爵に下半期の税収について説明をしていた。。
「といった状況で‥ 春の刈り入れでの小麦は、例年の半分ほどしか収穫できておりません 」
喜ばれざる報告にも、ロベール伯は納得したかのように頷(うなず)く。
「そうか‥ まあ、覚悟はしていたからね。 謎の傭兵団に畑を踏み荒らされ、火までつけられたんだ。 半分、収穫があっただけでも感謝しなくっちゃ 」
とはいえ、やはり大幅な減収が気になるのか、玉座で頬杖(ほおづえ)をついたロベール伯爵は浮かない表情になった。
そんな主人を励(はげ)まそうと、ティボーはつとめて明るく答えた。
「そうですとも! それに、この春の収穫には若が推進された『農業改革』の成果はまだ含まれておりません。 春に蒔(ま)いた大麦からが勝負です。 農機具の最新化によって、作業時間の短縮‥ それにともなって作付け面積も大幅に拡大しておりますから‥ 収穫は例年の1.5倍‥‥いや、2倍は見込めましょうぞ 」
徴税官もそれに同意した。
「ティボー様のおっしゃる通りでございます。 来週から始まる秋の収穫は大いにご期待くださいませ♡ 」
「そうか‥‥ 」
ロベール伯爵はふたりに、気の抜けた笑顔を返した。
ロベール伯爵が行(おこな)った農業改革は、暗中模索(あんちゅうもさく)の中で進められた。
耕地の鋤(す)き起こしをした農民達から、ロベールが与えた10台ほどの重量有輪犂(じゅうりょうゆうりんすき)がいかに素晴らしい農具であるか、その報告は受けていた。
だが、あとはすべて未知数である。
それゆえ、蓄(たくわ)えとなるはずだった春小麦の収穫減は、ファレーズ伯爵領の財政を逼迫(ひっぱく)させるに違いなかった。
報告を終えた徴税官が台帳とともに立ち去ると、広間にはロベール伯爵とティボーだけになった。
静まり返った広間で、ロベールは立ち上がろうとしなかった。難しい顔で玉座に坐ったままなのだ。
そんな主人をなんとか取り成そうと、ティボーは愛想笑いで語り掛けた。
「ま‥ まあ‥ そのようにご心配なさらずとも、数年後には若のお考えが正しかった事が必ずや立証されましょう。 それまでの辛抱(しんぼう)です。 頑張りましょう 」
「う‥ うん‥ 」
昨年までのティボーなら、『ホラ、やはりジイの申し上げた通りでしょう。 農業改革など時間と財政の無駄なのです。 おやめなさい 』と、イヤミのひとつ、文句の二つも言っていたであろう。
だが、ロベールを一人前の君主と認めた現在は、応援する事こそあれ、子供扱いする事などなくなっていた。
しかし、そんな執事(アンタンダン)の励(はげ)ましにも、ロベールは力なく頷(うなず)くばかりであった。
その時、ティボーは気づいた。
考えてみれば、伯爵はこのところずっと浮かない顔をしている。つまり、彼の気分がすぐれないのは、今日聞いた税収の事が原因ではないという事だ。
察(さっ)した彼は、それとなくカマを掛けてみた。
「おやおや‥ そのようなお返事の時は、違う事をお考えになっておられる場合―――もしや、ご結婚の事ではありますまいか? 」
ロベール伯は図星だと言わんばかりにティボーに目を向けた。
ティボーは胸を張って答えた。
「そちらも大丈夫でございます! ご安心ください。 ローマ教皇からのお許しは、まだ頂戴(ちょうだい)しておりませんが‥ 若はかならずや、エルレヴァ殿とご結婚できます! 」
「‥‥‥ 」
「叔父上(おじうえ)であられる、ロベールルーアン大司教様があれだけ確約なさったのですぞ。 ロベール2世フランス国王陛下のお許しも下りております。 これはもう、間違いございません。 手続きに時間が掛かっておるだけなのでしょう。 もうしばらくお待ちください 」
登場人物の名が『ロベール』ばかりでややこしい。
旧臣の慰(なぐさ)めに、ロベール伯爵はやっと安堵(あんど)の微笑(えみ)を返した。
「そうだな‥ ありがとう。 元気が出たよ 」
主人から発せられた久しぶりの感謝の言葉に、ティボーは密かに歓喜していた。
だが、ロベールの下(もと)へ結婚許可の通達が届かないのは、教皇庁の手続きの遅れなどではなかった。
作為的に遅らされていたのだ。
その背後には、イングランド国王クヌート1世の力が働いていた。
彼がローマ教皇ヨハネス19世に、『ノルマンディー大公の弟ロベール伯爵の妻には、我が妹・エストリドがふさわしい』と手紙で陳情していたからであった。
× × × × ×
その頃、頼純は『カラス団(コルブー)』達と旅に出ていた。
彼がロベール伯爵とその子ギヨームの剣術指南として雇われてすでに1ヶ月以上が経っていたが、ギヨームはまだ乳児であったし、ロベール伯はさほど剣の修行に熱心ではなかった。
それゆえ、日々『領主の館(メヌア)』に登城してみても、大してやる事はない。だが、無為(むい)に時間を過ごすわけにもいかなかった。なにせ、彼はロベール伯爵から毎月給金をもらっているからだ。
そこで、余った時間を、『カラス団(コルブー)』への指導と、その実践的捜査に充(あ)てる事にした―――それは、これまで通りといえば、これまで通りの事。無償でやるか、報酬(ほうしゅう)をもらってやるかの違いだけで、それ以外はなにも変わってはいなかったのだが‥‥‥。
そんな『カラス団(コルブー)』達は現在、9ヶ月前にファレーズを襲った傭兵軍団『シュヴェール』の調査・探索のため、各地を廻(まわ)っていた。
『シュヴェール』の生き残り達を伯爵親衛隊のエルリュインらが拷問し、いくつかの情報は得られていたが、その裏付けを取り、彼らを雇った真犯人を見つけ出さなければならなかった。
襲撃を依頼した者が判らない限り、ふたたびファレーズがその災禍(さいか)に見舞われる可能性もあるからだ。
しかし、いまだそれが誰なのか―――痕跡(こんせき)すらつかめていなかった。
公都ルーアンへと続く街道を歩きながら、頼純は自分の推理を『カラス団(コルブー)』達に語って聞かせた。
今回の出張調査には、グラン・レイ、ドニ、ブノア、ラウル、ニコラの5人が同行していた。ゴルティエやプチレイなどの6人は、ファレーズの治安を守るタメ、残してきていた。
「小規模ながらも、戦争に匹敵(ひってき)するほどの兵力を送り込んできたんだぞ。 支払われた依頼料は莫大であったはずだ。 そして、そんだけの戦費を捻出(ねんしゅつ)できんのは、よほどの大富豪か、貴族しかいネーだろう! 」
頼純と肩を並べて進む5人の若者は、頼純の顔を覗(のぞ)き込んで真剣にその話に聞き入っている。さほど広くない街道は、道幅の半分以上を占領されてしまっていた。他の通行人などそっちのけである。
「つまり‥ 公爵とか伯爵と同じくらい銭を持ってる奴って事ですよね? 」
「だったら‥ 大きな修道院や外国の大商人って可能性もありますよ 」
グラン・レイの相槌に、1番年下で1番の知恵者でもあるニコラが付け加えた。
「そういう事だ! じゃあ、それほどの費用を掛けて、ファレーズを陥落(かんらく)させる目的はナニか―――これが近隣諸国からの侵略ならば、相手は正規軍を使い、名乗りを上げて攻めてくるだろう。 そうでなけりゃ、たとえ戦争に勝ったとしても、ノルマンディー大公やフランス国王からファレーズを自領とする許可が下(お)りネーからな 」
「ふむふむ‥ 」
「なるほど! 」
「そりゃ、そうだ 」
黒ずくめの青年少年らは大きく頷(うなず)いた。彼らは頼純の話を理解しているのだ。それは飛躍的な進歩であった。
1年前まで、知性のかけらもなかった不良少年達が、今では噛み砕いて説明すれば政治経済の話でも十分理解できるようになっていた。
それは、多くの情報を入手し、それを整理して、犯人を突き止めていく『探索方』にとって、もっとも重要な素養であった。
そして彼らは意外にも、幅広い知識を取得するための学習を厭(いと)わず、むしろ積極的に努力していたのだ。
頼純は話を続ける。
「じゃあ‥ ファレーズの土地が欲しいんじゃなくて、街自体を潰(つぶ)す事が目的って場合だってある。 たとえば、隣町の市場が無くなれば、自分の街の市場が栄えるといったような場合だ 」
「あ、そっか‥ 」
「けど‥ 今まで、ファレーズで大きな市が立った事はねェし、近隣の街にも常設の市場は存在しねェ。 その他の理由も考えてみたが、地理的観点から、ファレーズを潰(つぶ)して利益を得る都市はネーんだ。 つまり、この説も成立しねェ 」
その時、賢いニコラが尋(たず)ねた。
「じゃあ、他国の謀略って可能性はどうでしょう? ファレーズを足掛かりにして、ノルマンディー公国を狙っているって事は? ブルターニュ公国やアンジュー公国‥ あと、イングランド王国あたりも怪しいと思うのですが 」
頼純がそれに頷(うなず)く。
「うむ‥ それは、十分に考えられる―――だから、それらも含めて、ありとあらゆる証拠集めをしなきゃならネーのさ 」
グラン・レイがうろ覚えの地名に顔を顰めながら、頼純に提案した。
「だったら‥ ルクセン‥ えっと、ルクセン‥ なんだっけ? そのルクセン何とかまで乗り込んでって‥ 傭兵団の団長をとっ捕まえましょうよ! そんで、いったい誰がファレーズを襲うように依頼したのか―――口を割らせるんです。 」
「お~~~お‥ 」
「なるほど! 」
仲間の賛同に気をよくしたグラン・レイは得意げに続きを語った。
「まあ、そう簡単に依頼人の事を漏らしゃしネーでしょうけど‥ コッチには、フィリッポさん譲りの拷問術(ごうもんじゅつ)がありますからね‥ 必ず口を割らせて見せますよ♡ 」
だが、頼純は呆(あき)れたように笑った。
「おいおいおいおい‥ オメーら、どうやって『シュヴェール』の本部に侵入するつもりだよ? 奴らは、大領主にも匹敵する500人以上の兵士を抱えてんだぞ。 その多くは仕事のため、各地の紛争に派遣されてんだろうが‥ それでも本部にゃ、常時200人ほどが待機してるって話だ。 そこに忍び込み、団長を誘拐する事なんて、今のオメーらにゃとても無理だ! 不可能だよ 」
「そ‥ そっかァ‥ 」
このようなやり取りを交わしては、『カラス団(コルブー)』達に推理のしかた、論理の組み立て方などを教えているのである。
だが、頼純の胸中には、すでに真犯人とおぼしき人物が浮かんでいた。
それは、ファレーズに『恨(うら)み』―――街を焼き尽くすほどに激しい『恨み』を持っている者ではないのか。
頼純には、そのような人物がひとりしか思い浮かばなかった。
新年の宴(うたげ)に乗り込んできたロベール伯の義理の弟―――ブルゴーニュ伯ルノー1世である。