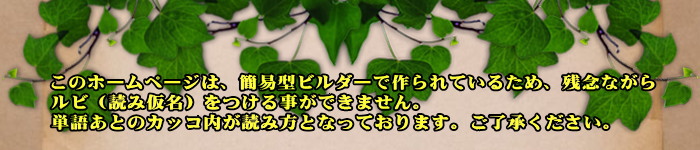
4
1026年 ファレーズの街
なじみの隊商(キャラバン)によって助け出されたロベールは、一行とともに馬に乗り、ファレーズ城へと向かっていた。
ファレーズ城の景色は、先ほどと同じように見えたが、そこにのんびりとした空気はなかった。領主ロベールが盗賊に襲われたという報告に、ピリピリとした緊張に包まれていたからである。教会の鐘はずっと鳴り続けていた。
慌てて城から駆けつけた二十人ほどの兵士が、ロベールの護衛として一行に合流している。
兵士に囲まれながら、ロレンツォと並んで進むロベールの馬には、鞍(くら)の前にエルレヴァも乗っていた。
よほど肝が太いのか、かなりの楽天家なのか、先ほどまでの絶望的な表情が嘘のように、楽しそうにロレンツォと語らっている。
「い~~~やァ‥ ホンッッットに凄いですよ、あの方は! たった一人で、十人以上を斬り倒して、二十人ほどもいた賊達を退散させてしまったんですから 」
興奮気味に話すロベールに、ロレンツォは自慢げな微笑を返す。
「しかも‥ 盗賊達を一人として殺してはおりませんぞ♡ 」
大きく頷いたロベールは、うっとりとした目を宙に漂わせると、謎の男の活躍ぶりを思い出していた。
「そうなんです、そうなんですよォ‥! そりゃあもう、圧倒的な強さで―――まるで、大天使(アークンジ)ミッシェル様が御身(おんみ)を変えて、現(あらわ)れられたかのようでした‥ 」
ロベールが例えた大天使(アークンジ)ミッシェルは、天界の守護天使の事である。ローマ教会では、悪魔が最も恐れる天使とされ、無敵の軍神として崇(あが)められていた。
気分が高揚しているロベールとは対照的に、彼の胸に顔を埋(うず)めたエルレヴァは、不安に眉をひそめていた。
女の身であれほどの恐怖を味わったのである。周囲の者達は、彼女の反応を当然のように思っていた。
しかし、彼女が脅えていたのは、盗賊達が自分を犯そうとした時、それを止めた男の言葉だった。
その女には指一本触れるな、それが今回の条件なんだ―――確かに、そう言っていた。
伯爵様は殺してもいいが、自分は無傷で帰せ―――そんな条件付きの暗殺を指示したのは、いったい誰なのか。その人物は、この地でもっとも有名な伯爵様と同じように、一介の町娘でしかないこの自分もよく知っているという事になる。つまり、『伯爵暗殺』という大罪を首謀した人物が、自分の知り合いという事なのだ。
それは、ロベールの子を身籠(みご)もった彼女にとって、とてつもない恐怖であった。
「で‥ あの方は何者なのです? 見た事のない風体(ふうてい)ですが、やはりサラセン人なのですか? 」
子供のように目を輝かせて尋ねてくるロベールに、ロレンツォは少々困惑気味(こんわくぎみ)の微笑(えみ)を返す。
「そうですね‥ どう、ご説明いたしましょうか――― 」
彼は、ヴェネツィアの大商人であり、遠隔地貿易によって大金を得た男である。四十を二つ三つ過ぎたくらいの年齢ではあるが、ガッチリとした体躯(たいく)に、整った顔立ちを持つ見た目のよい壮年(そうねん)であった。いくら旅の垢(あか)にまみれようとも、その風情(ふぜい)や仕草には気品があった。
「今までも何度かお話ししておりますが… 地中海の対岸から東側は、ずっとサラセン人の国々が広がっております。 そこをさらに東へ、東へと進んでいくと、遙かかなたに中国(スィーン)という場所があり、いまは『宋』という巨大な帝国が治めているというお話―――まだ覚えてらっしゃいますか? 」
「勿論です! あの絹(スワ)の布地を作っている所でしたよね? では、あの方はその『宋』の方なのですか? 」
ロレンツォはロベールの顔を覗き込むと、からかうようにニヤリと笑った。
「いいえ‥ その『宋』よりもさらに東―――世界の果ての地に、商人仲間達から『ワクワク』と呼ばれる黄金の島―――『日本国』があるのでございます 」
ロレンツォ自身は、『ワクワク』が黄金の国だという話を信じてはいなかったが、その話をすると誰もが食いつくので、あえてロベールにもそう告げてみた。
「え? お‥ 黄金の国‥ 『日本国』―――? 」
案の定、ロベールはその言葉に大いに驚いた。
「はい。 彼はその国の武人で―――名を『藤原頼純(ふじわらのよりずみ)』と申します 」
得意げに語るロレンツォ。彼は、頼純の事をかなり自慢に思っているようだった。
「『日本国』の武人で… 『藤原頼純』…… 」
男の名前を何度か復唱すると、ロベールはますます彼に興味が湧いてきた。
しかし、さらなる質問をロレンツォにしようと口を開いた時、前方を警護していたファレーズ兵士の大きな声でそれは遮(さえぎ)られた。
「道を開けい! 伯爵様のお通りだ! 」
「邪魔だ、邪魔だ! 下郎(げろう)ども、道を開けるのだ! 」
ロベール一行は城壁の外側に建ち並ぶ貧民街の目前にまで迫っていた。沿道にはロベールの無事な姿を一目見ようと、多くの領民達が集まっていたのだ。
「伯爵様だ! 」
「ご無事のご生還だ! 」
「ロベール様のお帰りだ! 」
領民達は口々に歓声を上げた。一行の後には、楽しそうに走り回る子供達の姿もあった。
ロベールは、領民達に好かれてはいた。しかし、彼らが騒ぐ理由はそれだけではない。楽しみの少ない彼らにとって、騒ぐ事自体が娯楽なのである。とくに、公開処刑と凱旋(がいせん)パレードは大いなる楽しみの一つであった。
一行は、ロベール達のすぐ後ろに、『藤原頼純』と彼の部下らしき四人のイタリア人傭兵(ようへい)が隊商(キャラバン)全体を警護すべく徒歩で追っていた。先ほど活躍したサラセン人の女も一緒ではあったが、奴隷である彼女はすべての武器を取り上げられているようである。
その後ろには、長持(ながもち)を山積みにした五台の荷車を牛が牽(ひ)き、ロレンツォの部下である商人が四人、たくさんの荷物を背に担(かつ)いだ奴隷(どれい)女五人が続いた。
さらには、大きな檻(おり)を乗せた馬車が追い掛ける。檻の中には、六人の男奴隷が入れられていた。
その後方を、五人のイタリア人傭兵(ようへい)が守っている。
最後尾には、ファレーズの兵士十人に連行される山犬のジャンがいた。ブレー(ズボン)以外何も身につけていないジャンは、ロープで厳重に縛られ、引き廻(まわ)されていた。ロープの端は馬の鞍(くら)に結(ゆ)わえられており、何度もこけたのであろうか、地面を引きずられたその体は泥まみれで、擦(す)り傷だらけになっていた。
「アイツが伯爵様を襲った犯人だ! 」
「この野郎、死んじまえ! 」
見物人達は、裸で引き廻(まわ)される山犬のジャンが、領主様を襲った犯人だと知るや、彼に向かって石や野菜クズ、泥団子を投げつけた。
ジャンは肩をすくめて、飛び来る石つぶてから頭部を守ろうとするが、石は体のあちこちに当たり、
「や‥ やめてェ‥ 助けてください! 」
と、泣き叫ぶ事しかできなかった。
だが、路上の人々は容赦(ようしゃ)しなかった。
「お前なんか死刑だ! 首を刎(は)ねられればいい! 」
「いいや、火炙(ひあぶ)りだ! 火炙りの刑にしろ! 」
口々にそう罵(ののし)ると、さらに物を投げつけたのである。
一行が跳(は)ね橋を渡り、第一の城門をくぐってファレーズ城内へ入る頃には、ジャンはもはや誰だかわからないくらいに、顔が腫(は)れ泥まみれになっていた。
× × × × ×
中世ヨーロッパの象徴ともいえる石造りの城は、11世紀初頭のヨーロッパには、まだ存在していなかった。一部の教会を除いて、石造りの建造物自体がほとんどなかったのだ。
それより500年以上も昔であるローマ時代には、帝国のみならず、属州(ぞくしゅう)のガリア―――西ヨーロッパ全体に、多くの石造建築物が存在していたにもかかわらずである。
石造建築の技術は、古代エジプトのピラミッドやアブシンベル神殿、ヒッタイトの城塞(じょうさい)都市ハットゥシャなど、紀元前三千年頃にはすでに古代オリエントで誕生していた。
その技術は、ギリシア・ローマ文明へと引き継がれ、さらなる研鑽(けんさん)を積む事となる。ギリシアではアテネのアクロポリス、ローマではパンテオンやコロッセオに代表される巨大石造建築物にその技術は使用された。
当時すでに、丈夫で成形しやすいコンクリートまでもが発明されており、カラカラ浴場やパンテオンはそれらの建材で建造されていた。
だが、その文明大国ローマ帝国も、4世紀になると王座の奪い合いを繰り返し、やがて東西ローマに分裂してしまう。
同じ頃、中央アジアから攻め入ったフン族に押されて、逃げ出した東ヨーロッパのゲルマン民族は、西ローマ帝国領内へと大量に移住し始める。
『ゲルマン民族の大移動』である。
彼らははじめ、空腹を満たすためにこそこそと泥棒を働いていたが、やがて強盗・殺人・強姦・放火を生業(なりわい)とする部族へと変質していった。
悪行の限りを尽くすゲルマン人のせいで、西ローマ帝国内の治安は極端に悪化し、帝国は混乱を極めた。
そして紀元476年、ついに西ローマ帝国は崩壊する。
帝国が消滅した西ヨーロッパには、その後、さまざまなゲルマン部族が国家を樹立(じゅりつ)した。
しかし蛮族(ばんぞく)である彼らには、何千年にも及ぶ科学技術の集大成であるローマ文明がまったく理解できず、それらを受け継ごうとはしなかった。
逆に、徹底的にローマの文明を破壊していったのだ。
建物を壊し、書物を焼き、知識人を殺した。それでも壊しきれない建造物はそのまま放置され、やがて朽ち果てるにまかせた。
一方、王たる血統を持たない強盗団の首領達にとって、国王として民衆を従わせるタメには、彼らを納得させるだけの権威(けんい)がどうしても必要であった。
その権威(けんい)を作ってくれたのが、信徒拡大に躍起(やっき)になっていたキリスト教会である。教会は彼らに、『神より選ばれし王(王権神授)』という、大義名分を与えてくれたのだ。
各ゲルマン人国家は、この権威を得るために、こぞってキリスト教へと改宗(かいしゅう)していく。
そして、そのローマキリスト教会こそが、みずからの神秘性を保つため、科学を完全否定していたのだ。つまり、ゲルマン人らが、ローマの科学を破壊する事は、教会にとって好都合であり、大いに推奨(すいしょう)された事だった。
こうした状況が数百年も続くと、かつての文明や技術は、すべて忘れ去られてしまう。建築学はもちろん、数学、哲学、医学、天文学―――あらゆる科学が無に帰(き)してしまうのである。
この文明の空白期間が、『暗黒時代』と呼ばれる年代である。
もちろん、外の世界――ビザンティン(東ローマ)帝国やイスラームの諸国には、ギリシャ・ローマの文明は受け継がれていた。それゆえに、一部の者がローマ教会の教えに背(そむ)き、その科学や技術をこっそりと西ヨーロッパに持ち込む事もあった。
また、ロレンツォ達のような、東西を行き来する商人も、当然その存在を知っていたのである。
そんな中、西ヨーロッパでは9世紀前後から、盗賊(バイキング)の襲撃や領土紛争など、敵対勢力による侵略が多発した。
各地の領主達は、これらの敵から自分や家族の生命、財産を守るタメに、城らしきモノを作りはじめる。
それは、屋敷の周囲を丸太の高い塀で囲み、その周りに壕(ほり)を堀った程度の砦(とりで)でしかなかったが、無防備よりはずっとマシだった。
10世紀後半頃からノルマン人領主達が作った城には、ひとつの工夫がなされていた。
土塁と城庭(モット&ベーリー)形式といわれたその城の特徴は、壕(ほり)をほった際に出た残土などで、屋敷の背後に小高い丘を作り、その上に敵から攻め込まれた際に逃げ込む、最後の『避難所』を設(もう)けるというモノだった。
ロベールが治める『ファレーズ城』もそんなノルマン人方式の城であった。
そして不思議な事に、この40年後、ロベールの息子であるギヨーム2世(ウィリアム1世)がイングランドを征服すると、それまで皆無だった石造りの城は、ヨーロッパ全土に急速に広まっていくのである。
× × × × ×
一行が進むファレーズ城内は、丘の斜面に裕福な人々の家が200戸ほど建っていた。斜面の中ほどには広場も設けられており、露店商による市場がにぎわっていた。
常にぬかるんだ通りの両側には、貧民街と同様に、ロベール伯の帰還を見逃すまいと、それぞれの家々から出て来た領民達であふれていた。
「おお、ロベール様だ 」
「ご無事でよかった 」
「ロベール様、万歳! ファレーズ、万歳! 」
そう叫びながら手を振る領民に、ロベールも笑顔を返した。
やがて観衆の視線は、伯爵と一緒に馬に乗ったエルレヴァへと向けられた。
はじめは、伯爵様が姫君をお連れになったぞ―――などと喜んでいた領民達もすぐに彼女の正体に気づき、そのあり得ない光景に大いに驚くのであった。
「え? 」
「あ‥ あれはエルレヴァだ! 革なめし屋(ペルティエ)の娘、エルレヴァだぞ! 」
「そんな‥ 馬鹿な‥ 」
伯爵の手前もあり、彼らもそれ以上は言葉を飲んだが、エルレヴァへの視線は困惑(こんわく)と落胆(らくたん)、幻滅(げんめつ)に満ちていた。
そのエルレヴァは、伯爵襲撃の真犯人の事で頭がいっぱいになっており、人々の視線に気づくのが遅れてしまった。
ロベールとの関係は、彼からの願いもあって秘密にされていた。それが今回の事件によって、公(おおやけ)になってしまったのである。だから、このパレードが、伯爵の恋人として初めてのお披露目(ひろめ)となるのだ。
我に返ったエルレヴァは、かわいく、お淑(しと)やかに見えるよう、はにかんだ笑顔を作ってみせた。しかし、自分に向けられる視線が否定的なモノであると知り、しだいに表情は強張(こわば)っていった。
なぜ、アタシではダメなの、どうして、身分の低い女は伯爵様と結婚できないの―――判っていたつもりだったが、人々の冷たい視線は改めて彼女に苛(いら)立ちを感じさせたのである。
そこへ、人垣を割って5人の少年達が進み出た。
「姉ちゃん! 」
エルレヴァは中央に立つ少年を見ると、やっと安堵(あんど)の表情を浮かべた。
「ゴルティエ‥! 」
『ゴルティエ』と呼ばれた若者も大いに安心し、エルレヴァに笑顔を返した。
「よかったァ‥ 無事だったんだね 」
彼は、ほかの少年に顎(あご)を使って指示をだす。どうやら、少年達のリーダーのようである。
5人の少年達は15から20歳くらいだろうか。みな、黒のチュニックに、黒のベスト、黒いブレーと全身黒ずくめの格好、腰にはナイフも吊っていた。目つき鋭く、周囲の人々を視線で威嚇(いかく)している。どう見ても、街の不良少年団に違いなかった。
ゴルティエも、姉に似てかなりの美男子ではあったが、その目にあどけなさや純粋さはなかった。
「カラス団(コルブー)だ‥ 」
「この悪童ども‥ 」
「まったく‥ 目障(めざわ)りな! 」
人々はコソコソと、悪態ともつかぬ声を上げる。
エルレヴァが人々から嫌な顔をされたのは、身分違いの恋だったからだけでなく、じつはこの弟やその父親も影響しているのだった。
エルレヴァは、領民達を無視するように、ツンとした表情でロベールを振り返り、
「伯爵様‥ 弟も迎えに参りましたので、本日はウチへ戻ります 」
と告げた。
彼女は妊娠した事をロベールに伝えて以来、彼に対して確実に強気になっていた。
それが、子を守ろうとする母性の目覚めゆえなのか、それとも、これでロベールが簡単には自分を捨てられなくなったと確信したからなのか―――エルレヴァ自身にもよく判らなかった。
ロベールも、彼女が表に出さないだけで、本当は気の強い女性である事は承知していた。しかし、今日のようにその本性を見せ付けられると、少々戸惑いを感じてしまう。
「お‥ おお‥ そうだね‥ それがいい 」
ゴルティエは指を組み合わせた両手を差し出すと、そこへエルレヴァの足を乗せ、彼女を馬から下ろそうとする。
「姉ちゃん、ここに足掛けて。 ゆっくりと‥ そう。 そっとだよ、そっと‥ 」
必要以上に姉の身を心配するゴルティエは彼女の妊娠を知っているようだ。
ロベールは、降り立ったエルレヴァを複雑な微笑(えみ)で見下ろす。
共に命が助かったという大きな喜びと、これから発生する様々な難問にどう向き合えばいいのかという不安が、入り混(ま)じっていたからであった。
「えと‥ じゃあ‥ 二、三日したら、城に来てよ。 子供の事は、その時に改めて話そう。 ね? ね! 」
馬上のロベールを見上げたエルレヴァは、彼の心の揺(ゆ)らぎを感じながらも、
「はい。 仰(おお)せの通りに! しかし、その時のお迎(むか)えは、白馬でお願いいたします 」
と、高飛車(たかびしゃ)に言い放(はな)った。